
発達障害のある子どもとお出かけしたいけれど、迷惑をかけてしまったらどうしよう
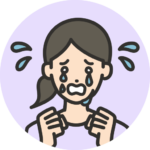
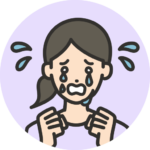
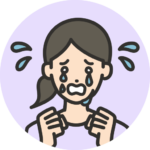
パニックの際に対処できるか心配
このような不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。筆者も最初は同じ気持ちでした。
しかし、公共交通機関には発達障害児やその家族が利用できるさまざまな支援制度が用意されています。この記事では、自閉スペクトラム症の娘と暮らす筆者が、公共交通機関を安心して利用するためのポイントをお伝えします。
事前の準備や工夫をして子どもと楽しく電車やバスに乗るための参考にしてみてください。
発達障害児とのお出かけ…どんなことが不安?
たとえば、筆者が娘とお出かけする際、以下のようなことが心配でした。
行動面での不安
- 急に大きな声を出したり走り回ったりしないか
- 座席から立ち上がって動き回ってしまわないか
- ドアや窓を触ったり開けようとしたりしないか
パニック・混乱への不安
- 突然パニックになって泣き叫んでしまわないか
- 人混みや騒音で興奮状態になってしまわないか
- 予定と違うことが起きた際に対応できるか
周囲への配慮に関する不安
- 他の乗客に迷惑をかけてしまうのではないか
- 周りの人から冷たい視線を向けられるのではないか
- 注意されたり文句を言われたりしないか



同じような心配を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか
発達障害児が利用できる!公共交通機関の支援制度



つい外出が億劫になってしまう…
そう思われている方も多いと思いますが、実は公共交通機関には、発達障害児とその家族が安心して利用できるよう、さまざまな支援制度が整備されています。知っているだけで、お出かけのハードルがぐっと下がるかもしれません。
優先席・多目的スペースの利用
多くの電車やバスには優先席が設けられており、発達障害児も利用の対象となっています。また、車両によっては車いす対応の多目的スペースがあり、こちらも利用可能です。
多目的スペースは通常の座席よりも広く、ベビーカーや大きな荷物も置けるため、感覚過敏の対策グッズを多く持参する必要がある場合に特に便利です。車掌や駅員に事前に声をかけておくと、より安心して利用できます。



筆者の娘は外の景色を見ることで気持ちが落ち着きやすいため、窓側の席を選んでいます
お客様サポートの活用
飛行機の場合は、航空会社のお客様サポートを利用できます。事前に確認しておくと安心です。
また、例えばANAでは、オリジナルパンフレット「そらぱすブック」で手続き方法や機内での過ごし方を予習・復習できます。搭乗から降機までの流れが写真付きで解説されているため、初めて飛行機に乗る場合や見通しが立っていないと不安な子どもにも安心です。
知的障がい・発達障がいのあるお客様向け飛行機搭乗のご案内_ANA
https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/flight_service_info/assist/disorders
障害者手帳や受給者証を提示することで受けられる障害者割引も使えるよ!詳しくはこちらの記事を読んでみてね
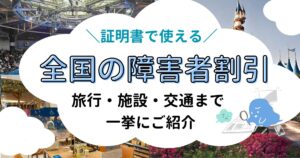
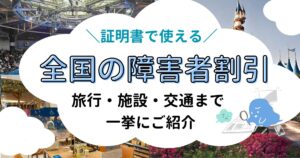
ヘルプマークの活用
ヘルプマークは、援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせるためのマークです。発達障害は見た目や外見からわかりにくいため、ヘルプマークを持つことで周囲の理解を得やすくなります。
ヘルプマークを活用すると、子どもが突然大きな声を出したり動き回ったりした際も「配慮が必要な子ども」として温かく見守ってもらいやすくなり、優先席を譲ってもらったり、パニック時に駅員や乗客から適切なサポートを受けやすくなります。
また、保護者自身も「周りに迷惑をかけているのでは」という心理的負担が軽減され、子どもへの対応に集中できるため、結果的に子ども自身も落ち着いて過ごしやすいのが特徴です。
▼ヘルプマークの入手方法や子どもに持たせるメリットは、こちらの記事からご覧いただけます
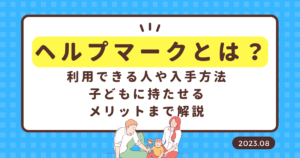
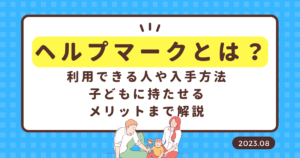
事前準備で安心!発達障害児と公共交通機関を利用する際のポイント



準備が大切なのはわかるけど、具体的にどんなことをしておいたほうがいい?
そんな疑問をお持ちの方へ、発達障害児が公共交通機関を利用する際に押さえておくと安心できるポイントをご紹介します。
視覚支援ツールを活用する
発達障害児にとって視覚支援ツールは、日常生活や学習において欠かせない「コミュニケーションの橋渡し役」のような存在です。言葉だけでは理解が難しい場合でも、視覚的に情報を示すことで、大幅に伝わりやすくなります。
例えば、以下のようなツールを用意しておくと安心です。
スケジュール表や絵カード
スケジュール表で出発から到着までの流れを写真やイラストで示すと、子どもは見通しを持って行動しやすくなります。「家を出る→駅まで歩く→切符を買う→電車に乗る→目的地の駅で降りる」など、一つひとつの行程を視覚化できるのが魅力です。
また、子どもが不安になったり混乱したりした際、言葉だけでは伝わりにくい状況を視覚的に説明するためには「絵カード」の活用もよいでしょう。「電車に乗る」「座って待つ」「静かにする」などの行動を絵で示すことで、子どもの理解が深まり、パニックを予防できます。周囲の人にも子どもの状況を伝えやすくなり、保護者の心理的負担も軽減されるためおすすめです。
▼絵カードの作り方などについては、こちらの記事をご覧ください
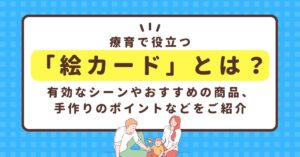
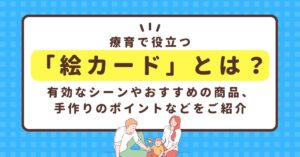
利用する乗り物の写真や路線図
実際に乗る乗り物の写真や路線図を事前に見せておくことで、当日の不安を軽減できます。「この電車に乗るよ」「ここの駅で降りるよ」と具体的に説明すると、子どもも心の準備が可能です。
タイマーやカウントダウンアプリ
発達障害児は視覚的な情報があると、時間の経過や移動距離をより理解しやすくなります。そのため「あと5分で着くよ」「あと3駅だよ」と、時間や距離の感覚を視覚的に示せるツールも有効です。スマートフォンのアプリを活用すれば、簡単に準備できます。


我が家では「キッズタイマー」というアプリで時間の進みを「見える化」しています
混雑する時間帯を避ける
感覚過敏がある発達障害児は、人混みの音や匂い、触れ合いなどの刺激が大きなストレスになり得ます。そのため、ラッシュアワーなどの混雑する時間帯はできるだけ避けてお出かけするのがおすすめです。



空いている時間帯は、子どもがリラックスして座れる席を確保しやすいのもメリットです!万が一パニックになった場合も、周囲への影響を最小限に抑えられます
対策グッズを持参する
感覚過敏への対処や安心感を得るために、以下のような対策グッズを準備しておくと安心です。
聴覚過敏への対策
乗り物の走行音やアナウンス、他の乗客の会話などが気になる子どもには、以下のグッズが効果的です。
- ノイズキャンセリングイヤホン
- 耳栓
- イヤーマフ



小さな音が気になる筆者の娘は、イヤーマフを常に活用しています
視覚過敏への対策
乗り物内の照明や外の景色の変化が気になる場合には、以下のグッズを活用してみましょう。
- サングラス
- 帽子
- お気に入りのぬいぐるみや本
触覚過敏への対策
座席の材質や人との接触が気になる子どもには、以下のグッズが適しています。
- お気に入りの毛布やタオル
- 感触のよいおもちゃ
- 座席に敷くクッション
その他気分がおちつくグッズ
- お気に入りの写真
- 小さなパズルや手遊びおもちゃ
- 好きなキャラクターグッズやお守り



「普段使っている愛着のあるもの」は、心を落ち着かせやすくなります
公共交通機関でパニックになった場合の対応は?
どんなに準備をしていても、予期せぬ出来事でパニックになってしまう場合があります。そんなときも冷静に対応できるよう、事前に対策を考えておきましょう。
緊急時の避難場所を確認しておく
電車内でパニックになった場合、まずは子どもと周囲の安全を確保することが最優先です。大きな駅や空港では静かなスペースが用意されていることが多く、子どもが落ち着くまでの避難場所として活用できます。以下の場所を事前に確認しておきましょう。
- 車両の端(デッキ部分)
- 多目的スペース周辺
- 乗務員室近く
- 駅事務室
- 比較的静かな休憩スペース
駅員や乗務員へ事前に相談する
できれば、乗車前に駅員や乗務員に「発達障害児と一緒に乗車する」と伝えておくと安心です。「子どもに発達障害があり、ときどきパニックになることがあります」と簡潔に説明するだけで構いません。
緊急時の連絡方法や、困った際にどこに行けばよいかなども教えてもらえる場合があります。
もしも乗務員が対応に慣れていなかった場合、「子どもは発達障害で、刺激に敏感なため混乱しています。少し時間をいただければ落ち着きます」と簡潔に説明しましょう。「静かな場所があれば移動したい」「大丈夫なので見守っていてほしい」「○分ほどで落ち着く予定です」など、必要な配慮と見通しを具体的に伝えると、乗務員も適切にサポートしやすくなります。
コミュニケーションカードを活用する
パニック時には保護者も動揺してしまいますよね。
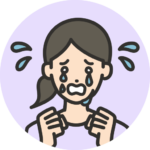
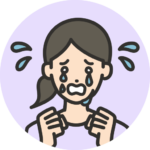
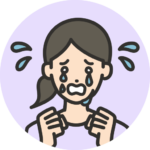
周りに迷惑かけないように早く落ち着かせなくちゃ



やっぱり外出は難しいのかもしれない…
など、焦る気持ちもあり、周囲への説明が難しくなるケースも少なくありません。そんな場合のために、子どもの特性や対応方法を記載したコミュニケーションカードを準備しておくと便利です。
▼カードに記載する内容の例
- 子どもの名前と年齢
- 発達障害の特性(「大きな音が苦手」「人混みでパニックになりやすい」など)
- 効果的な対応方法(「静かな場所に移動する」「好きな音楽を聞かせる」など)
- 緊急連絡先



このカードがあることで、周囲の人や駅員にも状況を理解してもらいやすくなり、適切なサポートを受けやすくなります
準備と工夫で広がる!発達障害児との外出の可能性
公共交通機関を利用できるようになると、さまざまな場所へのお出かけが可能になり、子どもの興味や関心を伸ばす機会も増えます。また、将来的な自立に向けた大切なスキルを身につけることにもつながります。
全てを一人きりで解決する必要はありません。事前の準備に加え、支援制度も活用しながら、ゆったり楽しくお出かけしてみてください。
障がい児とのお出かけ情報はこちらの特集をチェック!
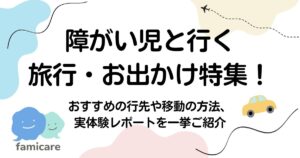
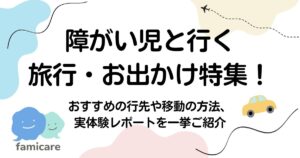


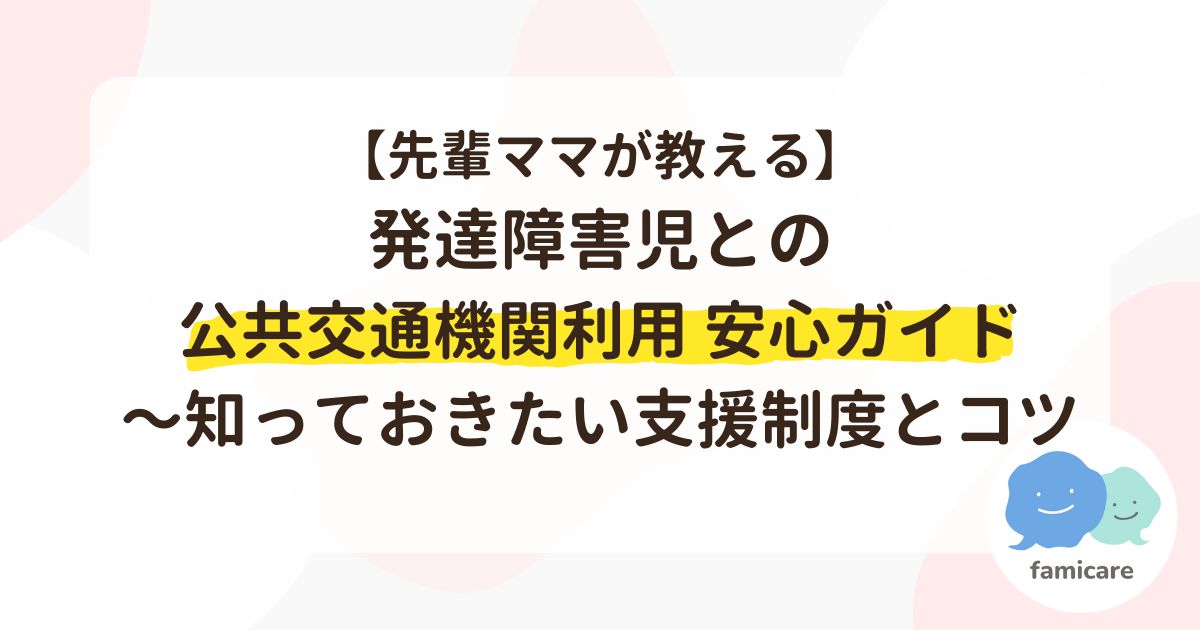

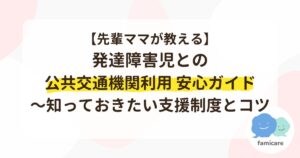

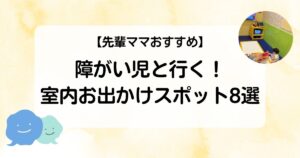
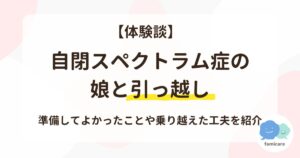
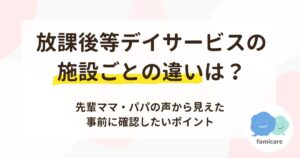

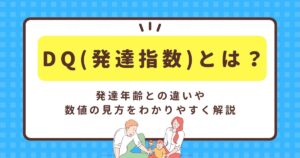

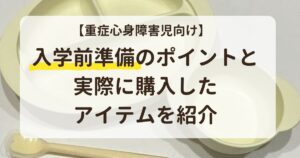

コメント