子どもが発達障害と診断された際「障害者手帳を取得すべき…?」と考えられる方も多いのではないでしょうか。障害者手帳の取得は支援を受けるための重要なステップですが、一方で懸念ポイントも存在します。
この記事では、発達障害で障害者手帳を取得するメリットとデメリットをわかりやすく解説していきます。

発達障害の子どもに障害者手帳を取得しようか迷っている
そのような方は、ぜひ参考にしてみてください。
障害者手帳とは?
障害者手帳は、障がいのある方々が支援やサービスを受けるための公的な証明書です。現在、以下の3種類に分類されています。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者福祉手帳
最近では、上記の3種類を「障害者手帳」とまとめて呼ぶ場合が多くなっています。障害者手帳があれば、障害者総合支援法によって定められたさまざまな支援制度を利用できるのが特徴です。
▼障害者手帳の詳しい役割やメリット・デメリットについては、こちらの記事からご覧いただけます
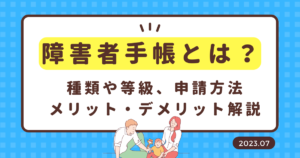
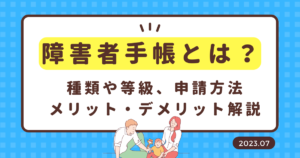
療育手帳とは?
療育手帳は、知的障害のある方に交付される障害者手帳です。発達障害のある方で、知的障害(知的発達症)を伴う場合に取得できます。
療育手帳の申請は診断の時期や年齢にかかわらず、対象となる条件を満たしていれば可能です。



一般的には10歳頃までに取得されるケースが多いものの、大人になってから発達障害の診断を受けた後に療育手帳を取得する方もいらっしゃいます。
▼療育手帳について対象者や申請方法を知りたい方はこちら
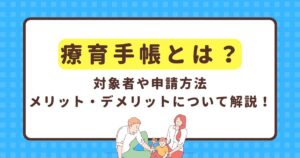
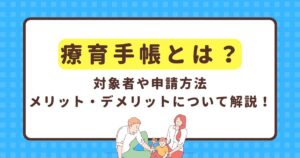
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳は、発達障害を含む精神疾患のある方が利用できる福祉サービスの証明書です。精神的な障害があることを公的に認定し、さまざまな支援を受けるための重要な手帳といえます。
精神障害者保健福祉手帳の交付の対象は「精神疾患があり、日常生活に長期にわたる困難や制限がある方」です。対象の条件として、診断を受けてから最低6か月以上経過していることを、診断書で証明する必要があります。



つまり、診断直後ではなく、症状の安定性や継続性が確認された後に申請が可能です
▼「発達障害のわが子は障害者手帳をもらえる?」と悩まれている方は、以下の記事もご覧ください
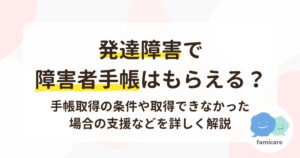
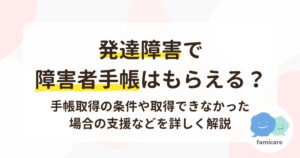
発達障害で障害者手帳を取得するメリットとデメリットって?
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の違いはなんとなくわかったけど、手帳を申請することのメリットは?デメリットもあるの?
そう感じている方に向けて、障害者手帳を取得すると受けられる支援、そして考慮すべき点について詳しくみていきます。
発達障害で障害者手帳を取得するメリット
障害者手帳を持っていることで受けることのできる主なメリットを紹介します。なお、手帳の種類や等級によっては利用できない場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
経済的な支援を受けられる
障害者手帳を持っていると以下のような支援を受けられる可能性があります。
・特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを、在宅で育てている保護者に支給される。
▼特別児童扶養手当について詳しくはこちらの記事で解説しています
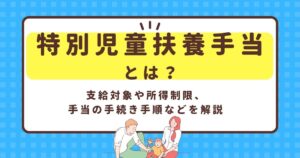
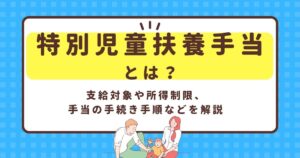
・心身障害者扶養共済
障がいのある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった際などに、障害のある方に対して一定額の年金が一生涯支給される
・税制の優遇
所得税や住民税、相続税などの控除、自動車税の減免など
・医療費の助成
・公営住宅への優先的な入居
・NHKの受信料免除
・公共交通機関の利用運賃の割引
・美術館、博物館、プール、動物園など公共施設利用料の割引
・携帯電話の基本料金の割引



日常生活の経済的負担が軽減されるのは、長い目でみても大きな恩恵です。自治体や障がいの等級によって異なるため、詳細はお住まいの自治体などにお問い合わせしてみてください
生活面でのサポートを受けられる
障害福祉サービスとして、居宅介護やショートステイ、移動支援などのサービスを利用できるのもメリットです。また、グループホームなどの居住系サービスも利用できます。将来的な住まいの選択肢が広がることは、子どもにとってもご家族にとっても大きな安心ですよね。
さらに、福祉サービスの利用手続きの援助や日常的な金銭管理のサポート、重要書類の預かりなど「日常生活自立支援事業」を受けられるのも利点です。



自立した生活を送りながらも必要な部分でのサポートを受けることができ、日常生活の負担を軽減できます
就労支援を受けられる
障害者手帳を持つと、将来、就職活動の可能性が大きく広がります。例えば、ハローワークの専門窓口で障害特性に合わせたきめ細かな就職支援を受けられるのは大きなメリットでしょう。
さらに、障がい者雇用枠のある企業への就職、就労継続支援事業所での就労など、これまで難しかった職場への道が開かれるのも利点です。



職場での合理的配慮や個別の支援を受けやすくなり、自分の能力を最大限に発揮できる環境づくりをサポートしてもらえます
発達障害で障害者手帳を取得するデメリット
生命保険への加入が難しくなる場合がある
保険会社によっては、障害の程度や種類によって加入を制限したり、特定の疾病において保険金や給付金の支払いを免除したりするケースがあります。ただし、近年は障がいのある方向けの保険商品も増えてきており、すべての加入が難しくなるわけではありません。
なお、すでに加入している保険に関しては、後から障害者手帳を取得しても既存の契約には影響しない場合がほとんどです。
住宅ローンが組めない可能性がある
療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていると、金融機関によっては住宅ローンの審査が厳しくなる可能性があります。特に団体信用生命保険(団信)への加入が条件となっている住宅ローンでは、生命保険と同様に制限がかかるケースも珍しくありません。
しかし、最近では障害のある方向けの住宅ローン商品や、公的な住宅融資制度も充実してきています。自治体によっては、障害者向けの住宅資金貸付制度を設けているところもあります。
「障がい者を証明するもの」と感じる方もいる
障害者手帳の取得をためらう理由として「障がい者というレッテルを貼られることへの抵抗感」を挙げる方もいます。わが子のアイデンティティの問題として、あるいは社会からの差別や偏見を懸念して、手帳取得に心理的な壁を感じる方もいるでしょう。
しかし障害者手帳は、自ら見せたり話したりしない限り他人に知られることはありません。プライバシーは守られるため、開示するかどうかは本人の自由です。



「障がい者」という言葉が子どもを縛ってしまわないか、そんな不安を持ってしまいますよね。どんな選択も、わが子の幸せを一番に考える深い愛情から生まれているものです。
療育手帳や精神障害者保健福祉手帳はどのように申請したらいい?
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請には、それぞれ以下のものが必要です。
療育手帳の申請
お住まいの地域の児童相談所(18歳未満の場合)または知的障害者更生相談所(18歳以上の場合)での判定が必要
▼療育手帳の詳しい申請方法については以下の記事からご覧いただけます
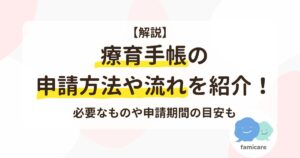
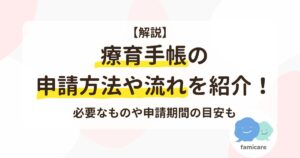
精神障害者保健福祉手帳の申請
精神科医による診断書が必要。療育手帳のような特別な検査は必要ないものの、発達障害の診断を受けているのが前提。
なお、申請の具体的な手順や必要書類は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉課や保健センターなどに事前に相談するのがおすすめです。
手帳の取得は子どもの可能性を広げるための大切な選択肢
障害者手帳は「障がい者というレッテル」ではなく、より豊かな生活を送るための「サポートツール」です。周囲の人に開示する必要はまったくなく、必要でなくなった場合はいつでも返還できます。
適切な支援を受けることで、より自分らしく生きるための選択肢が広がるとも考えられるため、デメリットは大きくないといえるでしょう。わが子の障害者手帳の取得に迷われている方は、子どもの主治医や発達障害者支援センターの相談支援専門員、自治体窓口にも相談しながら検討してみてください。
障害者手帳を取得してよかったエピソードや不安な気持ちなどの声は、ファミケア公式SNSまたは公式アプリから聞かせてね
【参考】
特別児童扶養手当について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
障害者扶養共済制度(しょうがい共済)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000195619.html
障害者と税|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm
ここが知りたい日常生活自立支援事業|全国社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/news/kako/materials/100517/nshien_1.pdf


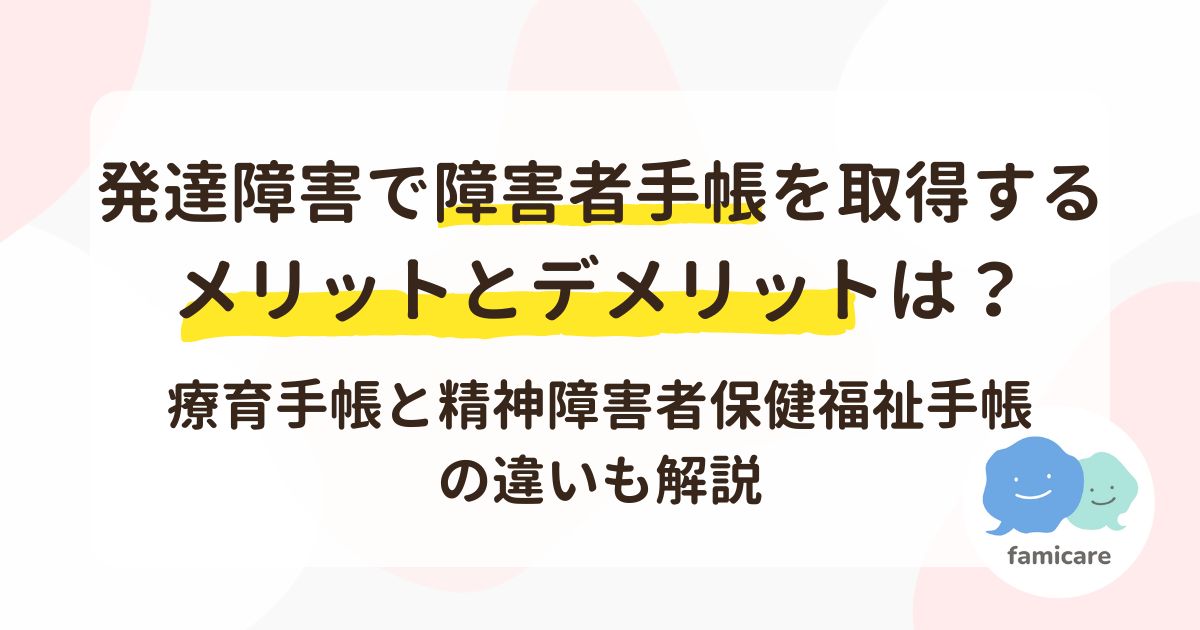

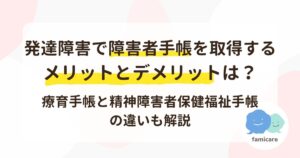

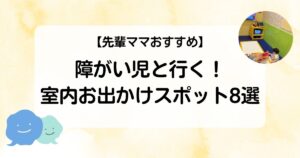
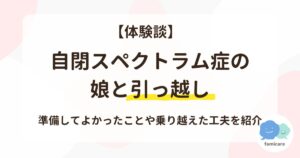

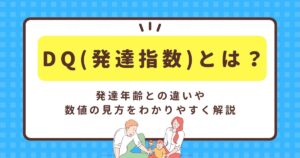


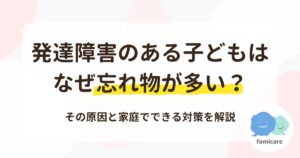

コメント