療育手帳とは、愛の手帳や緑の手帳とも呼ばれ、知的障害のある方に交付される障害者手帳のことです。
そもそも療育手帳って何?



申請するとどんなメリットがあるの?
など「療育手帳についてよく知らない」という方も多いと思います。
この記事では、子どもの療育手帳を取得した経験のあるママが療育手帳とは何か、対象者や申請方法、メリット・デメリットについて紹介していきます。
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障害のある方に交付される障害者手帳の1つです。療育手帳を取得することで税制上の優遇や手当の受給、公共交通機関の割引などができるようになります。
療育手帳は地域によって、さまざまな呼び方をされていますが、受けられるサービスや内容は同じものです。
療育手帳以外の地域ごとの呼称は以下です。呼び方は違っても同じものを指しています。
| 愛護手帳 | 青森県、名古屋市 |
| 愛の手帳 | 東京都 |
| みどりの手帳 | さいたま市 |
▼障害者手帳の詳しい内容や他の障害者手帳はこちら
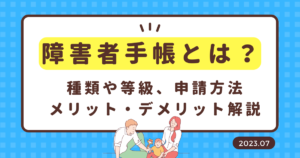
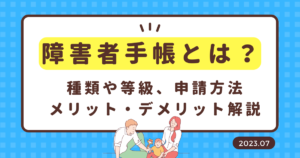



療育手帳は3歳児検診や小学校入学のタイミングで取得することが多くなっています
療育手帳の対象者
療育手帳の取得対象者は知的障害のある方です。厚生労働省は“児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された方に交付される”と定義しています。
【参考】障害者手帳について|厚生労働省
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
療育手帳を取得できる年齢は原則18歳までですが、厳密な年齢制限はなく、18歳以上でも申請することが可能です。
ただし、18歳以上で申請をする場合は「18歳より前から知的障害が生じていた」ことを証明する必要があるため、手続きが複雑化する場合があります。
また、他の障がいがある場合や障害者手帳を保有している場合もあわせて取得が可能です。たとえば、発達障害のある方で、知的障害を伴う方は療育手帳を取得できる可能性があります。
また、療育手帳と精神障害者保険福祉手帳の対象は異なるため、療育手帳の対象外であっても、精神障害者保健福祉手帳の対象になる場合があります。
知的障害を伴う発達障害のある方は、各自治体窓口に相談してみると良いでしょう。
療育手帳の等級と判定基準
療育手帳には等級があります。等級とは、知的障害の程度をあらわす区分のことです。
等級は大きくA(重度)とB(中軽度)に分類されます。
等級の判定基準は、厚生労働省が定めるガイドラインをもとに各自治体の運用によって決められています。厚生労働省が定める等級の判定基準は以下の表です。
多くの場合で発達検査(知能検査)の結果でわかる知能指数などを基準に判定されます。
- 重度(A)の基準
- 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
- 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
- 異食、興奮などの問題行動を有する。
- 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
- 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
- それ以外(B)の基準
- 重度(A)のもの以外
【参照】療育手帳制度の概要(PDF)
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001224062.pdf
▼発達検査や知能検査については詳しくこちらの記事で解説しています


自治体によってはA、Bをさらに2段階に分ける場合もあります。また、名称をA1、A2…と表す場合もあれば、1級、2級…と数字で表す自治体もあります。
東京都の場合では、18歳以上の判定基準が以下の表のような等級と判定基準になっています。
| 1度(最重度) | 知能指数(IQ)がおおむね19以下で、生活全般にわたり常時個別的な援助が必要な状態。 |
| 2度(重度) | 知能指数(IQ)がおおむね20から34で、社会生活をするには、個別的な援助が必要な状態。 |
| 3度(中等度) | 知能指数(IQ)がおおむね35から49で、何らかの援助のもとに社会生活が可能 |
| 4度(軽度) | 知能指数(IQ)がおおむね50から75で、簡単な社会生活の決まりに従って行動することが可能です。 |
【参照】対象者(愛の手帳Q&A)|東京都福祉局
URL:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/faq/techo_qa/taishou.html
児童の場合は発達の過渡期にあるため、18歳以下で一律の基準はありません。たとえば、3歳児と10歳児では発達段階が全く異なるため、同じ尺度で判定することは困難です。そのため、年齢に応じて異なった基準で等級を判定しています。
18歳以下の等級判定として具体的には、遠城寺式乳幼児発達検査や新版K式発達検査を用いて発達指数(DQ)を算出します。
算出した発達指数(DQ)を判定材料に、日常生活の様子や介助の必要度も加味して総合的に等級が判断されます。
18歳以下の場合は自治体によって判定基準が異なることが多いので、手帳を取得する時に説明を受けよう!
療育手帳の申請方法と流れ
療育手帳は申請に必要な書類を用意し、申請と検査を受ける必要があります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人写真(縦4㎝×横3㎝ 1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーカード
※場合によっては医師の意見書が求められることがあります。



筆者の住む自治体では、3歳未満の子どもの申請は医師の意見書が必要でした。
申請手順
- 自治体窓口(児童相談所等)で申請をする
- 発達検査の予約をする
- 発達検査を受ける
- 判定、交付
療育手帳を取得するメリットとデメリット
療育手帳を取得すると、税金の控除やサービスを利用する際の障害者割引を受けることができます。メリットデメリットや受けられるサービスについて、一部紹介していきます!
療育手帳を取得するメリット
税制上の優遇が受けられる
控除や減免など税金の面で優遇を受けることができます。
障害者控除
療育手帳を取得すると、所得税・住民税の控除を受けることができます。更にA判定であれば特別障害者として控除の金額が大きくなります。
年末調整、もしくは確定申告時に申請が必要です。
自動車税の減免
判定によっては自動車税の減免を受けることができます。家族が所有する車であっても、障害者本人の移動のために使用する車であれば対象です。
手当をもらうことができる
療育手帳の取得によって特別児童扶養手当を受給することができます。
また、判定によっては障害児福祉手当(20歳未満)、特別障害者手当(20歳以上)を受給できる可能性があります。
各種障がい者割引を受けることができる
公共交通機関や民間事業者の提供するサービスの割引を受けることができます。
公共交通機関の割引
| バス | 基本的に運賃5割額 |
| 電車(JRの場合) | ・1人で乗車する場合 第1種・第2種ともに対象(片道100kmを超える場合に限る)普通乗車券に限り運賃半額 |
| ・介助者同伴の場合 第1種の場合利用距離にかかわらず、本人と介助者1名が運賃5割引対象は普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 第2種で12歳未満の場合定期乗車券(小児定期乗車券を除く)が5割引 | |
| タクシー | 基本的に運賃1割引 |
| 飛行機(JAL) | 本人及び介助者1名の運賃が2割引※本人が3歳未満で席を利用しない場合は介助者も対象外 |
| 旅客船 | 基本的に運賃5割額 |
※移住地や使用する交通機関によって、割引率や対象者が異なる場合があります。
公共料金の割引
| NHK受信料 | ・全額免除世帯員のうち誰かが障害者手帳を持っており、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合。 ・半額免除世帯主、かつ受信契約者が一定の障害を持つ場合。(療育手帳では重度、最重度の場合) |
| 携帯電話 | 携帯電話料金の割引が受けられる。携帯会社によってプランや割引率は異なる。 |
| 高速自動車道走行料金 | ・第1種の場合通常料金、ETC料金ともに半額。基本的に事前登録した自動車のみが対象。 ※自治体窓口で自動車の事前登録が必要。併せてETC利用申請も行うことができる。 |
施設の利用割引
ディズニーランドやUSJなどのテーマパークのほか、美術館やアミューズメント施設など様々な施設が障害者割引を適用しています。
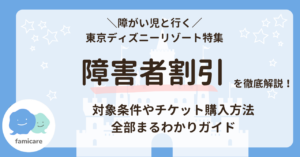
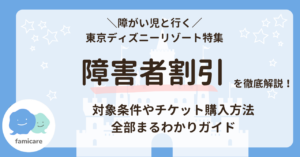
そのほかにもホテルや旅館などの宿泊施設で割引が受けられることがあります。
就労支援を受けることができる
療育手帳を持っていれば、障害者雇用で就職することができます。障害者雇用で働くことで、障害の特性に応じた支援を受けやすくなります。
また、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労定着支援」といった、障害のある方を対象とした支援が受けやすくなります。
これらは障害者手帳を取得していなくても要件を満たせば対象となりますが、療育手帳を取得していれば、障害があることの証明になるためスムーズに支援につなげることができます。
療育手帳を取得するデメリット
療育手帳を取得することで不利益を受けることは特にありません。療育手帳は使用するとき以外は提示の必要もなく、所持していることを誰かに知られることもありません。
無料で申請することができ、交付を受けた後にもし不要となれば返還することも可能です。
強いて言えば、特に軽度知的障害の方ですと、成長につれて「療育手帳を持っている」という事実が本人の自尊感情を傷つける…といった可能性は考えられます。また、親御さんにとっても自分の子どもを「障がい者だと認める」ことがつらい…といった気持ちもあるかもしれませんね。



筆者も息子が療育手帳を取得した当時は、複雑な思いがありました。ですが、手帳を取得したからと言って息子がかけがえのない存在であることに変わりなく、すぐに気にならなくなりました。メリットが大きく、助けられています。
療育手帳を活用しよう
療育手帳を取得すれば障がいの証明となるだけでなく、金銭的にも生活の上でも多くの支援を受けることができます。
街で障害者割引などを利用する際には療育手帳の提示が必要なため、持ち歩いて利用しましょう。サイズが大きめな紙タイプの持ち歩きが大変な人は、障害者手帳を電子化できるアプリもあります。
▼ミライロIDとは?


日々の障害児育児で使える制度はうまく活用して、負担を軽減していきましょう!

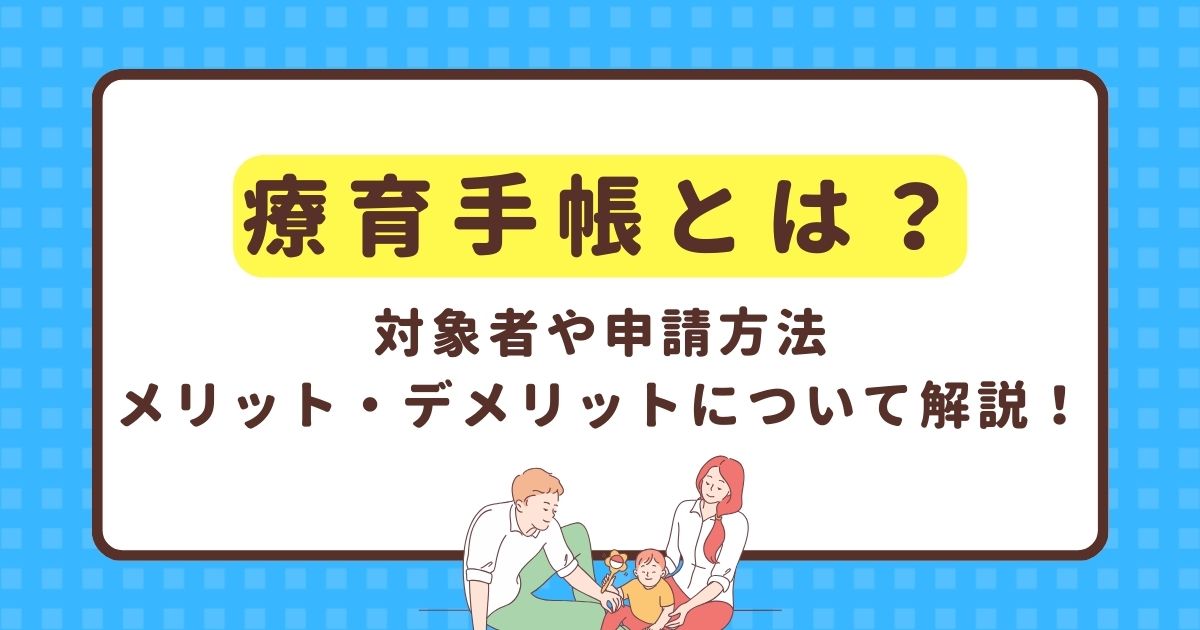
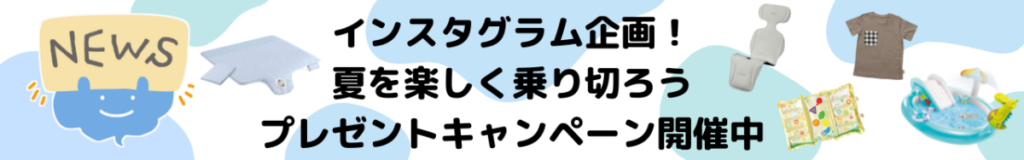

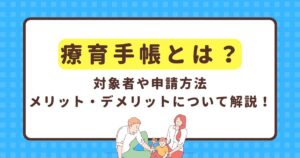

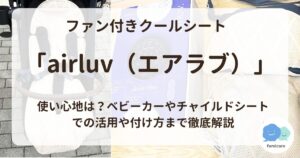
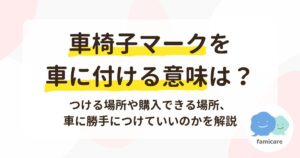
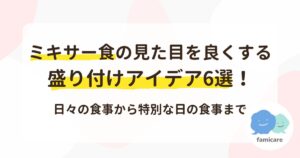

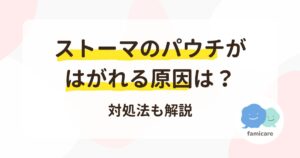
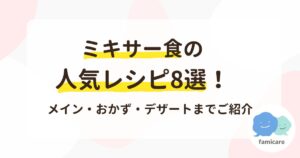
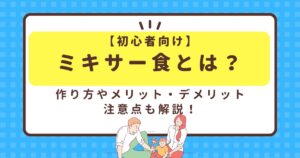
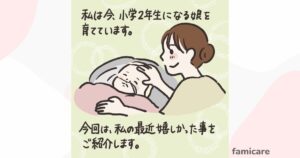
コメント