たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な子どものうち、運動面での障がいがなく、歩いたり走ったりできる子どものことを「動ける医療的ケア児(医ケア児)」と呼ぶことがあります。
歩ける・走れるなど子どものできることが多いことは喜ばしいですが、実は「利用したい制度の対象外になる」など独自の問題や生きづらさを感じることもあるのです。
そこで今回の記事では、「動ける医療的ケア児」を育てている筆者が、動ける医ケア児とはどんな子どものことなのか、抱えやすい問題や筆者の経験談をご紹介します。
▼医療的ケア児についての解説はこちら
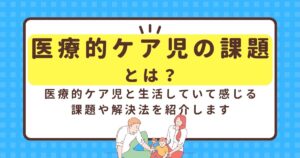
動ける医療的ケア児(動ける医ケア児)とは
「動ける医療的ケア児(動ける医ケア児)」とは、日常生活に医療的ケアが必要な子どもの中でも、歩行やその他の運動が自由にできる状態の子どもを指します。「動ける医療的ケア児」の他に「動く医療的ケア児」や「歩く(歩ける)医療的ケア児」という表現が使われることもあります。
動ける医療的ケア児の中には、知的発達に遅れがない子どもや、身体障害者手帳の交付対象にならない子どももいます。
「動ける医療的ケア児」の定義ははっきりとは決まっていませんが、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定では、医療的ケアの判定スコアが設けられ、その中の「見守りスコア」によってこれらの状況が客観的に評価されることになりました。
「見守りスコア」とは
医療的ケアが必要な子どもたちを評価する際に設けられている医療的ケア判定スコアには、「見守りスコア」という項目があります。これは、動ける医療的ケア児が自発的に動いた時に、装着されている医療機器の作動等を妨げる可能性があるかどうかを評価するものです。
【参照】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について|厚生労働省
動ける医療的ケア児の人口
現在、動ける医療的ケア児の全体数について正確なデータは報告されていません。動ける医療的ケア児の定義についても現状は曖昧なため、実数の把握も困難です。
ただ、医療的ケア児の中での「動ける医療的ケア児」の割合は2020年の厚生労働省による調査で報告されています。アンケートによると「歩くことができる」は17%、「走ることができる」は13.4%という結果が出ています。また、「背ばい・腹ばい・四つんばいができる」子どもは21.5%おり、4割近くの子どもが自ら移動可能であることが示されています。
 ライター あやこ
ライター あやこ仮に「移動可能な医療的ケア児」を「動ける医療的ケア児」と定義すると、かなりの数の子どもが該当します。それにも関わらず、制度が追いついていないのは社会的に大きな壁です。
それに加え、身体障害者手帳を「保有していない」と回答した医療的ケア児の割合は11%でした。
【参照】医療的ケア児者とその家族の生活実態調査報告書|厚生労働省
医療的ケア児はこれまで、知的障害と肢体不自由が重複する重症心身障害児(重症児)が多数でした。一方で医療が進歩し、気管切開や胃ろうなどの手術をしていても自由に動ける子どもの数は増加傾向にあります。
障害者手帳を持っていないケースがあることも、全数把握が難しい理由の一つなんだ。
動ける医療的ケア児が抱えやすい問題
動ける医療的ケア児やその家族は、子どもが動けるからこその独自の問題を抱えてしまうことがあります。
制度の狭間に陥る
福祉サービスについては障害者手帳の有無で必要性が判断されることも多いため、手帳がないからと各種福祉サービスの対象外になったり、手帳があっても歩行が可能という理由で放課後等デイサービスやショートステイなどの受け入れを断られたりするケースもあります。自由に動けるが故に安全性の確保が難しいという理由で、レスパイトなど家族以外に預けられる場所の選択肢が少ないという地域も多いです。
支援のための調整が負担になる
医療的ケアが必要でありながら動ける子どもの場合、放課後等デイサービスなどの受け入れ先等が見つからないことが多く、そのため関係各所への交渉や調整が大きな負担になることがあります。抱えている困りごとがなかなか理解されず、何度も行政窓口や事業所へ足を運ばなければならないことが日常茶飯事です。
動くことによる注意が必要
制度的な問題以外にも、動くこと自体が医療機器の抜去などの危険に繋がります。そのため、ケアの負担が増えることがあります。
子どもを追いかけながらケアをすることがある
特に乳幼児の場合、医療的ケアの途中にも、歩いたりハイハイすることがあります。時には注入ボトルや酸素ボンベといった重い医療的ケアグッズを持って追いかけることも。移動中は、何かにひっかかって医療機器が外れないか、またチューブに足をひっかけて子どもが怪我をしないかなど常に安全性に気を付けないといけません。
自分で医療機器を触ってしまう
自由に歩いたり手足を動かすことによって、身体に付いている医療機器に自ら触れて外してしまう危険があります。すぐに触れないようにしたり、本人に触ってはいけないことを繰り返し伝えるといった工夫が必要です。見守りの程度や必要性については、前述した医療的ケア判定スコア内の「見守りスコア」で評価されます。



筆者の息子は癇癪が起こると胃ろうボタンを引っ張ってしまうことがあり目が離せません。見守りスコアは高中低の3段階評価のみなので、見守りの説明をする時には、具体的にどんな時にどのような動きに注意が必要かをきちんと支援者と共有する必要があります。
他の子どもとの接触がリスクになることも
保育園などで同じように自由に動く子どもたちの中で過ごす環境では、子ども同士の接触が必然的に多くなります。子どもたち同士は医療機器が大切なものであること、いたずらに触れてはいけないことをよく理解できるものの、突発的な事故には注意しなければいけません。



我が家では、妹が胃ろうの接続チューブを握ったタイミングで親が抱っこしてしまい、その拍子に胃ろうが抜けてしまった事件がありました。活発に動く子ども同士が同じ空間にいると、思わぬことが起きることがあります。
動ける医療的ケア児を育てる親の気持ち
動ける医療的ケア児を育てる筆者の経験を踏まえた親としての気持ちを紹介します。
息子の情報
- 年齢:7歳
- 状態:重度知的障害、歩行可能
- 障害者手帳:療育手帳A(障害者手帳は無し)
- 必要な医療的ケア:胃ろう
子どもの状態を説明することが難しい



息子を育てていて一番に感じることは「息子の状態を説明するのが難しい…」ということです。
障がい児を育てている方の多くは、支援者や役所の窓口などで子どもの状態を説明する場面が多いと思いますが、我が家の場合も同様です。そしてこの説明がとても難しいといつも感じています。
特に「医療的ケアがある子どもが歩く」ということがどんな困難な状況を生み出しているのかを一から説明することや、動くこと特有の配慮についての説明はとても複雑です。
「うちの子の状態はこうです!」と一言で説明できる言葉や「身体障害1級」などの明確な区分が無いことも、説明が難しい理由の一つです。「医療的ケア児」という言葉の存在にはとても助けられていますが、さらに前進して「動ける医療的ケア児」という言葉や存在がもっともっと社会に浸透して欲しいと切実に思います。
サービスが利用できないことがとても多い
これまで新しい福祉サービスを検討するたびに「利用できません」や「対象ではありません」と言われることがとても多かったです。役所の窓口や事業所への問い合わせで断られることに少し慣れを感じるほど。
だからこそ、自分たちの状況や困りごとをきちんと訴えていく必要性を常に感じています。保育園に入れない、レスパイトが使えない、放課後等デイサービスが見つからないなど、利用したいと思うサービスを断られる度に、これを「当たり前」にしてはいけないという想いが湧き上がります。



筆者のファミケアでの活動意欲の根源は、「この状況を変えたい」という気持ちも大きいです。
サービスを利用したい時は、まずは相談と交渉が大切
それでも全てにおいてどうにもならなかったのかというとそうではなく、これまで様々な形で周りの方に助けられてきました。
事業所のウェブサイトなどで対象から外れていることが明記されていても、直接問い合わせてみたら検討してくれる事業所があったり、支援者の方が代替案を提示してくれたりということもありました。



一人で悩まず、まずは相談をしてみることが大切です。でも、問い合わせや交渉は精神的に負担が大きいので、無理のない範囲で進めていきましょう。
動ける医療的ケア児の課題解決の第一歩は、存在を知ってもらうこと
医療的ケアが日常的にありつつも、歩くことができたり、障害者手帳の交付対象ではなかったりするケースのある動ける医ケア児には、社会的な課題が複数あります。
「動ける医療的ケア児」という存在についてはまだまだ知られておらず、当事者家族からの丁寧な説明と訴えが必要不可欠です。
まずは「いわゆる動ける医療的ケア児」の“いわゆる”という言葉が早く外れて、多くの人の共通認識になって欲しい。そう筆者は願っています。


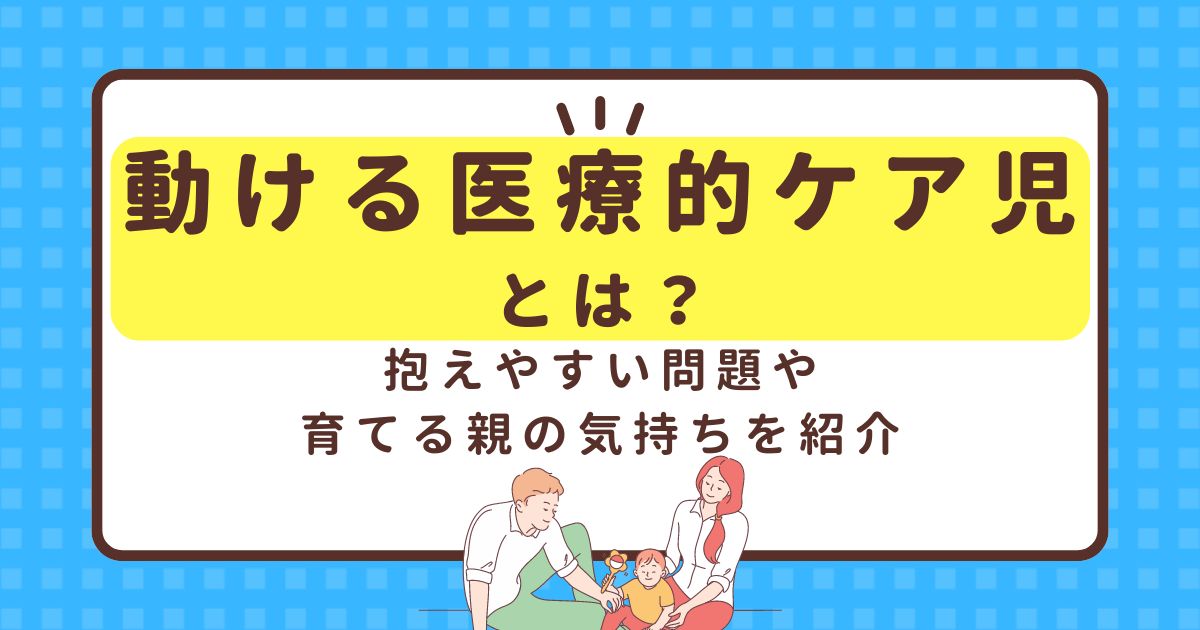

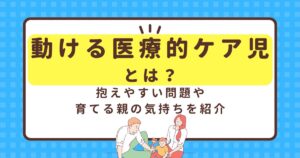

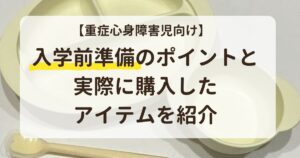

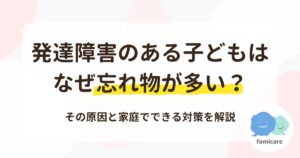


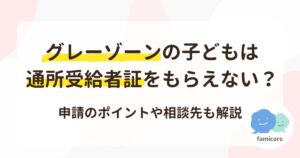
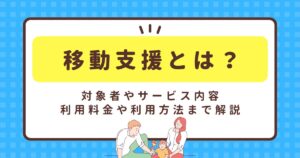
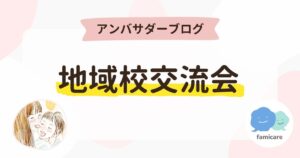
コメント