七五三を迎える年齢の子どもを育てている方の中には、
うちの子の七五三どうしようかな・・・
という方もいるのではないでしょうか。
「どんな着物を選ぶ?」「写真撮影はどうしたらいい?」など、疑問も浮かびますよね。
そんな迷いや不安を抱えるご家族に向けて、この記事では衣装の選び方、写真撮影や神社参拝の準備、当日の過ごし方など、七五三を安全で快適に楽しむための工夫を紹介します。
読んだあとに「わが家なりの七五三でOK」と安心して一歩を踏み出せるようになっていただけたら嬉しいです。
筆者やファミケアメンバーの経験談も交えながら紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
まずは七五三のプランを立てよう
障がい児の七五三は、前もって準備しておくことが大切です。情報を集めて、子どもや家族の負担が少ない安心できるプランを考えてみましょう。
神社でのお参りや写真撮影、家族での食事会などさまざまな要素がありますが、それらを全部やらなければいけないわけではありません。子どもの体調などに合わせて写真撮影だけする、撮影とお参りで別日にするなど、一般的な形にこだわらず“我が家流の七五三”でOK。無理のないプランを計画しましょう。
衣装と着付けはどうしたらいい?
華やかな衣装は七五三の楽しみのひとつ。でも「子どもに負担にならないかな?」と心配になることもありますよね。無理なく着られて心地よい衣装を選ぶことで、子どもも家族も安心して過ごせます。
衣装を選ぶときのポイント
衣装を選ぶポイントを以下に挙げました。
- 着脱のしやすいもの
着替えが簡単だと子どもの負担が減ります。例えば、紐ではなく、マジックテープでとめるタイプの着物や車椅子に乗ったままでも着脱できるセパレートタイプの着物もおすすめです。
- 快適さと安全性
動きやすく締めつけが少ない衣装なら、子どもも無理なく過ごせます。特に医療機器やチューブ類、装具を使用している場合は、圧迫や引っ掛かりを避けられるようにゆったりしたデザインを選ぶと安心です。
- 選択肢を広く持つ
着物にこだわらず、着脱しやすい洋服や普段着をアレンジして特別感を出すのもよいでしょう。写真は和装、参拝は洋装などシーン別に使い分けるのも一つの選択肢です。
- かわいさも忘れずに
機能性を優先しつつ、子どもらしい華やかさや特別感のあるデザインを選ぶと子どもも親も気分が上がります。
衣装選びに迷ったら、着物屋やレンタルショップ、写真撮影をするスタジオのスタッフが、子どもの状態や希望に合わせてアドバイスしてくれることがあります。



我が家は自作の下駄スリッポンを履きました。途中で脱げることもなく、履きやすかったのでおすすめです!




着付けの注意点やポイント
着付けの際には、以下のポイントを事前に打ち合わせをしておくと安心です。
- 安全面の注意点
人工呼吸器や経管栄養など、医療的ケアがある場合は共有しておきましょう。締めつけを避ける、チューブが引っ張られないようにするなど、注意点を伝えておくと、着付けをする側も安心です。
- 着付けをするときの姿勢
子どもの状態によって、着付けの方法を相談しておくと良いでしょう。保護者が支えながらなら立って着るのか、座ったり寝たりしたままでも着られるかなど、前もって確認しておくと当日も落ち着いて進められます。



私は着付けのことが心配で、着付けてもらう予定の写真撮影スタジオにあらかじめ問い合わせました。「ご両親に手伝ってもらうことがあるかもしれないですが、特に問題ないですよ」と言われて拍子抜けしたのを覚えています。うちの子は支えれば立てる子なのですが、本人が楽に過ごせるように寝転んだまま着付けていただきました。締め付けすぎないようにしていただき、ありがたかったです。
写真撮影はどうする?
衣装を整えたら、次に考えたいのは写真撮影です。撮影場所や方法によって子どもの負担は変わります。無理のない撮影スタイルを選ぶことが笑顔を残すポイントです。
写真撮影の方法を決める
まずは写真撮影の方法を決めましょう。撮影方法は大きく分けて以下の2つです。
- スタジオで撮影
スタジオで撮影する場合のメリットは、衣装のレンタルや着付けまで一括でお願いできることです。デメリットは、移動や待ち時間で子どもに負担がかかる場合もあることです - 個人のフォトグラファーに頼む
自宅や自宅近くなどで、子どものペースに合わせて落ち着いて撮影できるのがメリット。デメリットは、衣装や着付けを別に手配する必要があったり、設備が限られるため仕上がった写真の印象が異なったりする場合があることです。
▼障がい児の写真撮影におすすめなカメラマン・スタジオの情報はこちらの記事から
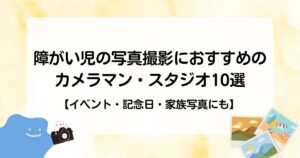
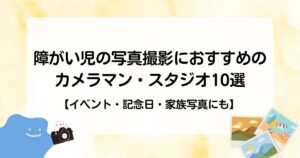
必要なサポートを事前に伝える
子どもの状態や必要なサポートについて、撮影希望のスタジオやフォトグラファーに事前に相談しておくとスムーズです。
障がい児の撮影経験があると、医療機器の写り方や、車椅子でも映えるポーズ、お子さんの状態に配慮した撮影方法を提案してくれるかもしれません。もし障がい児対応が明記されていなくても、あらかじめ要望をお伝えすれば個別対応していただけることも多いです。



我が家が写真撮影をしたスタジオは障がい児対応とは記載されていませんでしたが、ご経験はあるようで慣れている様子でした。立てない我が子が椅子に座ったかわいい写真を撮っていただきました。




お参りの神社はどこにする?
お参りする神社を決めるときは、段差やスロープの有無、多目的トイレの有無を確認しておくとよいでしょう。また、駐車場から境内の移動は、距離が短い方が安心です。
車椅子を使用している場合、路面の状況も確認しておくとスムーズです。祈祷場所に車椅子のまま入れるかどうかも事前に問い合わせておくのをおすすめします。



事前に問い合わせた際に、祈祷場所の入り口で車椅子のタイヤを拭き上げるタオルを持参するよう依頼された方、車椅子のタイヤにかぶせる「タイヤカバー」を準備していったという方も。
- 医療的ケアを行う場所の確認
医療的ケアを行う場合は、どこで行うのか想定しておくと安心です。待合室などのスペースがあるのか、ある場合はプライバシーがどの程度保たれるのか確認します。ケアを行う場所がない場合、車内で対応するのも選択肢です。
- 混雑や待ち時間
人が多い時間帯を避けると、子どもも家族も落ち着いて過ごせます。祈祷を受ける場合は予約が必要なこともあるので、確認しておきましょう。



神社のホームページなどを確認してみて、わからなければ直接神社に問い合わせましょう。もしお近くであれば、現地に下見に行くのもよいですね。
当日を安心して楽しむために
衣装や撮影、参拝の準備が整ったら、あとは当日をどう過ごすかがポイントです。子どもの体調やペースを最優先に、無理のない一日になるよう工夫していきましょう。
体調管理と持ち物の準備をしよう
体調管理に気を付けていても、いざ当日に体調がすぐれないこともあるかもしれません。当日を楽しむために、少しでも体調が優れない場合は無理をせず、日を改める勇気を持つことも大切です。
医療的ケアが必要な場合、使用する物品や医薬品など、忘れないようにあらかじめ用意し、持ち運びやすいバッグにまとめておくとスムーズです。
時間的余裕を持って無理ないスケジュールに
お子さんの体調やペースに合わせて、医療的ケアの時間などを考慮して無理のないスケジュールを組むと安心です。参拝、写真撮影、食事会など、それぞれのイベントを短時間で終えられるよう計画するのもよいでしょう。
祖父母も参加する場合は、親だけでなく祖父母とも役割分担することをおすすめします。場合によっては訪問看護師やヘルパーさんに、七五三の日の付き添いを相談してもよいかもしれません。



我が家は写真撮影とは別日に短時間でお参りをすませました。負担が少ないように家から一番近い神社で、着付けの必要がない洋装で行きました。写真撮影は和装でしたが、お参り当日のスナップ写真は洋装で撮れたので、これも記念になりました。
形にとらわれず、わが家らしい七五三の思い出を残そう
七五三は子どもの成長をお祝いする大切な節目です。障がいがある子どもでも、事前の準備や工夫をすれば、安心して楽しむことができます。
形にとらわれず、お子さんや家族に合った方法を選んで大丈夫。大切なのは「子どもの成長をみんなで喜ぶ気持ち」です。
衣装や写真撮影、参拝の方法などに配慮しながら、それぞれの家庭に合った形で、家族みんなの笑顔あふれる思い出をつくりましょう。


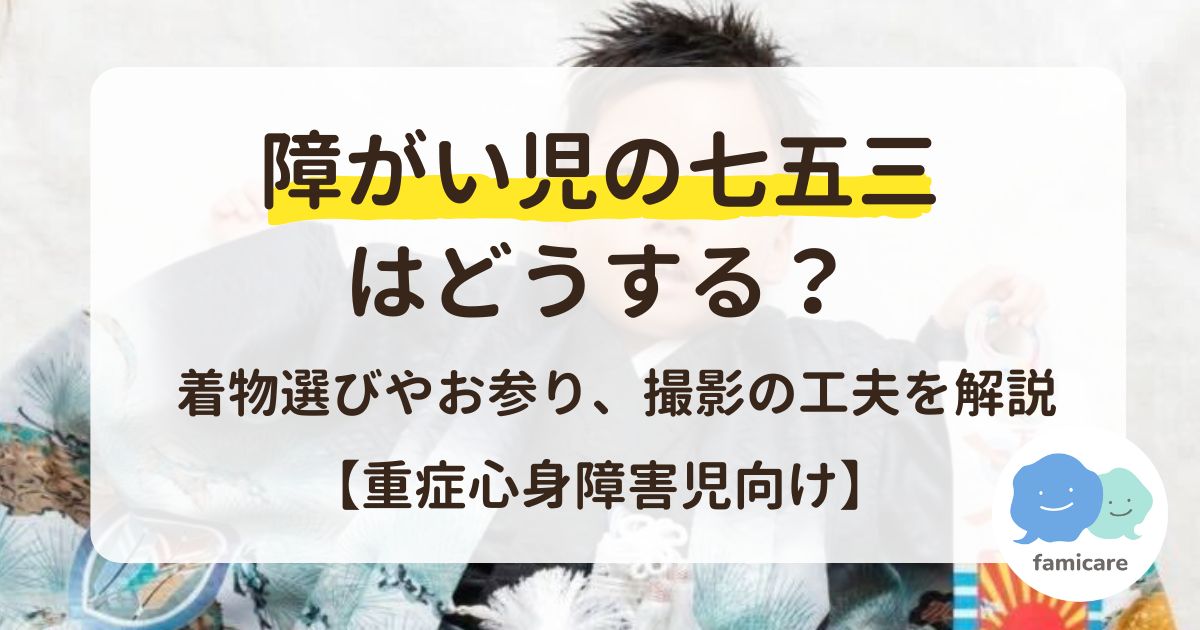

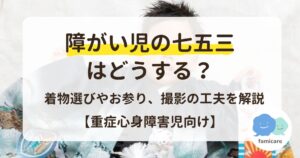


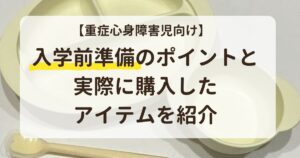

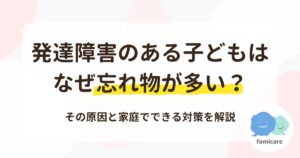

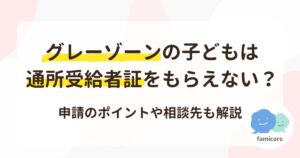
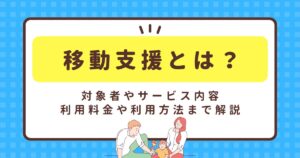
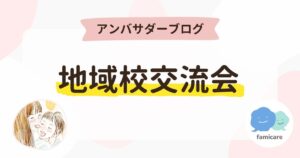
コメント