
わが子は日常のあらゆる場面で不安そうだけど、将来大丈夫…?



わが子の不安、どのように和らげてあげたらいい?
発達障害のある子どもは、日常のさまざまな場面で不安を感じやすい傾向があります。その不安は、見通しが立たない状況や感覚過敏など、障がいと密接に関連していることが少なくありません。
この記事では、発達障害のある子どもが感じる不安の特徴を理解し、家庭や学校で実践できる環境調整の方法、活用できるサポートなど、具体的な不安軽減の方法をご紹介します。
発達障害のある子どもは不安を感じやすい?
発達障害のある子どもは、環境の変化や予測できない状況に対して強い不安を感じやすい特性があります。例えば、自閉スペクトラム症(ASD)のある子どもは、日常のルーティンが変わることに強いストレスを感じやすいのが特徴です。また、感覚過敏がある場合は音や光、触感などの刺激に過剰に反応し、それが不安の原因になることも少なくありません。
注意欠如・多動症(ADHD)のある子どもは、不注意や衝動性により周囲の状況を正確に把握しづらく、そのことから生じる「わからない」という感覚が不安につながる場合があります。さらに、学習障害(LD)のある子どもは、学習面での困難さから自信をなくして不安を抱えてしまうケースも珍しくありません。
▼発達障害のある子どもが不安を感じる詳しい理由については、こちらの記事をご覧いただけます
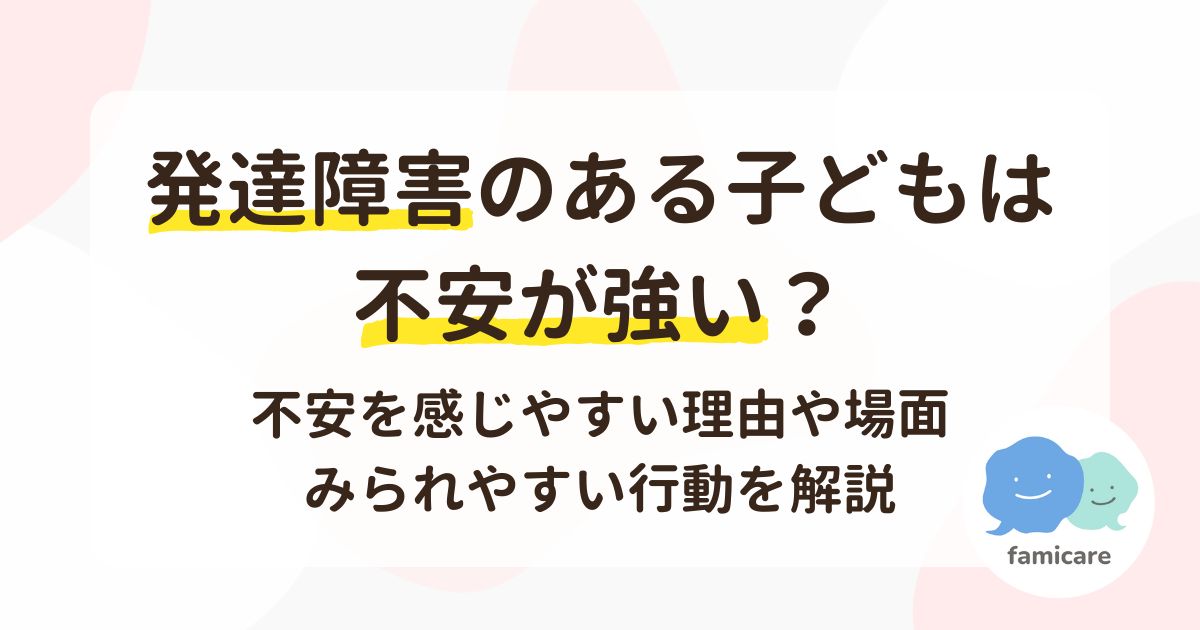
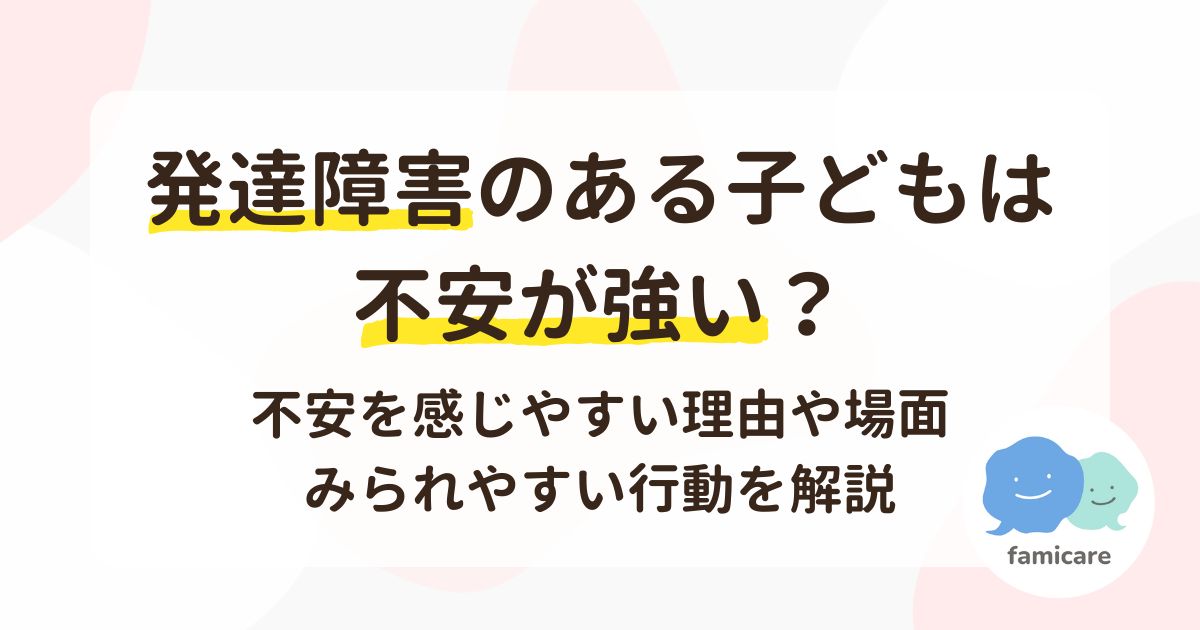
発達障害のある子どもの不安への対処法
上記のような不安は、周囲の理解と適切な環境調整で軽減しやすくなります。子どもの特性を理解したうえで、一人ひとりに合わせたサポート方法を見つけるのが大切です。
発達障害のある子どもの不安を和らげるために有効な方法を、以下にご紹介します。
対処法1. 見通しを立ててあげる
前述したとおり、発達障害の子どもは「先がわからない状況」に強い不安を感じやすい傾向があります。そのため「見通しの持てる環境づくり」が、ストレスを和らげるためのポイントです。
発達障害のなかでも特にASD(自閉スペクトラム症)のある場合は、視覚優位の特性を持つ方が多い傾向があるといわれています。そのため、スケジュールを図や時系列にして紙に書き出したり、必要に応じてイラストを添えて子どものイメージを助けたりなどするとより効果的です。
また、新しい状況への不安だけでなく「なぜそういう状況になるのかわからない」という不安を取り除くためにも「なぜそこに行くのか」「なぜそこを通るのか」という理由も説明するとよいでしょう。



筆者の娘は、保育園の頃からお遊戯や運動会、発表会などに強い不安を感じやすい傾向でした。そのため、前の年までの会の映像を知人から借りて事前に見せたり、あらかじめ会場を一緒に見たりなどしながらイメージをサポートしました
▼視覚支援として絵カードを用いることもあります
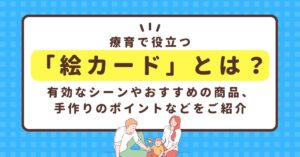
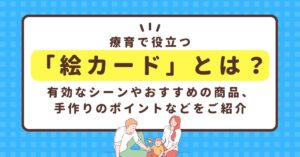
対処法2. 日常生活の環境を整える
感覚刺激への配慮
子どもの感覚過敏の特性を理解して、環境を整えるのも大切です。音が気になる場合はイヤーマフを用意したり、光が気になる場合はサングラスの使用を認めたりするなど、個々の特性に応じた対応が効果的といえます。
カームダウンスペースの確保
不安が強い子どもへのサポートで重要なものの一つが「ストレスが溜まった際に落ち着ける場所の確保」です。部屋の一角にカームダウンスペースを設けたり、学校では保健室や相談室を利用できるようにしたりすると、安心して過ごしやすくなります。
▼カームダウンスペースの詳細についてはこちらからご覧いただけます


快適な睡眠環境の整備
良質な睡眠のために欠かせないのが「寝室の環境」です。発達障害のある子どもの場合、温度や湿度の変化に対して感覚が過敏または鈍麻のケースがあるため、「寒い・暑い」の指標を明確な数値として温度で伝えたり、暖房や冷房を使う時間や設定温度を決めておいたりするとよいでしょう。
また、寝具やパジャマの素材を子どもの好みに合わせてみるのも有効です。その他、就寝前のルーティンを作ったり照明の色や寝室の香りを心地よいものに変えたりなども、不安感の軽減につながります。



窓から入る光が気にならないよう、わが家では寝室に遮光カーテンを使用しています
対処法3. 公的サポートを活用する
家庭でのサポートだけではなく、制度を上手に使ってみるのも一つです。例えば、以下の制度を適切に活用できれば、子どもが安心して過ごせる環境を整えやすくなります。
合理的配慮
子ども一人ひとりの特性に応じて環境を調整する制度です。「静かな席の確保」や「視覚的スケジュールの提供」などが挙げられます。
担任の先生や特別支援教育コーディネーターに子どもの特性やニーズを伝え、どのような配慮が可能か話し合いましょう。また、教育委員会や自治体の窓口でも具体的なアドバイスを得られる場合があります。
▼合理的配慮とは
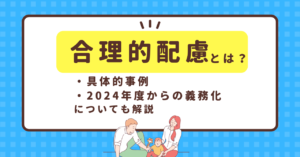
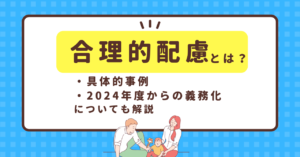
特別支援教育
専門の教員が障がいのある生徒の自立や社会参加、学習面などに対し、適切な指導および必要な支援を行うものです。子ども一人ひとりの教育に必要なニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善または克服することを目指します。
学校や地域の教育委員会に相談すれば、特別支援学級や通級指導教室の利用を検討可能です。また、学校内のスクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーターからも適切な情報を提供してもらえます。
児童発達支援
障がいのある子どもや発達に課題のある子どもが対象の福祉サービスです。日常生活や集団生活を営めるよう、一人ひとりに合わせた支援を行います。生活や社会性のスキル向上を目的とした療育サービスを提供しており、子どもの不安の軽減につながりやすいのが魅力です。
児童発達支援事業所や療育施設を利用する場合、市区町村の福祉課や子育て支援センターに相談してください。
▼児童発達支援について詳しくはこちらの記事で解説しています
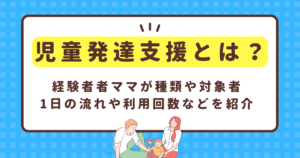
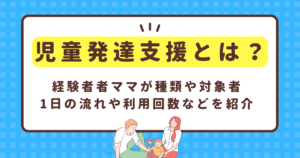
対処法4. 専門機関への相談を検討する
さまざまなサポートでも改善がみられない場合や、強い不安感により心身に支障が出ている場合は、専門機関と連携して対処法を考える必要があります。特に、発達障害の診断や治療方針の決定には、医療機関との連携が重要です。
必要に応じて投薬治療や心理療法を組み合わせることで、不安症状の改善が期待できます。定期的な受診を通じて子どもの状態の変化を専門家と共有しながら、適切な支援方法を見つけていきましょう。



保育園や学校、通っている施設などと普段の様子を報告し合うのも大切です
不安が強い子どもの成長には寄り添いと理解が大切
特性を理解しながら環境を整えて必要な支援を受けることは、子どもの強い不安の軽減につながっていきます。とはいえ、発達障害のある子どもの不安に寄り添いながら適切なサポートを考える毎日は、ご家族にとってもエネルギーが必要です。
家庭だけで抱え込まず、専門家や支援者と連携しながら、子どもの成長をサポートしていきましょう。子どもの「できた」という小さな成功体験の積み重ねは、自信を育み、不安と上手に付き合えるための道筋になるはずです。
「親として自分も不安な毎日だけど、子どもの前では見せられない…」そんな気持ちは、ファミケアの公式SNSやアプリでそっと吐き出してね
【参照】特別支援教育|文部科学省


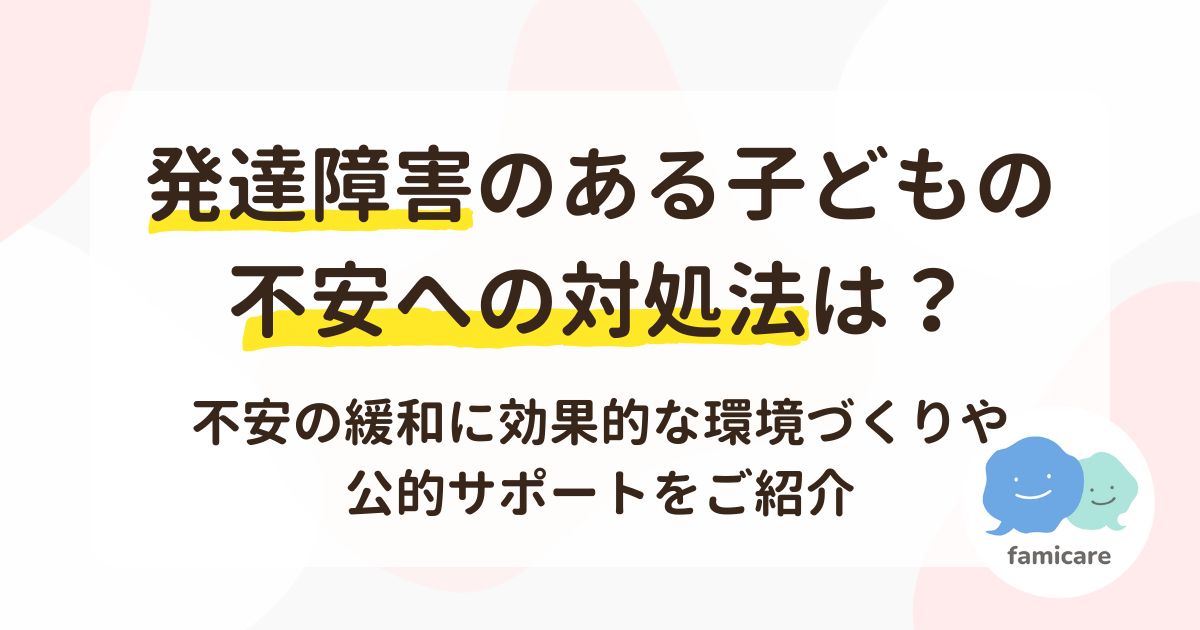

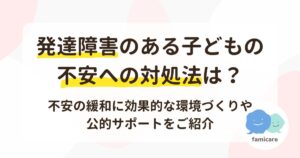

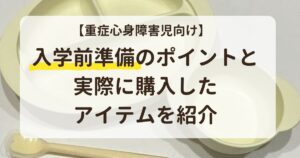

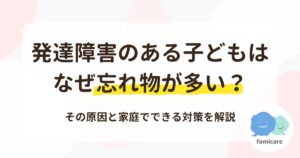


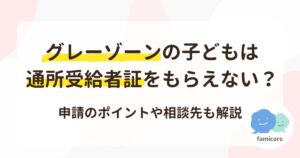
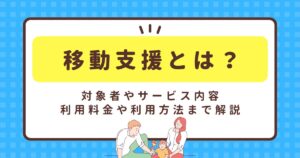
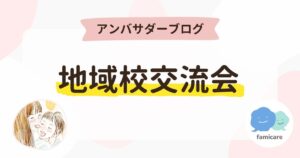
コメント