
1歳半健診で何もできなかった我が子はダメな子なの?
そんな不安な気持ちで、この記事にたどり着いた方は多いのではないでしょうか。でも、大丈夫です。「1歳半」は、子どもの成長にとって大きな個人差が出る時期といえます。
この記事では、我が子の1歳半健診後に発達の悩みを抱えた際の対処法や、専門家のアドバイス、家庭でできる支援方法などについて、認定心理士である筆者が詳しくご紹介します。
1歳半健診は子どもの発達を評価するものではない
まず前提として、1歳半健診は、子どもの発達を評価したり順位をつけたりするものではありません。1歳半健診の目的は、以下の2点です。
- 子どもの成長の様子を確認する
- 必要に応じて早期から適切な支援に繋げる
つまり1歳半健診は、子どもの健やかな成長をサポートするためのものです。
子どもたちの発達は一人ひとり違います。1歳半健診で全ての項目をクリアできなくても、それは決して我が子が他の子どもたちよりも劣っているのでもなければ、親の育て方が悪いのでもありません。



大切なのは、子どもの成長に焦らずそれぞれのペースで発達を促していくことです
▼1歳半健診の詳細についてはこちらの記事からご覧いただけます
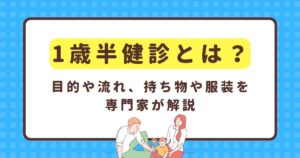
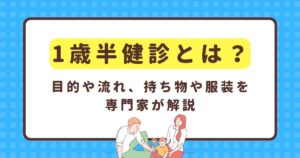
1歳半健診後のフォローアップをチェック
1歳半健診で気になる点があった場合、多くの自治体では次のようなフォローアップ体制を整えています。子どもの成長を適切にサポートするためには、これらを上手に活用するのがおすすめです。
経過観察
経過観察は、子どもの成長を継続的に見守るためのものです。定期的に、保健師や専門家が子どもの発達の様子をチェックします。
通常は、3〜6ヶ月ごとに実施されるのがほとんどです。しかし必要に応じて、以下のような専門的な支援に繋げる役割も担います。
- 小児科での精密検査
- 発達支援センターでのサポート
- 言語聴覚士による言語療法
- 作業療法士による日常生活動作や感覚統合へのサポート
- 理学療法士による運動発達の遅れに対しての専門的なアプローチ
- 子どもの行動や情緒面の課題に専門家が支援するための心理カウンセリング
- 保育所や幼稚園と連携した集団生活における子どものサポート
- 保護者への相談支援や育児指導
上記の支援は、子どもの個別のニーズに応じて選ばれ、場合によっては複数の支援を組み合わせるケースもあります。早期の適切な支援は、子どもの健全な発達を促進するうえで非常に重要です。



経過観察を勧められても、心配する必要はありません。筆者は「子どもの成長をより丁寧に見守るチャンスだ!」と捉えました
発達相談
発達相談では、心理士や言語聴覚士などの専門家へ個別に相談ができます。子どもの発達に関する詳しい評価や助言を受けられるのが特徴です。必要に応じて発達検査をする場合もあります。



発達相談を利用すると、子どもの成長をより専門的な視点から理解でき、適切な支援方法を見つけやすくなります
親子教室
親子教室は、同じような悩みを持つ親子が集まって一緒に活動する場です。専門家の指導のもと、遊びや運動を通じて発達の促進を目指します。
他の親子との交流を通じて、情報を交換したり悩みを共有できたりするのが魅力です。大半は、週1回や月2回など定期的に開催しています。



親子教室への参加は、子どもの成長を促すだけでなく、保護者の方の不安も和らげる効果が期待できます
療育機関の紹介
より専門的な支援が必要な場合は、児童発達支援センターや児童発達支援事業所などの療育機関を紹介されることがあります。療育機関では以下のような支援を行います。
- 個別指導や小集団活動を通じて発達をサポート
- 言語訓練、運動訓練、ソーシャルスキルトレーニングなど、専門的なプログラムを提供
療育機関の利用を勧められても、落胆する必要はありません。これらのサービスは、子どもの成長を支援するためのものです。



決して「レッテル貼り」ではなく、子どもの成長を最大限サポートするための選択肢のひとつだと考えるのがおすすめです
▼発達障害児の療育についてはこちらの記事で解説しています
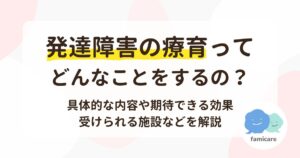
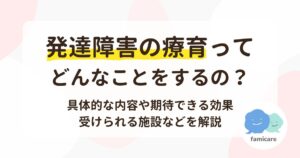
▼児童発達支援センターについてはこちらの記事で解説しています
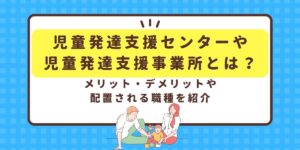
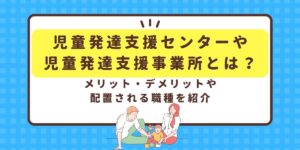
家庭でできる発達支援を取り入れる
専門家による支援と並行して、家庭でもできる発達支援を活用するのも一つの手段です。日常生活のなかで以下のような活動を楽しみながら取り入れていくと、子どもの成長を促すことができます。
言葉の発達を促す
言葉の発達は、コミュニケーション能力の基礎となる重要な要素です。例えば、家庭での以下のような活動を通じて、子どもの言葉の理解力と表現力を自然に育みやすくなります。
絵本の読み聞かせ
- 毎日10〜15分程度、子どもと一緒に絵本を楽しむ
- 絵を指さしながら、ゆっくりはっきりと言葉を伝える
歌やリズム遊び
- 手遊び歌や童謡を一緒に歌う
- リズムに合わせて体を動かして言葉とリズム感を育む
日常会話の充実
- 日々の生活の中で子どもへ積極的に話しかける
- 子どもの反応を待ってやりとりを楽しむ
運動発達を促す
体を動かす経験は、全身の協調性や空間認知能力の発達に繋がる大切な要素です。例えば、家庭での以下のような活動を通じて、子どもの粗大運動能力と微細運動能力の発達をバランスよく促すことができます。
外遊びの機会を増やす
- 公園で遊ぶ、散歩に行くなど、体を動かす機会を作る
- 草花や虫を探すなど、自然とふれあう体験をする
リズム体操や簡単な運動遊び
- 音楽に合わせて体を動かす
- ボール投げやフープくぐりなど、楽しみながら運動能力を高める
日常生活での活動を大切にする
- 着替えや食事の準備など、日常の活動を一緒に行う
- できたことを褒めて自信につなげる
社会性の発達を促す
他者との関わりを通じて、社会性やコミュニケーション能力を育む習慣も大切です。以下の活動では、子どもの社会性とコミュニケーション能力を自然に育めます。
子ども同士での交流
- 公園や子育てサークルなどで他の子どもと遊ぶ機会を作る
- 見守りながら子ども同士のやりとりを大切にする
ごっこ遊びの充実
- お店屋さんごっこやお医者さんごっこなど、役割を演じる遊びを楽しむ
- 想像力や表現力、他者理解の力を育む
感情表現の練習
- 絵本や日常生活でさまざまな感情について話し合う
- 子どもの気持ちを言葉で表現し、共感する
感覚統合を促す
感覚統合とは、さまざまな感覚情報を適切に処理し、行動につなげる能力のことです。以下のような活動では、子どもの感覚処理能力を高めることができ、日常生活での適応力の向上が期待できます。
触覚を刺激する遊び
- 砂遊びや粘土遊びなどさまざまな触感を楽しむ
- ボディペインティングや指絵の具遊びも効果的
前庭感覚を刺激する遊び
- ブランコやすべり台、回転遊具など、体の傾きや動きを感じる遊び
- バランスボードやトランポリンなど
固有感覚を刺激する遊び
- 重いものを押したり引いたりする遊び
- クッションやビーズクッションの中に潜る遊び
▼こちらの記事では療育になる遊びのアイデアを紹介しています




一人一人の子どもに寄り添う子育てを
1歳半健診後に発達の悩みを抱えることは、決して珍しくありません。むしろ、子どもの成長を真剣に考えているからこそ生じる悩みだといえます。
繰り返しになりますが、大切なのは、子どもの個性や成長のペースを尊重しつつ必要に応じて適切なサポートを受けることです。専門家への相談、家庭でのサポート、地域の支援サービスの利用など、さまざまな方法を組み合わせながら子どもの健やかな成長を見守っていきましょう。
同時に、ご自身の心のケアも忘れずにいてください。


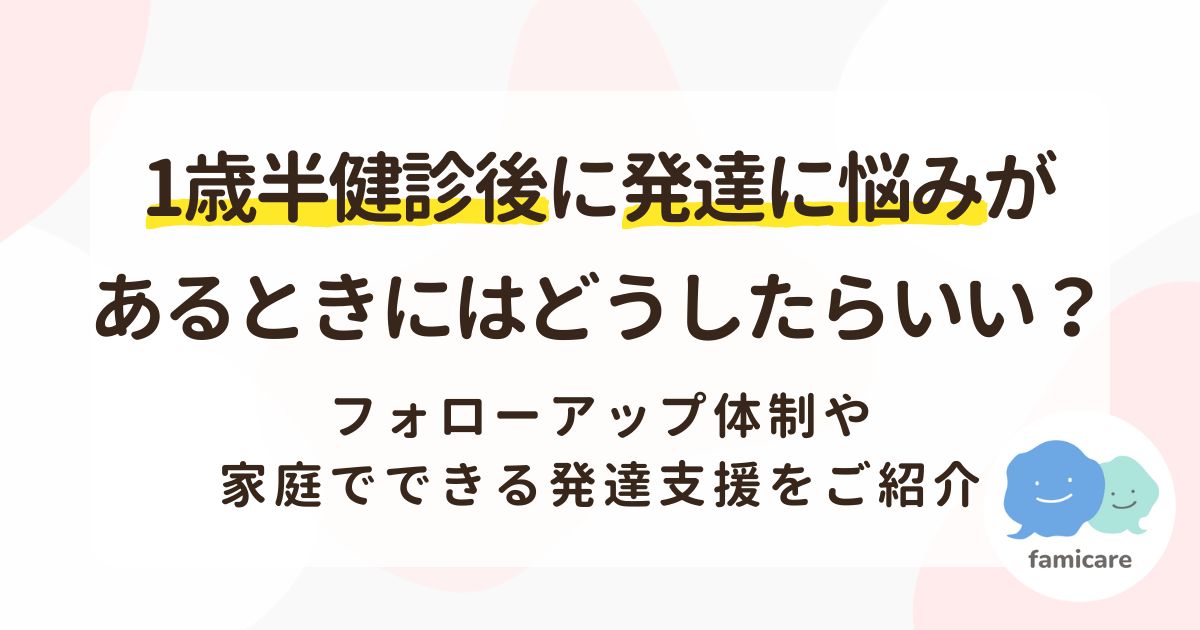
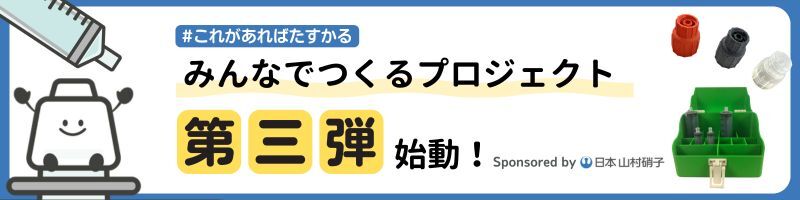

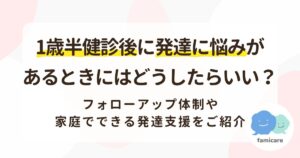

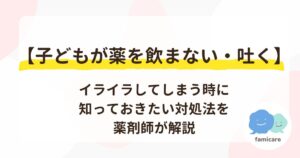
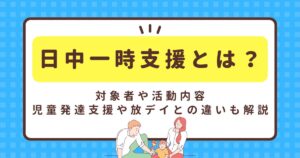
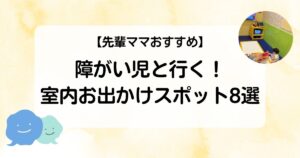

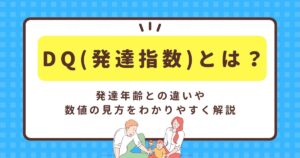



コメント