身体に障がいのあるお子さんがいるご家庭では、入浴などのシーンにおける負担軽減を目的としてリフトの導入を検討されるケースがあります。
リフトといっても様々な種類がありますが、筆者の場合は主に入浴時の介助者の負担軽減を目的として、新築時に天井走行リフトを導入しました。
同じように、住宅の新築や改修時に天井走行リフトを検討しているご家庭もあるかもしれません。しかし、特に新築の場合は費用補助がないこともあり、周囲で実際に導入した人から手順についてお話を聞く機会は少ないのが現状です。

実際何から決めればいいの?



どんな手順で誰に相談すればいい?
そんな疑問を抱えたままなかなか前に進めない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、筆者の経験を下に、天井走行リフトを導入するための手順や注意点について解説していきます!
天井走行リフトの設置手順
リフトの設置にあたっては、費用や住宅の間取りだけでなく、子どもの障がいの程度や特徴、家族の生活スタイルなど、様々な要因が関わってきます。
何から決めていいのかわからず考えを整理しにくい方も多いと思いますので、一つの考え方の例として、設置までの手順を以下にまとめてみました。参考にしていただけたら嬉しいです!
①主な利用目的を決めましょう
リフトが活用できる場面は、ベッドから車椅子への移乗、食事やトイレ、リハビリなど様々です。いざ設置するとなるとあれもこれもと考えてしまいがちですが、予算や空間の制約もあるため、まずは、ご家庭でリフトを導入する主な利用目的を決めましょう。利用目的が決まってはじめて、設計や目的に合ったリフトの種類を決めることができます。



筆者の場合は、入浴時をメインに動線を設置し、プラスアルファで将来的にベッドからバギーへの移乗やリハビリでも活用できるように考慮しました。
②レールの種類と設置方法を決めましょう
主な利用目的が決まったら、次はレールの種類と設置方法を検討しましょう。レールの種類はXYレールとシングルレールの2種類です。
XYレールを設置すれば面での動きが可能になり、様々な動きを想定したリハビリでの活用には適していますが、レールが活用できるように、広いスペースが必要になります。
一方で、入浴や食事、移乗など、主な利用シーンが限られている場合、シングルレールによる線での移動を想定するとよいかもしれません。シングルレールは天井への埋め込みも可能なので、家の雰囲気にも馴染みやすいというメリットもあります。
予算と合わせて利用目的に合ったレールの種類や設置方法を決めましょう。
③希望のメーカーと福祉機器販売業者を決めましょう
主な利用シーンや設置方法が決まったら、リフトのメーカーを検討し、購入する福祉機器販売業者を決めましょう。地域によっては、リフトを扱っている福祉機器販売業者が1社しかないこともありますが、利用目的にあわせてじっくりリフトメーカーを検討し、希望のリフトを扱っている業者を探してみるのがおすすめです。
▼リフトのメーカーについてはこちら
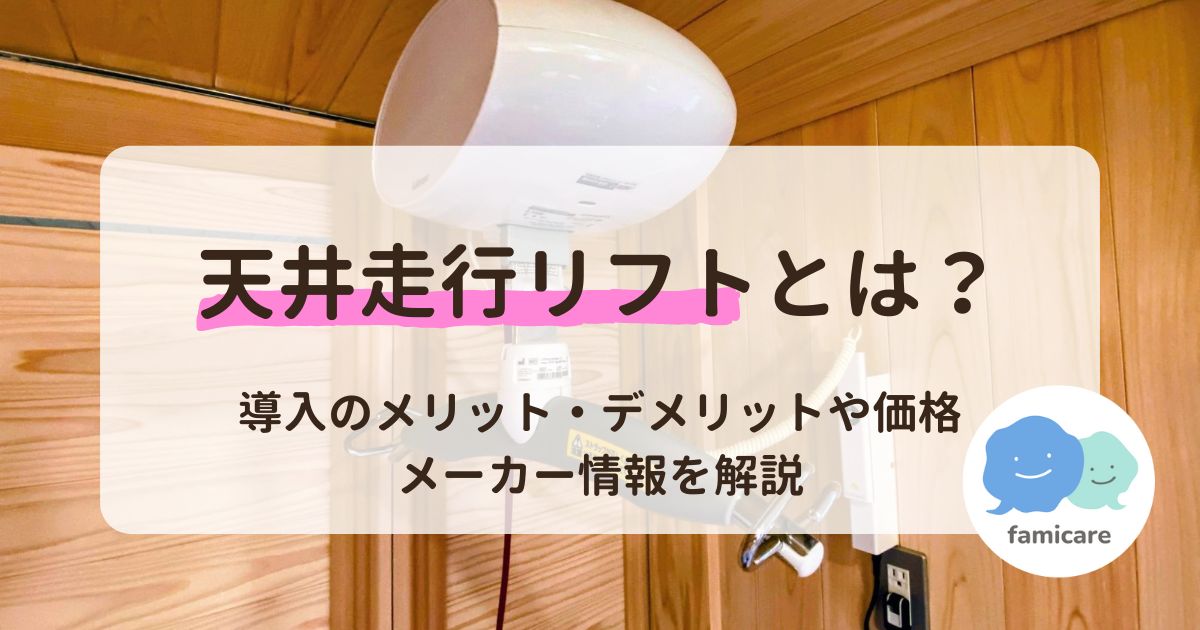
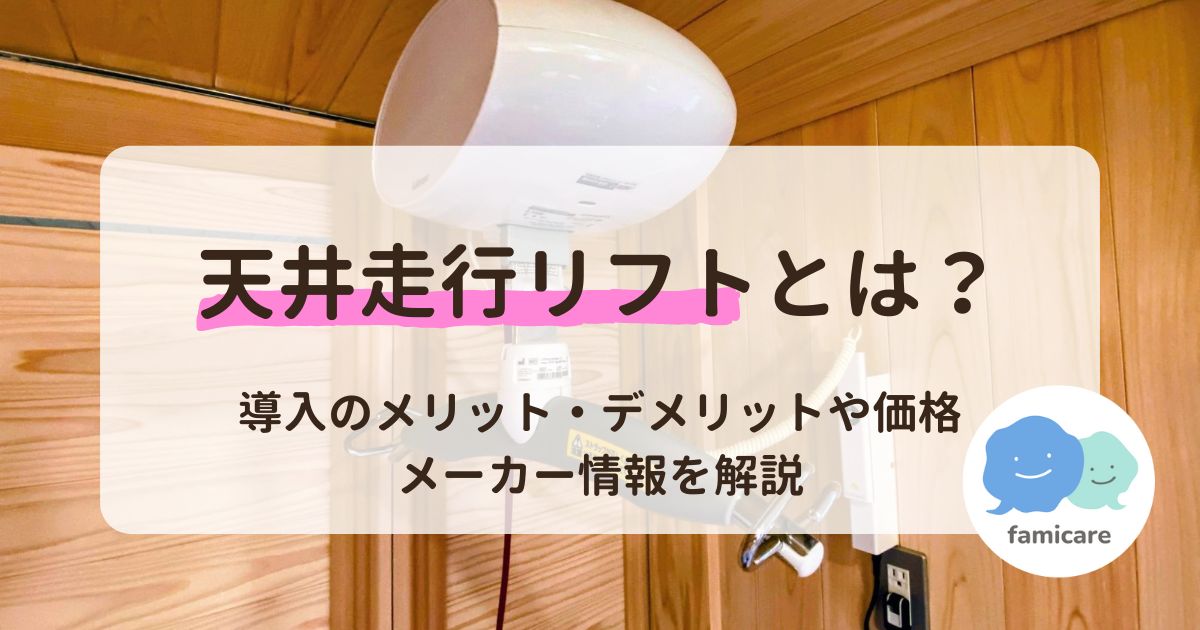
④リフトの設置場所や導線を決めましょう
利用目的に合わせたシミュレーションをして、設置場所や導線を決めましょう。利用したいシーンの動きを福祉機器販売業者や住宅の設計士に伝えて、構造上どこに設置ができそうかすり合わせをしていきます。この時、利用シーンをできるだけ具体的にイメージしながらシミュレーションするのがおすすめです。
⑤スリングの種類を決めましょう
リフト本体につけるスリングシートにも、いくつかの種類があります。
スリングの種類は、主に頭部の支えのありなしと脚部分の分離状況で分類できます。頭部の支えのあるハイバックタイプとないローバックタイプ、脚部分を左右まとめて包み込むシートタイプと脚分離タイプがあります。また、スリングの種類によりますが、基本的には素材もメッシュタイプとスタンダードタイプが選べます。
| ハイバックタイプ(頭部の支えあり) | ローバックタイプ(頭部の支えなし) | |
| シートタイプ(両足まとめる) | ハイバックシートタイプ | ローバックシートタイプ |
| クロスタイプ(脚分離) | ハイバッククロスタイプ | ローバッククロスタイプ |
他にも子どもの座位保持力によって、立位を支えるタイプのスリングやトイレ用のスリングなど、実はスリングにはたくさんのラインナップがあります。利用目的が具体的に決まっている場合は、スリングを最初に決めてからリフトの種類やメーカーを検討するのもよいかもしれません。
参考までに、筆者が検討した小児用ハイバックシートタイプと、小児用ハイバック脚分離タイプ(いずれもグルドマン社)についてご紹介します。
ハイバックシートタイプ


筆者が購入したのは、頭部を支える部位がしっかりあるハイバックタイプで、なおかつ両足を揃えて支えるシートタイプのスリングです。
利用する障がい児本人の首や腰を支える力が弱くても安定して吊り上げることができます。ずり落ちてしまう心配もなく、安心して利用できますが、スリングに乗せてベッドや床面に置いたあと、スリングを外す際に子どもを少しずらして抜き取る必要があることにやや不便さを感じています。
素材はスタンダードタイプのみでメッシュは選べませんでしたが、速乾性のある素材のため、浴室で使った後に軽く水気を切って干しておけば翌日には乾いています。
ハイバック脚分離(クロス)タイプ


シートタイプと違い、左右の足を別々にクロスして支える脚分離タイプ。こちらの利点はなんといってもスリングに乗せた状態でベッドや床面に置いたあと、本人の体を動かすことなくスリング部分だけ取り外せるという点です。入浴後の濡れた状態でも、手軽に乾いたスリングと交換することができるのが魅力です。
ただし、脚分離タイプの場合はおしり部分に穴があいた状態になるため、座位保持力や子どもの体の大きさ、リフトに乗っている時間の長さによってはずりおちてしまう心配があるかもしれません。
こちらはメッシュ素材を試しましたが、スタンダードタイプより乾きやすく軽い印象でした。ただし、長時間リフトに乗っていると、メッシュの目が食い込んで痛みを感じる場合があるそうです。子どもの姿勢や表情などから心地よさを確認してみましょう。
天井走行リフト導入時の注意点
次に、導入時の注意点についてまとめました。
利用シーンに合わせたシミュレーションが大切
大まかなリフトの設置方法が決まったら、生活導線上問題ないかどうか具体的にシミュレーションすることが大切です。
例えば入浴シーンであれば、どこに介助者が立ち、どのような向きで体を洗うのか。またバスタブに入るときはどのような角度で入り、頭はどこで支えるか。お風呂から上がるときは、どこで身体を拭き、どこで着衣するのかなど、具体的にシミュレーションすることで、細かな導線の調整を行うことができます。
スリングの試着は必須
リフトを導入する際に最も気をつけたいのは、体に合ったスリングを選ぶことです。興味のあるスリングシートを見つけたら、スリングの試着をしてみることを強くおすすめします。
釣り上げたときにお子さんの体がL字型になっていることが、スリングが体にフィットしていることの目安となるそうです。試着をせずに体に合っていないスリングを使ってしまうと、無理な力が働き、子どもの体に負荷がかかってしまう可能性もあります。


反転してしまいましたが、Lの字のイメージです
気になるスリングは、福祉機器販売業者に相談すれば貸し出しもしてくれます。また、病院やリハビリ施設、福祉機器販売業者の展示場などでも試着可能です。できれば実際の生活の中で使ってみることで、子どもの体や用途に合ったスリングかどうか確認してみるといいですね。



試着して実際にリフトを使ってみると、リフトを導入した後の生活のイメージもわき、設計の際の大切な判断材料にもなります。筆者はすべて試着せずに購入を決めたため、実際に使用を始めてから「こちらがよかった」と思うこともありました。すべてのスリングの試着を申し出ることには少し勇気が必要ですが、購入後の後悔を防ぐためにもぜひ試着をしてみてください。
ハンガー幅とスリングが合っているか確認
リフトのハンガー幅と合っているスリングかどうかを必ず確認しましょう。スリングは同じメーカーのハンガーの幅に合わせて装着できるように設計されていますので、リフト本体とスリングが異なるメーカーの時には注意が必要です。
住宅施工業者との連携が必要
天井走行リフトの導入を本格的に検討する場合、予算や設計の見通しをつけるためにも、早めに住宅の施工業者にその意思を伝えておくと安心です。希望を伝えておくことで、担当する設計士もリフトの導入に合わせた間取りや提案を一緒に考えてくれるはず。
具体的な間取りやリフトの設置方法が決まったら、設計士とリフトの施工業者の間で直接コミュニケーションをとり、細かな設計を進めていきます。
ちなみに我が家の場合、以下のような流れでリフトの導入を進めました。
- リフト導入の希望を住宅施工業者に伝える
- リフト業者より設計の必要要件を聞き取り
- 住宅の設計図完成
- リフト設置の詳細な図面を作成
- 竣工2ヶ月前にレール設置工事実施
- 竣工後、リフト本体の設置
住宅の設計士とリフト業者の連携はもちろんですが、実際の設置工事の際は大工の方とのコミュニケーションも必要になります。リフト業者の担当者の方と設計者、そして現場の大工とがうまく連携を取れるように進めましょう。
天井走行リフト導入でストレスフリーの入浴が実現
家庭にはまだあまり利用が普及していない天井走行リフトですが、思い切って導入したことで、娘を大好きなお風呂にストレスなく思う存分入れてあげられるようになりました。また、主な目的は入浴シーンでの負担軽減でしたが、将来的な負担増の不安も軽くなり、また入浴シーン以外での活用も検討できるようになりました。



娘はリフトに乗っている時の揺れもハンモックのようで心地よく、シンプルにリフトに乗ることを楽しんでいるようです。リハビリや遊びへの活用も今後探索していきたいです!
ご家族の構成や子どもの状態など、それぞれのご家庭の事情に合わせてリフト導入を検討してみてください。
▼家づくりに関するお役立ち情報が満載な特集がこちら!
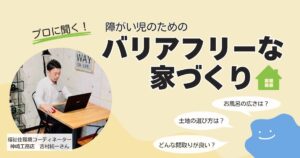
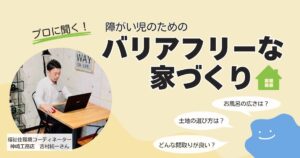


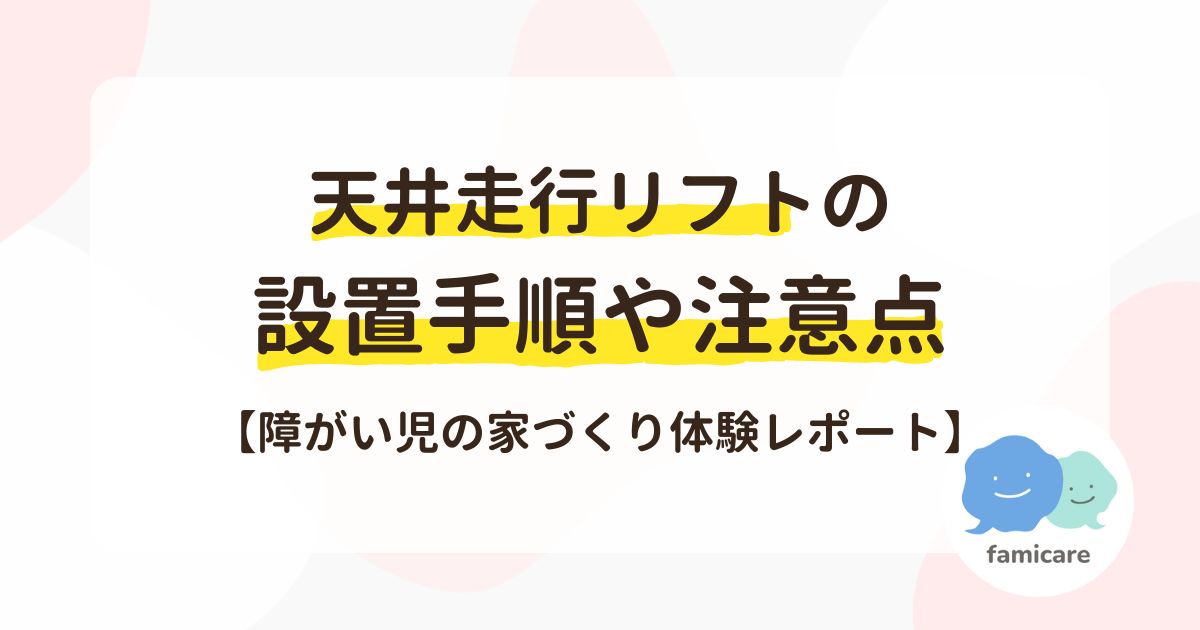





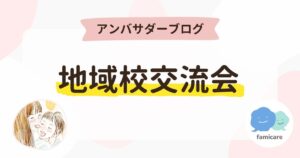
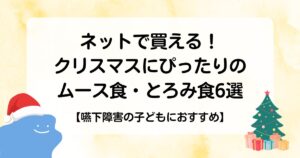
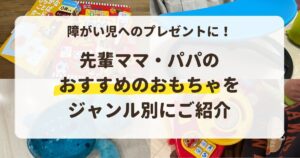
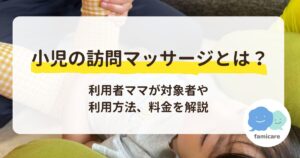

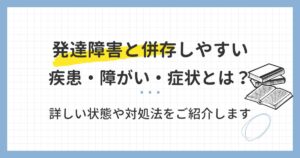
コメント