
自閉スペクトラム症の我が子、こだわりが強いし人とコミュニケーションを取るのも苦手だし、一人遊びが大好きで…
その心配、少し視点を変えて「子どもの得意なこと」に繋げてみませんか?
この記事では、特性から見える「得意なこと」を、自閉スペクトラム症の娘と暮らす筆者の目線でご紹介します。「得意をどう活かす?」にもスポットをあてていきますので、興味のある方法がありましたらぜひ実践してみてくださいね。
自閉スペクトラム症(ASD)の特性
自閉スペクトラム症は「対人関係や社会的なやりとり」「行動や関心へのこだわり」「感覚のかたより」などの特性がみられる状態です。Autism Spectrum Disorderの頭文字を取って「ASD」とも呼ばれています。
それぞれの特性の詳細は、次のとおりです。
対人関係や社会的なやりとりの特性
自閉スペクトラム症は「ちょっとだけ待って」「もう少し進めて」など、抽象的な言葉や指示、表情、身振りなどによるやりとりが苦手な傾向にあります。また、自分の視点で物事を思い込みすぎたり相手の気持ちを読み取りにくかったりするため、コミュニケーションが必要な場で困りごとが起こりやすいのが特徴です。
こだわりの特性
物の配置や順番、勝敗、マイルールへの強い固執など、興味や関心に極端なかたよりがみられるのも自閉スペクトラム症の特性です。こだわりの程度や種類には個人差がありますが、いずれも見通しを立てるのが難しいため、一貫性のあるパターンや予測可能な環境が過ごしやすいとされています。
感覚面の特性
自閉スペクトラム症は「刺激に著しく敏感、または著しく鈍感」という特性を持つ場合もあります。
音・におい・触り心地・味など、特定の感覚への苦手得意・好き嫌いは誰もが持っているものですよね。しかし、自閉スペクトラム症では、この「感覚」から耐えられないほどの苦痛や大きなストレスを感じることがあるのです。



自閉スペクトラム症は、情報の整理に必要な脳の中枢神経系のメカニズムに先天的な特性がみられる障がいの一つです。「親の育児が悪かったからかもしれない」「愛情不足だから?」と心配する方もいるかもしれませんが、親の育て方が原因ではありません。
▼自閉スペクトラム症について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。


自閉スペクトラム症(ASD)、こんなことが得意です
「人とうまく関われない」「習慣やマイルールが異なるのが許せない」「特定の感覚に強い苦手意識があるため生活に制限がある」ーー。障がいを持つ子どもにとって心地よい環境を目指していると、つい「できない」「嫌い」「不得意」に目が向きがちになってしまうことはありませんか?
確かに、子どもにとっての不快を生活から取り除くことはとっても大切です。しかし、実は「できない」「嫌い」「不得意」にこそ「できる」「好き」「得意」を見つけられるヒントが隠れています。
得意なこと①:ルーティンワーク
自閉スペクトラム症の特性の一つでもある「こだわり」。「柔軟性を欠く」「変化に対応しにくい」と捉えられがちですが、“自分で決めたルールを守りたい”という強い意志は、ルーティンワークの継続に活かしやすいのが長所です。
場所・内容・目的などをあらかじめ決め、その流れをメモや絵カード、カレンダーで見える化することで、安心して活動に取り組めます。
▼「こだわり」を活かしたルーティンワークの一例
- 決まった食生活や運動を継続し子どもなりの健康づくり
- 資格や習い事、技術の取得
- 事前に決めたスケジュールを正確に遂行する など
得意なこと②:「好き」に没頭
マイルールから逸れた物事への拒絶が強い一方で、「マイルールに沿った考えや好きな物事にはひたすら探求心を発揮できる」のも特徴です。興味を持ったものには、とことん没頭して熱心に取り組めます。ときには、電車や天気など特定の物事についての知識を深め、周囲から「〇〇博士」と呼ばれることも。



好きなことや興味の対象は、子どもによってさまざま。必ずしも周りから「すごいね!」と言われたり、学校の成績に反映できたりするものではないかもしれません。しかし「没頭できるくらい好きなものを見つけられた」という事実こそが、子どもにとっての宝物です。
得意なこと③:独創的発想
特性によって困りごとがある一方で、特性“ならでは”の感性や感受性があるのも強みです。多くの人が持っていない独創的発想は、クリエイティブ方面で「才能」として開花する可能性を秘めています。
日本のみならず海外でも、自閉スペクトラム症や注意欠如・多動性障害を公表しているアーティストが多数いるね
得意なこと④:最後まで粘り強く正確にやり遂げる
「マイルールがある」「こだわりが強い」などの特性は、「最後まで諦めずに粘り強く向き合う」と置き換えられます。一度決めたことや好きなことには強い意志を持って取り組むため、周囲が途中で諦めてしまう場合も正確にやり遂げようとするのが強みです。
自閉スペクトラム症(ASD)の特性を得意分野で生かすには
「自閉スペクトラム症の特性を、できるだけ子どもの得意分野で活かしてあげたい」。ご家族や周りの大人が、今日から始められるサポート方法をご紹介します。
「構造化」で子どもの理解をサポート
「構造化」とは、“どう動いたらいい?” “何をしたらいいの?”を子ども自身が考え、安心して行動に移せるようにするための方法です。いつ何をするかのスケジュールを可視化させる「時間の構造化」、どこが何をする場所なのかを明確にする「空間の構造化」、どんな順番で何をするのかを視覚的に示す「手続きの構造化」などがあります。
▼構造化で得られるメリット
- 子どもが混乱せずに物事に取り組める
- 行動に集中しやすくなる
- 子どもが学習や生活に自信を持ちやすくなる
- 学習を効率よく進めやすくなる
- 将来的な社会的自立に繋がる
- 家族の精神的な負荷を軽減できる
感覚過敏には配慮を
「服のタグがチクチクして気になる」「工事の音が気になって学習や遊びに集中できない」「アルコール消毒の匂いが苦手だから使いたくない」。自閉スペクトラム症の子どもの場合、このような訴えは単なるわがままではなく、感覚過敏による強いストレスからきている場合があります。
感覚のかたよりには個人差があるものの、子ども本人が自覚できていない可能性も。そのため、できるだけ周囲の支援者が生活をよく観察し、子どものストレスになりやすい感覚を見つけることが大切です。
▼感覚過敏への配慮の一例
- 「服のタグがチクチクして気になる」:タグを切ったりあらかじめタグ無しの衣服を選ぶ
- 「工事の音が気になって学習や遊びに集中できない」:窓を閉めたり別の部屋へ移動させる、イヤホンやイヤーマフを活用して耳をふさぐ
- 「アルコール消毒の匂いが苦手だから使いたくない」:ノンアルコールのウェットティッシュを持ち歩く



自閉スペクトラム症と診断されている筆者の娘は、エアータオルの「ゴーー」という音が大の苦手。そのため、外出の際は必ずハンカチを持参するように伝えています。
得意・不得意を自分自身で説明できるような支援
子どもが「自分は何が好きで何ができるだろう?」を明確にするためには、自分の得意・不得意を理解したり自覚したりする力が必要です。その上で、得意・不得意を他人にはっきりと説明できるスキルが身につけば「自分はこうすれば力を発揮しやすい」「ここは苦手なので手助けが欲しい」などを伝えられるようになります。
社会生活を助ける「自律スキル」と呼ばれるものです。
▼自律スキルを身につけるためにできること
- 「あなたはこれが得意なんだね」「これは苦手なんだね」と得意と苦手のどちらも肯定する
- 得意なことをどんどん伸ばしてあげる
- 自分の得意なことで誰かを助けてあげられた場合は褒める
- 自分の苦手なことで誰かに援助を求めることができた場合に「助けてって言えたからうまくいったね」と肯定する



得意なことをアピールしてうまくいった体験だけではなく「『できないことをできない』と周りに伝えたら協力を得られた」ことも成功体験の一つです。日々の小さな積み重ねで、自己肯定感を高められます。
まずは子ども本人と周りの支援者が特性を理解するところから
昨今では、社会に馴染むのが難しかった人を受け入れてお互いに尊重し合う「ニューロダイバーシティ(Neurodiversity、神経多様性)」という考え方が浸透しつつあります。発達障害の特性を活かして子どもの力を引き出すためには、まず「子どもの得意なこと・不得意なこと・好きなこと・苦手なこと」を知るのが大切です。
どんな人でも、得意・不得意はあります。子ども自身が力を発揮できる場所はどんなところで、発揮しづらい場所はどんなところなのか。まずはゆっくりと考えるところからスタートしてみてください。
▼こちらの記事もおすすめ
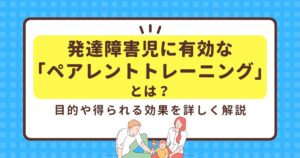
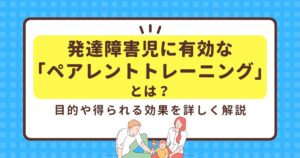
▼以下の記事を参考にして執筆しました
自閉スペクトラム症をご存じですか?|京都府自閉症協会
URL:https://as-kyoto.com/about/regit-resume/
ニューロダイバーシティの推進について|経済産業省
URL:https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/neurodiversity/neurodiversity.html


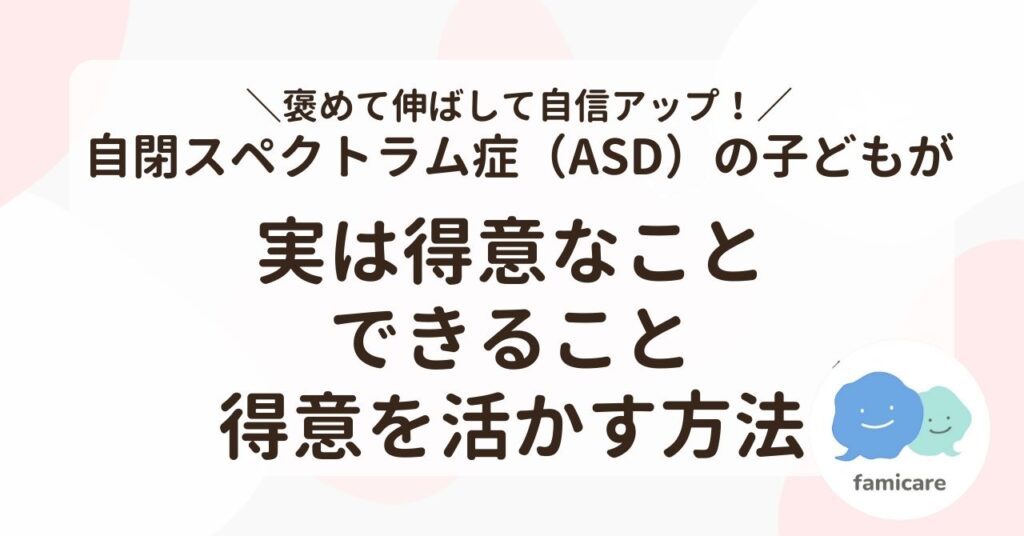

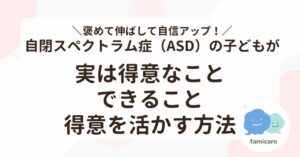

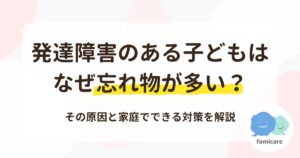

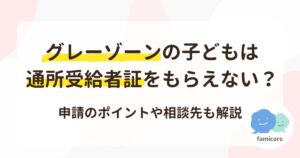
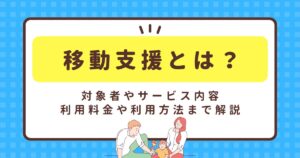
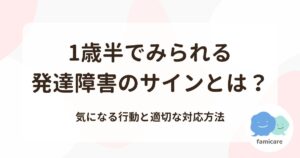
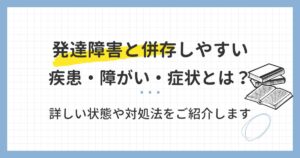
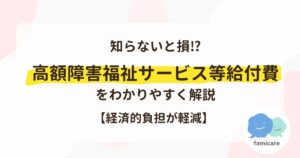
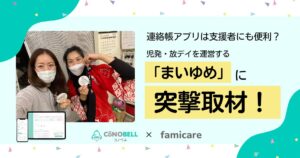
コメント