「外食でリフレッシュしたい、でも特性のある我が子にできるだけ無理はさせたくない」
子どもが発達障害と診断されているご家族で、そのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?発達障害のひとつ、自閉スペクトラム症と診断されている9歳の娘と暮らす筆者も、その一人です。
この記事では、筆者が自閉スペクトラム症の娘と少しずつ外食できるようになるまでの道のりや、実践したことをご紹介します。
たまには外食したいけれど一歩踏み出せない



いざ外食をしてみたけれど、うまくいかなかった…!
そんな経験のある方にとって「分かる分かる…我が家ももう一度やってみよう」と思っていただけるきっかけになると嬉しいです。
【娘について】
- 年齢:9歳
- 診断名:自閉スペクトラム症
- その他の情報:知的発達の遅れなし/興味やこだわりが強い/感覚過敏(主に視覚、聴覚)/強迫・不安症あり)
外食するときの娘の行動
自閉スペクトラム症と診断されている筆者の娘は、外食が苦手です。特に聴覚・視覚の過敏さやスケジュールが読めない不安感などから、外食を試みる際は、主に次のような行動がよくみられました。
【外食に行くまで】
- 「そもそも行きたくない」と泣いてしまう
- 「どこ行くの?何時に帰る?何のために?」と質問のオンパレード
【外食中】
- 混雑時に席へ案内されるまで待機できない
- ドリンクバーやおもちゃコーナーが気になり落ち着いて座っていられない
- 周囲の話し声や食器の音、視線にそわそわ
【外食から帰宅後】
- 外出疲れの反動か、癇癪や八つ当たりが増加



外食は「席が空くまで順番を待たなければいけないかもしれない」「注文してから何分ほどで料理がくるか読めない」など、見通しが立てにくい傾向にあります。その不安感やストレスから、エネルギーを消耗するようでした。
娘が訴えていた「外食したくない」理由
「親としてはたまには外食を楽しみたい、でも娘に無理はさせたくない」。そんな気持ちで揺れていた筆者は、あるとき娘に「外食に行きたくないと思う理由にはどんなことがある?」と尋ねてみました。そこで返ってきたのが、次のような答えです。
- 「自分でも分からないけど、何故かとってもつらい」
- 「外に出ると疲れる」
- 「好きなものを食べたいけれど、音が気になって食べられない」
- 「食べているのを見られるのが嫌、恥ずかしい」
- 「家でやりたいことがある」
やはり、感覚の過敏さやスケジュールの不安に関する訴えがほとんどでした。
また、癇癪に繋がるきっかけを少しでも避けるべく、外出先では親もつい気を張ってしまうもの。ネガティブな記憶はどうしても残るため「外出=注意されるかもしれない」と紐づきやすいのも、考えられる要因のひとつです。



いくら気を付けていても無意識にあれこれ注意してしまいがち…もちろん筆者も同じです。
「ゆっくり外食」を叶えるために実践したこと
「疲れるから行けない」と外食を拒む娘。とはいえ「できるなら行ってみたい…」とぽつりと言うときもありました。
「美味しいものを食べに行くささやかな楽しみを、ストレスを感じない範囲で知ってもらいたい」。そう考えた筆者が、快適な外食を叶えるために実践した例をご紹介します。
前もって見通しを立てて娘へ伝えておく
自閉スペクトラム症には、見通しを立てるのが苦手という特性があります。そのため、外食を考えている日の1週間ほど前から「〇日は外食へ行くよ」と伝えるようにしました。
その後、3日前を目途に具体的なスケジュールもお知らせ。「〇日にこのお店で外食をするよ」「〇時にはお店に着きたいから△時に家を出るよ」「お店にはこんなメニューがあるよ」など、事前に知ることで不安を拭えそうな項目を一緒に確認していきました。



「もしもこのお店が満員で入れなかったらあのお店に行こう」というように、計画が変更になった際の代替案も事前に伝えると、不安の緩和に繋げられます!
お店は娘の希望する場所を優先
外食をする際に最初に決めるのが「どのお店で食べるか」。自宅からの距離や大人のスケジュールでついお店を決めたくなってしまいますが、まずは「娘が行きたいと思える場所か」に重きを置いて検索しました。
子どもの「行きたい!」に大人が乗ることで、外食へのハードルを1つ下げられたように思います。
できるだけ感覚を刺激しない工夫をする
食べているときの視線や他のお客さんの話し声などが気になる娘のために、できるだけ感覚を刺激しない工夫を取り入れてみました。
▼例えば…
- 「好きなものを食べたいけど音が気になって食べられない」ので、耳栓やイヤーマフを持参
- 「食べているところを見られるのが嫌、恥ずかしい」ので、個室のあるお店を選ぶ
- 「トイレのエアータオルの音が苦手」なので、ハンカチを必ず持参



安心できる状況を娘に尋ねながら、サポートアイテムなどを使って心地よい環境に近付けていきました。
否定語をできるだけ使わない
この見出しから「注意しないっていうこと?それは無理…!」と思われた方もいるのではないでしょうか。しかし、「否定語をできるだけ使わない=注意しないこと」ではありません。
自閉スペクトラム症の人は「抽象的な指示」の意図をくみ取りにくい傾向があります。そのため「この場所では走ってはいけません」と言われると、「じゃあスキップならいいの?ジャンプは…?」との選択肢が残ってしまいやすいのです。
指示をする際には、できるだけ単語の数を少なくして簡潔に、かつポジティブに伝えるといいでしょう。
例えば「この場所は人がたくさんいるから走ってはいけません」ではなく「ここでは歩いてね」、「この場所では大きな声を出してはいけません」ではなく「静かに話そうね」と変換します。外食先へ行く前、外食中、否定語をちょっぴり言い換えるだけで親もポジティブになれるため不思議です。



うまくできたときには帰宅後に「守れたね」と思いきり褒めてあげると、自信もやる気もアップ!
時間を潰せるアイテムを持参
じっとしていられない場合や待ち時間を活用したいときのために、娘のお気に入りアイテムを持参。テーブルに広げても食事の妨げになりにくいよう、ミニサイズのノートやペン、シールなどが便利でした。



楽しく外食ができて自信がつくと、外出疲れの反動からくるイライラにも、少しずつ自分で対処できるようになりました。
▼娘のお気に入りおもちゃについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
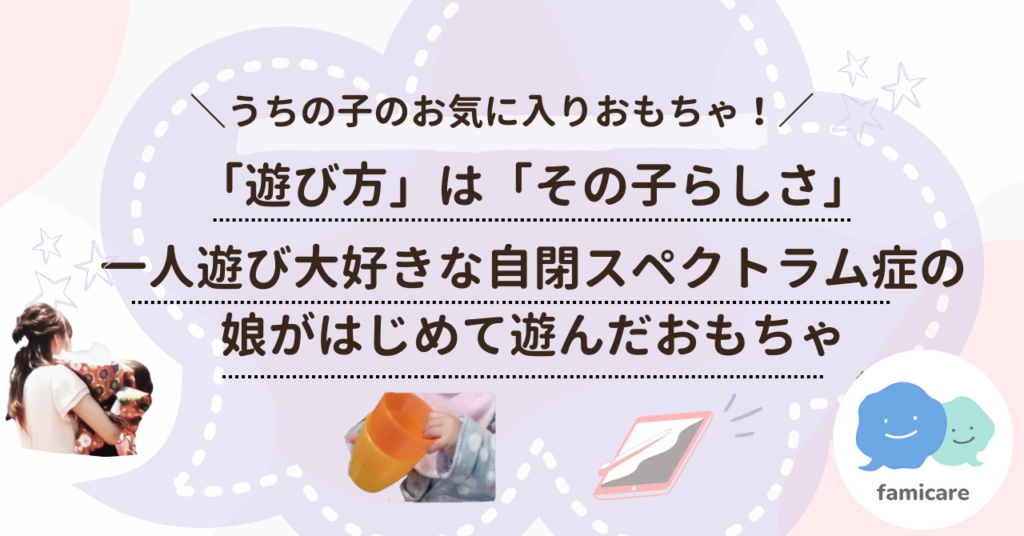
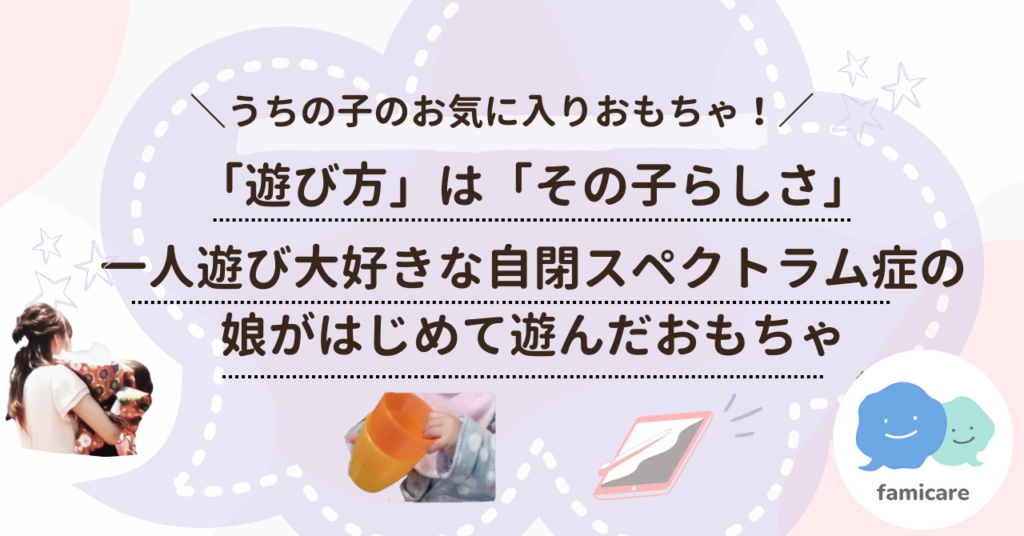
どうしても無理なら「おうちで非日常」もおすすめ
「何日も前から予定を伝えて楽しみにしていたのに、当日になって『やっぱり行かない』と言われてしまった」「いろいろと準備して行ったのに外食先で癇癪が起き、結局ヘトヘトになってしまった」…。筆者にとって堪えたパターンの一例です。
あの手この手と考えてみても、難しい場合がある。頭では分かっていても「いつになったら」と考えてしまいますよね。
娘にとって、そして筆者にとって外食がストレスになってしまいそうな際は、おうちで「非日常」を作ってリフレッシュしています。
キャンプ用テントを広げて非日常空間を演出
リビングにキャンプ用のテントを広げ、室内でアウトドア感を楽しむ方法です。「外食気分」を味わうため、好きなメニューを出前で頼み、テント内に置いたテーブルへ並べて食べます。
自宅なので、娘のお気に入りの遊び道具がすぐ近くに。とてもリラックスしながら楽しむ様子が見られます。移動の手間がなく天気にも左右されないのは、おうちキャンプの魅力です。
食器を変えて気分転換
あくまで「外食気分」のため、洗い物も極力削減します!



紙皿やペーパーカトラリーをあえて使うと「なんかパーティーみたい」と娘も嬉しそうでした。
食器以外にも、カフェミュージックを流してみたり間接照明にしてみたりなど「いつもと違う要素」をさりげなくプラス。ちょっとしたことですが、非日常を味わえるスパイスです。
大切なのは「成功体験」を一つずつ積み重ねること
「家族でおいしく楽しく外食したい」「今日は疲れたので食事は外で済ませたい」など、外食の目的はさまざま。子どもの特性を考えたとき、そのハードルは高く感じるかもしれません。
しかし「外食でのご飯がおいしかった」「約束を果たせた」など、一つひとつの成功体験が積み重なることでポジティブな記憶が残り、次も挑戦してみたいとの気持ちが生まれます。
時には「外食できないなら出前で外食ごっこだ~」とほどよく息抜きをしながら、我が子に合った方法をゆっくり探してみてください。
\おでかけ特集はこちら/
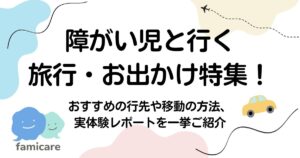
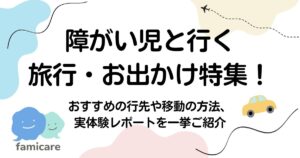


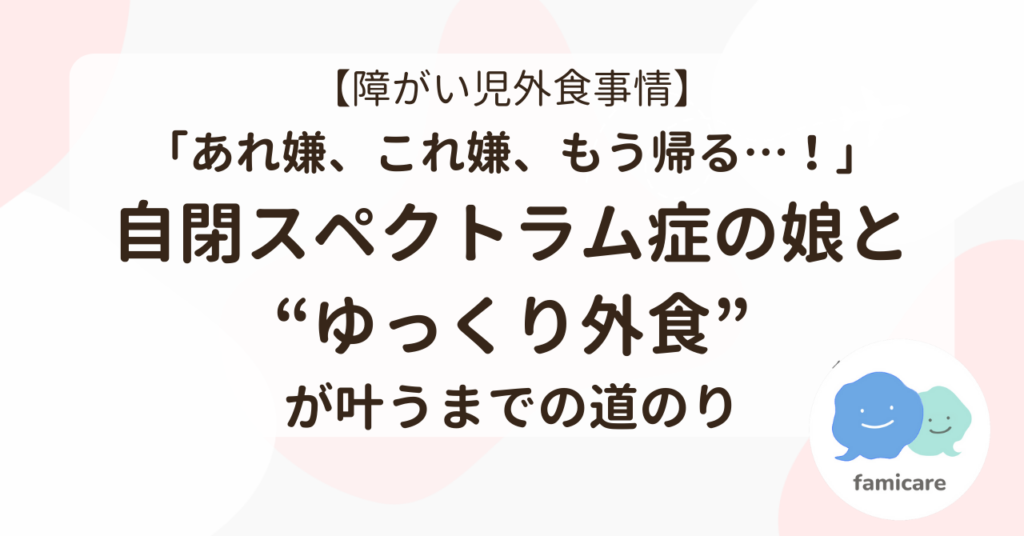

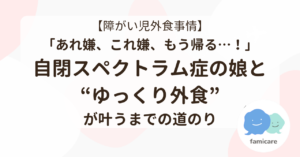


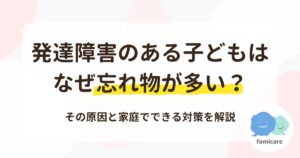

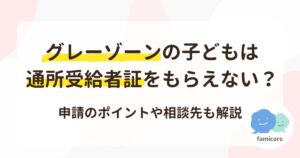
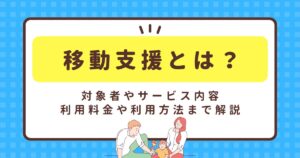
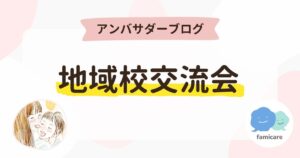
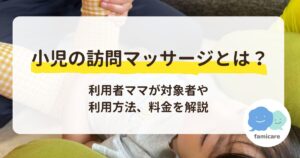
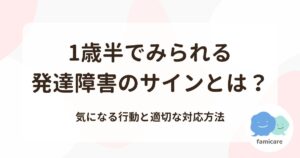
コメント