
医療的ケア児とおでかけしたいけれど、電車に乗るのはなんだか不安



電車でのおでかけは、まわりの人に迷惑をかけるんじゃないか…
と医療的ケア児との電車のおでかけで不安に思っている人は少なくないのではないでしょうか。
筆者もその1人でした。迷惑かけるんじゃないか、ベビーカー・車椅子ゾーンにはちゃんとたどり着けるだろうか、じろじろ見られるんじゃないか、などなどいろんな不安がありました。
でも、実際に電車でおでかけしてみたところ、想像していたよりずっとまわりの人は優しく、安全に移動することができたのです。その経験をもとに、今回は安心して電車に乗るための方法やポイントなどをここでご紹介したいと思います。
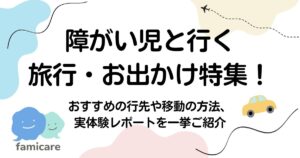
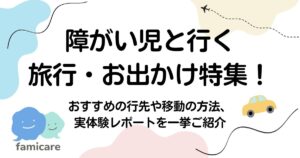
電車に乗る前に不安だったこと
電車にはじめて乗るまでは「どんな感じなんだろう」と不安に思うこともたくさんありました。
ベビーカーが邪魔になるのではないか
息子は1歳なのでベビーカーを使っています。そして、息子が使っているベビーカーは普通のものより2まわりくらい大きく、がっしりとしているため「電車に乗るには邪魔になるんじゃないか」というのが1番の不安でした。
ベビーカー・車椅子ゾーンまで辿り着けるかどうか
また、ベビーカー・車椅子ゾーンがあることは知っていましたが、そこに立っている人に嫌がられるんじゃないか、譲ってもらえないんじゃないかなど、場所取りの不安もありました。
緊急時にどうしたらいいのか
そしてさらに不安だったのが、息子に何かあったときの対応についてです。電車内でどのように対応したらいいのか、アンビューや酸素ボンベが必要になったとき、どのように場所を確保すればいいのかも不安な要素でした。
医療的ケア児と一緒に電車に安心して乗るためのポイント
そこで、安心して医療的ケア児の息子とはじめての電車を体験するために、困ったときのことを想定して対策や準備をしました。
1.電車のベビーカー・車椅子ゾーンをチェックしておく
電車には、JRや地下鉄などの鉄道会社に関わらず、ベビーカー・車椅子ゾーンが設けられています。このゾーンはベビーカーや車椅子を置くことができる大きめのスペースになっているので、電車内で安心して過ごすことができます。
「まわりの人の邪魔になってしまうのではないか」という不安な時も、乗る電車のベビーカー・車椅子ゾーンを事前に調べておくことで、居場所の確保をすることができて安心です。
ベビーカー・車椅子ゾーンは「Go! Free Space」というサイトなどで調べることができます。



乗る時にベビーカー・車椅子ゾーンに人が数人立っていましたが、私たちを見てすぐに場所を譲ってくれたので助かりました。譲ってもらった時はしっかりと顔を見てお礼を伝えました。
2.通勤ラッシュや帰宅ラッシュの時間を避ける
「大きなベビーカーやバギーで人に迷惑をかけるんじゃないか」と不安な人は、通勤ラッシュや帰宅ラッシュの時間の電車利用を避けましょう。
あまりに混んでいるとベビーカー・車椅子ゾーンも人でいっぱいになってしまい、そこまでたどり着くことも難しくなってしまいます。
用事のある時間にもよりますが、電車移動を予定した時点で、電車が混みにくい時間の移動予定を組んでおくのがおすすめです。
3.緊急用の酸素やアンビューなどの道具を用意しておく
これは電車に乗る時に限った話ではないかもしれませんが、緊急用の酸素やアンビューなど緊急セットを用意しておくことはとても大切なことです。
駅と駅との間隔次第ではありますが、いざ何かあったときは、できれば電車を降りて対処をすると、まわりの目を気にすることもなく冷静に対応することができます。
4.駅員の方に必要に応じて介助をお願いする
バギーや車椅子は重量があり、段差を乗り越えられない時もあります。そんな時は駅員の方に相談することで電車の乗り降りを介助してもらえます。
乗車や降車に時間がかかってドアが閉まってしまう心配などもないので安心です。注意点としては、介助を頼むと時間がかかり、予定の電車に乗れない場合もあることです。時間に余裕を持ってお願いするのが大切です。
実際に電車に乗っておでかけする流れ
実際に電車に乗っておでかけした経験をもとに、電車のおでかけの流れをレポートします。
1.目的地に向けて出発!
まずは事前に調べておいたベビーカー・車椅子ゾーンの車両のドアの列に並びます。
事前に乗る電車の車両数がわからない場合は、乗る電車が10両の場合でも15両の場合でも対応できるように、「Go! Free Space」の10両のベビーカー・車椅子ゾーンのページと、15両のベビーカー・車椅子ゾーンのページをそれぞれスクリーンショットで保存しておきます。
そして乗り場の電光掲示板を見て何両の電車に乗るのかを確認するときに、事前に保存しておいたスクリーンショットを見て確認できるようにしておきましょう。
2.電車に乗る
電車とホームの間には少し隙間や段差があるので、気をつけながら電車に乗車します。



足でベビーカーを持ち上げるようにして電車に乗りました。
ベビーカー・車椅子ゾーンがある車両のドアに並んでおくと、混んでいなければ、そのままベビーカー・車椅子ゾーンで場所を確保できます。



私が乗った時には人が数人立っていましたが、ベビーカーを見てすぐに場所を譲ってくれたのでとても助かりました。こういう時はしっかりとお礼を伝えることが大切だと思います。
自分の介助だけで乗車や降車をするのが不安な場合や隙間、段差が乗り越えなさそうな場合は駅員の方に介助を頼みましょう!車椅子用のスロープを用意してくれます。
3.子どもの様子を見ながら一緒に外の景色を眺める
電車に乗ったら子どもの様子を見ながら、一緒に外の景色を眺めたり、普段と少し違った環境を楽しんだりして過ごします。普段と違う様子や気になる様子があれば、無理せず途中で下車しましょう。



普段とは違う環境で、顔色が変わっていたり体調が悪そうにしていたりしていないかSpO2や心拍の数値を見ながら様子を見ていました。同時に息子が外の景色を眺められるようにベビーカーの位置を整え、退屈しないようにしました。
4.目的地に到着!電車を降りる
目的地の駅に到着したら、電車を降ります。段差や隙間に気をつけながら、乗る時同様、足でベビーカーを持ち上げるようにして降ります。



降りる時も誰も迷惑そうにはしておらず、私たちが降りられるようにちゃんとスペースを開けてくれていました。
電車でおでかけしてみてよかったこと
意外と他の人が優しいことに気づいた
電車に乗る前は、舌打ちをされたりため息をつかれたりするんじゃないかと不安だったのですが、そんなことは一切なく、1人の人が乗り降りするのと変わりない感覚でみなさん見守ってくれていました。とてもありがたかったです。
窓からの景色を見て楽しめる
電車でのおでかけの楽しみといえば、外の景色を眺められること。子どもと一緒にいろんな景色を楽しむことができます。なかなか落ち着くことができない子どもでも、外を眺めると気が紛れる可能性があるので、「〇〇があるね〜」と声をかけながら外を眺めることはおすすめです。



電車の中で退屈してしまうかな?と心配だったのですが、息子はずっと外を眺めていて、電車が走ることで変わっていく景色を楽しめていたのかなと思います。
電車での割引制度について
鉄道各社では、障害者手帳を持っている人向けに乗車料金の割引を提供しています。鉄道会社によって条件は異なりますが、乗車料金が半額になることが多くなっています。
チケットの購入の場合、介助者など大人はこども料金の切符を買うことで割引の代替とすることもできます。ICカードを利用する場合は、通常通り入場して退場の時に精算してもらいます。
中学生以上の子どもは障害者Suicaも利用できます。
医療的ケア児と一緒に電車で移動やおでかけ
たくさんの不安がある中で挑戦した医療的ケア児との電車でのおでかけ。
事前に準備しておくことで、不安も軽減され、安心して乗車することができました。また想像していたよりまわりの人たちは優しく、ベビーカーやバギーで電車に乗ることに対して特に何も思っておらず、「ベビーカースペースなんだから場所を譲るのは普通のこと」と思っているのではないかなと思いました。
医療的ケアのある子どもと電車でおでかけしてみたい人や、電車でおでかけする予定がある人が、この記事を読んで参考にしてもらえたら嬉しいです。


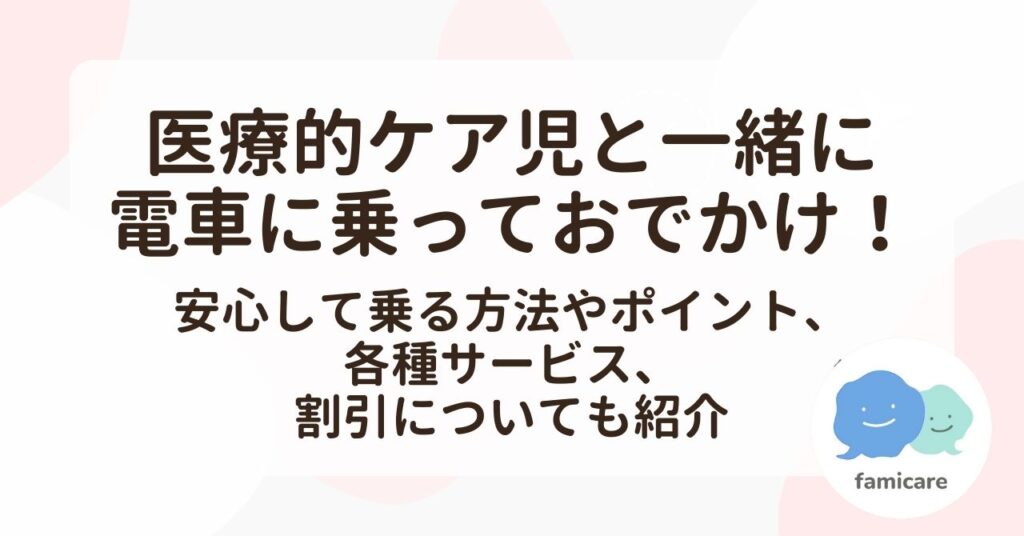

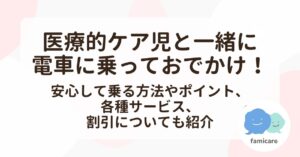

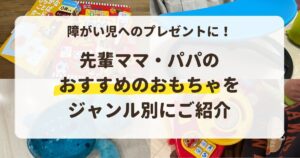
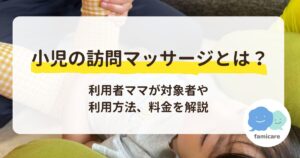

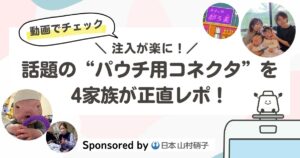
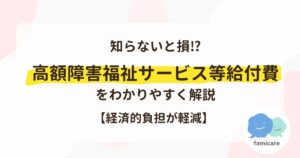



コメント