うちの子、他の子と比べて言葉が遅いかも



同年代の子どもと遊び方が違う気がする
そのような不安を抱えている保護者は少なくありません。特に1歳半頃になると、周りの子どもとの違いが目立ちやすくなり、発達について心配になる場合もありますよね。
この記事では、1歳半頃にみられる発達障害のサインについてわかりやすく解説します。



子どもの成長が気になるけど、どこに注目すればいいかわからない
そう悩んでいる方は、ぜひゆったりとお読みください。
一般的な1歳半児の成長の目安
1歳半は、子どもの発達が活発になる重要な時期です。この頃の子どもの発達の目安としては、以下のようなものが挙げられます。
- 歩行が安定し始めて行動範囲が広がる
- 指でつまんで積み木を積み上げることができる
- 「ママ」や「わんわん」などの意味のある簡単な言葉を話すようになる
- 興味のあるものを指差しで教える
- 大人の真似をして遊び出す



自分の意思を表現しようとする気持ちも強くなるため、イヤイヤや癇癪(かんしゃく)が見られる場合もあるでしょう。
また、この時期の子どもの成長発達を確認する「1歳半健診」もあります。発達の状況を観察し、疾患や障がいを早期発見する目的です。
1歳半健診での主なチェック項目って?
1歳半健診では、主に以下のような視点から子どもの成長発達をチェックします。
身体発達
- 片目ずつ手で隠しても嫌がらずに見るか
- 絵本を見て知っているものを指さすか
言語発達
- 「おいで」「ねんね」「ちょうだい」など大人の言う簡単な言葉がわかるか
- 何かに興味を持った時に、指さしで伝えようとしますか
社会性
- 周囲の人や他の子どもたちに関心を示すか
- 相手になると喜ぶか
発達障害のサインとして特に注意するポイントは「言葉でのやり取り」や「人との関わり方」です。
【参照】乳幼児健診における標準的な項目一覧|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/001028426.pdf
▼1歳半健診の詳しいチェック項目については、こちらの記事をご覧ください!
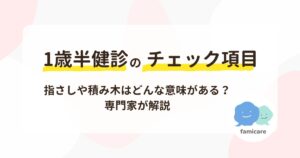
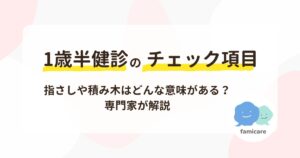
1歳半で注意したい発達障害のサインはある?



子どもの行動で気になることがあっても、それが発達障害のサインなのか判断に迷う…
記事を読みながら、そのように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。ここでは、1歳半の時期に注意深く見守りたいポイントをご紹介します。
コミュニケーションに関するサイン
言葉の発達について
1歳半頃の言葉の発達で気になる特徴には、以下のようなものがあります。
- 「ママ」「パパ」「わんわん」など意味のある単語が出ない
- 大人の話しかけに反応が薄い
- 欲しいものや興味のあるものを指で示さない
- 名前を呼んでも振り返らないことが多い
発達障害がある場合、脳の言語を処理する部分の発達がゆっくりだったり、音や言葉を理解する方法が他の子どもと違ったりすることがあります。そのため、周りの人が話している内容の意味を理解するのに時間がかかる場合や自分の気持ちを言葉で表現する方法がまだ身についていない場合があるのです。
とはいえ、言葉の発達には個人差が大きく、話し始めるのが遅くても、その後急に言葉が増える子どももいます。
そのため、上記の特徴が見られる場合でも、必ずしも発達障害というわけではなく、子どもなりの成長のペースの可能性があります。
非言語コミュニケーションについて
言葉以外のコミュニケーションにも注目してみましょう。
- アイコンタクトが取りにくい
- 「バイバイ」などの身振りを真似しない
- 大人と一緒に何かを見るのが少ない
発達障害がある子どもには、人の顔や表情から情報を読み取ることが苦手だったり、相手と気持ちを共有するのに時間がかかる特性を持つ場合があります。また、身振りや表情などの「言葉以外の方法」でのやり取りよりも、他のことに強く興味が向いている場合も少なくありません。
なお、発達障害の有無に限らず、子どもによっては人とのやり取りに時間がかかる場合もあります。
社会性・対人関係のサイン
他者との関わりについて
1歳半頃の社会性の発達で気になる行動には、以下のようなものが挙げられます。
- 大人や他の子どもにあまり関心を示さない
- 一人遊びを好み、他者と一緒の活動を嫌がる
- 抱っこを嫌がったり、身体接触を避けたりする
- 人見知りが全くない、または極端に強い
発達障害がある子どもは、人との関わり方を自然に身につけるのに時間がかかったり、感覚が敏感で人との距離感を調整するのが難しい場合があります。また、一人の時間や慣れ親しんだ環境の方が安心できるため、新しい人や場所に対して警戒心が強く現れるケースもあるのです。
なお、上記の行動も、子どもの性格や気質の違いを表している場合があります。内向的な子どもや慎重な性格の子どもにも見られる場合があるため、総合的な判断が重要です。
遊びや興味について
遊び方や興味の示し方にも特徴が現れる場合があります。
- 回るものをずっと見ている
- 同じ動作を繰り返す
- 逆さバイバイ(手のひらを自分に向けて振る行為)やクレーン現象(人の手を使って物を取ろうとする行為)が見られる
- つま先歩き、くるくる回りが見られる
- 新しい環境や変化に強い不安を示す
- おもちゃの本来の使い方とは違う遊び方をする (例:車を転がして遊ぶのではなく、ひっくり返してタイヤを回すなど)
発達障害がある子どもには、視覚や聴覚など特定の感覚に強い関心を持ったり、予測できる行動に安心感を覚えたりする特性がある場合があります。そのため、回転するものや繰り返しの動作に魅力を感じる、変化よりも同じパターンを好むといった傾向が見られるのです。
発達の個人差は、その子の個性や成長のペースを表しているものに過ぎません。活発な子どももいれば、慎重な子どももいますよね。
とはいえ「意思疎通が著しく難しい」「危険な行動を繰り返す」「感覚が過敏で生活に影響が出ている」などの様子がある場合は、子どもがより過ごしやすくなるような方法を一緒に考えてもらうため、かかりつけの小児科医に相談してみましょう。



「周りと比較してできるかできないか」ではなく「日常生活の中で困りごとが生じているか」という視点を持つとわかりやすいかもしれません
多くの保護者が気になること
1歳半の発達について心配になった際、多くの保護者が共通して抱く疑問があります。ここでは、特によくある質問にお答えします。
発達障害で現れやすい行動はある?
発達障害の子どもには、以下のような行動が見られる場合があります。
- 逆さバイバイ
- クレーン現象
- つま先歩き
- くるくる回る など
ただし、これらの行動が見られても必ずしも発達障害があるとは限りません。一時的に見られる場合もありますし、発達の過程で自然に改善していくケースもあります。
多動が見られたら発達障害?
あまりにも元気に動き回る子どもを見て「多動かもしれない」と心配になった経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし「活発=多動」とはいえません。
多動の判断には専門的な指標があり、保護者が日々の様子から「多動」と自己判断するのは困難です。に、気になる場合は専門機関に相談して医師の診断を受けるのも一つの方法です。
「1歳半頃の発達に不安を感じる…」そのとき知っておきたいこと



子どもの発達に不安がある…
そのように感じた際、家庭でできることや相談できる場所を知っておくと安心でしょう。
家庭では、子どもの興味のあることを保護者も一緒に楽しんでみるのがおすすめです。
たとえば
- 車のおもちゃが好きなら「ブーブー」と言いながら一緒に走らせる
- 絵本が好きなら膝の上で一緒にページをめくって音読する
また、しゃがんで目線を合わせ「ワンワンいるね」「おいしいね」などシンプルな言葉でゆっくり話しかけると、子どもが安心感を持ち、言葉への興味や理解が深まりやすくなります。
なお、忘れないようにしたいのは「兄弟姉妹でも発達のペースはそれぞれ」という点です。上の子が1歳で歩いたからといって、下の子も同じとは限りません。



子どもの個性やペースを尊重して小さな成長を褒めてあげられると、親自身もふっと肩の力が抜けます
迷った際は、まず身近な機関から相談してみましょう。かかりつけの小児科医に相談し、必要に応じて、以下の専門機関を紹介してもらうのもよい方法です。
具体的な相談先
市町村の保健センター:乳幼児健診でお馴染みの保健師が気軽に相談に応じてくれる
子育て支援センター:日常的な悩みから相談でき、他の保護者との情報交換も可能
発達支援センター:心理士に、より専門的な相談ができる
1歳半の子どもの発達は早期の気付きとサポートが大切
「我が子には、何か特別なサポートが必要かもしれない」と感じると、心配や混乱した気持ちになるのは自然なことです。しかし、子どもの特性に早めに気づくことで受けられる支援はとてもたくさんあります。
適切な時期に子どもに合った関わり方を見つけると、その子の持つ力をより引き出せる可能性があるのです。
保護者の直感は大切です。「何か違うかもしれない」と感じたら、一人で悩まずに専門機関に相談してみてください。子育てへの不安を共有できる場所が見つかると、子どもだけではなくあなたにとってもよりよい環境を整えやすくなります。
焦らず、温かい気持ちで子どもの成長を見守っていきましょう。
子どもの発達に関する素直な気持ちは、ファミケアの公式SNSやアプリでも話してみてね


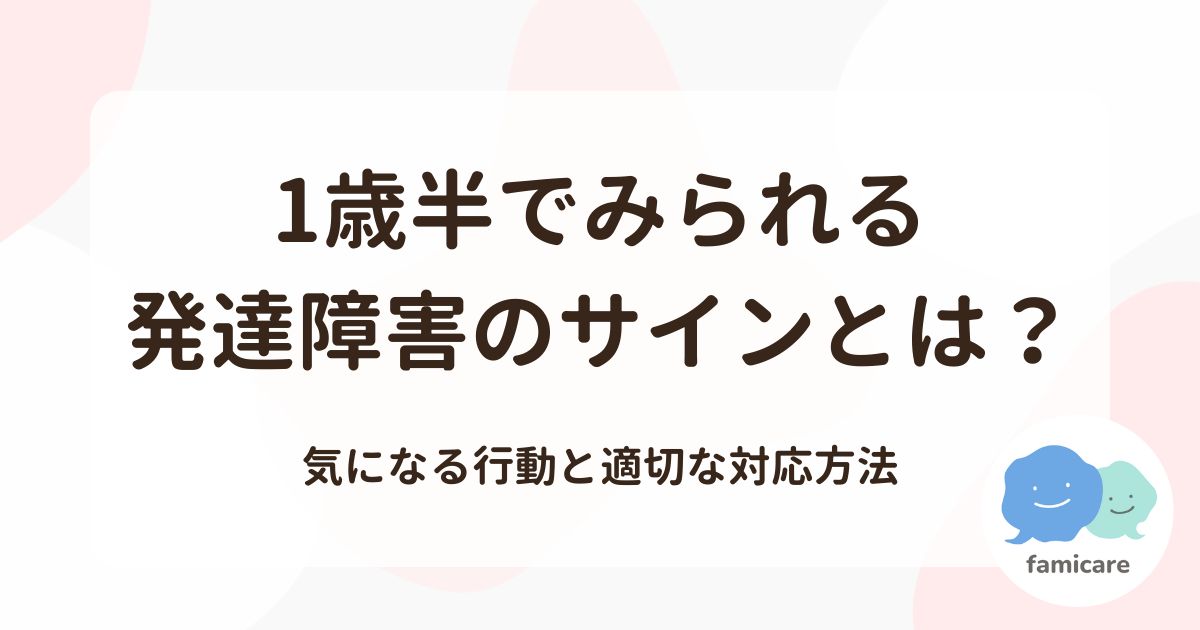
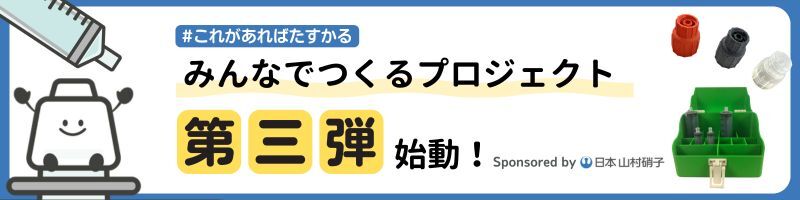

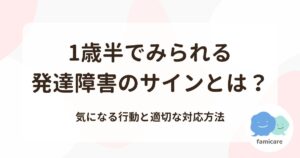

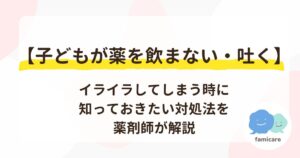
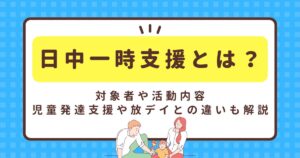
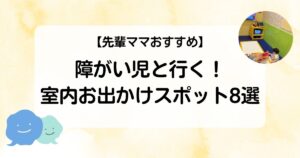
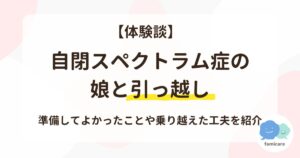

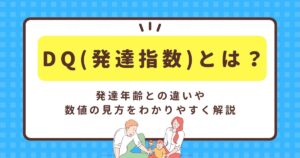


コメント