わが子に、いつ、どのように障がいのことを伝えればよいのか。多くの保護者の方が抱える大きな悩みの一つです。障がいについて適切な時期に寄り添った方法で伝えることで、子どもは自分自身をより深く理解し、自信を持って歩んでいけるようになります。
この記事では、子どもへの障がい告知を考えている方へ向けて、子どもの心に寄り添った伝え方のポイントをご紹介します。
障がい告知の際にはどんなことに気を付けるべき?



告知後はどんなふうにサポートしたらいい?
このように悩んでいる方はぜひお読みください。
障がい告知をする前に考えておきたいこと
子どもへの障がい告知をする前に考える前にまず考えておくとよいのが「伝えるタイミング」です。
障がい告知のタイミングは、子どもが「なぜ自分は他の人と違うのだろう」「どうして苦手なことがあるのだろう」と疑問を持ち始めたときが適切といえます。多くは、小学校中学年から高学年にかけての時期で、子ども自身が周囲との違いに気づき始めるのが特徴です。
また、告知の前に親の気持ちを整理したり、支援者とタイミングを相談したりする「土台作り」も大切です。土台作りをしておくことで、子どもの理解が得られやすく、より安心して障がい告知を行えます。例えば、日頃から「一人ひとりに得意なことと苦手なことがある」といった価値観を家庭で育んでおくのも大切です。
しかし、どんなに丁寧に準備をしても、子どもが必ずしも前向きに障がいを受け止められるとは限らない点も心に留めておきましょう。子どもがショックを受けたり、混乱したりするのも自然な反応です。



なるべく子どもが自分なりに受け止められためにに、親だけで障がい告知に取り組むのではなくに、子どもをよく知る専門家や療育の先生などに相談するのがおすすめです
▼障がい告知の土台作りについてはこちらの記事をご覧ください!
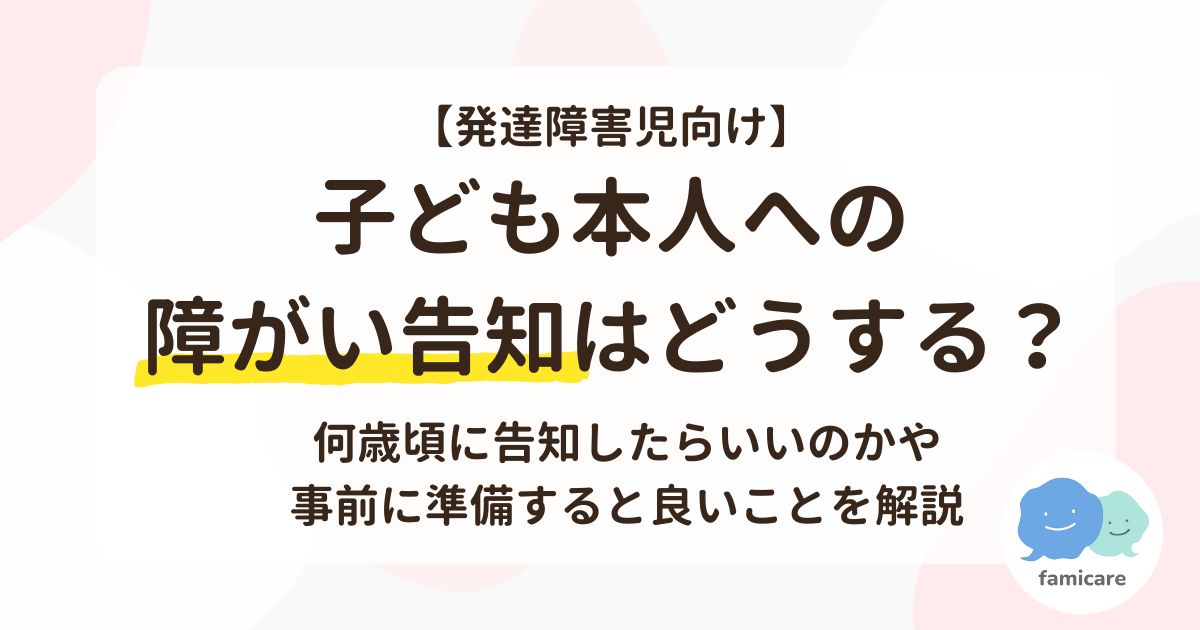
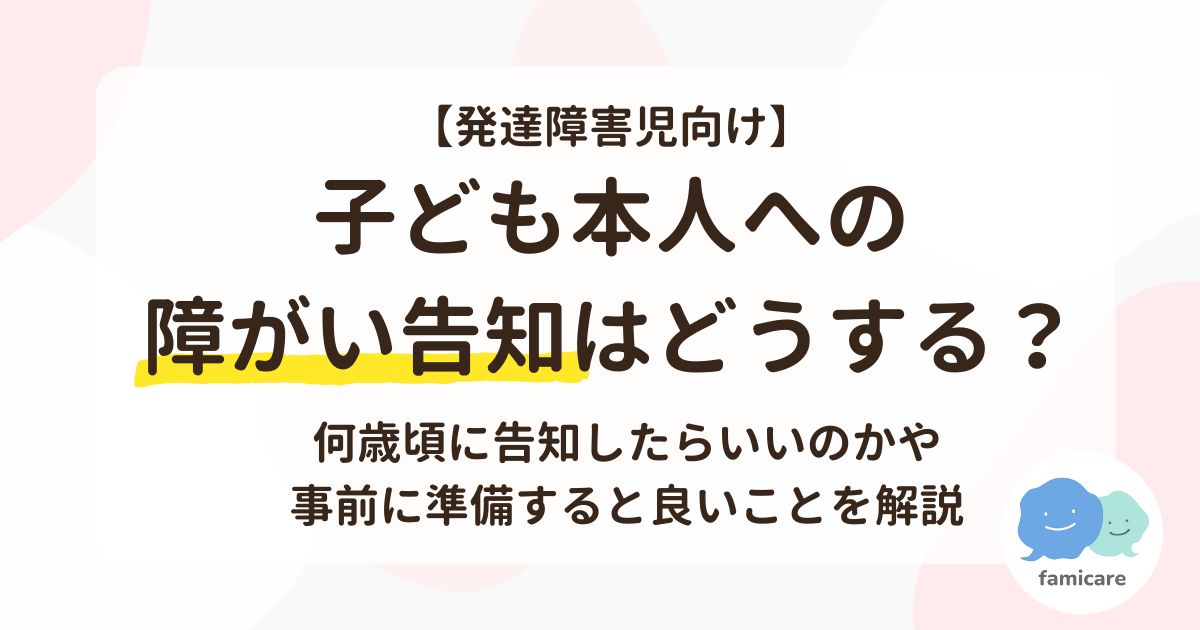
子ども本人に障がいを告知するときのポイント
障がい告知は一度きりのできごとではなく、子どもの成長に合わせて継続的に行うものです。以下のポイントを意識して、子どもの心に寄り添いながら伝えるとよいでしょう。
親子がリラックスできる環境で
障がい告知は、親子ともにリラックスできる環境で行うのがおすすめです。いつものくつろぎの時間や、二人だけでゆっくり話せる場所を選ぶとよいでしょう。
子どもが緊張していると感じた場合は、無理に続けず、別の機会を設けても構いません。また、親自身が緊張や不安を感じている状態では、その緊張感が伝わって子どもを構えさせてしまう可能性があります。親自身の精神状態もよく見極め、落ち着いて話せる状況を整えることが大切です。
「大事な話があるから聞いてほしい」と前置きをして、子どもの気持ちの準備ができてから話し始めるとよいでしょう。



焦らず、子どものペースに合わせることを心がけてください
「障がい=悪いこと」という言い回しをしない
障がいについて話す際は「障がい=悪いこと」という印象を与えないよう注意が必要です。「病気」「異常」「劣っている」といった否定的な表現は避け「特性」「個性」「違い」という言葉を使うとよいでしょう。
「あなたには○○という特性があって、それは決して悪いことではない」「みんなそれぞれ違った特性を持っている」といった伝え方で、子どもが自分を否定的に捉えないようサポートできると安心です。



子どもにとって「障がいは自分の一部」と感じられるのが理想です
「障がい名」だけではなく「障がいによる特性」を伝える
単に診断名を告げるだけでなく、その障がいによってどのような特性があるのかを具体的に説明すると、子どもにとってわかりやすくなります。たとえば「注意欠陥多動性障がい(ADHD)」という名前だけでなく「集中することが苦手だったり、じっとしていることが難しかったりする特性がある」と、できるだけ具体的に説明します。
また、困ることだけではなく、その特性から得られるよい面も一緒に伝えると、子どもは自分の特性をバランスよく理解できるようになります。



「集中は苦手だけど、好きなことには人一倍熱中できる」といった伝え方が効果的です
苦手なことがあるのは当たり前だと伝える
誰にでも、得意なことと苦手なことがあるものです。その事実を、具体例を交えてわかりやすく説明しましょう。
「お父さんは料理が苦手だけど、車の運転は得意」「お母さんは歌うことは苦手だけど、絵を描くのは上手」と身近な例を挙げると、子どもは苦手なことがある自然さを理解できます。そして「あなたにも苦手なことがあるけれど、それは当たり前のこと。そして、あなたには素晴らしい得意なこともたくさんある」と伝えると、子どもの自己肯定感を守りながら障がいについて理解を促せます。
周囲に話すかは自分の自由だと伝える
「障がいのことを友だちに話すかどうかは子ども自身が決められる」ことを伝えるのも、障がい告知では大切です。「このことを誰に話すかは、あなたが決めていい。話したくなったら話せばいいし、話したくなければ話さなくてもいい」と、子どもの主体性を尊重して伝えるとよいでしょう。
ただし、困ったときには信頼できる大人に相談する大切さも併せて伝えておくのが重要です。自分の障がいについて主体的に判断できるよう、選択肢があることを知らせると、子どもの自立心を育めます。
障がい告知後も断続的なサポートを



障がい告知を終え、あとは子ども自身がどう受け止めるか…その先でできる親としてのサポートが知りたい
このように考える方もいらっしゃいますよね。
障がい告知は一度で終わりではありません。子どもの成長に合わせて、継続的なサポートが必要です。以下のポイントを意識して、長期的に子どもを支えていきましょう。
質問があれば年齢に応じて正直に答える
子どもから障がいについて質問されたときは、年齢に応じて正直に答えてあげてください。難しい内容でも、子どもが理解できる言葉で説明するのが大切です。
「なぜ自分だけ?」「将来はどうなるの?」といった質問にも、事実を隠さず、希望を持てるような答え方を心がけるとよいでしょう。わからないことがあれば「一緒に調べてみよう」と提案して一緒に学ぶ姿勢を見せると、子どもの不安を和らげられます。
ただし、質問されるタイミングによっては、「ちょっと後で」と答えを先延ばしにしてしまったり、慌てて曖昧な答えをしてしまったりするケースがあるかもしれません。子どもに不信感を与えたり、さらなる不安を招いたりするのを避けるためにも「いまは時間が取れないから〇時になったら話そう」と具体的な時間を示すなど、子どもの質問を大切にしていると伝わるような対応を心がけましょう。



正直で温かい対応が、子どもとの信頼関係を深めます
「一人じゃない」ことを繰り返し伝える
子どもが孤独感を感じないように「一人じゃない」と繰り返し伝えるのも非常に大切です。家族はもちろん、同じような特性を持つ人たちや理解してくれる人たちがいることを具体例とともに説明します。
「あなたと同じような特性を持つ有名人もいる」「支援してくれる先生や友だちがいる」と具体的な情報を共有すると、子どもは安心感を得られます。



なにより「家族の愛情は変わらないこと」を言葉と行動で示し続けるのが、子どもの心の支えです
日常生活は変わらないことを確認する
障がいを知ったからといって、日常生活が大きく変わるわけではないことを確認しましょう。いままで通り学校に通い、友だちと遊び、家族と過ごすことができることを伝え、子どもの不安を取り除いてください。
「いままで通り、あなたはあなた。変わるのは、自分のことをより深く理解できるようになったということだけ」と説明すると、子どもは安心して日常を送れるようになります。必要に応じて支援方法を調整することはあっても、子どもの存在価値や家族の関係性は何も変わらないと強調しましょう。
成功体験を積み重ねる機会を作る
子どもが自信を持てるよう、得意なことや好きなことを伸ばす機会を積極的に作るのもおすすめです。小さな成功でも認めて褒めると、子どもの自己肯定感を高められます。
習い事やクラブ活動、家庭でのお手伝いなど、子どもが活躍できる場面を意識的に設けるのもよいでしょう。できた・認められたという体験を重ねると、子どもは「障がいがあっても自分には価値がある」と感じられるようになります。



成功体験は、将来への希望と自信の源です
周囲との連携をする
学校の先生や支援者との連携を密にし、子どもを多方面からサポートする体制を整えましょう。子どもの特性や支援方法について情報を共有して、一貫したアプローチで子どもを支えることが重要です。
また、必要に応じて専門機関や同じような境遇の家族とのつながりも大切にできると安心です。障がい者支援センターや親の会など、地域の支援ネットワークを活用すると、子どもと家族がより心配なく過ごせる環境を作れます。



一人で抱え込まずにチーム一丸となって子どもの成長を支えていけると、保護者自身も安心です
障がいを知るのは「自分を認める」ための大切な一歩
障がい告知は、子どもが自分自身を深く理解して、ありのままの自分を受け入れるための重要なステップです。自分の特性を知ると、子どもは自分らしく生きるための方法や工夫を見つけられるようになります。
困ったときに適切な支援を求められるようにもなるのも、障がい告知から得られる大きな結果です。丁寧な告知とその後の継続的なサポートで、わが子が自分らしく歩んでいくのを見守っていきましょう。


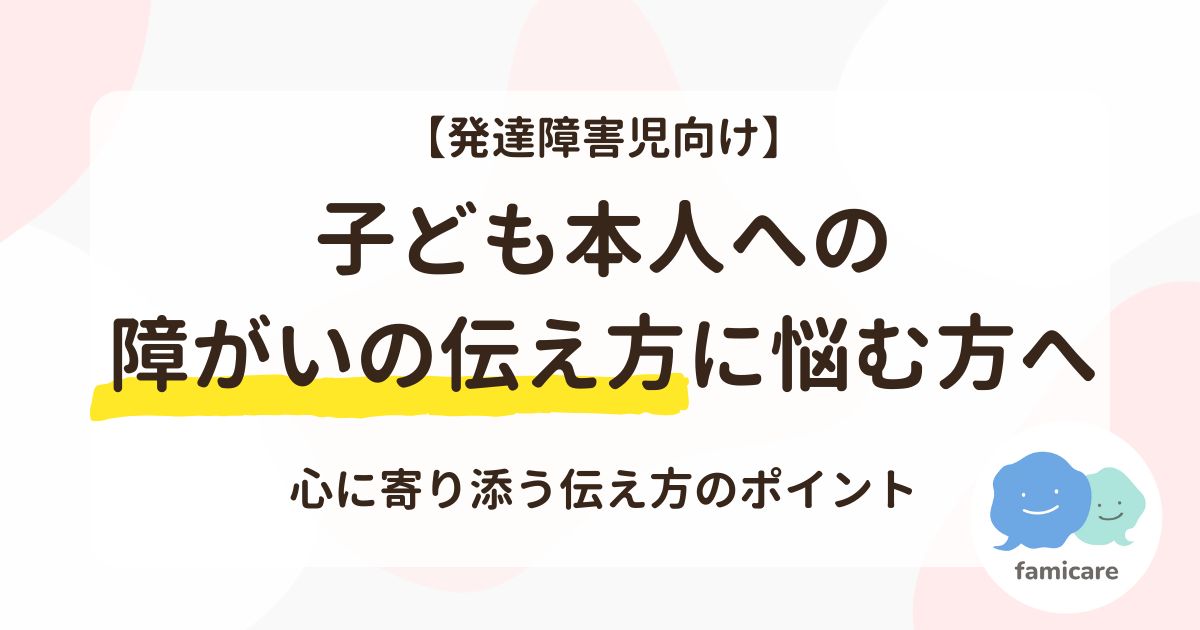

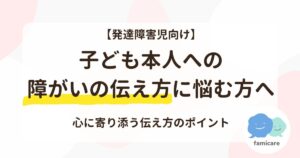

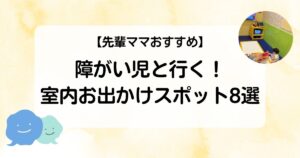
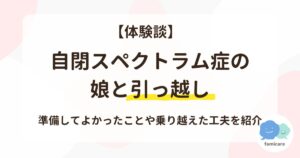
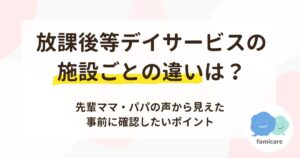

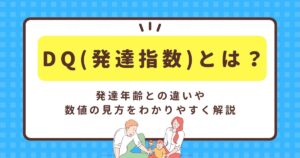

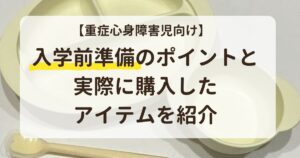

コメント