2025年度の補装具費支給制度の改正によって、補装具に使われる「完成用部品」のリストが大きく見直され、多くの部品が支給対象から外れました。
このことにより一部では
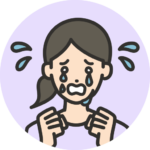
これまでと同じ補装具を申請したのに、今年は通らなかった
という声も聞かれています。
そこでこの記事では、2025年度の補装具費支給制度の改正で何が変わったのか、そして申請や修理の前に確認しておきたいポイントについて、できるだけわかりやすく解説します。
補装具費支給制度とは?
補装具費支給制度は、障害のある人が日常生活や社会活動を行うために必要な補装具の購入や修理にかかる費用を、自治体が補助する制度です。
▼詳細は以下の記事を参考にしてください
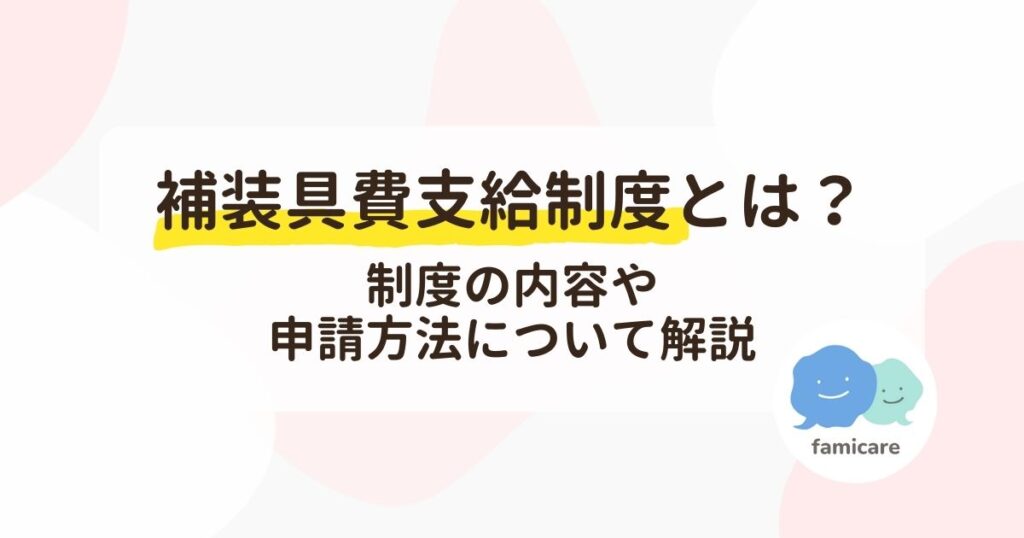
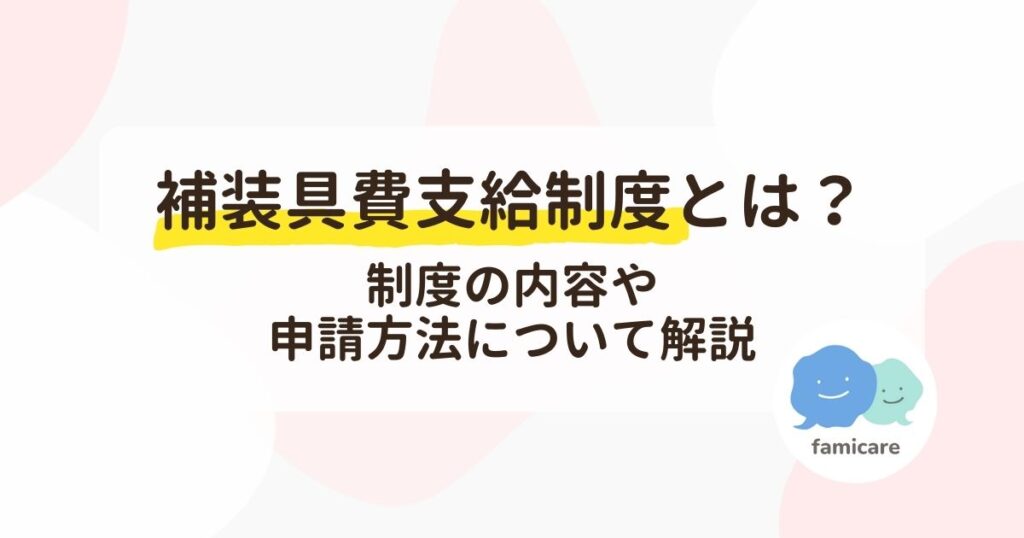
2025年度の補装具費支給制度改正で何が変わったのか
2025年度の制度改正により、補装具に使われる完成用部品のリストから多くの項目が削除されました。完成用部品とは、補装具をオーダーメイドで製作する際に必要な部品です。
障がい児・者の使用している車椅子や姿勢保持装置、装具などは一人ひとりの状況に合わせてオーダーメイドで作られています。その際に使われる一つひとつのパーツを「完成用部品」といいます。
完成用部品は、厚生労働省が専門的な審査・評価を経てリスト化しており、補装具支給制度の対象となるのは、この「完成用部品リスト」に載っている部品だけです。
「完成用部品リスト」は、市場価格の変動やニーズの変化を考慮して、厚生労働省の「補装具評価検討会」で毎年内容が見直されています。そして今年度の改正では、これまで対象となっていた多くの完成用部品がリストから削除=制度の対象から外れることとなりました。
制度改正による障がい児家族への影響
リストから削除された完成用部品には、子ども用車いすや姿勢保持装置のヘッドサポート、クッション、テーブル、ベルトなど、姿勢保持や安全性の確保に欠かせない重要なパーツが含まれています。
これまで支給対象だった部品が対象外となることで、補装具の種類によっては新規の申請が難しくなります。また、以前補装具費の支給を受けて使用している補装具であっても、修理時に必要な部品がリストから外れてしまった場合、補装具費の支給対象外となる可能性があります。
完成用部品から削除=使用不可ではない
しかし、完成用部品のリストから外れたからといって、その部品が使えなくなるわけではありません。場合によっては特例補装具費や一部特例という申請方法を利用できます。
申請の後、市区町村や身体障害者更生相談所で必要性が認められれば、補装具費の支給を受けることが可能です。
身体障害者更生相談所とは?
身体障害者更生相談所は、障害のある人や家族の相談に応じたり、補装具の処方や適合の判定、市区町村への技術支援などを行う専門機関です。
では、一部特例と特例補装具費について、どのような申請方法なのか解説していきます。
一部特例で申請
完成用部品リスト外から使用する部品が1つだけの場合は「一部特例」として補助が認められることがあります。
また、完成用部品リスト外のものであっても、市販のクッションやスイッチなどは条件を満たせば支給対象になり、基準外の部品としてカウントしない特別な扱いになっています。



市販のクッションやスイッチは特例の部品として数えなくていいので、他にもう1つだけ基準外の部品を使っても、一部特例として認められる可能性があります!
特例補装具で申請
「特例補装具」とは、国の基準に定められた名称・型式・基本構造などによる製作ができない補装具について、障害の状況や生活環境など「真にやむを得ない事情」があると認められた場合に、更生相談所の判定を経て支給対象となる制度です。
つまり、制度の対象外の補装具についても、子どもの状態などから「どうしても必要である」と認められた場合に限り、特例として申請できるということです。
ただし、「必要性」を証明するために、審査に提出する書類作成が必要です。また、申請までの負担が大きいものの、申請したからといって必ず支給が認められるわけではありません。自治体により、対応には差があります。
さらに、厚生労働省が定める『補装具費支給事務取扱指針』では、特例補装具を支給した場合、「本当に必要なものだったかどうかを確認するために」自治体には支給後の使用状況についても確認し、その結果を記録することが求められています。本人や家族、業者などにヒアリングしたり、写真や使用実績をもとに記録を残すケースもあります。



特例補装具は、基準に合わない部品でも「これは必要」と認められたときに使える制度です。身体状況によってやむを得ない場合などには申請できる可能性もあるので、困ったときは、医師やリハビリスタッフ、補装具業者の方に相談してみましょう。
補装具の申請・修理前に注意しておきたいこと
今回の補装具制度の改正をうけ、新しく補装具を申請する場合や修理を依頼する場合に注意しておきたいポイントをまとめました。
業者や自治体窓口での事前確認
申請の前に、補装具業者や自治体の窓口に相談し、使用する部品が支給対象かどうか、費用負担がどうなるかを確認しておきましょう。
特例補装具費の対象になるかどうか
必要な部品が基準外となっていても、一部特例や特例補装具費として申請できる場合があります。「通らないかも」と思っても、あきらめずにまずは相談してみることが大切です。
自治体ごとの運用の違い
同じ補装具でも、自治体によって判断や対応が異なることがあります。申請の流れや判断基準について、地域の制度運用や担当者の説明をよく確認しておきましょう。
修理に限っては、対象となる場合もあるみたい。「無理かも」と思っていても、まずは一度相談してみるといいよ!
補装具費支給制度の情報はどこで得られる?
制度の最新情報は、厚生労働省の公式サイトで確認できます。また「補装具格差をなくす会」がSNSを通じて情報を届けています。
さらに、現在利用している補装具の業者の方に相談してみるのもおすすめです。実際の申請経験や対応事例など、実務に基づいた具体的なアドバイスが得られるかもしれません。
必要な支援を受けるために制度の動きに目を向けよう
2025年度の改正では、多くの完成用部品が見直されました。その影響で、補装具費の申請が通らないケースも一部で出てきています。一部特例や特例補装具などの対応策も用意されているものの、申請が必ず通るとは限りません。
障がい児家族のできることとしては、まずは制度改正の内容について知ることです。国の制度は簡単に変えることができませんが、支給対象外となる理由や特例で対応できる可能性を知っておくことで、申請時の説明や交渉がしやすくなります。



今後の制度見直しに向けて、当事者の声を届けていくことも大切ですね。
【参考】
補装具費支給制度に関する通知(令和6年度)|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001494338.pdf
補装具評価検討会|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_141301.html
2025年度・補装具費支給制度が改正されました| 株式会社コボリン
https://koborin.com/topics/blog/24956/
身体障害者更生相談所|WAM NET(ワムネット)


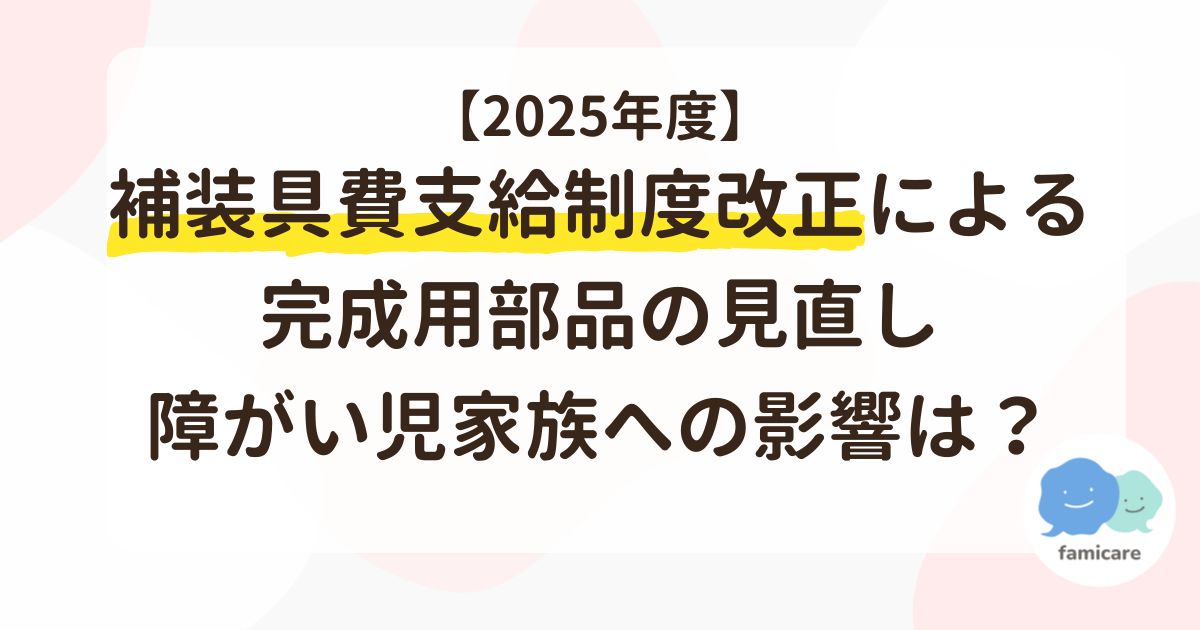

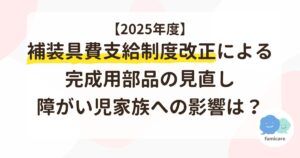


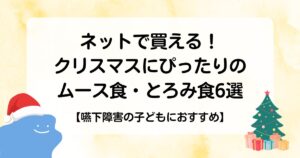
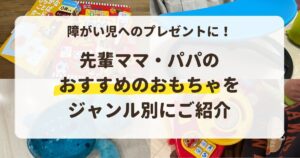
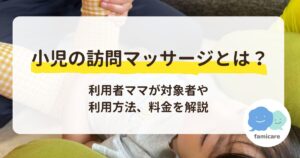

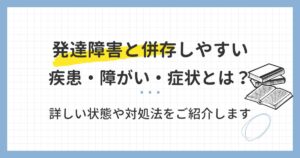
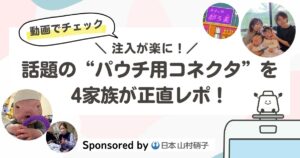
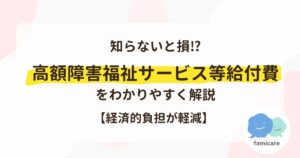
コメント