障がいを持つ子どもの親として、いつかは向き合う「障がい告知」。

子どもへの障がい告知は必要?



伝えるタイミングがわからない



障がい告知にはどんな準備が必要?
このような疑問は、多くの保護者が抱える共通の悩みです。
この記事では、子どもへの障がい告知のタイミングや事前準備について丁寧に解説していきます。わが子への障がい告知に不安や迷いを感じている方は、ぜひゆったりとお読みください。
子ども本人に障がい告知をする目的
そもそも、子どもへの障がい告知は必要なの?
そのように考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
子どもへの障がい告知は、決して「障がいがあることを受け入れさせる」ためだけに行うものではありません。障がい告知の本当の目的は、子ども自身が自分を理解してよりよい人生を歩むための土台を築くことです。
多くの子どもたちは、成長の過程で周りの子どもたちとの違いに気づき始めます。勉強が思うようにできない、友達とのコミュニケーションがうまくいかない、そんな経験を重ねるなかで「自分は悪い子だ」「自分には能力がない」と自己評価を下げてしまうケースも少なくありません。
障がい告知は、そうした負の感情を抱く前に、あるいは抱いてしまった後に「うまくいかなかった理由」を正しく理解して「今後どうすれば自分らしくよい結果につなげられるか」を考えるきっかけを与えます。



将来的な自立を目指すうえで「自分を理解する」のは大切な一歩なのです
子どもに障がい告知をするタイミング
障がい告知のタイミングは、子どもによって一人ひとり異なります。年齢だけではなく、子どもの理解力や心の準備状況をふまえた総合的な判断が大切です。では、どのような時期が適切なのか、具体的にみていきましょう。
「障がいを理解することが力になる時期」が告知の適切なタイミング
適切な告知のタイミングは「障がいへの理解が子どもにとって力になる時期」です。つまり、障がいについて知ることで、子どもが生活の中で抱える困難や課題について「なぜうまくいかないのか」の理由を理解し、これからどう対処していけばよいかを考えられるようになる時期を指します。
このタイミングを見極めるポイントは、日常生活のなかで子どもが見せるサインにあります。
たとえば、周りの子どもとの違いについて質問するようになったり「なぜ自分だけできないの?」という疑問を口にしたりする時期です。学校や園での困りごとが増え、子ども自身が「何かおかしい」と感じ始めている様子が見られる場合も、告知を検討する時期かもしれません。
また、保護者が「この子なら理解できそう」「今なら受け入れられそう」と感覚的に感じる瞬間も大切にしてください。日々子どもと向き合っているからこそ感じ取れる、子どもの心の準備状況があります。



この直感的な判断も、告知のタイミングを決める重要な要素の一つです
障がい告知をするタイミングの一例
具体的なタイミングの例として、以下のような場面が挙げられます。
- 小学校入学前後で学習面や生活面での困りごとが明確になってきたとき
- 中学年頃に友達関係での悩みが増え始めたとき
- 高学年で将来について考える機会が増えたとき
- 進学や進路を選ぶ際に支援の必要性について話し合うとき
一方で、子どもが大きなストレスを抱えている時期や家庭環境が不安定なとき、重要な行事や試験の直前などは、告知によってさらなる負担をかける可能性があります。そのため、この期間に障がい告知をするのは避けるのがおすすめです。



子どもの心の状態を慎重に見極めていきましょう
障がい告知をする前にするべき「土台作り」



タイミングがきても、何からしたらいいかわからない



いざとなったら伝え方が難しくて戸惑ってしまう
そう感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
障がい告知の前には、心の準備や環境を整えて「土台作り」をしておくと、子どもにとっても保護者にとっても安心できます。完璧な準備を目指す必要はありませんが、主に以下のポイントを押さえるとより穏やかな気持ちで告知に臨めるでしょう。
まずは親自身が「子どもの障がい」と向き合う
障がい告知の土台作りは、保護者自身の心の整理から始まります。子どもに障がいがあることを受け入れ、それを子どもにとってマイナスではなく「理解すべき大切な特性」として捉えられるようになるのが重要です。
とはいえ、気持ちの整理をするのは簡単なものではありませんよね。しかし、保護者が障がいに対してネガティブな感情を持ったままでは、その気持ちが子どもに伝わってしまいます。「障がいがあってもあなたは素晴らしい存在だ」「障がいは、あなたらしさの一部なんだ」と心から思えるようになるまで、時間をかけて自分自身と向き合ってみてください。



カウンセリングを受けたり同じ境遇の親御さんと話したりすることで、気持ちの整理ができる場合もあります。保護者自身が安定した気持ちで告知に臨めるのが、子どもにとって何よりの安心材料です。
本人にとってのタイミングを大切にする
告知のタイミングは、親の都合ではなく、あくまでも子ども本人にとって最適な時期を選ぶのが大切です。子どもの発達段階や理解力、心の準備状況を総合的に判断するとよいでしょう。
特に重要なのは、子どもが「知りたい」と思っているサインを見逃さない姿勢です。自分について疑問を持ち始めたとき、周りとの違いについて質問してきたときなどは、子ども自身が答えを求めているタイミングかもしれません。
また、告知後のフォローアップの時間が十分に確保できる時期を選ぶのも大切です。



告知は一度きりのできごとではなく、継続的なサポートが必要な工程といえます。子どもの反応に応じて、丁寧に対応できる環境を整えておくのがおすすめです
家族だけで決めずに支援者と相談する



自分の子どものことなんだから、親である自分がしっかり決めなければ…
そのように抱え込む必要はありません。障がい告知は、心理カウンセラーや医師をはじめ、学校の先生、療育の専門家など、子どもをよく知る人たちの意見を聞くとより適切な判断がしやすくなります。
支援者との相談では、告知の方法や言葉の選び方についても具体的なアドバイスを受けられるかもしれません。子どもの特性に応じて、どのような伝え方が最も理解しやすいか、どんな準備が必要かを一緒に考えてもらいましょう。
また、告知後のサポート体制についても事前に話し合っておけると安心です。告知の内容や方針を支援者間で共有すると、学校や療育の場でも一貫したかかわりができ、子どもにとってより安定した環境を作れます。



子どもが混乱したり不安になったりした際にどこに相談すればよいか、どのような支援が受けられるかを明確にしておくと、親自身も安心して告知に臨めます
子どもの心に届く障がい告知は準備から
障がい告知は、子どもが将来に向けて自分らしく生きていくための準備となる大切な機会です。だからこそ、事前の心の準備や環境づくりが重要になります。焦らずに、保護者自身の気持ちの整理や子どもの様子を見ながら、支援者の方々と相談しつつ進めていけるとよいでしょう。
「すべてを完璧に準備しなければ」と構える必要はありません。あなたなりのペースで子どもに寄り添いながら進めていくのが、何より大切です。
時間をかけて土台を整えることで、子どもにとってもより受け入れやすい告知となり、その後の成長にもつながっていきます。一人で抱え込まず、周りの支援を受けながら、子どもと一緒にゆっくりと歩んでいきましょう。


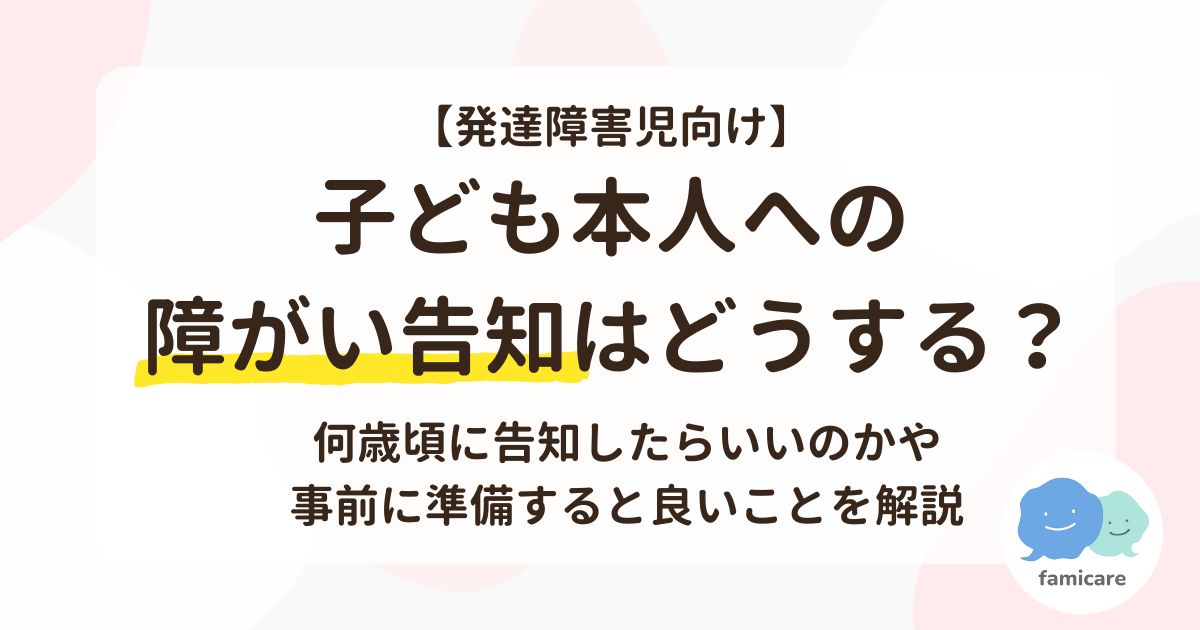

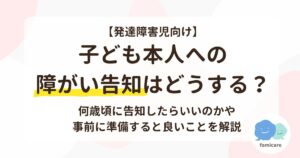

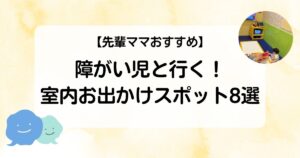
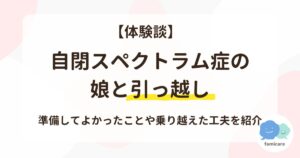
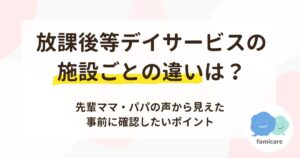

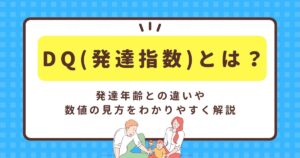

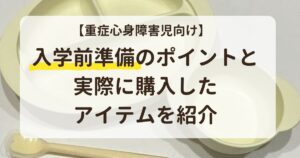

コメント