発達障害の特性と向き合う際、一緒に考えておきたいのが「併存症」です。
発達障害の一種、「自閉スペクトラム症」と診断されている9歳の筆者の娘は、コロナ禍の心配から、併存症の一つ「不安障害」と診断されました。現在は、認知行動療法にて治療中です。
この記事では、娘の症状から併存症とより向き合おうと決めた筆者が、発達障害の併存しやすい疾患や障がい、症状などを解説します。
「そもそもどんな状態を指すの?」「どのように対処したらいいの?」など、 発達障害の併存症に興味のある方はぜひご覧ください。
この記事を監修した専門家

株式会社ニト 訪問看護事業部
訪問看護ステーション ニト四谷・管理者
小児専門チーム・看護師 藤田有美(ふじたゆみ)さん
2022年 株式会社ニトに入社し、成人精神科を小児精神科を兼任。2025年8月にはニト初となる小児専門拠点、「訪問看護ステーション ニト四谷」の管理者に就任予定。成人と小児の両方で経験を積んだ今、その子の10年先を見据えたケアを目指している
株式会社ニト:https://nitor.co.jp/
発達障害と疾患・障がい・症状の併存
発達障害には、持っている特性とは別の疾患や障がい、症状が同時にみられる場合があります。発達障害の特性とうまく付き合っていくためには、併存しやすい疾患や障がい、症状への正しい理解が大切です。
 ライターMizuki
ライターMizuki「いま持っている特性に加えて、今後も疾患などが現れるの…?」と思う方もいるかもしれませんが、併存症は、発達障害のある方に必ずしも起こるとは限りません。
二次障害とは?併存症や併存障害とは違う?
「二次障害」とは、障がいによってさまざまな生活機能が低下した状態のことです。
二次障害という用語は、その中に「障害」を含んでいる。しかし、この場合の「障害」
は教育や福祉の領域、及び障害者基本法などで用いられる「障害(disability)」や医学的
診断名に用いられる「障害(disorder)」など、一般的にしばしば用いられる「障害」とは
意味するところが異なっている。
【引用】二次的な障害の概念整理(医学における定義より)|独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
一方「併存症」は、医学的に診断されている、もしくは医学的診断に該当する状態(未診断であっても)を指します。「心理・環境的な要因で起きるもの」と、発達障害と関連する「生物学的な要因で起きるもの」とがあるといわれているのが特徴です。



二次障害と併存症は、重複する場合としない場合とがあります。
▼二次障害と併存症の一例
- 発達障害の特性で繰り返し注意を受けて自己肯定感が低下することで、引きこもりがちになることは二次障害に該当(不登校、人間関係でのトラブル頻発、精神的不調など)
- 二次障害としての引きこもり状態から気分の落ち込みが出現し、うつ病や不安症になることは併存症に該当(精神疾患、暴力行為など)
発達障害と併存しやすい疾患・障がい・症状
発達障害と併存しやすい疾患や障がい、症状は、早めの対処を心がけることで、発症や悪化を予防できる可能性が高まります。
この記事で挙げている障がいや疾患、症状が発達障害のある方に必ずしも起こるとは限りません。
知的障害
発達期までにみられた知的発達の遅れによって、社会生活で支援を要する状態です。医療機関での問診や診察、行動観察、発達・知能検査などから、総合的な結果をもとに診断されます。
知的障害は、保育園や学校などでの学習科目に加えて、日常生活のコミュニケーション、行動や感情のコントロールなどにも支援を要するケースがあります。
発達性協調運動障害(DCD)
感覚をまとめ上げてなめらかな運動に繋げるための脳機能の一つ「協調運動」がコントロールできず、日常生活に支障が出る状態です。食事や着替えなどの日常生活の動作や、手作業、運動バランスや姿勢の保持、学習などがスムーズにできない状態を指します。
発達性協調運動障害は、一人ひとりの体の状態に合わせた運動プログラムで訓練をし、自分なりのペースで運動に取り組む習慣をつけることがポイントです。運動の楽しさや魅力を、徐々に味わえるようになります。
チック
「運動」や「音声」を、自分の意思とは関係なく繰り返す症状です。原因はまだ分かっていませんが、脳機能の発達の偏りがひとつの要因ではと考えられています。特に、ASDやADHD、不安障害の傾向がある子どもに併存しやすいといわれているのが特徴です。



チックは、自分の意思に関係なく起きるため、自分でやめるのは困難です。そのため、早くやめさせようと叱ったり症状を指摘したりせず、注目していないようにふるまうことを筆者も心掛けています。
【チック症状の一例】
- まばたき、顔をしかめる、口をゆがませたり尖らせたりするなどの動きを頻繁にする(運動チック)
- 咳払いを繰り返したりハミングのようにフンフン言う(音声チック)
双極性障害
双極性障害は、気分が落ち込む「抑うつ状態」と活発な「躁状態」を繰り返す疾患を指します。ADHDの多動や衝動性、不注意によって積み重なった気分の揺らぎから発展しやすいのが特徴です。症状や服薬状況などを総合的にみて、重度・軽度が診断されます。
治療は、躁・抑うつ・症状が安定しているなど、そのときの状態に合わせて異なります。薬物による治療が主ですが、自分の状態を理解したうえで症状のコントロールを目指す「心理社会的治療」が行われる場合もあります。
うつ病
うつ病は、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れて、気分や感情をうまくコントロールできずに心身への不調が出る疾患です。日本では、ADHDと診断された成人202名のうち49%、ASDと診断された成人339名のうち41%が「うつ病の診断を受けた経験がある」と答えたとの報告があります。
【参照】成人の発達障害に合併する精神及び身体症状・疾患に関する研究|厚生労働科学研究成果データベース
URL:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/192131/201918004A_upload/201918004A0008.pdf
原因のひとつは、「自分の特性との付き合い方が分からない」「人間関係がうまく築けない」「仕事でどうしてもミスをしてしまう」などの心理的ストレスです。そのため、相談体制の構築や職務上の役割の固定、個人的な教育などの支援が大切といえます。
不安障害
前触れなく動悸・呼吸困難・吐き気などの発作が起こる「パニック障害」や、極度に緊張する状況を回避する「社会不安障害」など、主に不安が基盤の疾患です。過剰な不安や心配が6ヵ月以上継続すると「全般性不安症」と診断されます。
ASDと診断された成人の4.1%、ADHDと診断された成人の2.5%が全般性不安症の診断を受けたとの報告もあります。
【参照】成人の発達障害に合併する精神及び身体症状・疾患に関する研究|厚生労働科学研究成果データベース
URL:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/192131/201918004A_upload/201918004A0008.pdf



子どもでも、最小限の薬物療法や認知行動療法を含む療法で対処可能です。
症状の強さや他の疾患、安全性の面を含めて慎重な検討が必要ですが、専門機関や医師と相談しながら、一人ひとりに適した治療を目指せます。
てんかん
「突然動作が止まる」「突然話が途切れて反応がなくなる」などの発作を繰り返す脳の疾患です。発達障害とてんかんの併存率は高く、ASDでは5~38%、ADHDでは12~17%の併存が報告されています。
また、知的障害をともなう場合は、知的障害がない場合と比較して約3倍にてんかんの併存が報告されているのが特徴です。発達障害にてんかんが併存した際は、抗てんかん薬の特性や症状との相互作用を十分に考慮した薬物治療をします。
【参照】てんかんと発達障害|国立精神・神経医療研究センター NCNP病院
URL:https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/special/epilepsy-column_6.html
感覚過敏
感覚過敏は、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚などの感覚が過剰に敏感な状態です。発達障害では刺激に対する「感覚」を脳が過敏に受け取ってしまいやすく、大きなストレスや苦痛を感じてしまう可能性があります。生活をしていて困難が生じるほど感覚がとても敏感な場合に、感覚過敏と診断されます。
感覚過敏の子どもは、「なにがどう嫌か」をうまく伝えられないケースも少なくありません。そのため、日常生活で不快・不安そうな様子に気付いた場合は、それらを軽減できるグッズを用意したり、不快な刺激から離れられる場所を作ってあげるとよいでしょう。
【感覚過敏の一例】
- 日光や白い紙、目から入る情報など特定の光や色が苦手または敏感(視覚過敏)
- サイレンや掃除機の音、会話の声など特定の音が苦手または敏感(聴覚過敏)
- 化粧品、動物園など特定のにおいが苦手または敏感(嗅覚過敏)
- もちもち、サクサクなど特定の食感を嫌がったり甘味や苦みなど特定の味が苦手または敏感(味覚過敏)
- 衣服のタグや縫い目が気になる、人から触られることに抵抗があるなど皮膚から受ける特定の刺激が苦手または敏感(触覚過敏)
感覚鈍麻
感覚や刺激に過剰に敏感な感覚過敏とは反対に、刺激に対して反応が低いのが「感覚鈍麻」です。光や音などをはじめとする五感や痛みなどの刺激を受けても、反応が低くなります。
【感覚鈍麻の一例】
- 怪我の痛みを感じにくい
- 熱いものに触れてもやけどするまで気が付かない
- 暑さや寒さの感覚が鈍い
発達障害同士が併存するパターンも
「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠如・多動症(ADHD)」「学習障害(LD)」をはじめとする発達障害は、種類や特性の表れ方、程度に個人差があります。ひとつの種類や特性がみられる人もいれば、複数の種類や特性が重なってみられる人もいるのが特徴です。



いくつかの種類や特性が重なっている場合、そうでない場合よりも生活の支援が多く必要な傾向にあります。一つひとつの特性や適切なケアを理解することで、スムーズな支援に繋げられます。
特性は生まれ持ったもの、でも併存症は「予防」や「対処」ができる
先述したように、発達障害と併存しやすい疾患や障がい、症状は予防と対処が可能です。
特性への理解も大切ですが、「無理をしすぎない、ストレスを感じすぎない環境を考える」ことも同じくらい重要といえます。子どもの生まれ持った特性を根本的に変えようとするのではなく、併存症の要因となりそうな100%の不安や心配を70%に、70を50に、50を20にしていくイメージです。
少しずつ一歩ずつの対策や対処は、実は子どものストレスを、そして家族である私たちの心配ごとを軽減できる大きな一歩に繋がります。この記事が、発達障害の併存症について考えるきっかけとなれば幸いです。
▼こちらの記事は下記サイトを参照した上で執筆しました
二次的な障害の概念整理(医学における定義より)|独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
協調運動の障害の早期の発見と適切な支援の普及のための調査|厚生労働省 令和4年度障害者総合福祉推進事業


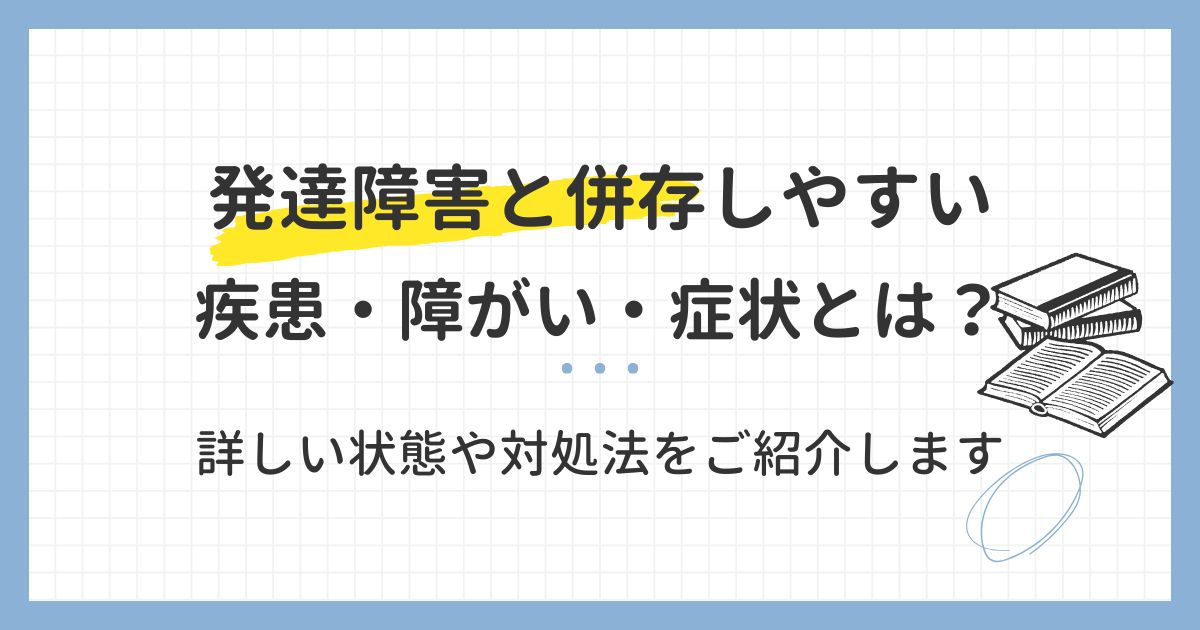

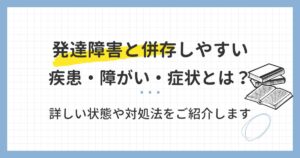

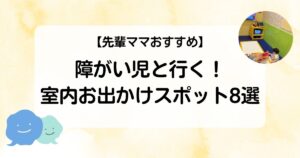
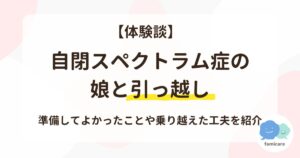

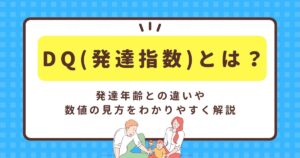


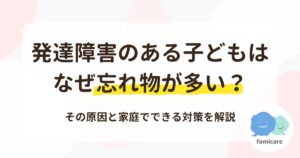

コメント