
自閉スペクトラム症の子どもを育てているけど、特性以外の症状が出ていて気になる…



併存症の存在は知ってるけど、実際どんな対応をしたらいい?
そう思われたことのあるご家族はいらっしゃいませんか?
個性や特性が一人ひとり違うのと同じく、必要なサポートや心地よいケアもさまざま。併存しやすい疾患や障がい、症状を把握しておくことは、本人と家族どちらにとっても安心です。
今回は、発達障害の一つ「自閉スペクトラム症」と併存しやすい疾患や障がい、症状に着目。自閉スペクトラム症の娘と暮らす筆者が、実際に心掛けていることも合わせてご紹介します。
この記事を監修した専門家


株式会社ニト 訪問看護事業部
訪問看護ステーション ニト四谷・管理者
小児専門チーム・看護師 藤田有美(ふじたゆみ)さん
2022年 株式会社ニトに入社し、成人精神科を小児精神科を兼任。2025年8月にはニト初となる小児専門拠点、「訪問看護ステーション ニト四谷」の管理者に就任予定。成人と小児の両方で経験を積んだ今、その子の10年先を見据えたケアを目指している
株式会社ニト:https://nitor.co.jp/
自閉スペクトラム症(ASD)とは?
自閉スペクトラム症とは、社会的な相互作用やコミュニケーションの困難、こだわりによる興味や行動の制限がみられる発達障害の一種です。Autism Spectrum Disorderの頭文字を取って、ASDとも呼ばれます。性別では男性に多く、女性の約2〜4倍の発生頻度といわれているのが特徴です。
自閉スペクトラム症は、かつて「自閉症」「アスペルガー症候群」「広汎性発達障害」「小児期崩壊性障害」「レット症候群」の5つに分類されていました。しかし、2013年にアメリカの精神医学会(APA)が発表したDSM-5では、レット症候群以外の4つが「自閉スペクトラム症または自閉症スペクトラム」に統合されています。
自閉スペクトラム症の原因は「乳幼児期の育て方」ではない
自閉スペクトラム症の正確な原因は、まだ分かっていません。



「じゃあ親の育児が悪かったからかも」「愛情不足が関係している」…答えはNoです!
自閉スペクトラム症は、親による乳幼児期の育て方が原因ではありません。自閉スペクトラム症の場合、情報の整理に必要な脳の中枢神経系のメカニズムに生まれつき特性があります。そのため「できる」「できない」にばらつきが出てしまうのです。
自閉スペクトラム症の要因は、現在のところ、次のようなことと考えられています。
- 遺伝
- 両親の年齢
- 出生時低体重
- 多産
- 妊娠中の母体感染症 など
自閉スペクトラム症と併存しやすい疾患・障がい・症状
実は、自閉スペクトラム症の方のうち、約7割以上の方が1つの精神疾患を、4割以上の方が2つ以上の精神疾患を持っているといわれています。
とはいえ先述したように、特性が十人十色なら、適切なケアも一人ひとり異なるもの。必ず併存するというわけではありませんが、併存しやすい疾患や障がい、症状を把握しておくことで、スムーズな対応に繋げられます。
知的障害
自閉スペクトラム症との併存症で特に多いといわれているのが、知的障害です。社会生活に関わる能力の発達に支障が出ている状態を指します。
幼少期~青年期の、いわゆる「発達期」までにみられるのが特徴です。表れ方には個人差があり、支援を受けながら働いている方もいれば、支援なしで生活を送っている方もいます。
医療機関での問診や診察、行動観察、発達・知能検査などの総合的な結果に基づいて診断可能です。
注意欠如・多動性障害(ADHD)
注意欠如・多動性障害は、集中力が散漫になりやすい「不注意」、じっとしていることが困難な「多動性」、やりたいと思ったことを我慢しにくい「衝動性」がみられる状態です。Attention-Deficit/Hyperactivity Disorderの頭文字を取って「ADHD」と呼ばれています。
自閉スペクトラム症と併存しているケースも珍しくなく、20~70歳で発達障害のある成人838名のうち、併存例は26.8%(225件)という報告もあります。
【参照】成人の発達障害に合併する精神及び身体症状・疾患に関する研究|令和元年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業
URL:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/192131/201918004A_upload/201918004A0008.pdf
「不注意が優勢」「多動・衝動性が優勢」「混同して存在」と、症状はさまざま。特性の表れ方によってそれぞれ分類されます。
学習障害(LD)
自閉スペクトラム症に約26%の頻度で併存すると報告されているのが、学習障害です。
【参照】LD と自閉スペクトラム症,注意欠如・多動症(併存障害)|岡牧郎 特集 限局性学習症(学習障害)
URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscap/58/2/58_236/_pdf/-char/ja
学習障害は、全般的な知的発達に遅れはないものの「書く」「読む」「計算する」「推論する」の能力を学んだり行ったりするのに支援を要する状態を指します。Learning Disabilitiesの頭文字を取って「LD」とも呼ばれています。



デジタル教科書やデジタルカメラ、そろばん、計算機など、子どもの特性に合わせたツールを活用すると、効果的な学習に繋げられます。担任や学年主任、スクールカウンセラーへ配慮を相談するのもおすすめです。
発達性協調運動障害(DCD)
発達性協調運動障害は、脳性麻痺や身体疾患が認められないものの、感覚をまとめ上げてなめらかな運動に繋げるための脳機能の一つ「協調運動」のコントロールが年齢相応にできず、生活に支障が出ている状態です。
自閉スペクトラム症の88.5%は少なくとも1つの発達障害の併存があるといわれていますが、そのうち63.2%に発達性協調運動症が併存しているとの報告もあります。
【参照】【プレスリリース】5歳における自閉スペクトラム症の有病率は推定3%以上であることを解明(医学研究科)|弘前大学
運動課題や困りごとのレベルに合わせ、「理学療法」「作業療法」「感覚統合療法」などを組み合わせた療育プログラムを行います。
チック
まばたき・顔をしかめる・口をゆがませたり尖らせたりするなどの動きを頻繁にする「運動チック」や、咳払いを繰り返したりハミングのようにフンフン言ったりする「音声チック」などを、自分の意思とは関係なく繰り返す症状です。自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症、不安障害の傾向がある子どもに併存しやすいといわれています。



筆者の娘は、「運動チック」「音声チック」ともに発現。周りが心配しすぎて子どもがストレスや緊張を感じる状況では治りにくいため、指摘したり治そうとしたりせずにゆったりと見守っています。
しかし、不謹慎な言葉の音声チックが出る場合はトゥレット症候群の可能性もあるため、児童精神科や小児神経科を受診しましょう。
うつ病や強迫症などの精神疾患
うつ病は、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れて、日常生活に支障が出るほどの強い気分の落ち込みや意欲低下が続く疾患です。強迫症は、非常に強い不安感や不快感(強迫観念)と、それを打ち消すための行為(強迫行為)が繰り返される状態を指します。
日本では、自閉スペクトラム症と診断された成人339名のうち41%が「うつ病の診断を受けた経験がある」と答えたとの報告があります。
【参照】成人の発達障害に合併する精神及び身体症状・疾患に関する研究|厚生労働科学研究成果データベース
URL:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/192131/201918004A_upload/201918004A0008.pdf



強迫症を併存している筆者の娘は、5分に1回手を洗ってしまう時期も。認知行動療法と服薬にて治療をしています。精神疾患は子どもにとっても非常に辛いため、専門家や医療機関への早急な相談がおすすめです。
睡眠障害
睡眠障害とは、不眠症や過眠症、睡眠時随伴症など睡眠に影響が出る症状の総称です。自閉スペクトラム症の場合、睡眠と覚醒リズムが不規則になる傾向があります。眠りが安定しにくいため、自閉スペクトラム症の特性が顕著になりやすいのが特徴です。
また、感覚過敏からくる症状が二次的に睡眠を妨げるケースもあります。



ルーティンが落ち着く自閉スペクトラム症の子どもにとって、“おやすみ前の決まりごと”は、安心材料の一つ。「寝る前に絵本を読む」「音楽を布団の中で1曲だけ聴く」など、寝るモードに繋がる儀式を作ってみるのも効果的です。
肥満
自閉スペクトラム症は偏食や運動不足傾向にあることから、肥満が表れやすくなります。
“たとえば、140人の7〜18歳の日本人自閉スペクトラム症(ASD)児童の25%が肥満で、特別支援学校在籍の413人(6〜17歳)の自閉スペクトラム症(ASD)児童のうち、男子22%、女子11%が肥満であったとされます。”
【引用】肥満は発達障害と関係がありますか?|精神医学 65巻5号
食材の食感を変えてみるなど偏食への対応も大切なものの、改善が難しい場合は、楽しく身体を動かすのが効果的。好きな音楽に合わせてのダンスや、座った状態でゆっくりとストレッチなどから始めてみるのもOKです。
てんかん
「突然動作が止まる」「突然話が途切れて反応がなくなる」などの発作を繰り返す脳の疾患です。自閉スペクトラム症とてんかんは、5~38%の併存が報告されています。
【参照】てんかんと発達障害|国立精神・神経医療研究センター NCNP病院
URL:https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/special/epilepsy-column_6.html
てんかんが併存した際は、抗てんかん薬の特性や症状との相互作用を十分に考慮したうえで薬物治療をします。
胃腸障害
胃腸障害とは、腹痛や吐き気、便秘または下痢などの症状がみられる状態です。自閉スペクトラム症の場合、感覚過敏からくる偏食で栄養バランスがかたよったり、ストレスの影響を受けやすかったりします。そのため、免疫異常、代謝異常などとともに、消化器症状の併存率は 23〜70%と高い傾向にあるのが特徴です。
【参考】腸内細菌と自閉症スペクトラム障害|日本生物学的精神医学会誌 30巻2号
URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbpjjpp/30/2/30_55/_pdf
お腹をくるくるとマッサージしてあげると、腸活だけではなく、リラックス効果からストレス軽減の期待ができるメリットも。
感覚過敏・感覚鈍麻
感覚過敏は、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚などの感覚が過剰に敏感な状態です。自閉スペクトラム症では、約40%に感覚過敏が認められています。
【参考】自閉症スペクトラム障害における感覚過敏の生理・病理学的背景|奈良学園大学
一方、特定の刺激に対して反応が低いのが「感覚鈍麻」です。光や音などをはじめとする五感や痛みなどの刺激を受けても、反応が低くなります。



感覚過敏は大きなストレスに繋がりやすいものの、刺激から守るグッズを活用するなど対策ができます。感覚鈍麻は怪我や空腹に気付きにくいため、周りの大人が目配りをして、気になることがあれば治療や診察を促してみるのがおすすめです。
「特性を理解する」とは「併存症と向き合う」こと
この記事で挙げた疾患や障がい、症状は、必ずしも自閉スペクトラム症と併存するわけではありません。しかし、詳しい状態を把握しておくことで、いざ症状が表れた際に的確かつスムーズな対応へ繋げられます。



「障がいの特性に加えて併存症なんて…と思っていたけど、対応していきたい」



「すでに我が子にも併存症が表れているけど、悩んでいるのは自分だけじゃなかった…!」
障がいの特性と併存症で悩む方が、そんな気持ちになっていただけたらと思います。
▼こちらの記事は下記サイトを参照した上で執筆しました
ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について|e-ヘルスネット(厚生労働省)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-005.html
自閉スペクトラム症児の睡眠に関する研究動向と今後の展望|川崎医療福祉学会誌
URL:https://i.kawasaki-m.ac.jp/mwsoc/journal/jp/2019-j29-1/P1-P7_ikeuchi.pdf


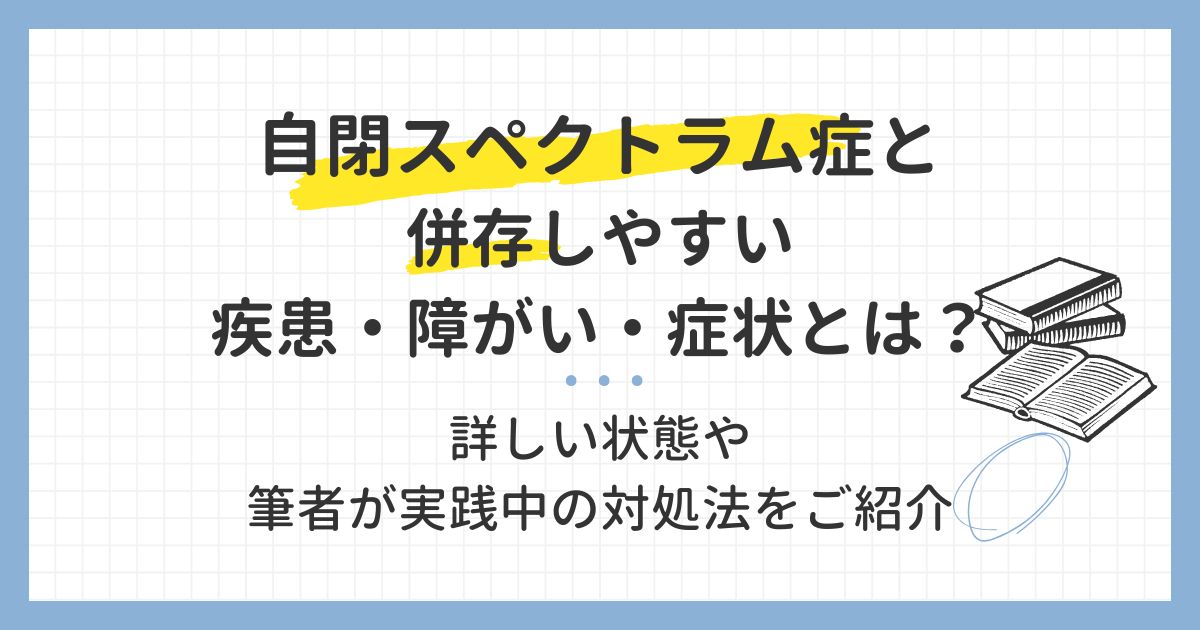

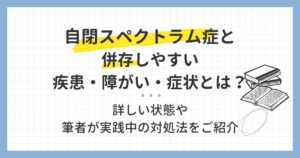




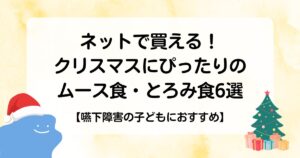
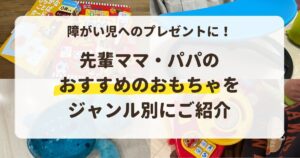
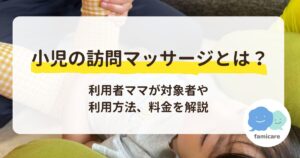

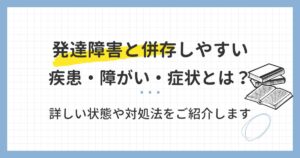
コメント