うちの子には特別支援学校と特別支援学級、どちらが合っているのだろう?
これから就学を迎える障がいのある子どもを育てているご家庭では、そんな疑問を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。どちらも子どもの成長を支える大切な場所ですが、それぞれに特徴があります。
この記事では、特別支援学校と特別支援学級の違いをわかりやすく解説し、それぞれのメリットとデメリットもご紹介します。子どもに適した教育環境を見つけるためのヒントにしてみてください。
▼就学に関する特集はこちら
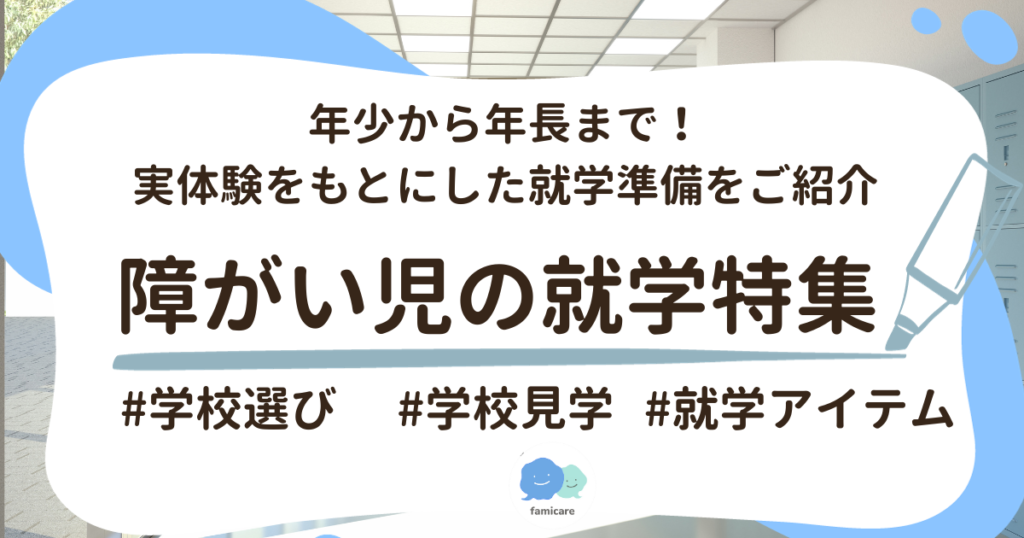
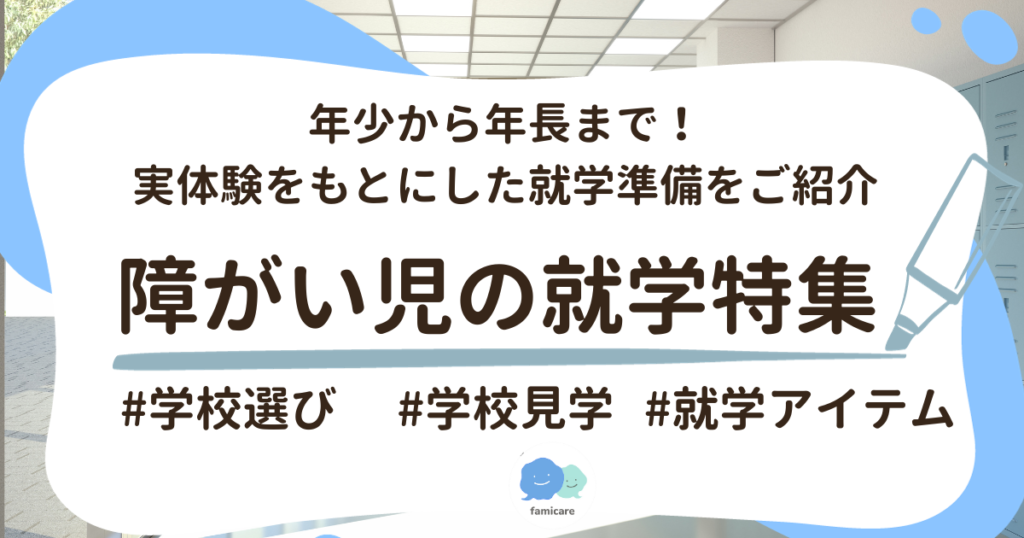
「特別支援学校」と「特別支援学級」はどう違う?
特別支援学校と特別支援学級では、主に以下の点が異なります。
特別支援学校は“障がいに特化した専門教育の場”
特別支援学校は、障がいのある子どもが学ぶための教育機関です。幼稚部から高等部まであり、さまざまな年代の児童・生徒に対して、日常生活で必要なスキルを身につけるための支援をしています。
▼特別支援学校の種類
- 視覚障害特別支援学校
- 聴覚障害特別支援学校
- 肢体不自由特別支援学校
- 知的障害特別支援学校
- 病弱特別支援学校
特別支援学校では、専門的な訓練を受けた教職員が、一人ひとりの状況を理解したうえでサポートをしています。そのため、それぞれの子どもの特性や成長に応じたきめ細やかな指導を受けられるのが特徴です。
特別支援学級は“地域の学校で受ける個別支援”
特別支援学級は、障がいのある子どものために小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数のクラスです。子どもたちの状況に応じて、特別支援学級で一日中過ごしたり、決まった時間だけ勉強したりします。
▼特別支援学級の種類
- 知的障害
- 肢体不自由
- 病弱・身体虚弱
- 弱視
- 難聴
- 言語障害
- 自閉症・情緒障害
日常生活には大きな困りごとがないものの通常のクラスでの学習に心配がある場合に、検討してみるとよいかもしれません。特別支援学級では、日々の生活スキルを身につけることよりも、勉強面でのサポートに重点を置いているためです。
特別支援学校に入る基準



支援学校と支援学級、どちらも障がいがある子が対象だけど、対象になる基準とかあるの?
特別支援学校の入学対象にあたる障がいの程度は、学校教育法施行令第二十二条の三で詳しく定められています。



特別支援学校へは、医師による診断をはじめ、心理検査、現在の学習状況や生活の様子の確認、保護者との面談や学校見学など、さまざまな過程を経て入学します。対象基準はあるものの、必ずしも特別支援学校でないと入学できない、というわけではありません。
教育内容や指導方法はどう違う?
同じ特別支援でも、学校と学級では教育の進め方に大きな違いがあります。入学の基準だけではなく「どんな環境がわが子に合っているか」は気になりますよね。
それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
教育・支援の内容
特別支援学校では、身の回りのことを自分でできるようになる練習や、将来働くために必要な技術を身につける授業など「障がいの種類や程度に合わせて作られた特別なカリキュラム」で学習します。また、医療的なケアが必要な子どもに対して、看護師がいつでもサポートできる体制が整っているのも特徴です。
一方、特別支援学級では、基本的には他の子どもたちと同じ教科書を使って勉強しますが「個人の理解度」で内容を調整してくれます。その子のペースで進めることができ、必要に応じて普通学級の児童と一緒に授業を受ける場合もあります。
教員の数
特別支援学校では、子ども3人に対して教員が1人の体制で教育が行われています。さらに、看護師さんやリハビリの専門家などのスタッフも一緒に子どもたちをサポートしているため、一人ひとりの子どもにじっくりと向き合えるのが特徴です。
特別支援学級では、基本的に教員1人が最大8人までの子どもたちを担当します。必要に応じて支援員の方がお手伝いしてくれる場合もあり、普通学級の教員とも連携を取りながら子どもをサポートしています。



実際の教員配置は、その地域の事情や学校の状況によって変わる場合があります。具体的な状況については、各学校に確認してください
専門性
特別支援学校の教員は、障がいのある子どもたちの教育に特化した専門的な勉強をしています。たとえば、目の見えない子どもには点字の読み書きを教えたり、耳の聞こえない子どもには手話でコミュニケーションを取ったりする技術を身につけています。
また、障がいのある子どもと他の子どもたちとの架け橋的な役割も兼ねているのが特徴です。地域の病院や福祉施設とも密に連携を取りながら、子どもの生活全体をサポートしています。
通学環境
特別支援学校は一般的な小学校よりも設置数が少なく、通学範囲が広いため、通学バスが運行していることが多いです。学校が家から少し遠い場所にあっても、バスが家の近くまで迎えに来てくれるので、安心して通学できるでしょう。学校にはスロープやエレベーターが設置されており、車いすでも快適に過ごせるような環境が整えられています。
特別支援学級は地域の学校内にあるため、歩いて通ったり自転車で通ったりできます。近所の友だちと一緒に登下校することもでき、ごく自然な子ども同士の関わりを持てるでしょう。



子どもの状態によっては、保護者が送り迎えをする場合もあります
子どもに合った教育環境を見つけるために
特別支援学校では、支援が必要な子どものために、専門的な知識を持ったスタッフによる手厚いケアが受けられます。特別支援学級は、一般的な学校の中に設けられたクラスで、主に勉強面でのお手伝いを行っています。
一律にどちらが優れているとは判断できません。子どもの困りごとの程度や特性によって、適している環境は変わるためです。
また、近年では「インクルーシブ教育」の考え方が広まり、障がいの程度にかかわらず、地域の学校の通常学級で必要な支援を受けながら学ぶ子どももいます。自治体や学校の体制、支援内容によって可能かどうかは異なりますが、特別支援学校や支援学級以外の選択肢もあります。
子どもに適した選択をするために「どちらが正解か」ではなく「その子にとって何が一番よいか」を考えていきましょう。
【参考】
第二章、視覚障害者等の障害の程度、第二十二条の三|学校教育法施行令
https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340/20210401_501CO0000000128
特別支援教育関係資料|文部科学省https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/113/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2015/07/08/1359123_05.pdf


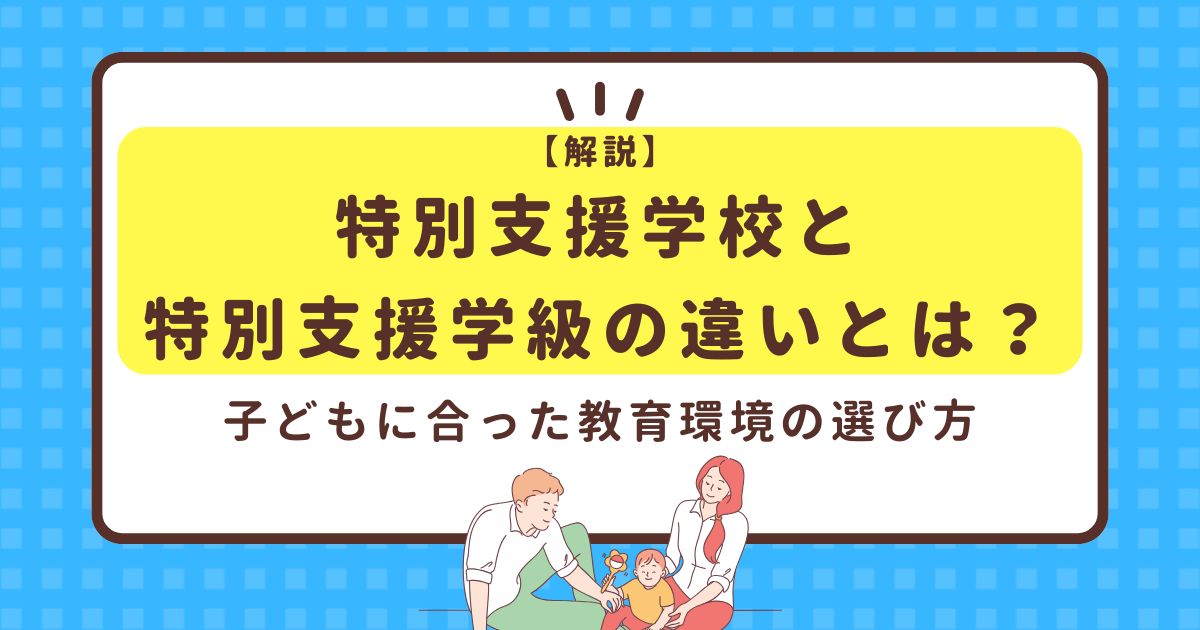

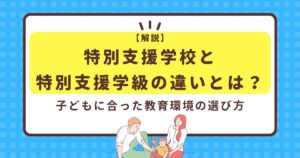

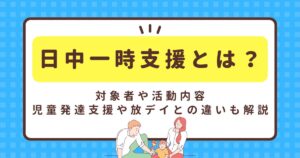
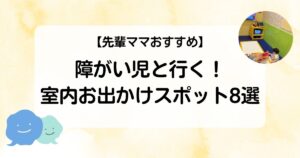
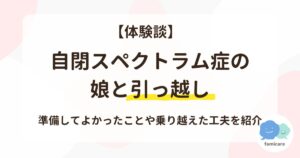
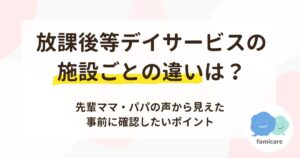


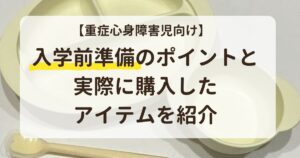

コメント