発達障害のある子どもの成長は、緩やかで気づきにくいものかもしれません。しかし、日々の小さな変化や成長の積み重ねを丁寧に記録してみることで、子どもの成長を実感しながらよりよい支援にもつながりやすくなります。

そうは言っても、成長記録ってどう残したらいいの?
そのように感じている方に向けて、この記事では、発達障害児の成長を記録して得られるメリットや具体的な方法、記録する際のポイントなどを、経験談や専門的な視点とともにお伝えします。
なぜ発達障害児の成長記録を残すのが大切?



発達障害児のわが子、日々の生活のなかで成長が見えづらい…
そのように感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、記録に残してみようと意識することで「これまで苦手だった歯磨きが少しずつできるようになる」「好きな遊びの種類が増える」「友だちと関わる時間が長くなる」など、日常の小さな変化に目が向きやすくなります。
また成長記録は、医療機関や療育施設、教育機関との連携においても重要なコミュニケーションツールです。言語発達の様子や生活習慣の変化、社会性の発達などを具体的に記録しておけば、より正確な情報を支援者と共有できます。



成長記録は、適切な支援方法を検討する際の「子どものトリセツ」になるのです
成長記録を残して得られる長期的なメリット
日々追われているなかで記録を残すのは結構大変。だからメリットを知りたい…!
発達障害児の成長記録を残すと、主に以下のようなメリットが得られます。
子どもの得意分野や興味の発見につながる
成長記録を通じて、子どもがどのような活動に興味を示すのか、どんな場面で生き生きとしているのかが見えてくるのは大きなメリットです。例えば、音楽に合わせて体を動かすことが好きな傾向や特定のおもちゃで集中して遊べる場面など、わが子ならではの興味や才能の芽を見つけやすくなります。
親自身の心理的な支えになる
発達障害のある子どもを育てるなかで孤独や不安を感じる…そのような方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、記録を通じて子どもの成長を客観的に見つめて成長過程を再確認すると、親自身も希望を見出せたり心の安定につながりやすくなったりします。
将来の自立支援に向けた資料になる
前述したとおり、成長記録は、将来の自立支援を考えるうえで重要な「子どものトリセツ」です。どのような環境で落ち着いて過ごせるか、どのような支援方法が効果的だったかなど、これまでの経験や対応の記録は、進学や就労の際の重要な参考情報になります。



子ども自身が自己理解を深める際にも、成長記録は貴重な資料です
成長記録にはどんなことを書けばいい?



発達障害児の成長記録が大切なのはわかるけどハードルが高い…
どんなことを記録したらいいのかわからない…
メリットがあるとはいえ、家事や仕事、育児をしながら細かく記録をつけるのは難しいですよね。「毎日つけなければ」と構える必要はありません。「簡単にできる範囲で記録してみよう」と意識すると、継続しやすくなります。
例えば、記録として筆者が書き残しているのは以下のような項目です。
初診日や検査結果など医療的情報
初診日、診断名、各種検査結果、処方薬の内容と効果、リハビリや療育の経過などを時系列で記録しています。
▼例えば
- 〇歳〇か月時の発達検査の結果:言語発達が〇歳〇か月相当、対人関係は〇歳〇か月相当だった
- STによる言語訓練を開始して3か月後、二語文が増えてきた
などの記録は、成長の客観的な指標となります。



専用のファイルを用意して診断書や検査結果の原本とともに整理すると、必要な際にすぐに参照できます
日常生活での変化や成長の様子
検診や知能検査では、さまざまなことが「数値」でわかりやすく示されます。しかし、家庭や学校などで日常的に起こる困ったエピソードや支援が必要な事柄などは、やはり日常的な生活の記録が頼りです。
そのため、食事や入浴、着替え、睡眠などの基本的な生活習慣の変化も定期的に記録しています。
▼例えば
- 自分でスプーンを使って食べられるようになった
- パジャマに自分から着替えようとする様子が見られた
など、具体的なできごとが大切な情報です。



特に印象的な場面は、写真や短い動画など視覚的な記録で残しています
コミュニケーションと社会性の発達
新しく話せるようになった言葉、表情やジェスチャーによる意思表示、友だちや家族との関わり方の変化なども記録している事柄です。
▼例えば
- 初めて『ママ』と言えた
- 友だちと砂場でそれぞれ自由に遊んでいた
- 視線を合わせる時間が長くなった
など、わが子なりのコミュニケーションがどのように変化しているかを、記録とともに見守っています。
感覚特性と環境への反応
音、光、触感、味、においなどに対する反応の変化や、特定の環境下での行動パターンなども大切にしている項目です。
▼例えば
- 大きな音への過敏さが○○することで和らいできた
- 特定の素材の服を受け入れられるようになった
- ○○することで人混みで過ごしやすくなった
など、子どもが過ごしやすくなった様子を記録しています。



記録をするツールは、手帳やノートなどの紙媒体をはじめ、スマートフォンのメモアプリや専用の発達記録アプリなど、自分が続けやすいと思うものを選ぶのがおすすめです。筆者は、市町村で配布している「サポートブック」を活用しています
▼サポートブック作成のポイントについては、こちらの記事からご覧いただけます
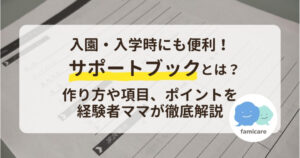
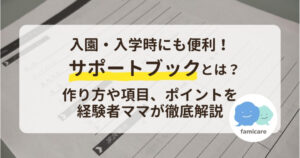
記録を残す際の重要なポイント
親だけではなく子どもが自身を知るうえでも強い味方になる成長記録ですが、効果的に残すためには、下記のようなポイントをおさえておきましょう。
「できたこと」だけに固執せず「成長の波」を記録する
成長記録と聞くとどうしても「できるようになったこと」に目が向きがちですが、実は「頑張っても難しいこと」「できなくなったこと」の記録も同じくらい大切です。発達には波があります。これは、とても自然なことです。
その分、できるようになったことを記録する際には「〇〇すればできるようになった」と、成功した過程をできるだけ残しておきましょう。成功までの手段がわかれば、より明確な支援につながりやすくなります。
客観的な視点を大切にする
感情的な記録も大切ですが、できるだけ具体的な事実を記録することを心がけましょう。例えば「今日は機嫌が悪かった」よりも「お昼ご飯に新しいメニューを準備したところ、食べなかった。しかし、普段の好きなおかずを出すと完食できた」というように、状況と行動を具体的に記録すると、後から振り返った際に有用な情報になります。
定期的な振り返りの時間を設ける
記録を残すだけでなく、定期的に内容を振り返る時間を設けることが重要です。月に一度など決まったタイミングで記録を見直すと、子どもの成長の傾向や支援の効果を確認できます。



次の目標を設定しやすくなるのも、記録を振り返るメリットです
保管場所に気をつける
発達障害児の成長記録の保管には、細心の注意が必要です。例えば、本人への障がい告知前の段階で成長記録が偶然目に入ってしまうと、自分の障がいを予期せず知ってしまう可能性があります。これは、子ども本人に心理的な衝撃を与えかねません。
また、発達特性や医療情報などのデリケートな個人情報が含まれるため、プライバシー保護の観点からも保管場所選びは重要です。家族以外の目に触れない安全な場所で保管したり、デジタルデータの場合はパスワードを設定したりなど、適切なアクセス制限を設けるようにしましょう。
発達障害児の成長記録、どんな風に活用したらいい?
コツコツと残した記録は、以下のようなさまざまな場面で活用することができます。子どもの支援に関わる人々と共有して、より効果的な支援につなげていきましょう。
医療機関や利用施設での相談時に活用
医療機関での相談時に記録を医師や専門家と共有すると、発達の経過や気になる行動の頻度、服薬の効果などを具体的に伝えられます。正確な情報提供ができ、適切な診断や治療方針の決定に役立てられるのがメリットです。
教育機関との連携に活用
保育所、幼稚園、学校などの教育機関との連携においても活用できます。記録を使って子どもの特性や支援の必要性を具体的に伝えることで、適切な配慮を得やすくなります。また、学校生活での様子を家庭での記録と照らし合わせれば、家庭と学校の両方で一貫した支援の仕組みを作りやすくなるのも利点です。
家族間での情報共有ツールとして活用
成長記録は、家族全員で子どもの成長を共有し理解を深めるための重要なツールにもなり得ます。両親だけでなく、必要に応じて祖父母や兄弟姉妹とも共有すれば、家族全体で子どもの特性を理解しながら適切な関わり方を考えられます。
成長記録は子どもの可能性を見出すためのお守り
子どもは、成長にともなって保護者から離れている時間がどうしても増えていきます。わが子の近くにいる人にできるだけ子どものことを理解してもらい、支援の方向性を見出すためにも、成長記録を断続的に残すことはとても大切です。
「できることもできないこともあって当たり前だよね、でもこうすれば少し過ごしやすくなるよね」とゆったりとした気持ちを持ちながら、焦らず、できる範囲で継続してみてください。


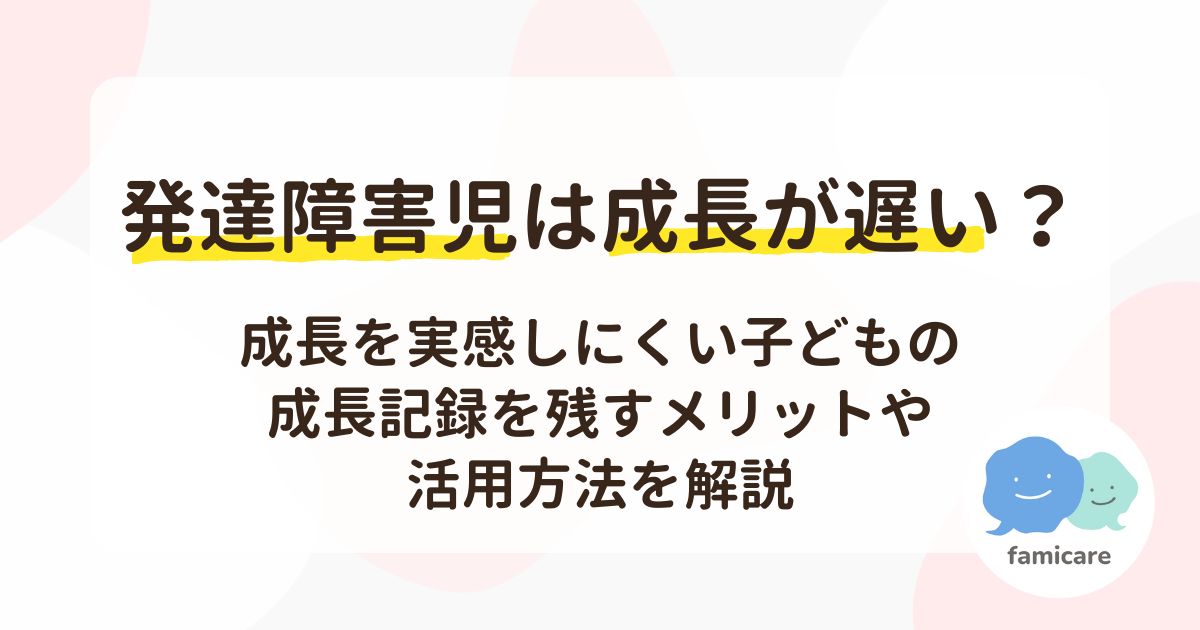

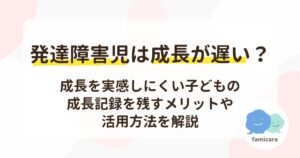

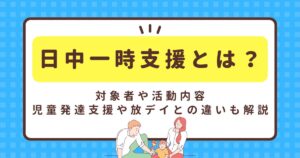
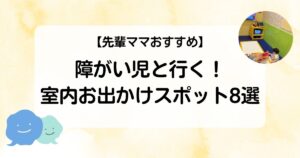
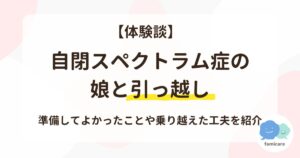
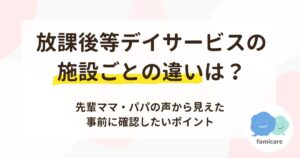

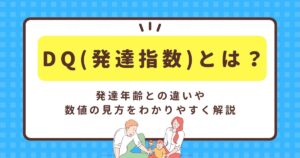

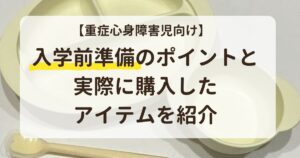
コメント