子どもの睡眠の問題は、多くのご家族が直面する大きな課題です。特に発達障害のある子どもの場合、睡眠の乱れが多くみられる場合もあります。
この記事では、発達障害のある子どもがなかなか寝ない原因や不眠からくる影響、よりよい睡眠習慣を築くためのサポート方法をご紹介します。

なかなか寝ないわが子は発達障害?
発達障害のわが子がすっきりと眠れるにはどうしたらいい?
そうお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
発達障害の子どもはなかなか寝ない?
発達障害の子どもが睡眠に関する困難を抱えるケースは多くあります。だからといって、発達障害だから必ず寝つきが悪いわけではなく、それぞれの子どもの特性や環境によって、睡眠の様子は大きく異なります。
全然寝ない赤ちゃんは発達障害?
赤ちゃんの睡眠パターンは個人差が大きく、夜泣きや寝つきの悪さは多くの赤ちゃんにみられる一般的な特徴です。そのため「寝つきが悪い」「夜中に何度も起きる」といった睡眠の問題だけで、発達障害かどうかの判断はできません。



実際に、発達障害があっても赤ちゃんの頃から寝つきがよい子、発達障害はなくても入眠までに時間がかかる子もいます。「寝つきが悪い=発達障害」という判断を避け、子ども一人ひとりの成長のペースがあることをまずは理解するのが大切です。
発達障害のある子どもが寝ないのはなぜ?
では、発達障害児の寝つきの悪さにはどのような原因があるのでしょうか。発達障害のある子どもの多くは「感覚の過敏さ」「刺激を求める」など感覚の処理や調整の特性、環境への反応の違いから、睡眠に関する困難を抱えています。例えば、以下のようなものです。
感覚過敏で落ち着けない
発達障害のある子どものなかには、音や光、触覚などに対して敏感な反応を示す方が多くいます。夜間でも小さな物音が気になってしまったり、寝具の感触が気になって落ち着けなかったりするケースも少なくありません。



自閉スペクトラム症と診断されている筆者の娘の場合「エアコンの動作音や外からの車の音が気になって眠れない」「パジャマのタグがチクチクして不快に感じる」との訴えがありました
体内時計のズレ
発達障害のある子どもは、体内時計の乱れにより睡眠リズムの調整が難しい場合があります。「夜になっても眠くならない」「朝になかなか起きられない」といった症状の背景には、体内時計の乱れがあるかもしれません。
興奮・緊張状態が続きやすい
新しい出来事や楽しい活動の後は、その興奮が持続しやすい傾向があります。



これは、私たち大人も経験があるのではないでしょうか
例えば「楽しい遊びの後や特別なイベントがあった日は、頭の中で出来事が繰り返し再生されてなかなか気持ちが落ち着かない…」そんな経験ありますよね。
発達障害の子どもの場合、状況や環境への過敏な反応によって、興奮がより続きやすくなります。学校での出来事や翌日の心配事が頭から離れなくてリラックスできず、なかなか寝付けない子どもも少なくありません。
睡眠の問題が子どもと家族に与える影響
睡眠の乱れは、子どもの日中の生活や発達に大きな影響を及ぼすだけではなく、ご家族全体の生活の質にも影響を与えかねません。具体的には、以下のような影響を及ぼす場合があります。
子どもへの影響
睡眠不足は、日中の集中力低下や情緒の不安定さを引き起こします。特に発達障害のある子どもの場合、睡眠の乱れから感覚過敏がより強くなったり、コミュニケーションの困難さが増したりするケースも珍しくありません。また、学習面での困難さも増加する可能性があります。
家族への影響
子どもの睡眠の乱れは、保護者の方の睡眠時間も制限してしまいます。夜遅くまで寝かしつけに時間がかかったり夜中に何度も起きたりすることで、保護者の方も十分な睡眠が取れず、日中の疲労感が強くなっている…この記事を読んでいて、そのように感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。



睡眠の乱れは、家族全体のストレスレベルを高めてしまう要因になり得ます
具体的な睡眠改善のためのサポート方法
ここからは、子どもの睡眠の質を改善するための具体的なサポート方法をご紹介します。
発達障害児の睡眠には、一人ひとりの特性に合わせた環境調整と、一貫した就寝ルーティンの確立が重要です。眠れない要因は個人で異なるはずですが、主に以下のようなサポート方法があります。
感覚過敏に配慮して睡眠環境を整える
光や音、温度など、子どもの感覚特性に配慮した環境作りを心がけましょう。例えば、遮光カーテンの使用、騒音をシャットアウトするホワイトノイズマシンの活用、子どもが心地よく感じる温度設定などが効果的です。
▼視覚過敏への配慮
- 調光できる照明で明るさを調節する
- 暖色系の光を選ぶ
- 天井や壁に光を反射させて間接照明にする
▼聴覚過敏への配慮
- 時計の針の音や冷蔵庫の作動音などを避ける
- 心地良く感じられる音楽をかける
▼嗅覚過敏への配慮
- 定期的に寝室を換気する
- 無香料の洗剤・柔軟剤を使う
- 天然の消臭材を活用する



自閉スペクトラム症と診断されている筆者の娘は、繊維のチクチクが苦手なため、柔らかい素材の寝具やオーガニックコットンのパジャマを使っています
就寝前のルーティン作り
発達障害の子どもは、予測ができる状態に安心感を覚える傾向があります。そのため、就寝ルーティンを作って「寝るまでの見通し」を立てるのも一つです。



例えば「お風呂→パジャマに着替え→絵本の読み聞かせ→消灯」という流れを毎日同じ順序で行うと決めておくと、体も心も自然と眠りモードに入りやすくなります
日中の活動量を調整する
発達障害の有無にかかわらず、日中の適度な運動や活動は、夜の良質な睡眠につながります。ただし、就寝直前の激しい運動は避け、徐々に活動レベルを下げていくのが大切です。



例えば、夕方は穏やかな外遊びや散歩、夕食後はゆったりとした室内遊びに切り替えるなどの工夫が効果的です
スクリーンタイムを減らす
スマートフォンやタブレット、テレビなどの電子機器から発せられるブルーライトは脳を興奮させ「メラトニン」という睡眠を促すホルモンの分泌を抑制します。特に発達障害のある子どもは、画面の強い光や動きのある映像に影響を受けやすいのが特徴です。
そのため、就寝2時間前からはテレビやタブレットなどの使用を控えるとよいでしょう。ブルーライトカットフィルターを活用したり、画面の明るさを最小限に調整したりする工夫も効果的です。



わが家では、本を読んだりパズルで遊んだりするなど、就寝前は静かな遊びに切り替えるようにしています
リラックスタイムを設ける
就寝前のリラックスタイムは、心身を穏やかな状態に導いて、スムーズな入眠を促します。
やさしい音楽を聴いたりゆっくりとストレッチをしたり、深呼吸を一緒に実践したりするなど、子どもの好みに合わせて落ち着けるものを見つけてみましょう。
特に、スヌーズレンを取り入れた感覚遊びは、発達障害のある多くの子どもにとって効果的なリラックス方法といえます。柔らかい布やクッションに触れる、アロマオイルの優しい香りを楽しむ、やわらかな光の動きを眺めるなど、子どもの感覚特性に合わせた活動を選ぶのがおすすめです。
▼「スヌーズレン」の詳細についてはこちらからご覧いただけます!
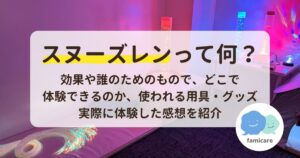
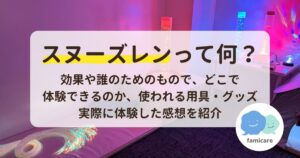
専門家への相談のタイミング



わが子に適した対処法がわからない



さまざまな対処法を試してみたけどダメだった…
そのような気持ちで本記事を見つけた方もいらっしゃるのではないでしょうか。睡眠の問題だけではなく、障がい児との暮らしのなかでさまざまな工夫を重ねるのは、簡単なことではありませんよね。
目に見える改善がまだ現れていなくても、子どもへの深い愛情と献身的なサポートは、必ず心に届いています。しかし、一人では解決が難しい課題に直面する場合があるのも事実です。
決して保護者としての努力が足りないということではありません。むしろ専門家の手を借りると、新しい視点や方法を見出せる可能性があります。
相談を検討すべき状況
毎日の睡眠時間が著しく少ない、または不規則な場合や睡眠不足が日中の生活に大きな支障をきたしている場合は、専門家へ相談してみるのがおすすめです。また、すでに対策を試してもなかなか改善が見られない場合や、子どもが睡眠に関する強い不安や恐怖を感じている場合も、一人で抱え込まないようにしましょう。



子どもへの適切な支援のためには、まずは保護者の方がストレスを溜め込みすぎないようにするのが大切です
相談できる専門機関
発達障害児の睡眠に関する悩みは、以下の機関で相談できます。子どもの特性を理解したうえで個別の状況に応じた具体的なアドバイスを提供してくれるため、全て家庭で完結させなければと思わず、気軽に活用してみるのがおすすめです。
- かかりつけの小児科
- 地域の保健センター
- 睡眠専門医
- 発達障害支援センター
- 児童発達支援センター など
発達障害児の「眠れない」には「心地よい環境づくり」から
一人ひとりの特性や生活環境が異なるように、発達障害のある子どもの睡眠問題への効果的な対処法も子どもによって異なります。
大切なのは、子どものペースを尊重しながら、できることから少しずつ取り組んでいくことです。環境調整や就寝ルーティンの確立、感覚特性への配慮など、工夫を組み合わせれば徐々に安定した睡眠リズムを築きやすくなります。
また、この過程で行き詰まりを感じることがあっても、一人で抱え込む必要はありません。専門家のサポートや同じような課題を持つご家族との情報交換も、解決の糸口として活用してみてくださいね。
「わが子はこんな対処法を試しても難しい…」「わが家ではこんな対処法を実践しています」などの声は、ファミケア公式SNSやアプリなどで聞かせてね


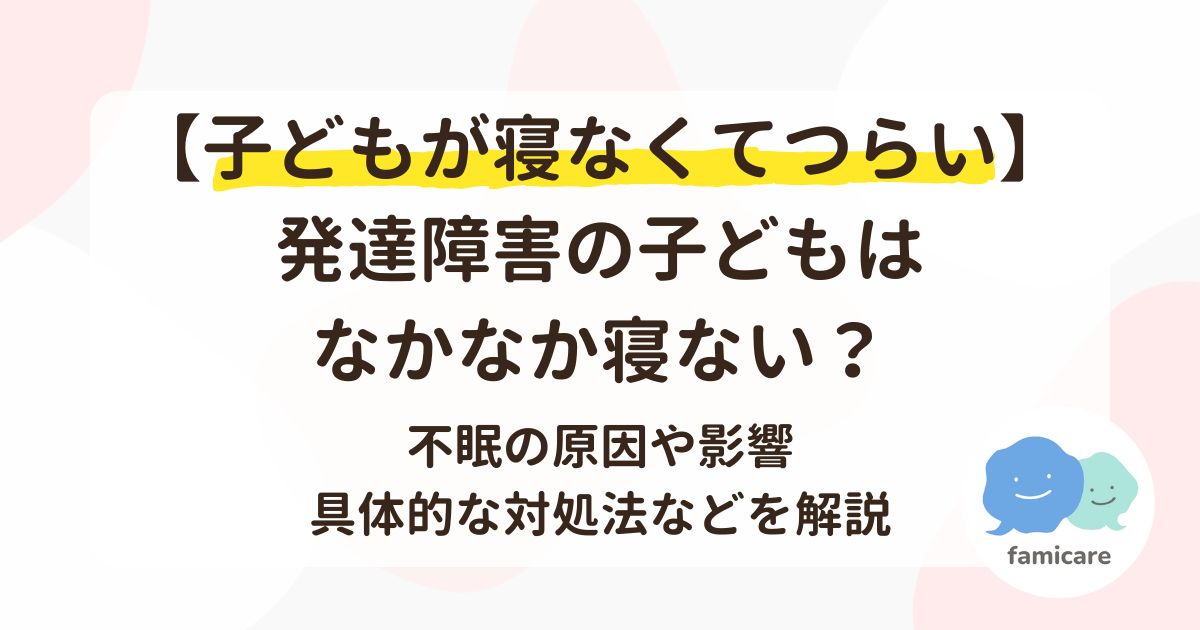

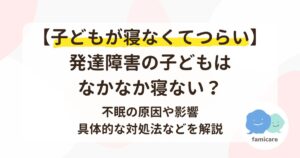

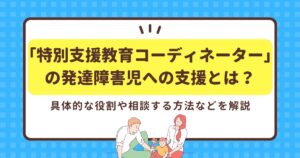
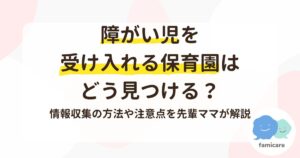
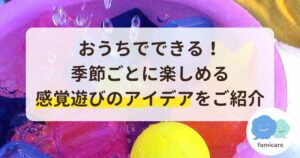
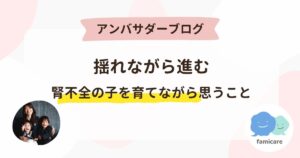
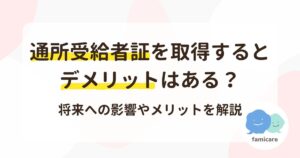
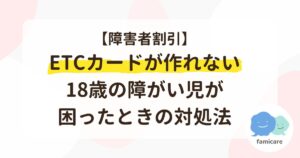
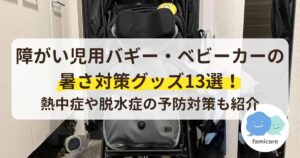
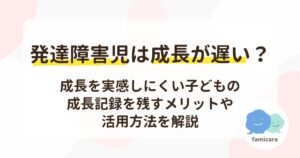
コメント