自分の子どもに障がいがあると分かった場合、不安に襲われるご家族は少なくありません。同様に、妊娠中に「もしもお腹の子に障がいがあったら…」と心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

現在妊娠中だけど、将来が不安
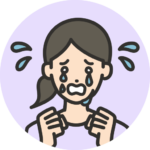
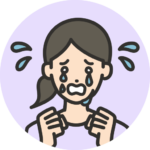
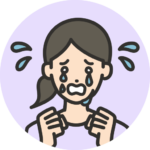
もしも障がい児が生まれたら、どう受け止めたらいい?



出生前診断を受けようか迷っている
そんな方に向けて、この記事では実際に障がい児を育てている筆者の体験談を交えながら、考えられる不安とそれに対する対処法をご紹介します。
▼障がい児が生まれる要因についてはこちらの記事で紹介しています
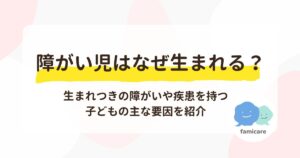
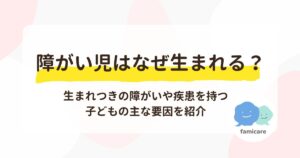
娘は障がい児…診断時に感じた不安
筆者の9歳の娘は、発達障害の一つ「自閉スペクトラム症」です。正式に診断を受けたのは、4歳4ヶ月の頃。しかし、それまでに「もしかして」と思う機会は多々あったため、明確な診断名がついたときには納得の気持ちが大きかったのを覚えています。
とはいえ、やはり不安や心配もありました。同時に「まさか自分が障がい児の母親になるとは」という思いを持ったのも事実です。我が子が障がい児だと診断を受けた際、筆者は次のような気持ちになりました。
本当に自分は育てられるのだろうか?
療育センターで診断書を目の当たりにした際、真っ先に思ったのが「自分はこの子を幸せにできるだろうか」でした。障がいを抱える我が子を、果たして適切に世話できるのだろうか。この子を本当に育てられるだろうか。そんなことをぐるぐると考えていました。
これから始まる未知の大変さって?
同時に「これからどんな生活になっていくのだろう…?」と、未知の子育ての大変さも不安でした。
筆者の場合、仕事柄さまざまな障がいの知識はあったものの、実際に発達障害児と暮らすのは初めて。発達の遅れは今後どの程度になるか、この子ならではの行動の特徴はどのようなことか、どのような療育が必要かなど、漠然としたさまざまな心配がありました。
将来はどうなるのだろうか?
そしてやはり、娘の将来についてです。娘の自立に向けて今後どのような支援が受けられるか、お友達とのコミュニケーションは取れるようになるか。
また、日々の生活に加えて療育や通院の付き添いも必要なため、仕事をセーブせざるを得ない状況を想像して経済的な心配も拭えませんでした。



先の見えないことと分かりつつ、つい考えてしまうのですよね。筆者も一緒でした。
障がい児を産むべき?産まないべき?



もしも妊娠中に子どもが障がい児と分かったら…産むべき?産まないべき?
この問いに、確かな答えはありません。しかし、障がいがあってもその子らしく幸せに生きられる道は必ずあります。
妊娠中の心配や不安は、当然のことです。「障がいがあれば大変なことになるのではないか」「私に育てられるだろうか」そう思うのは自然な感情です。例えば出生前診断を受けるかどうかなど、先の選択は簡単ではありませんよね。
しかし、一つだけ言えることがあります。障がい児を産むと必ずしも家族の人生が暗くなったり幸せを失ったりする、そんなことは決してありません。
確かに障がい児育児には特別な負担があり、予期せぬ壁にも直面します。しかし、障がい児との暮らしを支援するサービスや制度、施設は数多くあります。
なにより、一人で背負う必要はありません。例えば、同じ境遇の仲間と情報を共有し合えば、新しい育児のヒントが見つかりやすくなります。
なお「やみくもに子どもの情報を共有したくない」という方は、匿名で使える子育て支援アプリやクローズドの育児コミュニティなどを活用するのもひとつです。



かくいう筆者も、娘が生後3ヶ月の頃に故郷から離れた県外で数年間生活した際、支援センターなどには一切通っていませんでした。育休中なのも相まって気軽に悩みを話せる知り合いが近くにいない、とはいえ寝不足が続いており支援施設に出向くのも億劫になってしまう…子育て支援アプリで自分と似た境遇の方のお悩みを検索しては、私も頑張ろうと奮起する日々でした。
障がい児の子育てに向き合う心構え



障がい児との暮らし、あまり想像が付かないけどどんな風に向き合ってる?
そう思われる方がほとんどだと思います。障がいの名称や特性はそれなりに聞いたことがあっても、実際の暮らしや心構えは、やはり当事者になって初めて分かることだらけです。
障がいを受け入れる前に「不安」を受け入れる
障がい児を育てることへの不安は、誰もが抱える自然な感情です。「この子の将来が心配」「育てられるだろうか」など、さまざまな懸念が浮かびます。
その不安を否定したり、無理に払拭したりする必要はありません。自分にとっての不安や限界が分かるからこそ、必要な支援が見えてきます。
「頼ってみる」を自分に定着
障がい児との暮らしは、一人で抱え込むには大きな負担が伴います。そのため、医療や行政の専門家、同じ境遇の仲間など頼れる存在に頼ってみることを自分の中に定着させるのも大切です。



子育てで誰かに頼ると後ろめたさが出てしまう



頼る勇気が出ずに一人でこなそうとしてしまう
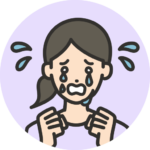
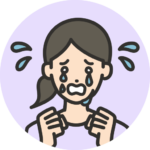
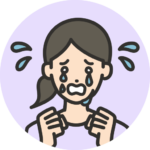
他人に預けるのが不安で任せられない
そうお話されるご家族もいらっしゃいます。しかし「毎日一緒にいる自分以外の大人と過ごす時間は、実は子どもにとってもよい刺激」と考えると、少しだけ心が軽くなりませんか?「自分の心身の健康は家族の要」と考え、背負いすぎてしまう前に相談しましょう。



筆者も、娘に発達障害の診断が出たときから小児科医や作業療法士、相談支援専門員などさまざまな専門家に相談してきました。
▼相談支援専門員について詳しくはこちら
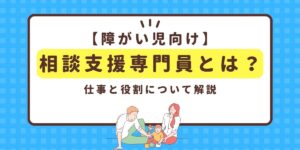
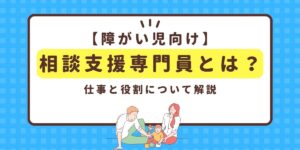
障がい児の生まれた後に育てるための支援



どんな状況の子育てでも、支援を求めていいんだ…!
障がい児との暮らしでは、例えば次のような支援が活用できます。
医療的ケアに対しての支援
主治医や療育施設と連携し、定期的な診察と療育に通って障がいの程度に合わせた適切な支援を受けられます。障がいの状態や対処法についてアドバイスを受けながら、安心して育児に取り組みやすくなりますよ。
日中に活動するための場の支援
放課後等デイサービスなどの児童福祉サービスでは、障がい児の発達を支援する専門的なプログラムが用意されています。そこで集団生活の機会を得ながら、生活能力の向上や社会との関わりを培っていけるのが特徴です。
▼障がい児育児の公的支援サービスはこちらの記事でまとめています
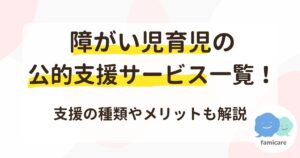
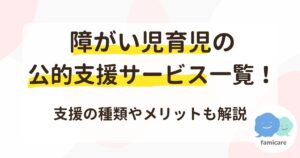
経済的支援な支援
障がい児の育児には、医療費や教育費、介護費用など大きな経済的負担を伴う場合があります。しかし、障害者手帳の取得や特別児童扶養手当の申請により、医療費の一部負担軽減や手当の受給が可能です。
さらに、税制優遇措置なども用意されているので、積極的に制度を活用しましょう。



障がい児の子育ては容易ではありませんが、心強い支援がたくさんあります。まずは「自分の状況に適した支援を知る」のがポイントです。
▼障がい児育児で利用できる経済的支援はこちらの記事でまとめています
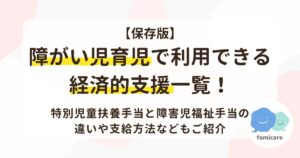
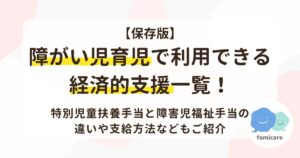
障がい児として生まれた子どもに親がしてあげられること
障がい児として生まれた子どもに、親ができることは数多くあります。華々しいことばかりではないかもしれませんが、大切なのは、地に足をつけた実践的な取り組みです。
こつこつと続ける療育
障がい児の発達のサポートには、療育を欠かせません。しかし、子どもに合わせた適切な療育を見つけるまでには、試行錯誤を重ねる必要があります。
「これが合っているのか分からない」「続けても効果は出ないのではないか」そんな不安もありますが、家族の心身も尊重しながら諦めずにこつこつと続けることが何より大切です。
伴走者として寄り添う
障がい児の成長には、いくつものハードルが待ち構えています。親としてできるのは、ゆっくりでも乗り越えられるよう、過剰に期待をかけるのではなく焦らず子どものペースに合わせて伴走することです。



「引っ張っていく」と力むよりも「横に並んで走る」とのイメージに近いかもしれません。
子育ての喜びを見つける
「障がい児育児」と聞くと、つらく重い日々の連続のような印象を持つかもしれません。しかし実際は、子どもの小さな成長を見てうれしくなるのは、どんな状況の子育てでも同じです。
例えば、療育の成果が現れた際の喜びは嬉しさ以上のものがあります。「できない」「できないかもしれない」と無意識に考えがちだったことができるようになった瞬間は、子どもの可能性を感じられる何にも代えがたい時間です。



筆者の娘は特に時間の見通しを持つのが難しく、外出の際に家を出るギリギリまで準備ができない自分にイライラし、癇癪を起こしていました。しかし「〇時に出発するよ」と事前に聞き、その時間までの予定を自分でホワイトボードへ書き込んで見通しを立てる方法を少しずつ習得。その結果、癇癪の回数は減りましたが、それよりも「工夫すれば自分にもできるんだ」と自信を持った娘を見られたのが、親にとってなにより嬉しいことでした。
まずは手厚いサポートの存在を知ることから
障がい児を授かることへの不安は、誰もが抱えるものです。「可愛いとは思えるだろうけ ど、本当に自分に育てられるのか」「産む前からそんなことを考えてしまう自分は親になれないのではないか」…いろいろと考えてしまいますよね。
しかし、障がいの有無に関係なく、子育て自体が大変な作業です。その分、うれしさを感じる瞬間も障がいの有無に関係なくあります。
一人で背負い込む必要はありません。助けになってくれる人や手厚い支援の存在を知ったうえで、家族や医療関係者、行政のサポート窓口など頼れる場所に気兼ねなく相談してみてくださいね。
なかなか吐き出しにくい思いは、ファミケアの公式SNSやアプリでも待ってるよ


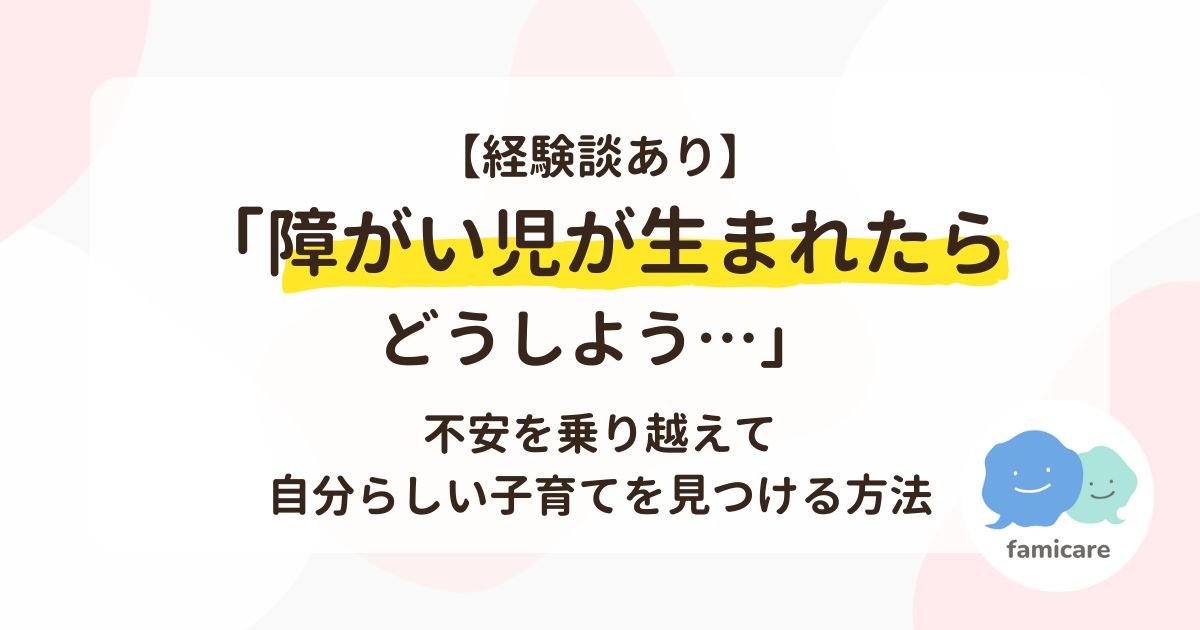
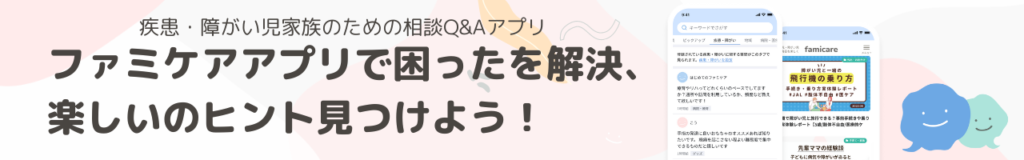



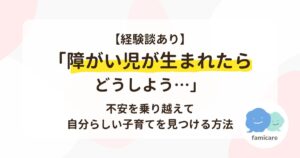


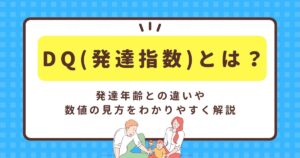

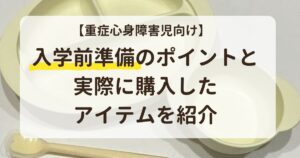

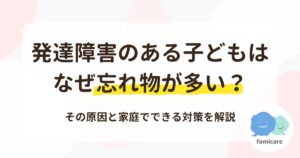


コメント