障がいのある子どもの発達支援には、さまざまな制度やサービスが利用できます。しかし、

具体的にどんな支援をどうやって受けられるの?
支援を受ける具体的なメリットって?
そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障がい児育児で支援を利用するメリットや上手な受け方、心掛けたいポイントを解説します。障がい児育児に疲れが溜まってつらい方、障がい児育児の支援をどのように受けたらいいか迷っている方はぜひ参考にしてみてくださいね。
▼支援の種類についてはこちらの特集でも詳しく紹介しています。
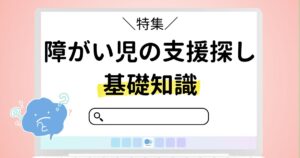
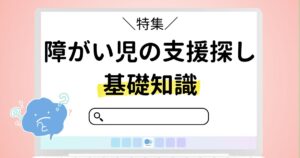
障がい児育児支援を利用するメリット
障がい児育児支援の利用には、次のようなメリットが挙げられます。
子どもの長所を伸ばして社会参加を支援できる
障がい児育児支援を利用する大きなメリットとして挙げられるのが、子どもの「苦手」「不得意」の細やかなサポートに加えて「好き」や「得意」をさらに伸ばせる点です。
例えば、以下のような形で支援を受けることができます。
【ケース例1】
言葉に遅れが見られる子どもへ言語聴覚士が絵カードでの言語訓練や単語の暗記練習をする
【ケース例2】
手先に不器用さが見られる場合は、作業療法士がボールや積み木など子どもの興味を引くさまざまな遊びを活用して、日常生活動作や感覚面、認知・学習面をサポートする
障がいの特性に応じた丁寧な支援を受ければ、子ども一人ひとりの長所や可能性を伸ばせる効果が期待できます。



一回一回の支援を長い目で見ると、特性を活かしながら自立と社会参加を後押しすることに繋がります。
保護者の負担を軽減できる
障がい児の育児は、精神的にも体力的にも保護者の負担が大きくなりがち。支援を利用すれば介護や療育の一部を専門家に任せられるので、ご家族が休める時間を作ることができます。
例えば、放課後等デイサービスを利用すれば、学童保育の延長線上で障がい児の居場所が確保可能。遊びを通した生活訓練や家庭への送迎付きサービスなども組み合わせられるのは、障がい児育児支援の大きなメリットです。
また、相談支援事業所では、日常の悩みを気軽に相談できる窓口も設けられています。孤立しがちな育児から開放され、前向きな気持ちを持続できるよう後押ししてもらえるのは、心強いものです。
二次障害のリスクの回避に繋がる
発達障害のある子どもの場合は、二次障害のリスク回避にも繋がります。
二次障害とは?
本来抱えているさまざまな障がいの特性を「一次障害」とすると、家庭や学校など取り巻く環境から起きる反応を「二次障害」といいます。
例えば、周囲が発達障害だと理解していない状態で特性によるミスなどを繰り返し、非難されたり叱責されたりする機会が増えて自信喪失や孤立が見られたとします。そこから引き起こされる心身症や不登校、大人への反抗的行動、意欲の低下などが二次障害です。
障がい児育児支援では、子どもの様子をきめ細かく見守る専門家が介入してくれます。適切な支援を受けながら子ども本人やご家族が障がいに対する正しい知識を得られるため、子どもの生きやすい環境を見つけて、二次障害のリスクの回避に繋がるのが魅力です。
障がい児育児支援はこう活用する!上手な受け方



障がい児育児支援を受けるのはメリットがありそうだけど、実際どう活用したらいいの?
そんな方に向けて、障がい児育児支援の受け方を3点挙げてみます。
自治体の障害福祉課への相談
障がい児育児の支援は、身近なところだとお住まいの自治体の障害福祉課で相談できます。自治体の障害福祉課では、地域に特化した支援制度や情報を得やすいのが特徴です。
一方で、事業所の詳細や支援の細かな内容までは聞けない場合があります。そのため、障害福祉課での相談中に気になる事業所を見つけたら、サービス内容や利用可能時間、見学可能かなどを直接問い合わせてみるのもおすすめです。
相談窓口の活用
障がい児育児支援へのわかりやすい入り口になるのが、お住まいの市区町村や近隣にある相談窓口です。子どもの状況を詳しく相談すれば、必要な支援メニューを一緒に検討してもらえます。
活用できる各相談窓口の一例は、次の通りです。
発達障害者支援センター
医療や福祉をはじめ、保健、教育、労働などさまざまな分野の関係機関と密に連携しながら、地域に根ざした幅広い支援を探せる場所です。発達障がいのある子どもを支援する地域の機関についても情報提供をしています。
▼発達障害者支援センターの一覧はこちら
http://www.rehab.go.jp/ddis/action/center/
精神保健福祉センター
悩んでいる方からの相談に乗り、精神面の健康と医療についてサポートしてもらえる場所です。特性のある子どもの日常的な相談だけではなく、障がい児育児に疲れているご家族にも寄り添ったうえで必要な支援を提案してくれます。
▼全国の精神保健福祉センター一覧はこちら
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/hoken_fukushi/index.html



児童発達支援や放課後デイサービス、相談支援事業所の利用など、住んでいる地域でどんなサービスを受けるのが適しているかも見えてきます。
家族や専門家との連携
障がい児の成長には、さまざまな分野の専門性が必要といえます。子どもの日常をよく理解しているご家族が、障がいの知識を持つ専門家と連携すれば、より適切な支援を見つけやすくなるのです。



例えば、多くの事業所と連携しており豊富な情報を持つ相談支援専門員を頼れば、各事業所の特徴や評判を聞けます。専門家と協力体制を築ければ、ご家族の精神的・肉体的負担も軽減できますよ。
同じ境遇の方から情報を収集
障がい児の育児の課題や悩みは、ご家庭によって本当にさまざまですよね。親の会やコミュニティ、SNSなどで同じ境遇のご家族と交流して体験に基づく情報を共有すれば、実践的なアドバイスやサポートを得やすくなります。
実際に支援を利用してみた感想やコツ、制度の活用法など、公的な情報のみでは分からない役立つ情報を教えてもらうのも一つです。



自分だけでは気付けない支援の利用法や対処法のヒントを得られるだけではなく、孤立感の解消にも繋がります。
▼障がい児の親のコミュニティについてはこちらの記事で解説しています
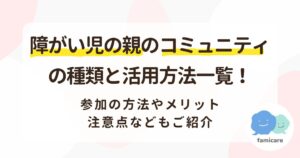
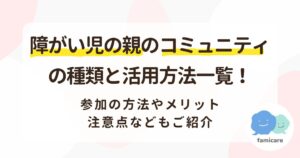
障がい児育児支援を受ける際のポイント



障がい児育児支援のメリットや受け方が分かったところで、支援を受ける際に気を付けておきたいことも知りたい!
そんな方へ向けて、障がい児育児支援を受ける際に押さえておきたいポイントを3点ご紹介します。
支援制度や手続きについての情報収集
障がい児育児支援は、自治体や国の制度に基づいてサービスが提供されています。そのため、サービスの種類や利用の手続き、費用負担について事前に情報を集めておくのがおすすめです。
インターネットで調べるのはもちろん、相談窓口に出向いて直接質問するのも有効な方法といえます。分からないことがあれば遠慮なく聞き、理解を深めていきましょう。
自分のペースで無理なく続ける
障がい児育児では、望むサービスを一度に全て受けられるわけではありません。経済的な理由や地域の事情によって、得られる支援に制約がある場合もあります。そんなときも焦らず、無理のない範囲で継続していくのが大切です。
サービスを組み合わせる順番を工夫したり、利用頻度を調整したりと、子どもとご家族に合ったペースを作っていきましょう。例えゆっくりとでも前に進めば、充実した支援に繋がります。
子どもの成長に合わせた支援の見直し
子どもの年齢や発達段階に応じて、必要な支援は変わっていくもの。普段の子どもの様子を家庭内で共有し、定期的に専門家とも振り返れば、成長に合わせてサービスの組み合わせを見直せます。
大切なのは、入園や就学時期、思春期など細やかな配慮が必要なライフステージ以外の時期にも周囲や専門家をどんどん頼ることです。
▼障がい児育児の公的支援サービスはこちらでまとめています
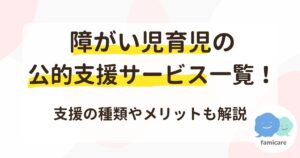
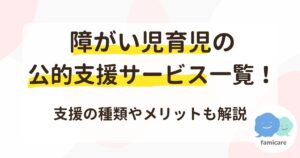
専門家やサービスを頼りながら“我が家らしい”障がい児育児支援を
障がい児育児をするなかで、つらかったり孤独を感じたりすることもありますよね。一人で抱え込まずに専門的な支援を利用すれば、子どもの可能性を最大限に伸ばせるだけでなく、ご家族の負担も軽減できます。
障がい児育児には、社会的な理解と支えが欠かせません。地域や専門家と力を合わせて、子どもの成長を見守っていきましょう。
「こんな支援を活用中!」「障がい児育児、こんな工夫しています!」そんな声は、ファミケア公式SNSやアプリでも聞かせてね


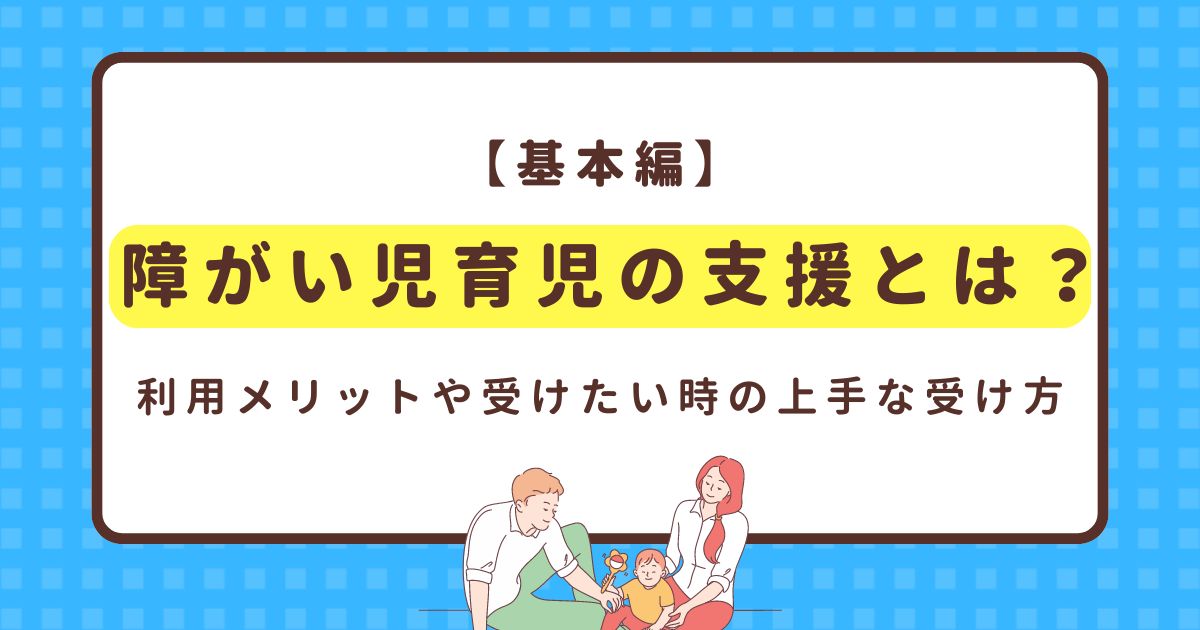
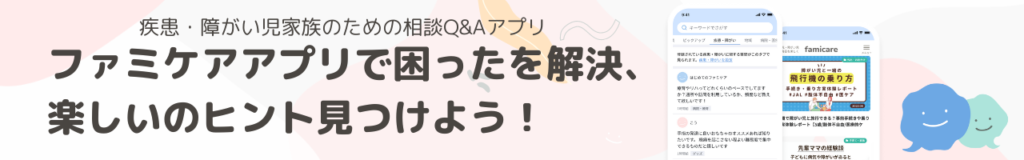



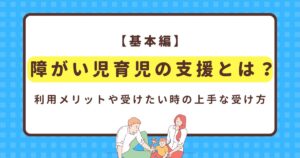

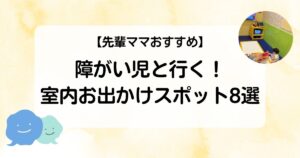
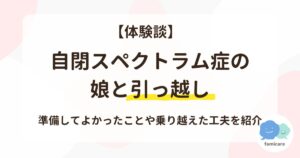

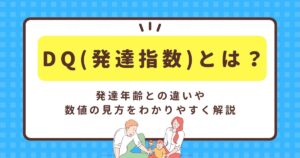


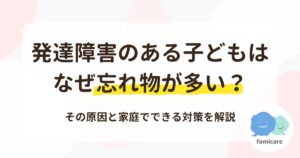

コメント