NICUに入院している子どもが、どのような流れで退院するのか、退院までになにをすればいいのか、わからなくて不安な人もいるのではないでしょうか。

退院までになにを準備すればいいかわからない



退院するまでに必要なことはなに?
と思う方もいるはずです。筆者もその1人でした。
そこで今回は、医療的ケア児を育てる筆者が、息子がNICUから退院する際にした退院準備や入院してから退院するまでの流れを紹介します。
息子の情報
- 保育園に入園した年齢:1歳7ヶ月
- 疾患名:先天性ミオパチー(ミオチュブラーミオパチー)
- 必要な医療的ケア:人工呼吸器、吸引、経管栄養(NG→ED)
- 入院期間:約半年
▼NICUの情報がまとまっているサポートガイドはこちら


NICUから退院準備までの息子の状況の変化


2022年7月19日、重症新生児仮死状態で生まれた息子は、お腹から出てきてすぐ緊急処置をされ、NICUへと運ばれていきました。
週1回、1回15分の面会に通い、出産から約3ヶ月経った10月3日、遺伝子検査の結果により指定難病である先天性ミオパチーの中のミオチュブラーミオパチーであることが確定。家に帰るには気管切開の手術と、人工呼吸器管理が必要である旨も伝えられました。
出産した病院は家から1時間かかり遠く、また気管切開できる体重が4kgと時間がかかるため、家の近くの大きい病院への転院を勧められ検討し、決定しました。
10月に体重3kgで気管切開手術ができる病院へ転院しNICUで入院、気管切開手術を受けました。その後、小児病棟へ転棟し、そこから退院に向けて2ヵ月半程度の間、医療的ケアの手技の練習やその他退院に向けての準備が始まりました。
NICUに入院した医療的ケア児の子どもの退院準備
今回は筆者家族が経験したNICUから退院する際の子どもの退院の準備を紹介します。人によって子どもの状況や必要な医療的ケアはさまざまなため、ざっくりとした流れを参考にしていただけたら嬉しいです。
準備することはたくさんありますが、焦らず1つずつ進めていけば、不安を少しでも解消して退院できますよ。
在宅生活を送るための準備
医療的ケアの手技の練習
医師との相談で退院の目安や相談がはじまった後、医療的ケアがある子どもの場合、ケアの手技の練習が必要不可欠になります。
練習の開始タイミングは子どもの状況や病院の体制によって異なります。
病院側がスケジュールを設定し、最初は看護師が教えてくれながら、面会時などで練習を進めました。看護師さんが冊子を用意してくれたので、それを参考に練習します。
実際にやってみて、不安なことやわからないことは看護師になんでも聞くといいと感じました。不安を残したままにせず、どんなに小さなことでも質問してみると、丁寧に教えてくれます。



息子の場合は生後約3ヶ月で行った気管切開手術のあと、医療的ケアの手技の練習が始まりました。
最初は何もわからず不安でいっぱいで、終わる頃にはどっと疲れている状態でした。しかし時間が経つにつれ慣れていき、医療的ケアへの不安は少なくなっていきました。
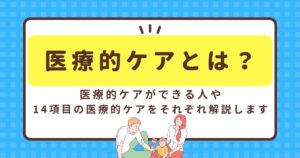
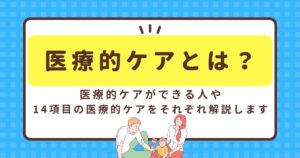
院内外泊の有無の確認・準備・実施
退院する前に、退院後の生活を見据えた練習として院内で家族で過ごす院内外泊をしました。院内外泊の有無は医師に確認し、確認や準備をして、実施します。
個室の部屋で子どもと夫と私で一緒に過ごし、できるだけ医療者が関与しないようにして生活しました。



医療者が関与しないことで、退院後の生活の練習になったので、やってよかったなと思っています。ちなみに筆者は2回行い、1回目は1泊2日、2回めは2泊3日で行いました。1回目は不安でいっぱいでしたが、2回目にもなると少し慣れ、息子との生活をイメージできるようになっていました。
関係者が全員集まって行われる簡単なカンファレンスの実施
相談支援専門員、訪問看護ステーション、訪問医、役所の支援課の担当の方など、退院後お世話になる方々が決まったら、全員が病院に集まってカンファレンスを行いました。
本当に簡単なもので、自己紹介と「これからよろしくお願いします」といった挨拶程度のものでしたが、これだけの人たちが今後息子に関わっていくのだとわかるので、とても心強く感じました。
医療・福祉サービスを受けるための準備
障害者手帳や小児慢性特定疾病受給者証などの申請の準備
退院後の在宅生活に向けて、障害者手帳や小児慢性特定疾病受給者証などの準備が必要です。手続きをしておくことで、サービスの利用や医療・福祉にかかる費用の補助を受けることができます。



どの申請にも、医師に診断書を書いてもらうことが必要なので、担当医にお願いしました。
▼障害者手帳に関してはこちらの記事をチェック
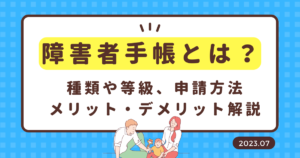
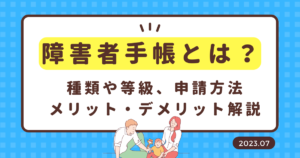
相談支援専門員と面談
個別計画の作成や福祉サービスの利用までのサポートをしてくれる相談支援専門員と面談をします。
家族の事情や家庭状況をヒアリングしてもらうことで、必要な福祉サービスを提案してくれます。



我が家の場合は、家庭状況を聞いてもらったところ、夜間のヘルパーさんが必要なのではないかと提案されました。
▼相談支援専門員についてはこちらの記事をCheck!
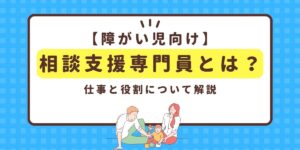
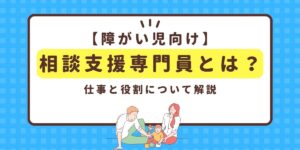
訪問医・訪問看護ステーションの検討・面談・決定
退院後の生活で訪問医や訪問看護が必要な場合、お世話になる訪問医と訪問看護ステーションを検討して決定します。決定までには退院前に面談を行いました。
退院調整看護師が私たちの地域に合わせていくつか候補をちらしで持ってきてくれたので、訪問医や訪問看護ステーションの候補はその中から決めました。
どうやって決めたらいいか悩みましたが、ネットで検索したり、SNSで質問してみたり、退院調整看護師に相談したりしながら決めていきました。



退院調整看護師に教えてもらったのは、「この訪問看護ステーションはこの訪問医と連携した経験がある」のような情報や、「ここには男性の看護師もいるのでパパさんの悩みを聞いてもらいやすい」などのアドバイスでした。これらの情報やアドバイスが役に立ち、今でも訪問医と訪問看護師には問題なくお世話になっています。
▼訪問看護師についてはこちらの記事をCheck!
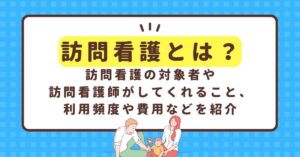
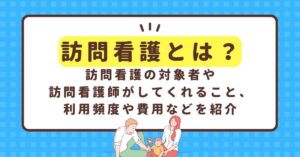
利用する福祉サービスの決定
相談支援専門員との面談や情報収集した内容を踏まえて、退院後に利用する福祉サービスを決定しました。家庭内で利用を決めたら、相談支援専門員に相談し、手続きを支援してもらいます。



筆者の場合は、面談の時に提案された夜間ヘルパーを利用したかったので、その旨を伝え、事業所を紹介してもらいました。
在宅生活に必要なものの準備
吸引器など在宅生活で使う医療機器の準備
在宅生活に医療的ケアのための医療機器が必要な場合、購入やレンタルで吸引器のような医療機器の準備をします。
我が家の場合は吸引器が必要だったため、吸引器を購入する業者に見積りを出してもらいました。
すでに手続きをすませていた小児慢性特定疾病受給者証と見積書、印鑑を持参し、市区町村の支援課に見積もりを提出することで、吸引器を補助を受けて購入することができました。
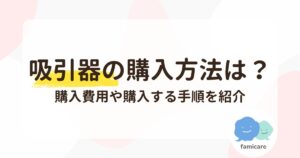
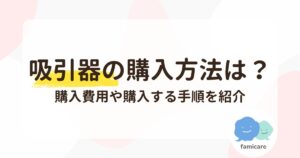
外出用の吸引器や持続吸引器の準備
退院する前に、外出時に使えるような吸引器や必要な人は持続吸引器の準備をします。
自宅用の吸引器は大きく、持ち運びに不便なのでコンパクトなサイズの外出用の吸引器を準備しておくと便利です。



筆者の息子の場合は持続吸引器も必要だったため、外出用の吸引器と持続吸引のための吸引器を一緒にネットで購入しました。
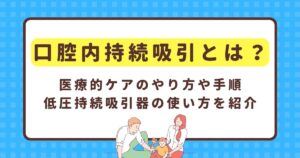
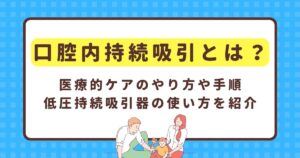
酸素濃縮器や酸素ボンベ、サチュレーションモニターの準備
酸素濃縮器や酸素ボンベ、サチュレーションモニターの業者に病院に来てもらい、何が必要なのかを相談しました。
我が家の場合は常に酸素が必要なわけではありませんでしたが、何かあったときのための酸素濃縮器と自宅用の酸素ボンベ、外出用の酸素ボンベ、サチュレーションモニターを用意してもらうことになりました。
ベビーカーやバギーの準備
退院後に必要になってくるベビーカーやバギーの準備をします。
医療的ケアがどのくらいあるのか、荷物は多いのかなどによって選ぶベビーカーやバギーの種類は変わってきます。



筆者の息子の場合は、人工呼吸器や持続吸引器など荷物が大きく、重たかったので、頑丈で荷台の耐荷重が大きいものを選びました。
▼医療的ケア児のベビーカー選びについてはこちらの記事をCheck!
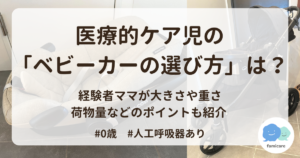
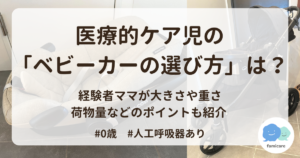
自宅での生活を見据えた生活用品の準備
退院後、自宅での生活を見据えた用具の準備もします。
まず子どもがどこで過ごすのかを決め、医療的ケアに必要な物品を置くワゴンを準備したり、寝て過ごせるようにマットレスやタオル類を準備したりします。



筆者の息子の場合は、息子が過ごす場所は小上がりと決め、マットレスを用意しました。また医療的ケアに人工呼吸器、吸引、経管栄養があったので、それらを収納するワゴンや点滴スタンドを準備しました。
▼収納ワゴンについての記事はこちらをCheck!
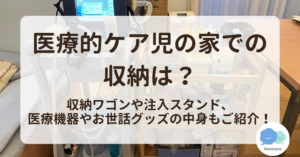
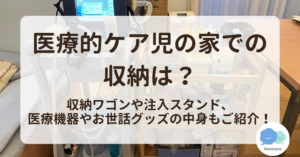
▼快眠マットレスSOYOの記事についてはこちらをCheck!
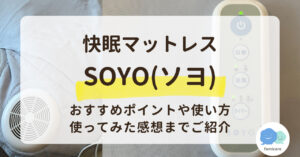
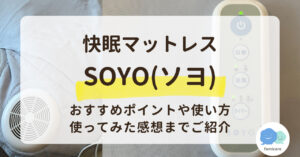
退院準備を進める上でのコツ
退院準備を進める上でのコツを紹介します。
コツ1:退院後の生活を見据えた準備をする
退院準備で大切なのが、退院後の子どもとの家での生活を見据えた準備をすることです。
医療的ケアの手技の練習や申請するもの、準備する用具、利用するサービスだけでなく、院内外泊という実際に医療者のいない環境で生活する準備などもしておくと、退院後の生活の心の準備ができます。
子どもと安心して生活するためにも、退院後の生活を想像して準備を進めることが重要です。
コツ2:不安や心配なことはなんでもまわりに相談しておく
入院している間に、不安や心配なことはなんでもまわりに相談しておきましょう。
医療的ケアの手技の練習のことは看護師に、訪問医や訪問看護ステーションについては退院調整看護師に、障害福祉サービスの利用については相談支援専門員になど、それぞれの分野で強みのある人に相談しておくと安心です。
もちろん退院後でも、不安や心配なことはまわりに相談することはできます。しかし退院する前に相談しておくことで、退院前の漠然とした不安は解消されると思います。



筆者は退院前、漠然とした不安でいっぱいだったので、わからないことはすべて看護師や退院調整看護師などに相談していました。話を聞いてもらうだけでも、少し安心することができました。
NICU入院から退院するまでの準備は在宅生活を安心して過ごすために必要なこと
NICUに入院してから退院するまでに必要な準備はたくさんあります。
医療的ケアがあれば手技の練習、必要な証明書の準備、退院後お世話になる方たちとの面談や使うサービスの検討、必要な用具の準備など、退院後必要になるものやサービスばかりです。
また院内外泊という、退院後の生活を見据えた家族だけの時間を過ごすことで、より鮮明に在宅生活をイメージすることができます。
たくさんやることがあって不安もあると思いますが、それぞれの専門家の力を借りて、慌てずにコツコツと準備を進めましょう。そうすれば、安心して子どもとの在宅生活を送ることができますよ。


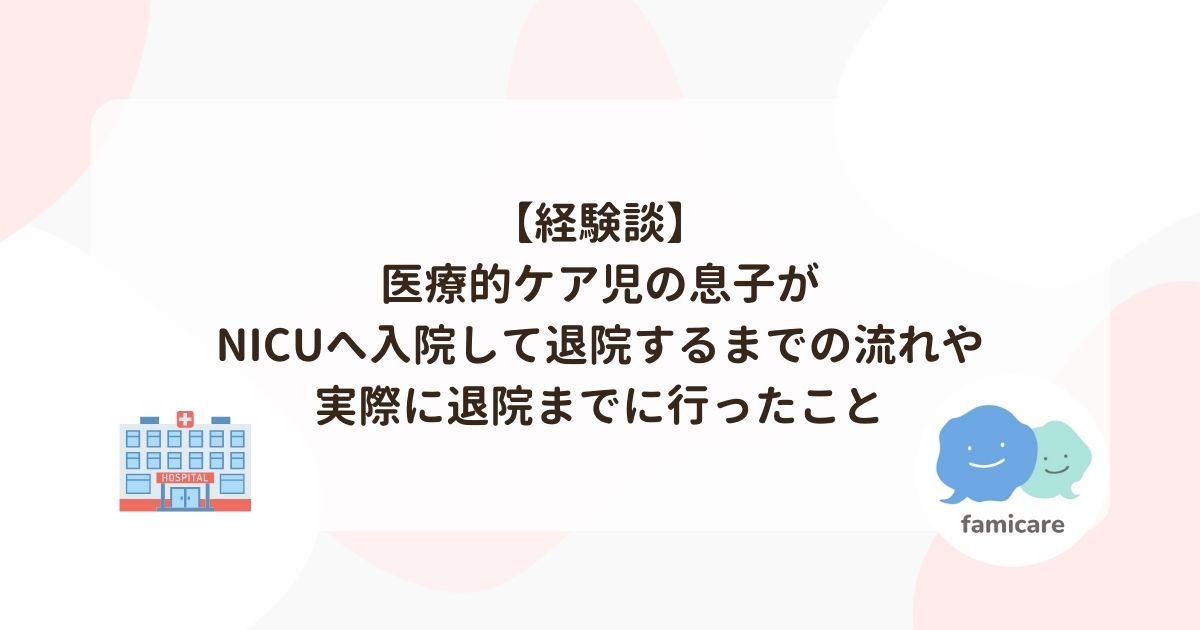

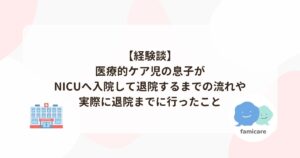




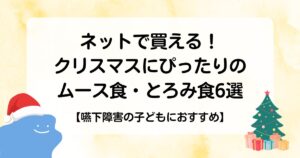
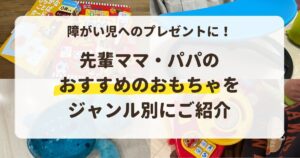
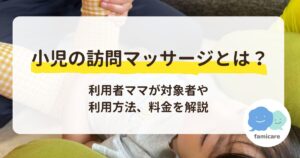
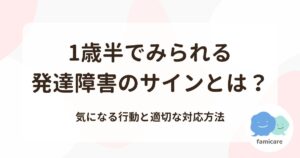

コメント