発達障害に分類されている「ADHD(注意欠如・多動障害)」と「ASD(自閉スペクトラム症)」。
名前は知っているけれど、違いがいまいち分からない…!
そんな方のために、本記事では「ADHDとASDとの違い」について分かりやすく解説していきます。それぞれの特性を詳しく知ったうえで適切なケアを考えたい方、違いや共通点を知りたい方は参考にしてみてください。
\この記事を監修してくれた先生/


言語聴覚士 佐々木 美都樹(ササキミヅキ)先生 / ササミ先生
北里大学言語聴覚療法学専攻を首席卒業。言語聴覚士免許(国家資格)及びパーキンソン病治療「 LSVT®︎LOUD」ライセンス所持。マカトン法ワークショップ基礎1、PECS®︎レベル1ワークショップ修了。成人を対象とした外来リハビリテーション施設・訪問リハビリテーション施設・介護老人保健施設、小児を対象とした児童発達支援事業所に勤務。息子の超希少進行性遺伝子疾患をきっかけに、オンラインでの相談事業を立ち上げる。現在は、児童発達支援事業所で勤務する傍ら、ことばの相談室Hopalを運営している。
ADHD(注意欠如・多動障害)とASD(自閉スペクトラム症)は異なる疾患
ADHD(注意欠如・多動障害)とASD(自閉スペクトラム症)は同じ発達障害に分類されていますが、別の疾患です。特性が異なるため、接し方や困り事への対処法も異なります。ADHDとASDの違いは発達検査によって診断されます。
また、ADHDとASDは併発する場合もあり、どちらの特性を持っている人もいます。
ADHD(注意欠如・多動障害)とは?
ADHD(注意欠如・多動症障害)は「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの特性がみられる状態です。Attention-Deficit/Hyperactivity Disorderの頭文字を取って「ADHD」と呼ばれています。



ADHDは、以前「注意欠陥・多動性障害」とも呼ばれていました。しかし、2013年にアメリカの精神医学会が出版した「DSM‐5」(「精神疾患の診断・統計マニュアル」第5版)にて「注意欠如・多動性障害」に変更されています。
3つの特性の一例は、次のとおりです。
「不注意」傾向
- 活動に集中できない
- 物をなくしやすい
- ミスが多い
- 気が散りやすい
- 活動に集中し過ぎて切り替えが難しい(過集中)
- 順序立てて活動に取り組むことができない など
ほどほどに集中する、というのが難しいんだね〜
「多動性・衝動性」傾向
- じっとしていられない
- 静かにしていられない
- 手足をそわそわと動かしている
- 急に走り出す
- ついしゃべり過ぎてしまう
- 相手が話し終わる前に話し出してしまう
- 順番が待てない



ADHDは「不注意が優勢」「多動・衝動性が優勢」「混同して存在」と、症状に個人差があります。
ASD(自閉スペクトラム症)とは?
ASD(自閉スペクトラム症)は「社会的コミュニケーション面」「行動や関心へのこだわり」「感覚のかたより」などの特性がみられる状態です。Autism Spectrum Disorderの頭文字を取って「ASD」とも呼ばれています。
特性の一例は、次のとおりです。
対人関係や社会的なやりとりの困難さ
- 友達の言葉や視線、表情や身振りなどを用いたやりとりが苦手
- 自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちをくみ取ることが難しい
- セリフを棒読みするように話す、妙に大人びた言葉遣いをする
- 人が言った言葉をそのまま、または少し時間を置いてから繰り返す(エコラリア)
- 一方的に話し続けてしまう
- 新しい環境が苦手
- 自分視点での思い込みが多くみられる など
興味の限定や反復行動
- 特定のことやモノに強いこだわりを持つ
- 好き嫌いが極端
- 自分なりのルールが決まっていて曲げられない
- ルーティン通りに行動しないと不安 など
感覚の過敏さ、または鈍麻さ
- 特定の音や大きな音が苦手
- 日光や電気など、特定のまぶしい光が苦手
- 好きな匂いや嫌いな匂いが顕著
- 特定のものだけを食べる、もしくは特定のものを一切食べない(偏食)
- 痛みを感じにくい



ADHDは「集中の継続が難しい」との一方で、ASDは「こだわりが強い物事に対して高い集中力を発揮する傾向」がみられます。また対人関係においては、相手の感情や思考が直観的に理解しにくく場にそぐわない発言をしてしまいやすいASDに対し、ADHDは相手の思考や感情は理解できるものの、高い衝動性から思ったことをそのまま口に出してしまいやすいのが特徴です。
ADHDとASDの診断基準とは?
ADHDとASDは、基本的にDSM-5に基づいて医師によって診断されます。DSM-5におけるADHDとASDそれぞれの基準は、次のとおりです。
ADHDの診断基準
DSM-5におけるADHDの主な診断基準は「不注意傾向」と「多動性・衝動性傾向」の2つ。それぞれの具体的な項目は次のとおりです。
不注意傾向
- 細かい注意を払えない
- 注意の継続が難しい
- 不注意から失敗することがよくある
- 話を聞いていないように見える
- 指示されたことをやり遂げるのが困難
- 順序立てて課題を進めるのが困難
- 課題に取り組みにくい
- 必要な物をなくしやすい
- 気が散りやすい
- 大切な予定や約束を忘れる、抜け漏れることがある
多動性・衝動性傾向
- そわそわと手足を動かす、座っていてももじもじ動いてしまう
- 着席し続けることが難しく、席を離れてしまう
- じっとしていられないような気分になる
- 遊びや余暇活動に静かに取り組みにくい
- 思いつきで行動し続ける、じっとしていると落ち着かない
- しゃべり過ぎることが多い
- 相手の話が終わる前に話し始めてしまう、相手の言葉を先取りしてしまう
- 他の人の活動を遮ってしまう
ADHDは、これら「不注意傾向」「多動性・衝動性」をふまえて次の基準を満たした際に診断される傾向にあります。
- 不注意または多動性・衝動性の各項目で、6つ以上当てはまる状態が6ヶ月以上ある
- 不注意または多動性・衝動性の症状のうちいくつかが12歳になる前から存在していた
- 不注意または多動性・衝動性の症状のうちいくつかが2つ以上の状況において存在する
- これらの症状が、社会的、学業的、または就職的機能を損なわせている、またはその質を低下させているという明確な証拠がある
- その症状は、統合失調症、または他の精神病性障害の経過中にのみ起こるものではなく、他の精神疾患ではうまく説明されない
ASDの診断基準
ASDは、次の基準を満たした際に診断される傾向にあります。
- 社会でのコミュニケーションや対人交流に持続的な障害が起きている
- 限られたパターンの行動や興味、活動が繰り返されて日常生活に支障が出ている
- 発達早期に症状が存在している(ただし、社会的な要求が限られた能力を超えるまでは症状は完全に明らかにならないかもしれない。その後の生活の対応の仕方によって隠されている場合もある)
- その症状は、社会的、職業的、または他の重要な領域における現在の機能に臨床的に意味のある障害を引き起こしている
- 知的能力障害(知的発達症)または全般的発達遅延ではうまく説明されない



ADHDとASDには「ミスが多い」「相手に失礼な言動を無意識にしてしまいやすい」などの共通点もあるのが特徴です。ADHDとASDどちらによるものかが分かることで適切な対処法が変わる場合があるため、慎重に診断されます。
ADHDとASDは併発する場合も
実は、ADHDとASDが併発する場合も珍しくありません。発達障害のある成人(20〜70歳)838名のうち、ADHDとASDを併存しているケースは26.8%(225例)という報告もあります。
【参照】:成人の発達障害に合併する精神及び身体症状・疾患に関する研究|令和元年度厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業
URL:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/192131/201918004A_upload/201918004A0008.pdf
発達障害の症状は、診断名で明確に分類できるものではありません。しかし、いくつかの特性が重なっている場合「ASDのみ」「ADHDのみ」に焦点をあてた対処法ではなく、困りごとの度合いなどを見ながら合わせたアプローチが必要です。
ADHDとASDを見極めたいときは専門家へ相談を
前述したように、ADHDとASDの見定めには慎重さが必要です。とはいえ「我が子はADHD優位?ASD優位?どっちなんだろう…?」と気になる方もいらっしゃいますよね。
ADHDとASDとをどうしても見定めたい場合は、自己判断せずに、病院や療育センターなどで専門家に相談してみましょう。医師や専門家は「症状がどれくらいの期間継続しているか」「発達検査の数値や結果はどうか」「AQ(自閉スペクトラム症指数)テストやADHDチェックリストなどで高い点数が出るか」などから総合的に判断します。



「どの程度の強さの症状で当てはめるか」の基準は医者や専門家によって異なりますが、環境を整えて適切な対応をするための貴重な手がかりにできます。「いきなり病院に連絡するのは気が引けて…」という方は、保健センターや発達支援センターなどからお気軽にご相談ください。
▼こちらの記事は下記を参考に執筆しました
【書籍】
発達障害の子どもの心と行動がわかる本|田中康雄(監修 2014年 西東社
【サイト】
自閉スペクトラム症(ASD)とは?|一般社団法人 日本自閉症協会
URL:https://www.autism.or.jp/about-autism/
DSM5 病名・用語翻訳ガイドライン(初版)
URL:https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/dsm-5_guideline.pdf
注意欠如・多動症(ADD,ADHD)|MSDマニュアル プロフェッショナル版
自閉スペクトラム症|MSDマニュアル プロフェッショナル版


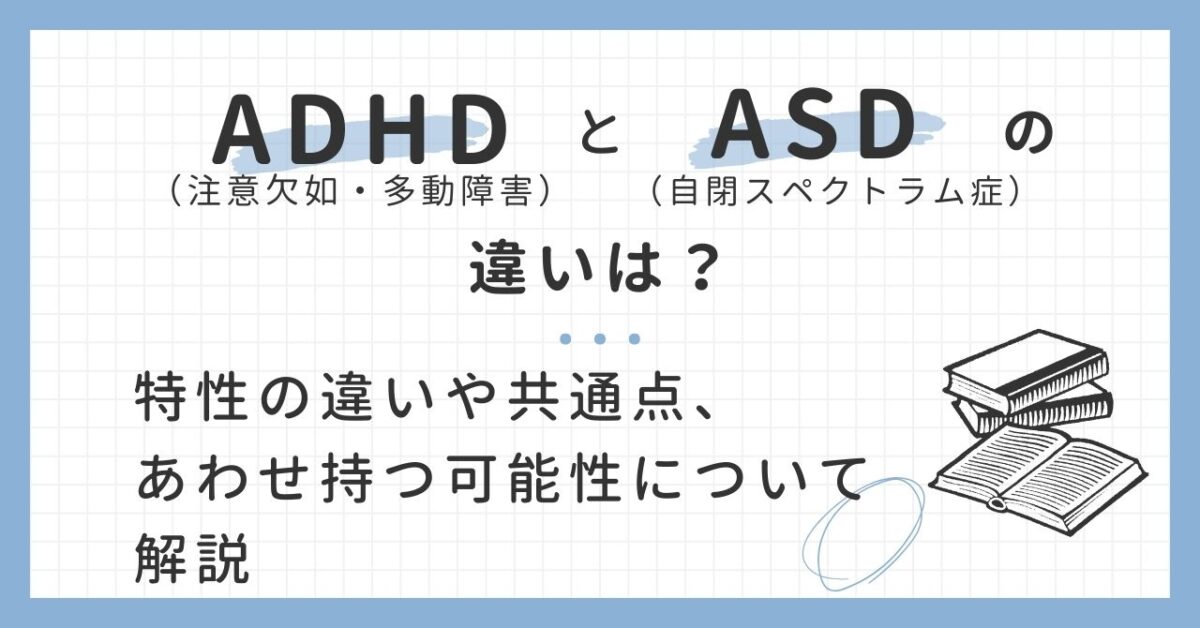

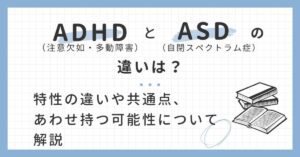


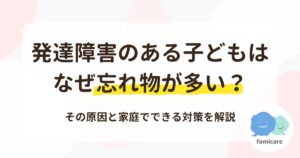

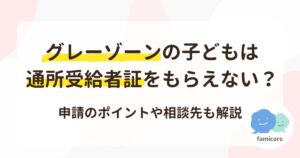
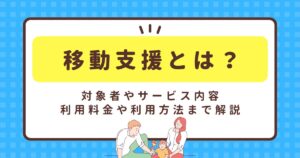
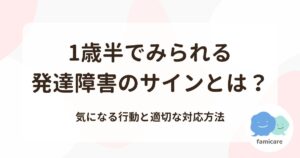
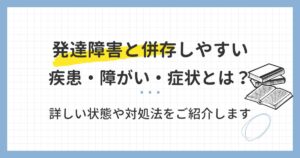
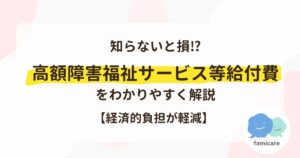
コメント