「小児がん」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?
がんと聞いて多くの人がイメージするのは、大人のがんではないでしょうか。もしかしたら、生活習慣病というイメージも強いかもしれません。
でも、小児がんは種類や発症理由、治療法や課題など、大人のがんとは異なる点が多いのです。
そこでファミケアでは、2月15日の国際小児がんデーに合わせ、実際に小児がんで闘病した子どもの親御さんへのインタビューを交えながら、小児がんの課題や実情についてお伝えしたいと思います。
子どもなら誰でも発症する可能性のある小児がんは、決して他人事ではありません。まずはこの記事を読むことで、実情を知ることから始めてもらえたら嬉しいです。
国際小児がんデーとは
国際小児がんデーは、2002年に「国際小児がんの会(Childhood Cancer International)」によって提唱された、世界共同のキャンペーンです。世界各地で、小児がんについての正しい理解を促し、支援に繋げるための啓発活動を行っています。
この記事を監修してくれた先生
医師 おkら先生

呼吸器専門医、がん薬物療法専門医、総合内科専門医。嚥下機能評価研修会修了、医療型児童発達支援/放課後等デイサービスの嘱託医。仕事大好き、2児の母。長男がダウン症、気管切開をしている医療的ケア児。障害児を育てる環境が優しくなって欲しい。その為に自分に何か出来る事はないかと日々考えています。
X:@oke_et_al,ブログ:じょいく児。
小児がんとは?
小児がんは、子ども(15歳未満)がかかるがんのことです。日本では年間2,000〜2,500人が診断されています。2023年現在、約8割が治癒すると言われていますが、いまだに子どもの死因では常に上位を占めています。
大人のがんの中には生活習慣が原因となるケースも多いですが、小児がんは成長に伴う細胞分裂の際に遺伝子変異で起きることも多いため、どんなに気をつけていても発症を避けられません。つまり、子どもなら誰でも小児がんになる可能性があるということです。
小児がんの課題
小児がんには大人のがんとは違う課題があります。
治療後の後遺症(晩期合併症)
抗がん剤や放射線治療など、治療の副作用によって後遺症(晩期合併症)が残るケースもあります。患者が子どもであるだけに、その先の人生も長く、学校生活や進学、就職、結婚など、さまざまなライフイベントに影響してしまう問題です。
長期療養による社会生活の制限や経済的負担
小児がんの治療は、数ヶ月にわたる通院や入院を必要とします。そのため、子どもの遊びや学習の機会が制限されるだけでなく、付き添う家族にも負担がかかります。長期入院による付き添い入院で親も仕事ができなくなったり、通院・入院のための交通費が多くかかったりするなどの経済的負担も見過ごせない課題です。
希少疾患ゆえに課題として認識されにくい
がん全体の年間罹患数は100万人程度で、そのうち小児がんは2,000〜2,500人ほど。がん全体で見ると0.25%ほどであり、大人のがんに比べると発生率が低い希少疾患であることから、海外では治療効果が認められ承認されている薬が日本国内での薬事承認を得るまでに長い年月を要するという「ドラッグラグ」など課題があっても世間に認識されにくい現状となっています。
小児がん患者の家族に必要だった支援とは?当事者にインタビュー
ファミケアでは、このように、なかなか認識が進まない小児がんをより深く知るため、実際に小児がんの闘病経験のあるご家族にインタビューしました。今回お話を聞いたのは、闘病の末、天国に旅立った子どもがいる千葉友里さん。闘病中に困ったことや、必要だった支援について聞きました。
お子さんの簡単な情報
- 名前:千葉雄太(ちば ゆうだい)くん
- 2021年4月 小学校に上がって2週間ほどした頃、異変を訴える
- 2021年5月 「小児脳幹部グリオーマ(DIPG)」と診断(7歳)
- 2022年7月 1年余りの闘病の末、天国へ(8歳)

小児脳幹部グリオーマ(DIPG)とは
ーーお子さんが患っていた「小児脳幹部グリオーマ(DIPG)」とはどんな病気ですか?
小児脳幹部グリオーマ(DIPG)は、小児がんの一種で、脳にできるがんです。悪性腫瘍が脳の中枢に発生するため、摘出手術ができないことがほとんどであり、今のところ効果的な治療法が見つかっていません。判明とともに余命1年を宣告される、小児がんの中でも特に悪性度の高い残酷な病気です。
一番欲しかったのは繋がりと自分の支援
ーー診断と同時に余命1年…想像もつかないほどつらかったと思います…実際闘病中に大変だったのはどんなことでしたか?
大変だったことはたくさんあります。長期で付き添い入院をしなければならなくて、仕事が続けられなかったこととか、うちはきょうだいがいるので、きょうだいにさみしい思いをさせてしまったこととか…退院して、学校に復学しようとした時の学校との話し合いも思うように進まず、大変でした。
でも一番大変だったのは、「情報」と「人と繋がれる場」がなかったことです。
小児脳幹部グリオーマは、小児がんの中でも珍しい病気で、情報が全然なかったんです。患者の数も少ないので、同じ病気の人とも出会えなくて…。すごく孤独でした。子どもを支えるために自分だけは潰れないようにしないと、と意識していたのですが、その自分を支えてくれる人の存在を、いつも求めていました。
インターネット上で同じ病気の親の会との繋がりを持てたり、SNSで同じ病気のママや病気を理解してくれる人と繋がれたりして、それはすごくありがたかったです。でも、やっぱり住んでいる地域によって支援や制度が違うので、同じ地域に住む人との繋がりというのが私は欲しかったですね。
子どもが亡くなって2ヶ月で団体を立ち上げ
ーーなるほど、お子さんが亡くなって2ヶ月で小児がんの支援団体を立ち上げたと聞きましたが、それはご自身が繋がりを求めていたから、ということなのでしょうか?
そうです。たった2ヶ月で、と驚かれることも多いですが、それは1日の大切さを理解していたからです。
私は余命1年と宣告された雄太と過ごす中で、1日1日がどんなに貴重か、ということが本当に身に染みてわかりました。闘病中もずっとその意識があって、その時その時のベストを尽くして過ごしてきたと思っています。
雄太が教えてくれた「1日の貴重さ」が胸にあったから、少しでも早く動きたいと思い、小児がんの支援団体を立ち上げられたんです。私が欲しかったものを形にすることで、私のように苦しい想いをする人がいなくなるようにしたいと思いました。それに、ただ悲しんで過ごすのは、雄太の好きなママじゃないと思って。
小児がん支援団体「ひまわりスマイルプロジェクト」の活動
ーー支援団体ではどのような活動をされているんですか?
私が立ち上げた支援団体「ひまわりスマイルプロジェクト」の今の活動は、大きく二つです。一つは、小児がんの啓発活動、もう一つは小児がん患者と家族の支援活動です。
小児がんの啓発活動は、主に「レモネードスタンド」の定期的な開催です。全国的に小児がん支援として行われているレモネードスタンドを、宮城でも始めました。具体的には、ペットボトルのレモネードを売って、売上の一部を寄付したり、活動資金にあてたりしています。

そして今力を入れているのが小児がん患者と家族の支援活動です。最近で言うと、子ども向けの「お仕事体験」を実施しました。地元の企業に協力してもらい、パン屋さんや理容室で子どもたちにお仕事の体験をしてもらうイベントです。
小児がんや子どもの病気には、家族全体で向き合わないといけません。きょうだいももちろんその一人。家族がどうしても闘病中の子どもにかかりきりになってしまったり、外出しづらくなってしまったりと、経験の機会が失われてしまう子もいます。
そんな子どもたちに色んな経験をしてもらいたいなと思って始めた活動です。


また、今は親御さんへの付き添い入院支援ということで「長期入院の付き添い応援パック」を準備中です。私自身、付き添い入院中に支援団体から付き添い入院支援パックをもらった時にとてもありがたかったので、付き添い入院中の親御さんに「応援している人がいるよ」というメッセージも込めて送りたいと思っています。
希少がんの場合なかなか話せる人がいない。孤独にならないような声かけを。
ーーきょうだいへの支援や、付き添い入院の支援、そして人との繋がり。ご自身がお子さんの闘病中に欲しいと思ったものをしっかり形にされているんですね。最後に、千葉さんの経験から、子どもが小児がんになった時、周りからのこんなサポートがあると嬉しいなと思うことはありますか?
色んな人がいるので、一概には言えませんが…私は「困った時は相談してね」とか、支えになれるよ、という声かけをしてくれると嬉しいかなと思います。
先ほども言いましたが、情報も、人との繋がりもなくて私は苦しかったので、頼れる人や支えてくれる人が欲しいと思いました。闘病中は、本当にさまざまな困りごとが起こります。家族だけで乗り越えるのは時には難しいこともあります。
私も、ママ友に助けてもらったことがあります。きょうだいをお友達と一緒に遊びに連れて行ってくれたり、とても心強かったです。特別なことじゃなくても、一緒に遊んでくれるとか、手作りのおかずをお裾分けしてくれるとか、そうやって日常的にできる範囲で支援してくれたらとてもありがたいですね。もし余計なお世話かも?と心配になるようであれば、「こういうことならできるから言ってね」とさりげなく声をかけてもらえるといいんじゃないかなと思います。
「小児がん=かわいそう」で終わるのではなく、知ることから支援を
小児がんのことやその課題を知っている人は、まだ多くありません。希少疾患とはいえ、今も苦しんでいる子どもや家族が確実に存在する病気です。だからこそ、「子どもががんになるなんてかわいそう」という感情だけで終わるのではなく、もっと深く知って、自分にできる必要な支援を行っていけるといいのではないかと筆者は感じました。
レモネードスタンドが近くで開催されていたら行ってみる、小児がんの支援団体を調べてできる範囲で寄付してみる、など、小さくてもできることは必ずあります。子どもなら誰にでも発症する可能性がある小児がん。だからこそ、社会全体の問題として認識していく必要があるのではないでしょうか。
「ひまわりスマイルプロジェクト」の詳細はこちら
X:@himawarismile_p
Instagram:@himawarismile_p


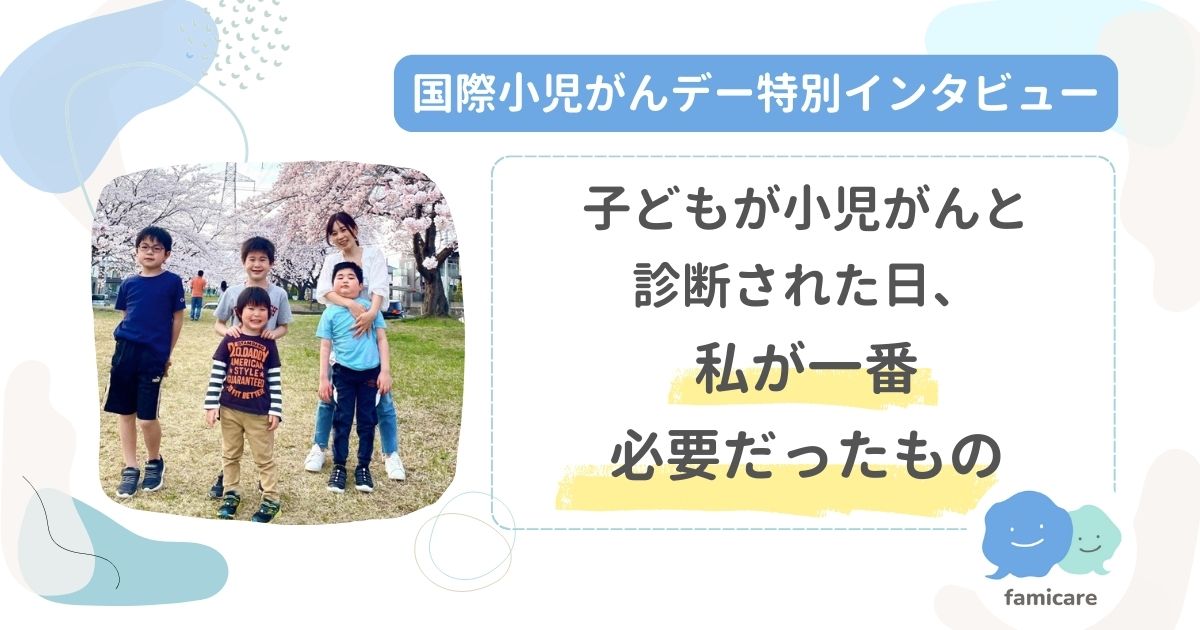




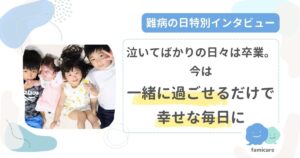

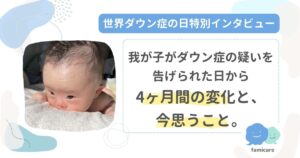
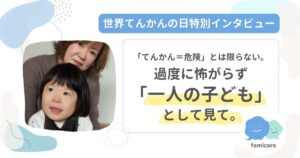
コメント