「相談支援専門員」という職業があるのを知っていますか?障がい児育児をしている方は、一度は耳にしたことがあるかもしれません。
 ライター小澤
ライター小澤筆者は児童発達支援センターで知り合った先輩ママに聞いて初めて知りました!
でも、言葉だけは聞いたことがあっても実際どんなことをする人なのか、何が相談できるのか、どんな時に頼れるのか、よく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
かく言う筆者も、2年ほど相談支援専門員にお世話になっていますが、「何をする人なのか?」「どこまでお願いしていいのか?」はっきりわかるまで時間がかかりました。
そこで今回は、相談支援専門員の仕事と期待される役割(お願いすると何が叶うのか)について解説します。
\この記事を監修してくれた先生/
相談支援専門員・看護師 井上悠貴(いのうえゆき)先生


岡山県立倉敷中央高等学校専攻科を卒業。看護師免許を取得し、小児科病棟や保育園に勤務する。現在2児の母であるが、上の息子が3歳の時に発達障害と診断される。その中で相談支援専門員の方にお世話になり、その経験から自身も相談支援専門員の資格を取得。現在相談支援事業所うえまつで相談支援専門員として活動中。
Instagram:@fukushinail_mikan
相談支援専門員とは?
相談支援専門員は、障がい児・者に寄り添って相談を受け、個人の自立や社会参加等の生活を支援してくれる専門職です。個別計画の作成や福祉サービスの利用までのサポートなどを「相談支援」によって支援してくれます。略称では、相談員と呼ばれることもあります。
相談支援専門員になるには一定の実務経験と相談支援従事者初任者研修の修了が必要ですが、特に必須の資格などはありません。
2020年6月に日本相談支援専門員協会によって定められた「相談支援専門員の行動指針」では、相談支援専門員について、次のように定義しています。
私たち相談支援専門員は、障害児・者等(以下、利用者※とする)が自ら望む自立した地域生活の実現に向けて、本人の意思、人格ならびに最善の利益を尊重し、常に本人の立場に立ち、個別生活支援と地域づくりを両輪とした相談支援を実践するソーシャルワーク専門職です。
引用元:相談支援専門員の行動指針|日本相談支援専門員協会
URL:https://nsk2009.org/?page_id=458#index_id0
つまり、障がい児者本人が「こうしたい」と思うことを実現するために福祉資源や地域の力を借りてサポートしていくのが相談支援専門員なんだね。
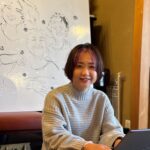
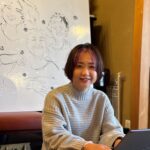
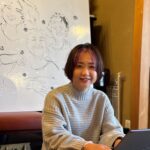
そうですね。地域によっては、相談支援専門員がつかないと福祉サービスを利用できないこともあるほど、障がい児者の生活に密着した仕事なんですよ。
相談支援とは
相談支援は、相談支援専門員が障がい児・者に提供するサービスです。相談支援専門員が行っている仕事を「相談支援事業」ともいいます。相談支援専門員は、「相談支援」を通じて障がい児・者の生活において「こうしたい」状態を実現していきます。
具体的には、障がい児・者の状況や生活の希望、悩みなどをヒアリングし、その方の目的に合わせた障害福祉サービスの提案や福祉サービスを利用する場合の計画作成、利用までのサポートまでを支援として行います。
障がい者向けのサービスは、障害者総合支援法第5条第18項で規定された「基本相談支援」「地域相談支援」「計画相談支援」の3つあります。障がい児向けのサービスは、児童福祉法6条2−2で定められた「障害児相談支援」で、合計4つが制度として認められた「相談支援」です。
障がい児の相談を受けてくれる相談支援は「障害児相談支援」で、元になっている法律が違うから行うサポートも少し変わるんだね。
障がい児向け相談支援専門員の仕事や役割は?
障がい児向け相談支援専門員の仕事は「相談支援」ですが、さらに細かい分類では「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」の2つを担っています。
障害児支援利用援助とは
障害児支援利用援助では、障害福祉サービス等の支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を作成します。また、 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、サービス等利用計画・障害児支援計画の作成も担います。
継続障害児支援利用援助とは
継続障害児支援利用援助では、利用者本人等の心身の状況、置かれている環境、援助の方針や解決すべき課題、目標や達成時期等並びに厚生労働省令で定める期間を勘案して市町村が決定した期間毎に、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行います(モニタリング)。 サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨なども役割の範囲です。
障がい児向け相談支援専門員が実際にしてくれること
専門用語が多くて難しいな…実際何をしてくれるの?



簡単にいうと3つのプロセスで生活を支援してくれるよ。
1.アセスメント:利用者の状況把握
まず、利用者の現在の情報収集をしたり、利用者が何を実現したいのかを把握します。
これは、今の状況と障がい児本人や家族が求めることとの差を把握し、希望する暮らしを実現するためにはどんなことが必要なのか、考えるために重要なプロセスです。
2.プランニング:計画案の作成
その上で、求めることを実現するにはどんな支援やサービスを利用するのが望ましいか検討し、利用者に提案して、利用計画を作ります。
3.モニタリング:計画を実行してみてどうだったかを検証
利用計画を立案、実行してみて一定の期間(一般的には3ヶ月または6ヶ月程度)が過ぎたら、この期間を振り返り、改めてアセスメントを行い計画やサービスの調整をします。これをモニタリングといいます。
利用者と家族の環境や希望は常に変化していきますので、相談支援専門員は、定期的にモニタリングをすることで、その変化を把握し続けていかなければなりません。
▼相談支援事業所を利用するにはどうしたらいい?という方はこちらの記事がおすすめ
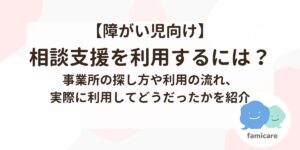
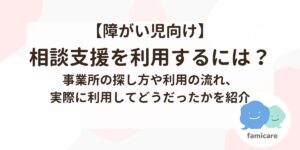
障がい児向け相談支援専門員が必要に応じて行うこと
1.サービス事業者等との連絡調整
プランニングで計画を立てたら、相談支援専門員はその計画の実現のために利用するサービス事業者に連絡を行い、利用開始できるよう調整をします。たとえば、施設の見学や、契約のための日時調整などです。
ただし、保護者が連絡調整を行う場合もあり、実際は担当の相談支援専門員によって、これをしてくれる人、してくれない人がいるというのが現状のようです。
2.サービス担当者会議の開催
サービス利用開始前、もしくはサービス利用期間中に、「サービス担当者会議」を開催する場合もあります。
サービス担当者会議とは、相談支援専門員が各サービス事業所や担当者に呼びかけ、オンラインで、もしくは直接、顔を合わせて利用者とその家族の現状と課題を共有し、今後の支援方針を確認していくものです。
この会議の結果を次の支援計画に反映させたり、事業所の繋がりを作ることにより一人の利用者に対し包括的に支援していくことを目指します。
サービス担当者会議は、必ずしもモニタリングの度に行われるわけではありません。目標が変わったり、新たにサービスの利用が始まったりする時など、本人やご家族にとって節目となるタイミングに行われることが多いようです。
このように、相談支援専門員の仕事は計画を立てて終わり、ではありません。本人や家族のことを把握し、計画を立て、実行し、モニタリングし、また状況の把握をする、というふうに、サービスを利用する限り継続していき、利用者と家族の暮らしの経過に関わり続けていくのが相談支援専門員の仕事です。
相談支援専門員に相談できること
目標や希望に関してどんな福祉サービスが受けられるか、使用するとしたらどんなスケジュールで利用するか、という計画を立案し、実行した後にモニタリングを行い、利用サービスの調整をする、というのが相談支援専門員の役割です。
ですので相談できることとしては、この支援計画に関すること、となります。
たとえば以下のような場合です。
- 今使っている児童発達支援の利用日数を変えたい(多くしたい/少なくしたい)
- 通所(通園)している事業所(保育園・幼稚園)での困りごとを解決したい
- 新しくヘルパー事業所を利用したい
- 通所先を探している
今利用しているサービスの変更・解約についての相談はもちろん、新規に利用したいサービスの相談も可能です。
また、具体的には解決策がわからない困りごとについても相談することができます。
たとえば、このような相談です。
- 腰が痛くて子どもの入浴介助が困難になっている
- 子どもの預け先がなくて困っている
- 子どものケアで睡眠不足が続いている
相談したからといって必ずしも何かしらの支援が提案されるわけではありません。ただ、地域の支援について相談支援専門員はよく知っています。自分では思いつかない解決策を提案してくれる可能性もあります。
困った時には相談できる人、と言えそうだね
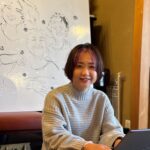
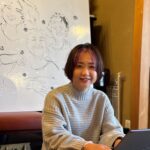
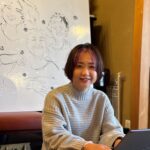
そうですね!基本的には困ったことがあればとりあえず相談してくださいというスタンスで私は仕事をしています。地域によっても相談支援専門員ができることが違ったりする(たとえば受給者証の更新手続きにかかる書類の提出を代理でできることもある)ため、まずは一度相談してみるといいと思います。
一方、支援計画以外のことについては相談してもわからないケースもあります。たとえば、障がい児家庭がもらえる手当や補助金、医療的なことまでのアドバイスはできないことも多いので、相談支援専門員がいるから支援については全部お任せ、というわけにはいかないということに注意が必要です。
相談支援専門員は本人と家族の「叶えたい生き方」をサポートする役割
相談支援専門員が担うのは、本人と家族の希望をしっかり聞き、必要な支援計画を立て、叶えたい生き方をサポートする役割です。
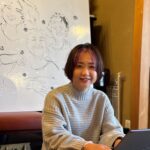
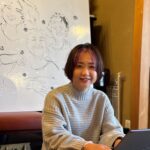
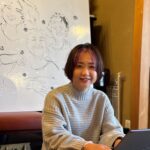
障がい児やご家族の役に立ちたいという想いで仕事をされてる方が多いので、困ったことがあったら何でも相談してください!


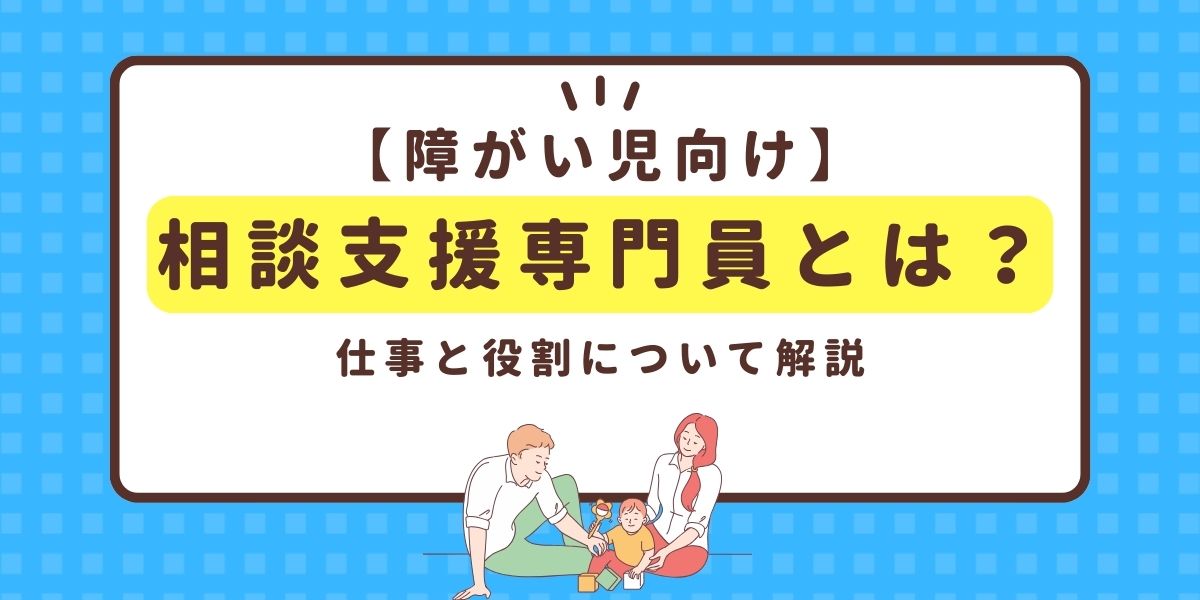

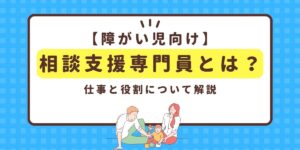

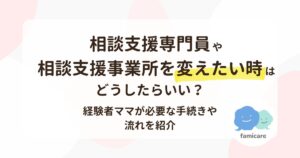
コメント