身の回りを見ると、眼鏡をかけている大人って結構たくさんいますよね。筆者もその1人です。
一方、小学校入学前くらいの子どもでも眼鏡をかけている子もたまに見かけますよね。そのような子の中には、単なる近視などの矯正ではなく、視力の発達を助けるための「治療用眼鏡」をかけている子もいます。
今回は、子どもの治療用眼鏡とはどんなものか、どのように作るのか、実際に娘の治療用眼鏡を作った筆者が紹介します。
小児治療用眼鏡(等)とは?
小児治療用眼鏡とは、弱視や斜視、先天性白内障の手術後の治療のための眼鏡やコンタクトレンズのことです。大人用と同じ眼鏡ですが、近視などの矯正のために大人がかける眼鏡とは目的が少し異なります。
小児治療用眼鏡の場合、視力が発達する時期にものをしっかりと見えるようにすることで、視力や脳の発達を促してくれます。
また、作成時はその子の特徴によって、フレームやレンズなどを医師から指定されることもあります。
治療用眼鏡作成のきっかけと娘の状況
娘の状況
- 年齢:1歳1ヶ月
- 診断名:福山型先天性筋ジストロフィー
- 医療的ケアなし
小児治療用眼鏡を作成することになったきっかけは、定期受診で弱視だとわかったことでした。
もともと主疾患の福山型筋ジストロフィーと診断されるきっかけが哺乳時の眼振(眼球が左右に激しく振動すること)だったため、眼科を定期的に受診していました。
そして眼振以外にも、気がついたら寄り目になっていることが多く、主疾患の筋ジストロフィーに加えて目にもなにかしら異常があるのではないかと心配していました。
1歳を過ぎてからの検査で、視力が1歳児の平均よりも弱く、10数cmより遠くのピントが合わずぼやけて見えるほどの強い弱視であることが判明。視力が弱いと外界からの刺激が少なくなり、視力そのものの発達に加えて、認知機能など脳の発達にも影響するため、治療用の眼鏡を製作することになりました。
 ライターこうすけ
ライターこうすけ今までパパの顔がぼやけて見えていたかと思うと少しショックでしたが、ちゃんと見えているのか心配になることも多かったので、弱視だと診断がついて治療できるようになったのは良かったです。眼鏡のパパとお揃いになるのもちょっと嬉しかったです。
小児治療用眼鏡を作成する流れ
子どもの治療用眼鏡が必要かも、となった際の流れを実際の筆者と娘の経験をもとに紹介します。
1.医師の診断を受け処方箋と作成指示書を受け取る
治療用眼鏡を作成していく方向性になったら、まずは眼科で視力検査を受け、眼鏡の処方箋と作成指示書を受け取ります。処方箋には作成するレンズの度数などが書かれています。
眼鏡の処方箋や作成指示書に関しては、定期受診と別途文書料が請求されることはありませんでした。



この時に矯正してどのくらいの視力になっているかを次回の診察で測定するので、早めに眼鏡を作ってほしいと言われました。
2.眼鏡店で眼鏡選び!
医師からの処方箋と作成指示書を持って、子ども用眼鏡を扱っている眼鏡店に行きます。
眼鏡店の選び方に関しては、病院からも眼鏡店の紹介がありましたが、同じ病気の子がいるご家族からおすすめのメーカーを聞いていたので、そのメーカーを取り扱っている眼鏡店に向かいました。
子ども用眼鏡店に行くのは初めてで少しドキドキしていましたが、さすが店員の方は子どもの接客にも慣れています。娘にも優しい声をかけて案内してくれました。
フレーム選び
年齢にあった大きさの眼鏡の中から好きなフレームを選びます。丸い形から四角い形まで、色も赤、青、緑、ピンク、オレンジ…など思ったよりもたくさんの選択肢がありました。
娘よりも小さな子ども用になるとバリエーションは減ってしまうようですが、医師からのフレームの指定などがなければ、かなりの選択肢があると思います。



いろんな形と色のフレームを娘の顔にかけて、似合うものを探すのは楽しかったです!
娘は座位がしっかり取れず、まだベビーラックなどで過ごすことも多いため、顔が痛くならないようにと、フレームがとても柔らかくぐにゃぐにゃ曲がるものを選びました。
フレームが柔らかいと、そのままではしっかりと固定してかけられないので、頭の後ろにバンドを通して固定します。お気に入りのフレームが決まったら、店員の方にお顔をみてもらい、フレームのサイズを決めます。
初めて眼鏡をかけるときは泣いてしまう子どもも多いとのことでしたが、娘は嫌がるそぶりを全く見せず、サイズ決めの時も良い子でいてくれて助かりました。
レンズの選択
次に、レンズの種類を選択します。大人と同じように球面レンズ(値段安め、視界の端が歪んで見えやすい)や非球面レンズ(値段高め、視界の端まで歪まずに見える)などを選択できました。
大人用のレンズと同じで、基本的に値段が高いものほど薄く、軽く、歪みが少なく見えます。娘はまだ小さいので、レンズはできるだけ軽い方がいいと考え、ちょっと奮発して(?)非球面レンズにすることにしました。
また、追加料金ですがブルーライトカットや曇り止めつきのレンズもありました。もうこの辺りは大人の眼鏡選びとほとんど変わりませんね。
レンズ選びで値段の話が出てきたので、ここで補助制度の説明もしていただきました。申請方法など不明点があれば、店員の方に相談すると教えてくれます。
フレームの在庫やレンズの種類によりますが、娘の場合は10日程度で完成するとのことでした。



思っていたより早くできてびっくり!
3. 作成した眼鏡をいよいよ受け取り!
眼鏡の作成完了予定日になったら、いよいよ待ちに待った眼鏡の受け取りです。できあがった眼鏡をかけて、耳にきちんとかかるようにテンプル(つる)の長さを調整してもらって完成です!



一度試着をしていますが、改めて見ると眼鏡をかけた娘もかわいい!店員さんにも「よく似合うね」と言っていただきご機嫌のようでした。
最後に、保証サービスの説明などを受け、お支払いをしておしまいです。
小児治療用眼鏡等の購入費用と補助制度
小児(9歳未満)の治療用眼鏡には健康保険と公費による補助制度があります。購入時には代金の全額を支払う必要がありますが、これらの制度を利用すると上限金額の範囲内で償還払いを受けられ、負担を大きく減らすことができます。
健康保険による補助
購入金額の7割または8割(小学校就学前まで)が健康保険から支給されます。
保険適用の条件
- 9歳未満であること
- 弱視等の治療用であること(医師の処方箋や作成指示書が必要)
参照:小児弱視治療用眼鏡等の療養費支給について|公益財団法人日本眼科学会
URL:https://www.nichigan.or.jp/member/journal/syaho/ryoyohi.html
加入している健康保険によって申請方法などが異なる場合がありますので、詳しくは加入している健康保険組合などに相談してみてください。
健康保険による補助を受けるためには処方箋や作成指示書の原本が必要になる場合がありますので、後述の公費による補助も受けるために、必ずコピーを取っておきましょう!
公費による補助
健康保険で助成される分を引いた残りの3割または2割(小学校就学前まで)は、市区町村の医療費助成制度により補助されます。
お住まいの地域により、所得制限や対象年齢の制限などがある場合がありますので、詳しくは各市区町村の担当窓口に相談してみてください。
注意点として、これらの補助制度には上限金額があり、健康保険による補助と公費による補助の総額は決められた上限金額までとなります。現在の上限金額は38,902円(コンタクトレンズの場合は1枚16,139円)です。
例えば、38,902円以下の治療用眼鏡の場合は全額を補助で賄うことができますが、これ以上の治療用眼鏡については、38,902円を超えた分は自己負担となります。



娘の場合、約43,000円の治療用眼鏡を自己負担約4,000円で作成することができました!
小児治療用眼鏡の保証サービスもある
今回購入した眼鏡店では、保証期間内なら無料でレンズの度数変更などができるサービスがついていました。受診して眼科医の処方箋を改めて発行してもらう必要がありますが、視力の成長に伴って度数変更をする可能性はあると思うので、とても助かります!
他にも、破損時の修理交換が無料だったり、紛失時の再購入割引があったりと、盛りだくさんの保証がついていました。子どもの場合、大人と違って遊んでいて壊したりする危険性が高いので、このような保証サービスはありがたいですね。
大人用の眼鏡と比べると眼鏡自体の購入代金は高めですが、これだけ手厚い保証がついているなら納得ですね。眼鏡店によっては、このような保証はオプション料金になっているところもあるようです。
小児治療用眼鏡での日常生活
理想としては日中はずっと眼鏡をかけて、はっきりと物が見えるようにして過ごすことを目指します。
まずは眼鏡をかけるという状態に少しずつ慣れてもらうため、眼鏡デビューしてから1週間程度は、慣れるために朝夕のご飯の時だけかけるようにしました。



嫌がってすぐ外してしまうかな?と思っていたのですが、何事にも動じない性格の娘は、泣くこともなく意外とすんなりと受け入れてくれてすごく助かりました!
しかし、ご飯中は食事に集中してくれますが、ご飯が終わると手持ち無沙汰になるのか、毎回のようにフレームを掴んで眼鏡を口に持っていってむしゃむしゃしてしまいます。
それでも、嫌がって外そうとしているわけではないようなので、「眼鏡は食べないよ〜」と毎日諭しています。
眼鏡での登園
眼鏡をかけはじめて1週間経ったところで、いよいよ保育園にも眼鏡で登園してみました!
保育園には、眼鏡をかけるので保育園でもつけ外しをしてもらえないかを事前に相談し、快諾していただいていました。
初めての眼鏡登園の際には、次のようなことを保育士さんにお伝えしました。
- 眼鏡のつけ外しの仕方(バンドタイプだったためその説明)
- 眼鏡を舐めたりしてしまった際のお手入れ方法(素材によっては、アルコール入りの布巾でふくとフレームが割れてしまうそうです)
- 機嫌が悪くなってしまったら、無理にかけさせずに過ごさせてほしいこと
ちなみに、保育園に持っていく眼鏡ケースを買っていないことに、眼鏡店から帰ってきてから気づきました!
慌ててネット通販で購入しましたが、配達されたのが初めての眼鏡登園より後になってしまったのは反省です…!
保育士さんによると、眼鏡をかけていると、かける前に比べて反応がよくなったとのことでした!刺激が増えているようでとても安心しました。
自宅での生活には慣れすぎてしまっているのか、家での反応は思ったほど変わらなかったので、保育園でも眼鏡で過ごせて良かったです。
ちょっと後悔したこと
弱視の診断から眼鏡デビューまで、想像していたよりもスムーズに事が運びましたが、「もっとこうすればよかったかな…」と思うこともありました。
焦って情報収集を疎かにしてしまった
娘が弱視であると診断が下りたその瞬間から、「早く眼鏡を作ってあげなきゃ!」という思いが突っ走り、翌々日には眼鏡店で注文を済ませました。
早く眼鏡が手に入ったのは良かったですが、「肢体不自由の娘には本当にこのタイプの眼鏡で良かったのかな?」と気になる時がありました。
娘と同じ病気で治療用眼鏡をかけている子とお話しした際も、おすすめのメーカーさんは聞いていましたが、どういうフレームがいいのかなど、細かい話は全然聞けていませんでした。
当時は、娘が眼鏡をかけるのはもっとずっと先の話だと思っており、細かいことは突っ込んで聞かなかったのだと思います。
焦るのも仕方なかったと思いますが、簡単に作り直せる物では無いので、一旦落ち着いて眼鏡を使っている子どもを育てているご家族に相談しておけば良かったかなとも思います。眼鏡店に出す処方箋の有効期限は30日間なので、今思えば、話を聞いて考える時間は十分ありました。
小児治療用眼鏡は子どもの心身の成長の助け
まだ小さいうちから眼鏡をかけさせることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、なるべく早いうちから視力を矯正することで、心身の成長の助けになります。
それに、眼鏡をかけた子どもの少し凛々しい顔も可愛いものです。(笑)治療用眼鏡が必要になったら、ぜひ参考にしてみてください。


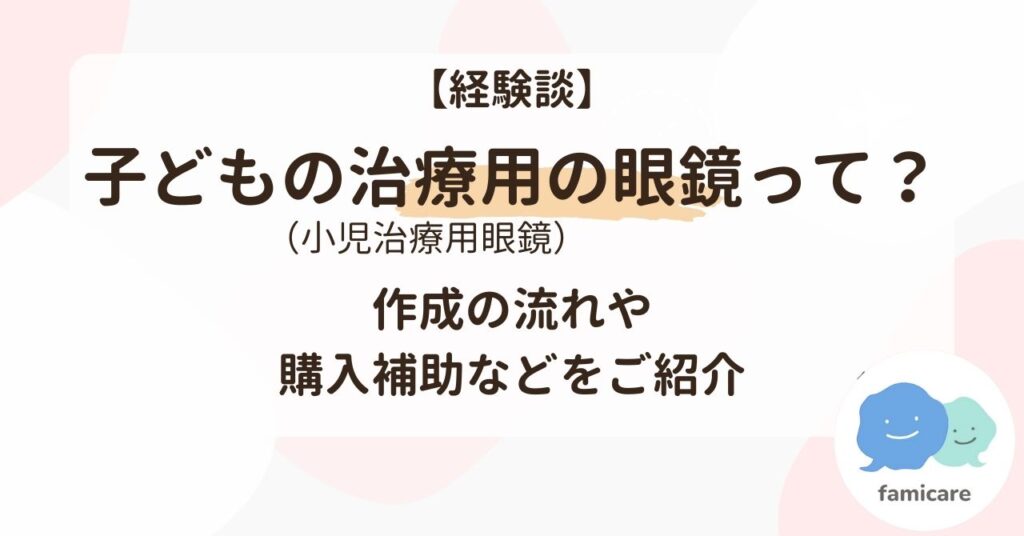

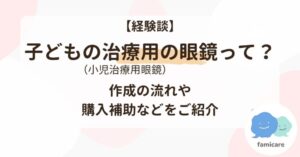

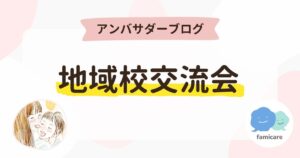
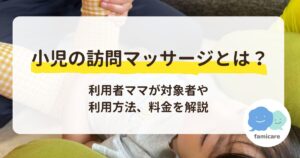
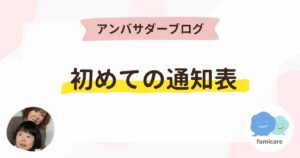
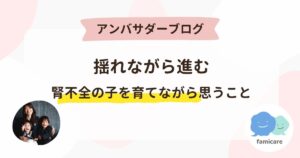
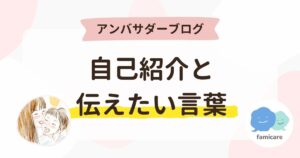
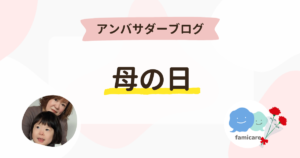
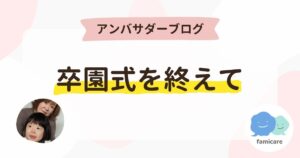
SUSUGU特集_牛乳石鹸共進社-300x158.jpg)
コメント