障がいや疾患、特性による困りごとがある人も、ない人と同じように社会生活を送れるようにするために2016年から日本に普及した「合理的配慮」という考え方。これまでは学校などの行政機関でのみ義務とされていましたが、2024年4月からは塾や習い事などの事業者でも義務化されます。
この記事では合理的配慮についての基本的な考え方と、学校における合理的配慮の具体例、さらに2024年4月から義務化される事業者による合理的配慮について、事例とともにわかりやすく解説します。
合理的配慮とは?
合理的配慮とは、障がいにより困りごとを抱える人に対し、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの特性や困りごとに合わせて負担が重すぎない範囲で対応に努めることです。
合理的配慮は2016年4月に「障害者差別解消法」が施行されたことで、行政機関(公立園・学校を含む)による提供が義務化されました。あわせて、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いの禁止や、事業者による合理的配慮の提供も努力義務とする内容が盛り込まれました。
障害者差別解消法を策定するきっかけともなった、2006年に国連で採択された「障害者権利条約」の第2条では、合理的配慮は以下のように定義されています。
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
(出典:外務省)
また、同じ第2条「障害に基づく差別」の中には、
障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
(出典:外務省)
と記載されており、合理的配慮を否定することは「障害者差別」であることも明記されています。
「合理的配慮をできるのにやらないのは差別」とはっきり定義されているんだね!
教育現場における合理的配慮
では、実際に困りごとを抱える子どもたちは、学校などで具体的にどういった合理的配慮を受けることができるのでしょうか。
文部科学省の資料では、障がいや特性にあわせて以下のような事例が合理的配慮の具体例とされています。
(出典:障害種別の学校における「合理的配慮」の観点(案) より一部を改変して抜粋)
| 障がいや特性 | 合理的配慮の例 |
| 視覚障害 | ・座席を前にする ・教材や掲示物のコントラスト、文字サイズの配慮 |
| 聴覚障害 | ・教師の話が聞こえやすい座席配置 ・板書及び視覚的教材の活用 |
| 知的障害 | 数量や言語などの理解のための教材を活用する(フラッシュカード、文字や数カード、数え棒、パソコンなど) |
| 肢体不自由 | 自助具や補助具の使用を認める(固定されたはさみや包丁、握りやすくした筆記具、片手用の笛など) |
| 学習障害(LD) | ・板書計画を印刷して事前に配布する ・カメラ等による板書の撮影 |
| 自閉スペクトラム症・情緒障害 | 言葉による指示だけでは理解できない場合に、活動方法などが視覚的に分かるようにする |
| ADHD | ・好きなことに集中できる時間や場所の確保 ・数多くアイディアを出せる場やユニークな発想を生かせる場を学習活動の中で設ける |
| 言語障害 | 教科書の音読や音楽の合唱などを個別指導にする |
| 病弱 | 入院している子どものコミュニケーションに配慮する ・友達や担任とのつながりを持つため、手紙や学級だよりを届ける ・ビデオ通話などを通して、友達とコミュニケーションをとる |
もう少し具体的な合理的配慮の事例としては、どのようなものがあるのでしょうか?
以下は令和4年度に目黒区内の学校で実際に提供された、合理的配慮の事例です。
(出典:目黒区「令和4年度版 合理的配慮の提供事例集」 より一部を改変して抜粋)
ケース1:医療的ケアとして、たんの吸引が必要なAくん
<場面>
たんの吸引が必要なAくんは自分での吸引は難しく、支援者に様子を見てもらいながら適切なタイミングで吸引してもらう必要があります。そのためには吸引器を安全に置いておく場所や、支援者が吸引を行うための場所が必要です。
<合理的配慮の例>
扉のある個室に吸引器を安全に置くことができるよう、専用の台を用意しました。また扉のある個室で医療的ケアを行うことで、落ち着いてたんの吸引ができるようになりました。
ケース2:音が聞こえにくいBくん
<場面>
難聴があるBくんは、運動会で音楽や声援、号令などが全く聞き取れません。特に徒競走では号令ではなく周りが動いてから走り出すので、いつも出遅れてしまいます。
<合理的配慮の例>
徒競走のスタートでは、ピストルと同時に旗を振り上げる視覚に訴える合図もあわせて行いました。その結果、Bくんは旗を見てスタートを切ることができました。
ケース3:場面緘黙のあるCさん
<場面>
場面緘黙のあるCさんは、家族や仲の良い友達と二人きりなら話をすることができますが、知らない人やたくさんの人の前では全く話せなくなってしまいます。そうした中、今度の英語の授業ではクラス全員の前でのスピーチテストがあります。
<合理的配慮の例>
時間と場所を変えて、個別で英語のスピーチテストを行えるようにしました。その結果Cさんもスピーチをすることができました。
これらはあくまでも一例にすぎず、合理的配慮の内容は子ども自身の意思やニーズ、取り巻く環境によって異なるでしょう。また配慮を提供する学校側にも資源の限界があるため、負担が重すぎない・実現可能な配慮をすり合わせていくことが重要です。
家庭側と学校側で合意した合理的配慮の内容については、個別の教育支援計画などの文書に明記しておくのがおすすめです。そうすることで、何か困りごとが起こった際にお互いに確認や見直しがしやすく、次年度以降への引き継ぎもスムーズになります。
その他の合理的配慮の具体例については、内閣府「合理的配慮サーチ」で探すこともできるので参考にしてみてくださいね。
内閣府「合理的配慮サーチ」
URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/
2024年度から合理的配慮の提供が義務化


2021年に障害者差別解消法が改正されたことにより、2024年4月1日からはこれまで努力義務だった民間の事業者の合理的配慮の提供が義務に変わります。
ここでの事業者とは、以下のように定義されています。
【事業者】
● 商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。
● 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
【分野】
● 教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
(出典:内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」)
つまりこの変更により、これまで学校等でしか義務とされていなかった合理的配慮が、塾や習い事などでも受けられるようになります。
塾などで合理的配慮を受ける具体例としては、内閣府のリーフレットで以下のようなケースが挙げられています。
ケース1:聴覚過敏のあるDくん
<場面>
聴覚過敏のあるDくん。塾に通っていますが、毎回特定の時間に聞こえる飛行機の音が気になってしまい、授業に集中できません。イヤーマフを持たせても、自分では装着タイミングがなかなかわかりません。
<合理的配慮の例>
飛行機の通過時間はだいたい決まっているので、塾講師がイヤーマフ着用の声がけやお手伝いをします。イヤーマフをしたままだと聞き取りづらい音声教材を使うタイミングについても配慮を行います。
合理的配慮は受けることはわがままではなく権利
「合理的配慮を受けたい!」と思っている子どもや保護者の方の中には、
合理的配慮を受けることは、わがままなの?
と悩んでいる方もいるかもしれません。しかしこの記事でも解説した通り、すでに学校などの行政機関では合理的配慮の提供は義務化されており、2024年4月からは塾や習い事などの事業者でも現在の努力義務から義務に変わります。
もちろん合理的配慮の内容は提供側にとって「過度な負担とならないもの」とされているため、学校や塾・習い事とのすり合わせは必要不可欠ですが、決して合理的配慮=わがままではなく、子どもが自分の力を発揮しやすいようにするための工夫なのです。
目が悪い人がメガネをかけるのと同じように、合理的配慮も困りごとに対する一つのサポートです!
合理的配慮に基づいた適切な支援によって、障がいや疾患による困りごとを抱えた子どもたちも自分の力を十分に発揮し、さらにいきいきとした生活が送れる社会になることを願います。
※本記事で挙げた合理的配慮の具体例は、官公庁や地方自治体の情報に基づいたものではありますが、合理的配慮の内容はそれぞれの場面や状況に応じて異なるため、すべての行政機関・事業者が必ずしも実施するものではないことをご了承ください。
▼こちらの記事は下記サイトを参照した上で執筆しました。
・内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
・内閣府 障害者差別解消法リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html
・内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html


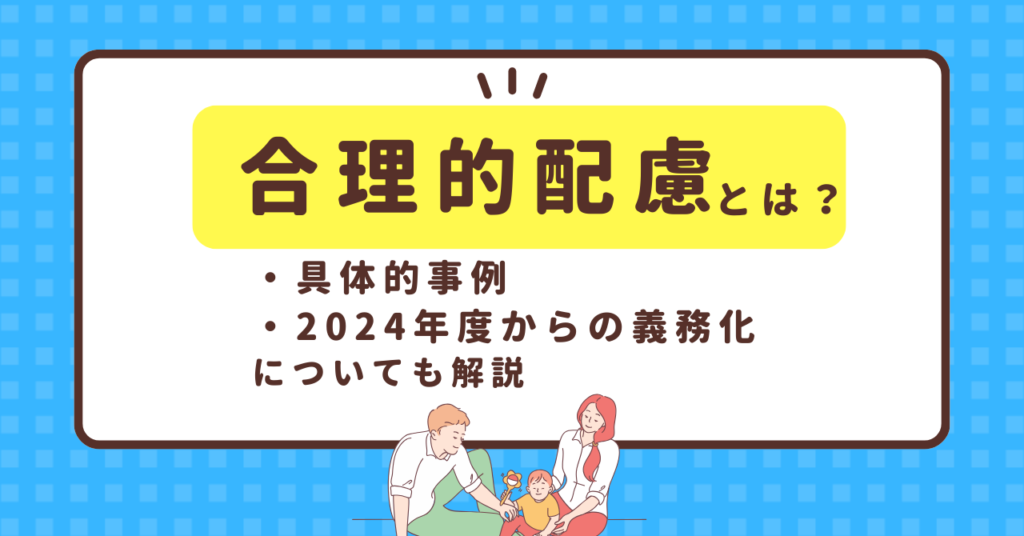

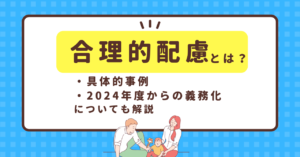

コメント