障がいのある子どもを保育園に預けたいと考えたとき、申し込む前に見学に行きましょう。実際の様子を見学すると、情報だけではわからないことが見えてきます。保育園の環境や雰囲気を見て、先生方に話を聞いて、子どもが安心して過ごせる保育園を選ぶことがとても大切です。
この記事では、保育園見学の流れから当日の確認ポイントまでを具体的にご紹介します。安心して預けられる園を見つけるためのヒントにしてください。
まずは障がい児の受け入れ可能な保育園を探す
障がいのある子どもを保育園に預けたいと思ったとき、まずは受け入れ可能な保育園を探す必要があります。
障がい児の受け入れ可能な保育園の情報については、まずお住まいの市区町村の保育園を担当する課に相談してみましょう。その他、支援者や支援施設、同じ地域に住んでいる親やコミュニティから情報を得られる場合もあるかもしれません。
▼具体的な情報収集の方法については過去の記事をご覧ください。
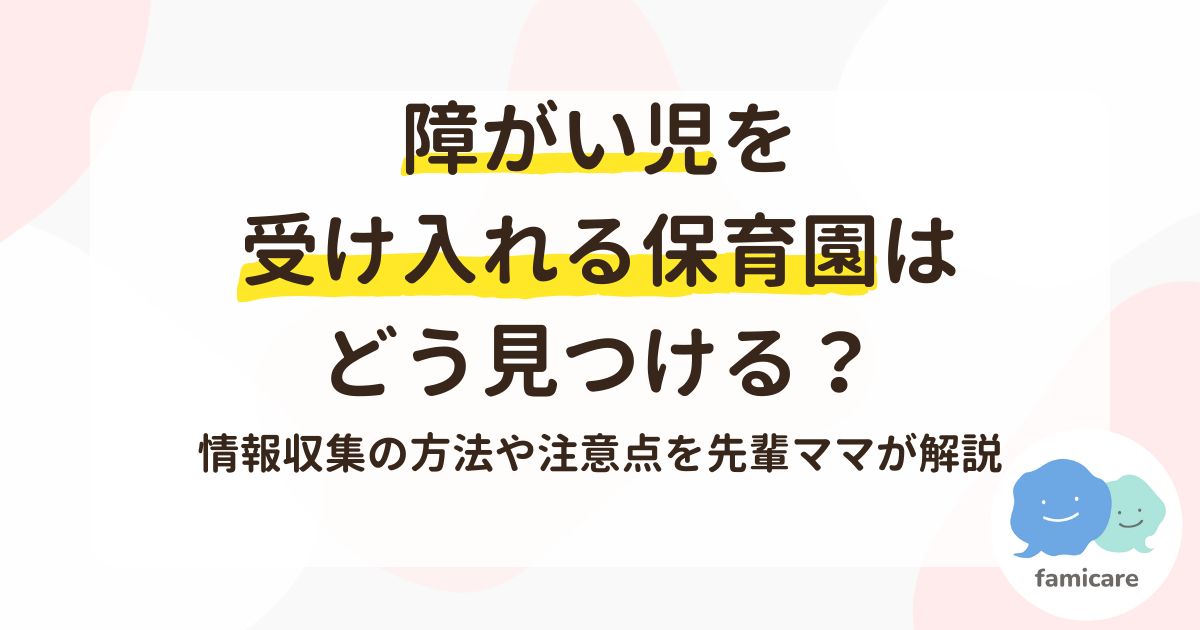
気になる保育園が見つかったら、障がい児の受け入れ意向について確認しましょう。受け入れる意向を確認できたら、保育園の見学を予約をします。
 ライターKeiko
ライターKeiko希望の保育園にはぜひ見学に行きましょう。話を聞くだけではわからないことが見えてきます。比較することでわかることもあるので、できれば複数の園を見学するのがおすすめです。筆者も複数の園を見学しました。数カ所行くだけでも違いを感じました。
情報収集をしたら、保育園見学の前に準備しておくと良いこと
保育園の見学は、限られた時間の中で園の雰囲気や対応をしっかり見極める大切な機会です。よりスムーズで充実した見学にするためにいくつかの事前準備をしておくと安心です。
まずは、自分の子どもの特性や必要な配慮を整理しておきましょう。一言で「障がい」といっても、人それぞれ多種多様です。運動機能や発語の有無、医療的ケアの有無、その他の特性や健康上の注意点など、共有できるようにしておくとスムーズです。具体的にどの程度、どんなサポートが必要なのかを簡単に説明できるようにしておくことも大事です。先生方も、入園後に実際どう対応したらよいか、想像がつきやすくなります。
また、質問したいことは前もってまとめておくと効率的です。気になる点は事前に書き出しておくと聞き漏らしも防げます。
実際の見学時の持ち物や服装はどうしたら良い?



見学時の説明や気づきを記録するメモ帳やスマホなどを持って行きましょう。園によっては室内履きが必要なことがあります。服装は清潔感があり、動きやすいものがよいでしょう。
保育園を見学する時の確認ポイント7選
保育園見学では、先生方の雰囲気や子どもたちの表情、支援の実際の様子などを見ることが大切です。子どもが安心して過ごせる保育園かどうか、自分の目でしっかりと確認しましょう。
ここからは、保育園を見学する際にチェックしたいポイントを、筆者の経験も踏まえて具体的に紹介します。
1.障がい児の受け入れ体制
保育園によって、これまで受け入れてきた子どもの特性や支援の内容は異なります。障がい児へのかかわりについてどのようなことを大切にしているか、どんなサポートが可能か、これまでの経験も含めて園長先生に確認するとよいでしょう。
今まで障がい児の受け入れ経験がない保育園であっても、子どもの様子を共有しながらサポート方法を一緒に考えてくれる園もあります。話をする中で感じる安心感も大切な判断材料になるでしょう。
また、障がい児の場合は一般的な保育時間に比べて預かり時間が短かったり、慣らし保育に時間がかかったりすることがあります。、入園後の対応についても、合わせて確認するとよいでしょう。
2.加配保育士の配置が可能か
障がい児を預かる場合、特別な配慮が必要なことが多いため、通常の保育士配置基準よりも多くの保育士を配置できる「加配」という制度があります。この追加の保育士を「加配保育士」と呼びます。
人員的に加配保育士の配置ができるか、過去に加配保育士を配置したことがあるかを尋ねてみましょう。人手不足が課題の園も多いため、配置が難しい場合もあります。
加配保育士の配置は、自治体が決めます。現場で加配保育士の必要性を訴えても、 自治体から許可が下りないと配置は難しいので、加配が認められるかどうかは役所にも相談しておくと安心です。
3.医療的ケアの対応は可能か
子どもに医療的ケアがある場合は、看護師が常駐しているか、どこまでのケアに対応可能か確認が必要です。看護師がいない場合でも、柔軟に対応してもらえることもあります。吸引や投薬など具体的なケア内容を伝え、園としてどこまで対応ができるか確認しましょう。
4.園内の環境
園内の設備や環境をみて、子どもが無理なく生活できるかどうかの確認をしましょう。段差がないか、階段の手すりやエレベーターがあるか、静かなスペースがあるか、などの設備を確認します。
大切なのは、環境が整っているかどうかよりも、この環境で子どもが生活できるか、という観点です。もしも見学時点で課題があっても、環境を工夫したり、新たに設備を整えたりして、より過ごしやすいように配慮してもらえることもあります。
例えば、段差があっても職員がスムーズに手を貸してくれる体制になっていたり、エレベーターがなくても1階で生活できるようにしてもらえたりする場合もあります。



筆者の子はエレベーターのない保育園でしたが、体重が重くなってきてから階段昇降機を手配してくださいました!
5.食事に対する配慮
食事の形態に配慮が必要な場合、刻み食やペースト食などが給食で対応可能かどうかもポイントです。自分で食べることが難しい子どもの場合は、どのように食事介助をしてもらえるのか、どこまで支援が可能かも確認しましょう。
6.日々の過ごし方
子どもが日中どのように過ごすのか確認することも、とても大切です。特に幼児期以降の過ごし方は保育園によってかなり異なるため、のびのびと遊んで過ごすのか、学習プログラムがあるのかなど、日々の活動内容も確認するとよいでしょう。どの保育園でも障がい児に対する配慮はあると思いますが、子どもがついていけない内容が多いと、他の子どもと別に過ごす時間が多くなってしまう可能性があります。
障がいの程度によっては、実際の年齢より低年齢のクラスで過ごす場合もあるので、クラス分けについても確認しておきましょう。低年齢で過ごす場合、それが本人や親にとって心地よいのかどうか、しっかり考える必要があります。
7.緊急時の対応
園の緊急時対応についても確認しておきましょう。体調の変化や医療的ケアが必要な場面で、どのような対応をしてくれるのかは非常に重要です。
例えば、発熱時の呼び出しの基準は園によって異なります。37.5℃ですぐに呼び出される園もあれば、子どもの様子や他の症状を総合的に判断してくれる園もあります。「体温が何度以上で連絡が来るか」「その後どのように対応するか」といった具体的な基準を事前に聞いておくと安心です。
特に医療的ケアが必要な場合は、緊急時の対応についても確認しましょう。痰詰まりやてんかん発作の対応、経管栄養中のトラブルなど、どのような対応が可能か確認しておくと安心です。
また、園によっては、入園の際に保護者と一緒に個別の対応手順を話し合い、マニュアル化しているところもあります。事前にどのような相談ができるか確認しておきましょう。



最後は直感も大事です!見学時点で違和感を覚えた場合は大切なサインかもしれません。納得できる子どもの居場所を見つけましょう
見学に行った後は
見学が終わったら、得られた情報や感じたことをすぐメモに残しましょう。良かった点、気になった点などを園ごとに書き留めておくと、あとで複数の園を比較しやすくなります。
また、家族と情報共有し、意見を聞いてみましょう。気になった園は家族にも見学してもらい、印象を聞くと安心です。
子どもと家族にとって安心できる保育園を見つけよう
障がい児を受け入れる保育園は増えてきているものの、まだまだ少ない現状があります。また、子どもによって必要な支援は多様で、子どもに合った保育園を見つけるのは簡単ではありません。
保育園を選ぶときには必ず見学を行い、受け入れ体制や環境面などを確認しましょう。そして最後は「ここなら安心して預けられそう」という直感も大切にしてください。
子どもと家族にとって心地よく、安心できる保育園が見つかると良いですね!


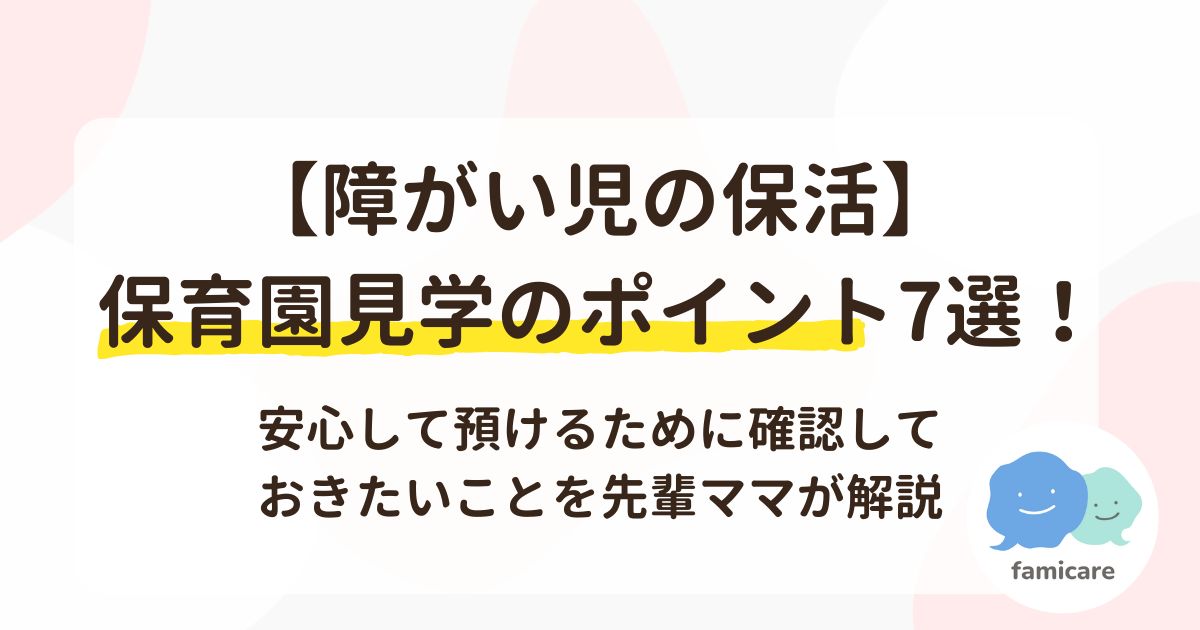

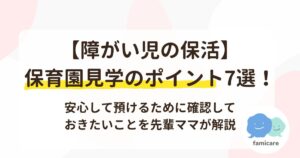

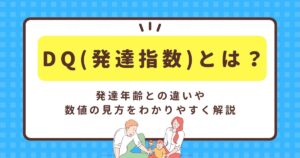

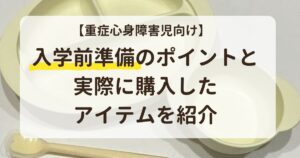



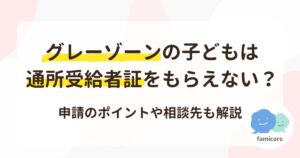
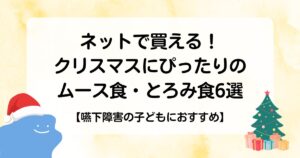
コメント