乳幼児に起こりやすい「こもり熱」ですが、障がい児(者)にも体温調整の苦手な人は多く、発熱との見極め方に困っている親御さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に熱のこもりやすい体質の娘を育てる筆者が、こもり熱と発熱の違いや、それぞれの原因・対策などを解説します。
この記事を監修してくれた先生
医師 おkら先生

呼吸器専門医、がん薬物療法専門医、総合内科専門医。嚥下機能評価研修会修了、医療型児童発達支援/放課後等デイサービスの嘱託医。仕事大好き、2児の母。長男がダウン症、気管切開をしている医療的ケア児。障害児を育てる環境が優しくなって欲しい。その為に自分に何か出来る事はないかと日々考えています。
X:@oke_et_al,ブログ:じょいく児。
こもり熱(うつ熱)とは?
こもり熱は、医学用語では「うつ熱」と呼ばれ、身体から熱をうまく放散できないために、体温が上がってしまっている状態を指します。
高温・多湿環境の他、外的衣類の着込み過ぎや就寝時の布団類のかけすぎなど、熱の放散が妨げられることによって高体温を引き起こすものです。
 ライター 原島
ライター 原島特に乳幼児は体温の調整機能が未発達なため、周囲の環境温度によって容易に体温が変動してしまうため熱がこもりやすいのだそう。
子どもが高体温になるケースとして、こうした熱の放散障害による「うつ熱」と、病気による「発熱」の大きく分けて2パターンがあります。
(※編集部註:本記事では、うつ熱ではなく「こもり熱」と表記します)
こもり熱の原因
こもり熱の場合、内因性の高熱ではなく、高温環境や放熱を遮る何らかのトラブルなど外部環境の異常による高熱です。
たとえば、以下のような環境だと身体の体温調節機構の働きが鈍くなり、こもり熱による高体温を招いてしまいます。
▼こもり熱の原因(例)
- 環境温が熱い(夏の炎天下・室内温度が高い・車の中・暖房器具に近いなど)
- 多湿
- 無風
- 厚着をしている
- 布団のかけ過ぎ
- うつぶせ寝をしている
- 水分補給が足りていない など
こもり熱になりやすい人って?
特に乳幼児は体温の調整機能が未発達なため、こもり熱になりやすいといわれています。また、障がい児の場合にも、脳性麻痺や脳症の後遺症など、何らかの原因で体温調整機能や発汗機能が損なわれてしまっているケースでは、こもり熱を引き起こしやすくなることがあります。



筆者の娘も急性脳症の後遺症が原因とみられる無汗症で汗をかけなくなり、熱がこもりやすくなりました。
▼こもり熱についてはこちらで詳しく解説しています
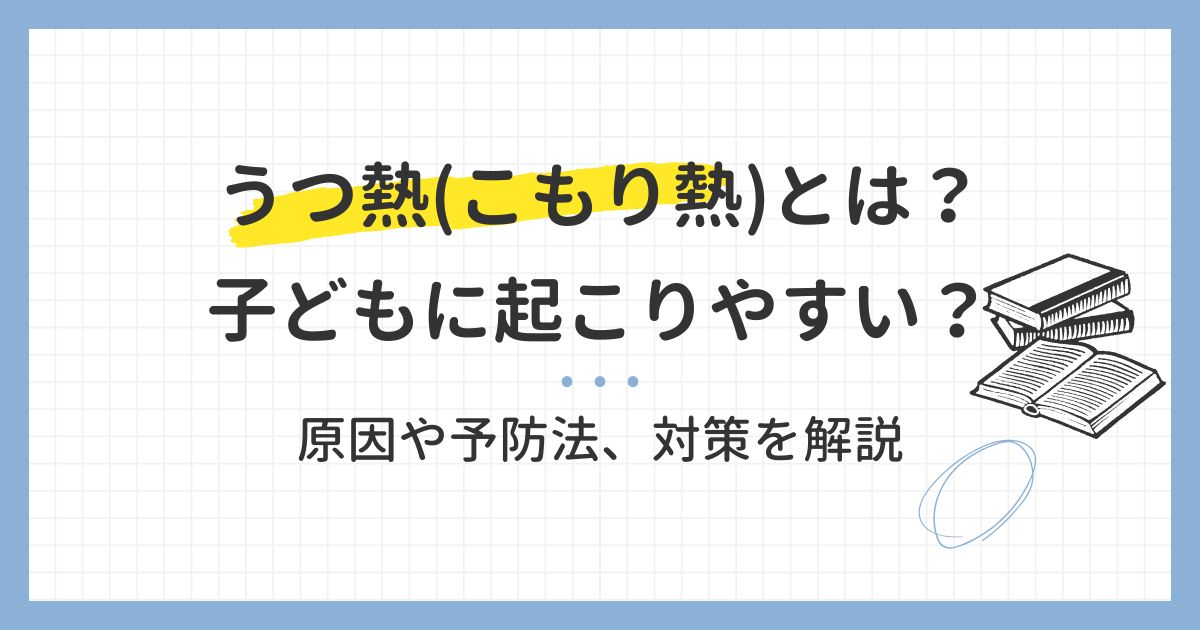
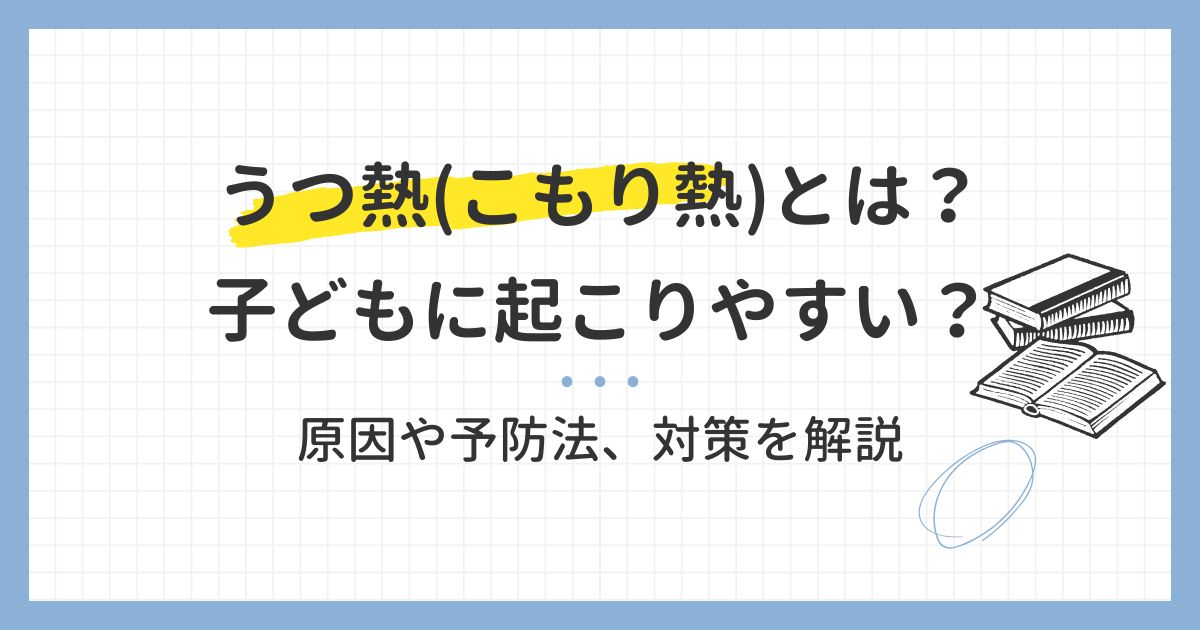
発熱とは?
発熱とは体内の何らかの異常により、平熱の範囲を超えて体温が上昇することです。子どもの場合、病気による「発熱」は、風邪をはじめとするウイルス性の感染症を原因とすることが多いです。
この記事では、最もポピュラーな原因である感染性の「発熱」について解説します。
感染性の発熱のメカニズム
発熱は、免疫機能を高めるための生体防御反応のひとつです。
体内にウイルスや細菌といった病原体が侵入した際に、病原体の増殖を抑えるために身体が防御反応を起こし、体温調節中枢の設定温度が高くなることで高体温となります。
こもり熱と発熱の違い
子どもが高体温になった場合、それがこもり熱なのか、または感染症などによる発熱なのかを見極めるのは難しいものです。
一般的に、こもり熱と発熱は以下のような違いがあるといわれています。
| こもり熱 | 発熱 | |
| 体温 | 37~38度の微熱 | 38度以上の高熱 |
| 手足の温度 | あたたかい | 冷たい(解熱後:暖かい) |
| 発汗 | あり | なし(解熱後:あり) |
| うとうとする様子 | あり | なし(解熱後:あり) |
| 筋緊張による熱産生 | 抑制 | 亢進 |
| その他の特徴 | 気温が高い場所で症状が出る | 風邪の症状がある |
【参照】高体温(発熱・うつ熱)の原因と体温調節のメカニズム



上記はあくまでも一例です。心配な点があったり、普段と違う様子を感じた場合には、医療機関の受診や「♯7119」(または地域ごとに定められた電話番号)へ救急電話相談をしましょう。
では、いざ子どもの熱が高い時にどう対応したらよいのでしょうか。ここからは、こもり熱と発熱、それぞれの対処法について解説します。
こもり熱になってしまった場合の対処法
こもり熱により高体温を起こした場合は、以下のような対処を行いましょう。
- 涼しい環境をつくる
- 薄着にして体温を下げる
- 首やわきの下、足の付け根を冷やす
- 水分補給をする
▼こもり熱の対処については詳しくはこちらのページで解説しています
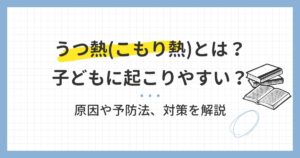
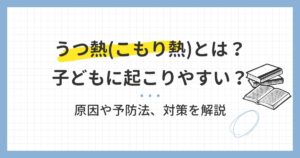
発熱したときの対応
子どもが発熱した場合、経過観察をするか、医療機関を受診するか非常に悩ましいものですよね。判断の基準となる目安は、以下のとおりです。
至急受診が必要と考えられる場合
- 38℃以上の発熱の有無に関わらず、
⚪︎顔色が悪く、苦しそうなとき
⚪︎小鼻がピクピクして呼吸が速いとき
⚪︎意識がはっきりしないとき
⚪︎何度も嘔吐や下痢があるとき
⚪︎不機嫌でぐったりしているとき
⚪︎けいれんが起きたとき
- 3ヶ月未満で38℃以上の発熱があるとき
このような状態の場合には、早急に医療機関を受診することをおすすめします。
また、熱性けいれんの既往歴がある場合には、発熱時の対応に関してかかりつけ医に予め確認しておきましょう。
自宅で様子を見る場合のポイント
自宅で療養する際には、以下のポイントに気を付けましょう。
- 熱がこもらないように注意する
体温が上がりきるまでは寒く感じることもありますが、体温が上がりきったあとは、厚着や布団の掛け過ぎで熱がこもってしまうことがあります。体温調整が上手くできるよう、こまめにケアしましょう。
- 水分補給をする
発熱により汗をたくさんかくので、普段以上に水分補給をしっかり行いましょう。 おしっこの回数が減ったり、脇や唇がかさかさしている、泣いても涙が出ない場合は、脱水の初期症状かもしれません。うまく水分補給が出来ない場合には点滴が必要になることもあるので、注意しましょう。
- 安静にする
熱があっても元気に過ごしてしまうお子さんもいますが、発熱している間は普段以上に体力を消耗しています。なるべく安静に過ごしましょう。
こもり熱と発熱の違いを知って、正しく備えよう
こもり熱と発熱では、どちらも同じ高体温ではあるものの、原因や対処法などにおいて根本的な違いがあります。
まずは熱がこもらないように予防することと、感染症対策を徹底し、高熱になってしまっても焦らず落ち着いて対応しましょう。
心配な点や普段と違う様子があれば、無理なく受診・相談をしてください。


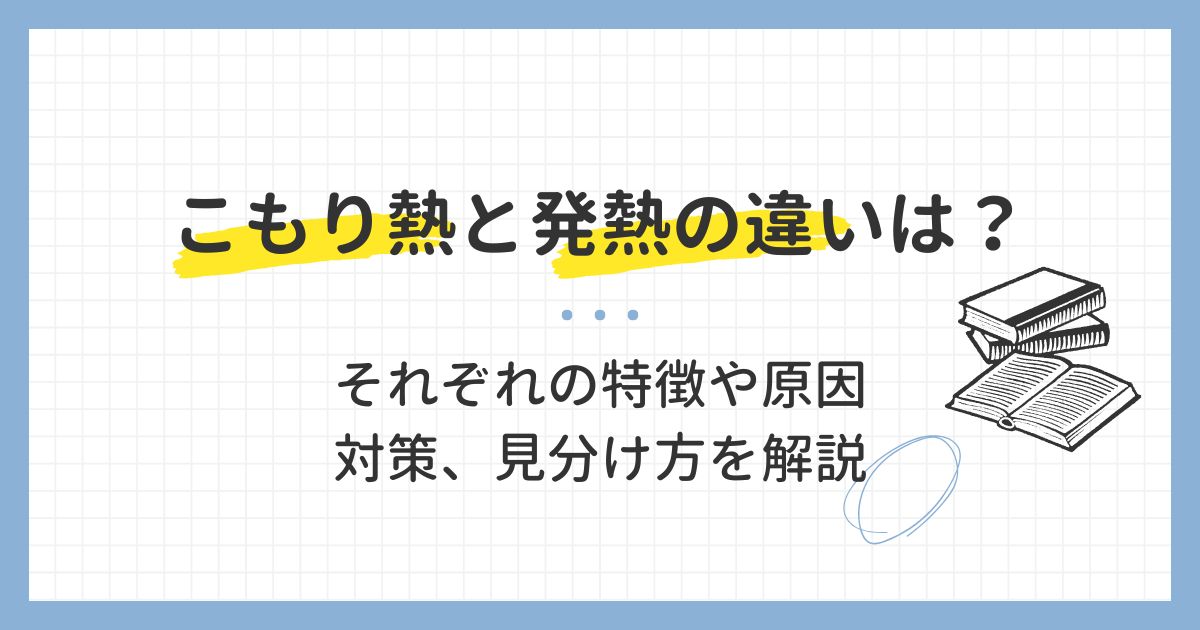

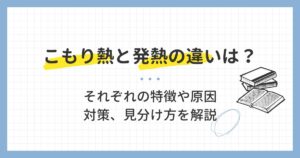




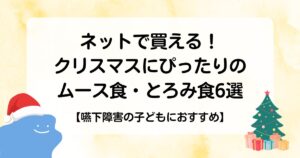
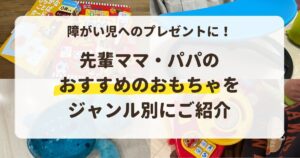
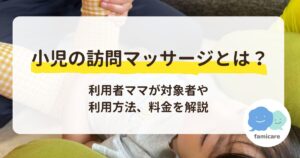

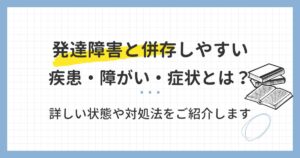
コメント