夏休みが近づくと、発達障害のある子どもを育てる保護者の方は「今年はどうやって過ごそう」と不安になる場合が多いのではないでしょうか。子どもの混乱を最小限に抑えつつ親子で穏やかに過ごしたい気持ちは、とても自然で大切なものです。
この記事では、子どもの特性を理解したうえで工夫を重ねながら、長期休みを楽しく過ごすためのヒントをお伝えします。
うちの子、学校がないと生活リズムが崩れてしまう



一日中家にいると何をしてあげればいいのかわからない
このようにお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
発達障害児との長期休み、どんなことに戸惑う?
発達障害のある子どもにとって、長期休みは予想以上に大きな変化となる場合があります。まずは多くのご家庭で感じる戸惑いを整理してみましょう。
生活リズムの変化による混乱
学校がある日は決まった時間に起床し、授業のスケジュールに沿って一日を過ごしていた子どもにとって、急に自由な時間が増えるのは不安要素の一つです。「今日は何をするの?」「いつ起きればいいの?」という疑問が子どもの心に生まれ、落ち着かない気持ちになる場合があります。
感覚刺激の変化とストレス
普段は学校という決まったスケジュールや決まった場所で過ごしている子どもが、家庭という比較的自由な環境に長時間いると、刺激の感じ方のバランスが変わる場合があります。兄弟姉妹の声や家庭内の音、テレビの音などが普段より気になったり、逆に刺激が少なすぎて物足りなさを感じたりする場合もあります。
社会的な期待とのギャップ
世間では「夏休みは楽しいもの」「家族でお出かけするもの」といった期待がありますが、発達障害のある子どもや家族にとってそうとは限りません。このギャップが保護者の心理的な負担となり「普通の家族のように過ごせない」という罪悪感を生むケースがあります。
宿題への取り組みの困難さ
「どの宿題からやればいいかわからない」「一日にどのくらいやればいいかがわからない」など、宿題に関する問題が表面化しやすいのも長期休みの特徴です。「集中できない」「きれいに書けないからやり直したい」などと子どもが癇癪を起こして保護者が疲れてしまう…そんなケースも珍しくありません。
長期休みは「計画的な備え」で楽しくなる!



長期休みをゆったり過ごすために、事前にできる準備があれば知りたい
そんな方もいらっしゃいますよね。長期休みを穏やかに過ごすための第一歩は「事前の準備」です。子どもの特性を理解したうえで、無理なく以下のような計画を立ててみましょう。
子どもと一緒にスケジュールを作る
週単位や日単位で大まかな予定を立て、子どもに見通しを持たせてあげます。子どもが電車好きなら「火曜日は電車の動画を見る時間」「金曜日は近所の電車を見に行く」など、子どもの好きな活動も盛り込むと、より楽しく過ごせます。
また、学校があるときの要素を完全になくすのではなく「いつもと同じ」部分を適度に残すのも大切です。朝の体操の時間や決まった時間の読書など、子どもが慣れ親しんだルーティンを取り入れるとよいでしょう。



柔軟に変更できるよう、余裕を持たせたスケジュールにするのがポイントです
「生活リズムを維持できる作戦」を一緒に考える
学校があるときの起床時間が7時なら、長期休み中は8時頃に設定するなど、少しゆるやかにしながらも一定のリズムを保てる工夫を考えてみましょう。完全に自由にするのではなく「子どもが混乱しない程度に緩める」のがポイントです。
起床時間だけでなく、朝食の時間や勉強時間、昼食、午後の活動、夕食、就寝時間などもおおよその目安を決めておくと安心です。



子どもと一緒に「夏休みの一日の流れ」を紙に書いて、見える場所に貼っておくのも効果的です!
長期休み中に利用できるサービスや支援を確認
放課後等デイサービスの夏休みプログラム、地域の支援センターでの活動、子育てサポート事業など、利用できそうなイベントについて事前に情報収集しておくのもおすすめです。これらのサービスの活用は、子どもにとっては新しい刺激や社会性の維持、保護者にとっては一息つける時間を確保できます。



地域の図書館や公民館でも、夏休み期間中に子ども向けのイベントを開催している場合があります
宿題も「ルール化」で快適に
宿題は、一目で進捗がわかるように計画表を作成して「今日はここまで」と目標を明確にすると取り組みやすくなります。子どもが集中できる時間帯を宿題タイムに設定するのもおすすめです。また、宿題に集中しやすい場所を決めて、必要な文具をすぐに取り出せるようにしておきます。



子どもなりのルールで一日少しずつすると、達成感を大切にしながら宿題を進められます
長期休み中、一日を家で安心して過ごすには?
家庭で過ごす時間が長くなる長期休み。子どもが安心して過ごせる環境づくりのポイントをご紹介します。
起床後のルーティンを決める
「起きる→洗顔→着替え→朝食」など、朝の流れを決めておくと、一日のスタートを切りやすくなります。学校がある日とできるだけ似た流れにしておくと、発達障害のある子どもにとって戸惑いが少なく、馴染みやすいです。
ルーティンは、絵や文字で表にして子どもが自分で確認できるようにしておくと、自立への第一歩にもなります。完璧にできなくても、少しずつ習慣として身につけていけば大丈夫です。
活動ごとにタイマーを使って時間を区切る
「勉強は30分」「ゲームは1時間」「お昼寝は1時間」など、活動ごとに時間を区切ると、メリハリのある一日を過ごせます。タイマーを使うと、時間の感覚を身につける練習にもなるためおすすめです。
タイマーの音が苦手な子どもの場合は、砂時計や光で知らせてくれるなど、子どもに合ったものを選んでみてください。



強制的に終了するのではなく「あと少しで時間だよ」という予告をしてあげるのも大切です
感覚特性に配慮した環境を作る
音に敏感な子どもには静かな環境を、逆に音がないと落ち着かない子どもには適度な背景音を用意するなど、子どもの感覚特性に合わせた環境づくりを心がけましょう。照明の明るさや室温なども、子どもが快適に過ごせるよう調整します。
また、子どもが一人になりたいときの「避難場所」を作っておくのも大切です。



自閉スペクトラム症の娘が暮らすわが家では、クローゼットの中やパーテーションで区切った小さなスペースなど、安心できる場所を確保しています
▼こちらの記事も参考にしてください


「今日やること」リストを作って達成感を味わう
朝起きたら、その日にやることを子どもと一緒に確認し、一つずつクリアしていく楽しさを味わってもらいましょう。「朝ごはんを食べる」「歯を磨く」「本を読む」など、小さな目標で構いません。
できたことには、チェックマークをつけたりシールを貼ったりして視覚的に達成感を味わえるようにすると、子どものやる気も持続しやすくなります。
長期休みを終えて学校生活に戻るのが不安…その気持ちに寄り添うには?
夏休みが終わりに近づくと、多くの子どもが「あと何日で学校が始まるの?」「朝起きられるかな」「給食を食べられるかな」「友達と話せるかな」という不安を抱えます。これは発達障害のある子どもに限らず、多くの子どもが感じる自然な感情です。
また、普段は気にしないことに過敏に反応したり家族への八つ当たりが増えたり、一人になりたがる行動が見られることもあります。これらは、子どもなりに不安や緊張を表現している行動として、温かく受け止めてあげる姿勢が大切です。
▼対策として心がけたいポイント
- 「学校が始まるのは心配だよね」と子どもの気持ちを受け止める
- 「まず○○先生に会えるね」「給食は好きなカレーが出る日もあるよ」など、具体的に見通しを立てる
- 夏休み最後の週は少し早めに起きる練習をしたり制服を着る練習をしたりなど、学校への準備を段階的に進める
- 好きなことをしたり家族でゆっくり過ごしたりなど、子どもがリラックスできる時間を作る
- 身体的な不調の訴えがあった場合は「気のせい」と決めつけず、必要に応じて休息を取らせてあげる



子どもの不安な気持ちに向き合っていると、保護者自身も心配になったり疲れたりする場合が少なくありません。完璧な対応を求めず「一緒に乗り越えよう」という気持ちで寄り添ってあげるのが、何より子どもの安心につながります。
準備と工夫で長期休みをのんびり楽しもう
発達障害のある子どもとの長期休みでは、大変な面に目が向きがちです。しかし、長期休みは普段はできない特別な体験をしたり、親子でゆっくり過ごす貴重な時間でもあります。完璧を目指さず、子どもの特性を理解したうえで、無理のない範囲で過ごすのが大切です。
事前の準備と日々の小さな工夫の積み重ねが、きっと親子で穏やかに過ごせる時間につながります。子どもの笑顔と家族の安らぎを大切にしながら、思い出に残る長期休みを過ごしてくださいね。


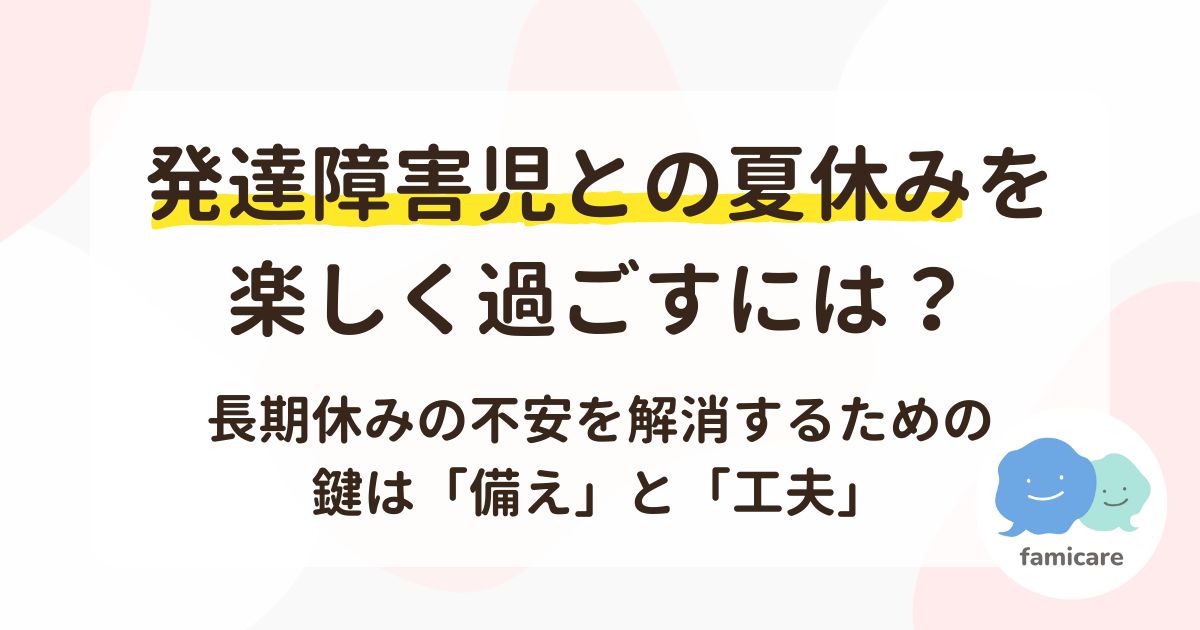
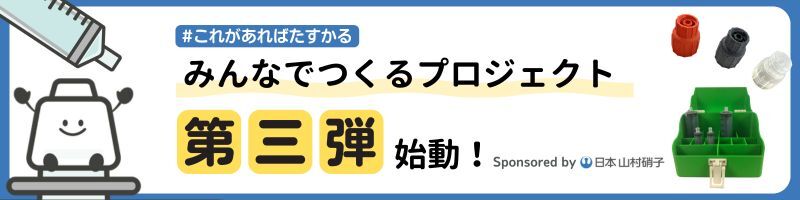

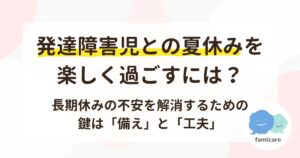

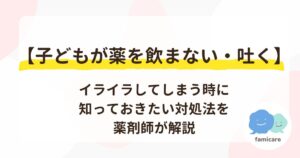
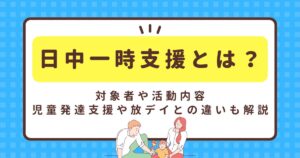
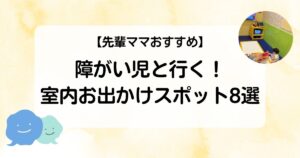
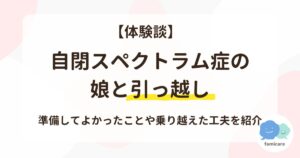
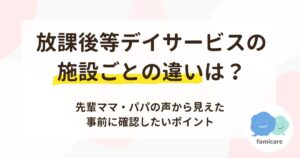

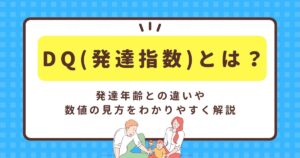

コメント