低出生体重児とは、出生時の体重が2,500g未満の赤ちゃんのこと。小さく生まれた赤ちゃんは発達が未熟なことが多く、出産後に特別なケアやサポートが必要です。
どんな赤ちゃんでも成長には個人差があるものですが、特に赤ちゃんが小さく生まれた場合、成長に何らかの影響が出るのか、具体的にどのような発育過程をたどるのか、よくわからず不安に思う保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、低出生体重児が生まれる原因や発達の特徴、生後に受けることができる医療や支援について、低出生体重児だった娘をもつ筆者が紹介します。
低出生体重児の定義
低出生体重児とは、生まれたときの体重が2,500g未満の赤ちゃんのことをいいます。さらに、1,500g未満の赤ちゃんを極低出生体重児、1,000g未満になると超低出生体重児と呼び、区別します。
母子保健法第6条によると以下のように定義されています。
“「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。”
【引用】母子保健法|e-Gov法令検索
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141#Mp-Ch_1
※世界保健機関(WHO)では、これまで、出生体重2,500g未満の赤ちゃんを未熟児と表記していました。現在は低出生体重児としています。
低出生体重児が生まれる確率
厚生労働省が行う人口動態統計調査によると、低出生体重児の出生数は2019年で81,462人。出生総数865,239人うち9.4%を占め、およそ10人に1人の割合で生まれています。
1980年代から増加傾向にあり、割合は1975年の5.1%からおよそ4.3%上昇していることがわかります。
【参照】人口動態統計特殊報告2(5)出生時の体重|厚生労働省
URL:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo07/index.html
低出生体重児が生まれる要因
赤ちゃんが小さく生まれる要因は大きく分けて二つあります。
一つ目は「早産」です。早産とは、妊娠22~36週6日目までの出産のこと。生まれた時期が早ければ早いほど体重も少なく、身体の機能も未熟であるため将来の発達にも影響をおよぼす可能性が高くなります。
二つ目の要因は「胎児発育不全」です。胎児発育不全とは、何らかの理由で実際の週数相当の発育ができない状態です。
胎児発育不全の原因は妊娠高血圧などの母体因子、先天性異常などの胎児因子、赤ちゃんに栄養を送るへその緒や胎盤の異常などです。その他、妊娠中の喫煙や妊婦の体重増加不良、妊娠前の痩せすぎなど、さまざまな環境要因も関連することがあります。
これらの原因が複雑に絡み合い、結果として発育を阻んでしまうと考えられています。
低出生体重児の特徴
個人差があり一概にまとめることはできませんが、低出生体重児は体重や身長の伸びが遅く、同時期に生まれた正常出生体重児に比べると成長に時間がかかるケースがあります。
また、出生時の体重が少なければ少ないほど、身体の器官が未成熟な状態であり、体温調節しにくい、哺乳力が弱め、感染症にかかりやすいといったさまざまなリスクがあります。
低出生体重児の体重と増加目安
小さく生まれた赤ちゃんの身体的な発育を確認する指標として低出生体重児の発育曲線があります。2022年、約30年ぶりに改定された資料で、出生時の体重によって下記5グループに分け、それぞれ男⼥別に作成されています。
- 500g未満
- 500〜1000g未満
- 1000〜1500g未満
- 1500〜2000g未満
- 2000〜2500g未満
 ライター 永田
ライター 永田個人差の大きな低出生体重児の発育、周囲と比較して焦ってしまう保護者の方も多いのではないでしょうか。小さく生まれた赤ちゃんがどのような成長をたどるのか、ひとつの目安としてぜひ参考にしてください。
【参照】医療機関退院後の低出生体重児の身体発育曲線(2022年) <出生体重別>|健やか親子21
また、低出生体重児の発育を観察する際には、よく修正月齢が用いられることがあります。
修正月齢とは赤ちゃんの誕生日ではなく、本来の出産予定日から数えた月数のこと。たとえば、出産予定日より2ヶ月早く生まれてきた場合、生後2ヶ月目を「修正月齢0ヶ月」とします。
月数をマイナスして観察することで、実際の月数にとらわれず赤ちゃんの成長を観察することができます。
「修正評価はいつまで行うか」について明確な答えはありませんが、より早い週数で生まれた赤ちゃんほど修正月齢と暦月齢の差は大きく、より長い期間修正が必要です。逆に在胎34~36週の後期早産児では差が小さく、1歳程度で修正は不要になることが多いです。
低出生体重児が抱えるリスク
低出生体重児は早産などの原因から、全身の器官が十分に成熟する前に生まれることも多く、以下のような合併症を発症する可能性があります。
呼吸器系の問題
- 新生児呼吸窮迫症候群
- 気管支肺異形成
- 新生児一過性多呼吸
- 未熟児無呼吸発作
循環器系の問題
- 動脈管開存症
神経系の問題
- 脳室内出血
- 脳室周囲白質軟化症
消化器系の問題
- 壊死性腸炎
合併症のリスクはありますが、必ずしも小さく生まれたすべての赤ちゃんに発症するわけではありません。NICUの医師や看護師はそうしたリスクを認識した上で赤ちゃんのケアをしてくれますので、気になることや不安なことがあれば相談してみましょう。



筆者の娘も2,100gの低出生体重児でした。妊婦健診では2,500gを超えていただけに、出生後に体重を聞いたときは驚きました。幸い、重篤な合併症もなく、1ヶ月ほどで退院できました。
生まれる週数や出生体重の影響
生まれる週数がより早く、体重が少なければ少ないほど、合併症のリスクは高くなります。
近年は医療の進歩によって、出生体重が500g程度の超低出生体重児でも救命できるようになりましたが、症状の長期化、重篤化によって新生児期以降、医療的ケアを要することもあります。低出生体重児の中でも、特に出生体重1500g以下で生まれた極低出生体重児の場合はよりハイリスクです。
出生体重がおよそ2,000~2,500g以上であると重篤な合併症なども少ない傾向ですが、個人差が大きく、子どもによっては心肺機能や体温調節、免疫が未熟な場合もあります。また、長期的には知的障害や発達障害の診断を受けるケースもあります。発達の遅れは学童期に入ってから授業中に座っていられない、成績が極端に悪いといったことから発見されることもあります。



そのため、低出生体重児は退院後も定期的にフォローアップ健診を受け、成長や発達の異常がないか慎重に経過をチェックされます。
低出生体重児へのサポートや支援
小さく生まれた赤ちゃんには、生まれてすぐから自宅に帰った後まで、以下のようなさまざまなサポートがあります。
入院中のサポート
入院中のサポートには以下のようなものがあります。
NICU(新生児集中管理治療室)でのサポート
小さく生まれた赤ちゃんの多くは生後すぐにNICUに入院となり、哺乳や呼吸のフォロー、身体の観察など24時間体制で適切なケアを受けることができます。
退院時には指導もあり、院内外泊などもしながら少しずつ自宅に帰る準備も進められるため、安心です。



筆者の娘は低体重以外の身体の疾患もあってすぐにNICUへと入院が決まりましたが、その後1ヶ月ほどでなんと1㎏も体重が増加!NICU入院中の日々の様子は看護師の方々が写真やメモでたくさん記録を残してくださっていて、サポートのあたたかさに涙が出たのを覚えています。
生まれてすぐに我が子と暮らせない寂しさはもちろん感じていましたが、医療スタッフの皆さんが親身に寄り添ってくださり安心できました。
▼NICUの情報がまとまっているサポートガイドはこちら


未熟児養育医療制度
未熟児養育医療制度は、入院費や医療費の全額、または一部を自治体が負担してくれる制度です。保護者の所得に応じ一部自己負担となる地域もありますが、負担分については乳幼児(子ども)医療助成の対象となります。
対象者は医師が低出生体重児・早産児と認めた満1才未満の赤ちゃんです。なお、低出生体重児、早産児の治療以外の治療行為や差額ベッド代、おむつ代など、保険適用外と判断される費用は、対象になりません。
退院後のサポート
退院後のサポートには以下のようなものがあります。
低出生体重児への家庭訪問
保健師や助産師が家庭を訪問し、赤ちゃんの健康状態の確認や必要な保健指導を行います。同時に、家族の不安や悩みを聞き、相談も受け付けます。
特に超低出生体重児などの場合は医療機関からの連絡を受け、退院前から、地域の保健師による医療機関訪問が行われることも増えているようです。
リトルベビーサークルなどのピアサポート
お住まいの地域によっては、小さく生まれた赤ちゃん向けの成長記録「リトルベビーハンドブック」を発行しているところもあります。また、小さく生まれた赤ちゃんのいる家族ならではの悩みや不安を共有できるリトルベビーサークルという家族会のある地域もありますので、ぜひ確認してみてください。
▼リトルベビーハンドブックやリトルベビーサークルの詳細はこちらから確認できます
https://www.kaneson.co.jp/topics/activity/detail.php?34
適切なケアで子どもの育ちを応援する
我が子が小さく生まれたとき、多くのお母さんは
「私のせいだったのでは」「これから無事に、大きくなるのだろうか」「赤ちゃんが退院してからの生活はどうなるのだろう…」など、自己嫌悪感やさまざまな不安、焦りを感じます。



かくいう私もその一人。娘が予想外に小さく生まれたとき、私自身の妊娠中の生活スタイルがいけなかったのかなど、自分を責める気持ちがありました。
しかしその後、NICUで担当医、看護師の皆さんからのサポートを受けながら、どんどん大きくなる娘の姿に「この子には生きようとする力がある!」と感じ、気持ちを持ち直しました。
育児書はあまり見ないで。周りと比べすぎず、まずは目の前の子どもの成長を見つめてくださいね
これは、娘がNICUからGCUに移るときに担当看護師さんがくださった言葉です。
子どもの将来を思うと、ついあれやこれやと心配しがちですが、小さく生まれても、ゆるやかながら、でも確実に赤ちゃんは成長していくのだと勇気づけてもらいました。一人ひとりの成長を見つめながら、赤ちゃんの育ちを応援したいですね。
▼この記事は以下のサイトを参考に作成しました
低出生体重児とは? ~定義とリスク、サポート体制~ |メディカルノート
小さく生まれた赤ちゃんについて | はじめてのNICU
低出生体重児の発育曲線(2022年)が公開されました |国立成育医療研究センター
https://www.ncchd.go.jp/news/2023/0621.html
未熟児養育医療制度|SmallBaby|スモールベイビー


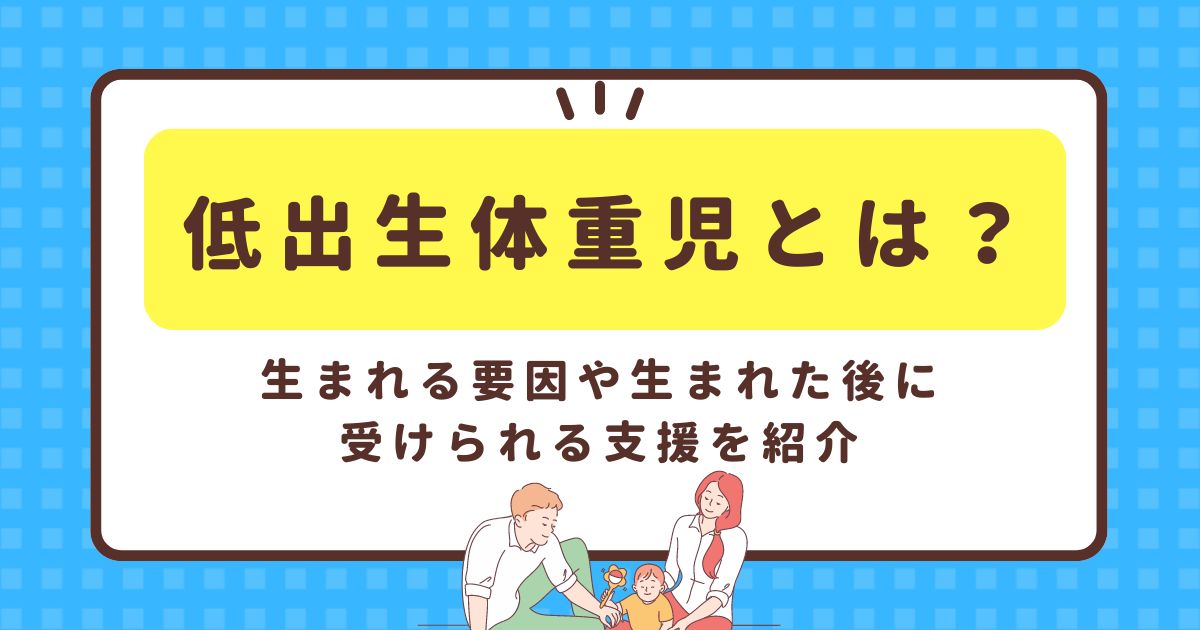

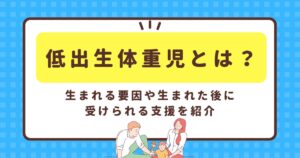

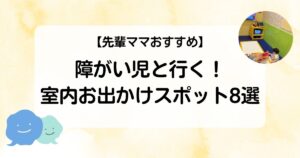

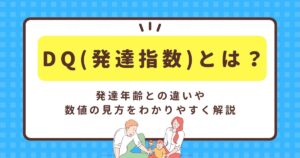



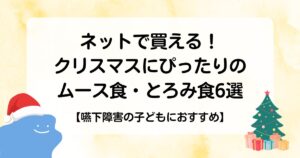
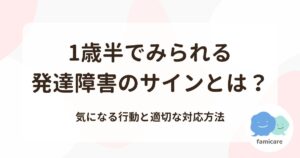
コメント