普段私達が病院を受診する際は、健康保険証を提示することで医療費を3割負担におさえることができます。しかし、生まれたばかりの新生児はもちろん健康保険に入っておらず、保険加入手続きをしても、保険証が手元に届くまでは日数がかかります。
保険証が手元にないけど、全額実費になるの?



保険証が間に合わない場合の対処法にはどんなものがある?
などの不安や疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では、NICU退院時や1カ月健診などに、新生児の保険証が間に合わなかった場合の対処法について紹介していきます。
▼NICUの情報がまとまっているサポートガイドはこちら


新生児の保険証はいつできる?
新生児の保険証ができるには、早くても1~2週間程度かかります。
2024年12月から、従来の健康保険証は原則新規発行は終了し、マイナンバーカードと保険証を紐づけた「マイナ保険証」を利用する流れになっています。そのため、出産後は赤ちゃんのマイナンバーカードの発行と健康保険加入の手続きが必要です。通常マイナンバーカードの発行には2~3週間かかりますが、新生児のマイナンバーカードは「特急発行」の対象であり、基本的には1週間で手元に届きます。
マイナンバーカードが手元に届き、健康保険の手続きが完了次第、マイナポータルアプリから利用登録をすることで、マイナ保険証として使用することができるようになります。
詳しい手続きは後ほど解説します。
退院時に保険証が間に合わないとどうなる?
1カ月健診の場合
もともと健診は健康保険の対象外であり、原則自費となります。そのため、保険証の提示は必要ありません。健診費用は大体5,000円から10,000円で、自治体によっては補助が出る場合もあります。
ただし、健診の結果により、追加で必要な検査や薬の処方にが必要になった場合には、追加分は健康保険の対象となります。基本的には一時的に10割負担分を支払って、保険証が届き次第、払い戻しの手続きを行います。病院によっては後日払いも可能です。
NICU退院時の場合
NICUの退院時までに保険証の提出が間に合わない場合にも、基本的には医療費全額(10割)の支払いが必要です。
しかし、NICUの入院費用は実費だとかなり高額になりますので、一時的とはいえ全額支払うのは現実的ではありません。前述のような原則はありますが、実際は保険証が提出できるまで、支払いを保留にしてくれる病院がほとんどです。



筆者の子どものかかりつけ病院に問い合わせてみたところ、全額実費の原則はあるものの、実際は後日払いとしている医療機関がほとんどであろうとのことでした。また、筆者の周りやファミケア編集部内のメンバーに聞いてみても、NICUの費用を全額実費で支払った方はいませんでした。
NICUの入院費用はどのくらい?
NICUは高度な医療、集中管理が行われる病棟です。医療費は、重症度による違いはありますが1日あたりおよそ8〜10万円程度かかります。また、医療費とは別に、ミルク代やおむつ代などの自己負担金があります。
【参照】
中央社会保険医療協議会 総会(第569回)議事次第 個別事項(その9)P25|厚生労働省
通常ではかなり高額になりますが、健康保険証を利用することで医療費の支払いが2割におさえられます。つまり、2割の医療費+自己負担金の支払いで済むということです。
更に「乳幼児医療費助成制度」や「未熟児養育医療制度」など、各種制度を利用することで更に医療費をおさえることができます。



ファミケア編集部のNICU卒メンバーに聞いてみると、医療費の自己負担はなく、おむつやミルク、リネン代のみかかったという人が多かったです。
▼NICUの費用や各種制度についてはこちらの記事で詳しく解説
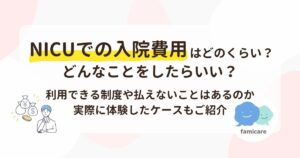
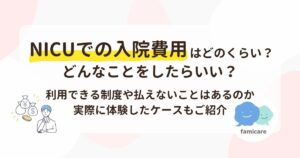
次に、保険証が間に合わない場合の手続きについて解説します。
新生児の保険証が間に合わない場合に必要な手続き
子どもの保険証が支払い時までに間に合わない可能性がある場合、まずは病院の診療費支払い窓口や病院スタッフなどに相談しましょう。前述のように、保険証ができてからの後日払いとしてくれる可能性が高いです。
後日払いにする場合、誓約書が必要になったり、連帯保証人の署名が必要になったりすることもあります。病院によって手続きが異なりますので相談した際に確認しておくと安心です。



後日払いにした際には、保険証が手元に届き次第、速やかに病院窓口に提出することをお忘れなく!
また病院によっては、加入手続き中の健康保険を仮登録して支払うという方法ができる場合もあります。
子どもが加入予定の健康保険を仮登録し、支払額を計算する方法です。患者は一旦健康保険を適用した2割の負担額+自己負担金(ミルク代やおむつ代)を支払い、子ども医療費助成など各種制度が利用できるようになったら差額の払い戻しを受けます。
この場合、被保険者の健康保険証を提出する必要があります。つまり、子どもがパパの扶養となり健康保険に加入するのであれば、パパの健康保険証が必要ということです。



仮登録の場合の計算方法は病院によって異なるため、どの程度自己負担が発生するのか、子ども医療費助成制度などがどのタイミングで適用されるかなどはかかりつけの病院に確認いただくのが確実です。
支払い時までに保険証を間に合わせるためにできること
手続きを早めにする
基本的なことですが、まずはできるだけ早く手続きを行うことが大切です。
健康保険の手続きをするには、子どもの住民票が必要です。住民票を発行するには、出生届を提出し、戸籍に登録しなければなりません。健康保険の加入にかかわらず、様々な手続きをスムーズに行うためにも、まずは出生届を早めに提出することが最重要です!
その後、速やかに健康保険加入の手続きをしましょう。
健康保険被保険者資格証明書を発行してもらう
健康保険被保険者資格証明書(以下、資格証明書)とは、健康保険に加入していることを証明する証書のことです。資格証明書があれば、保険証が手元に届いていなくても、保険証の代わりとして使用することができます。
資格証明書は、健康保険加入の手続きの際に申請すれば発行できます。基本的には当日交付が可能な証書ですが、新生児の場合は新規での加入なので数日かかる可能性があります。
マイナ保険証をなるべく早く受け取る手順
前述のように、2024年12月から従来の健康保険証が廃止となり、マイナ保険証の利用が始まりました。以前と手続きが異なるため、戸惑う方も多いはず。そこで、マイナ保険証を なるべく早く受けとるための手順を詳しく紹介します。
まずは出生届を提出し、戸籍に登録しましょう。
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を提出し、マイナンバーカードの発行の手続きをします。新生児の場合は顔写真は必要ありません。
「出生届兼マイナンバーカード交付申請書」を利用すれば、出生届とマイナンバーカードの手続きが同時に可能です。役所の窓口か、「マイナンバーカード総合サイト」からダウンロードできます。
新生児の場合は特急発行の対象となるため、原則1週間でマイナンバーカードが手元に届きます。ただし、里帰り出産などで居住地以外で申請した場合は、さらに日数がかかる場合があります。
健康保険の加入にはマイナンバーが必要です。マイナンバーカードが届いたら、速やかに健康保険加入の手続きを行いましょう。その際に保険証の代わりとして使用できる「資格証明書」の発行手続きをしておくと安心です。
健康保険に加入できたら、マイナポータルアプリでマイナンバーカードを読み取り、保険証利用の手続きを行います。その際にあらかじめ設定した4桁の暗証番号が必要です。
支払いに関する不安や困りごとは早めに相談しよう!
NICUの退院時でも1カ月健診でも、保険証が間に合わなくても対応できる方法があります。
事前に病院へ相談しておけば柔軟に対応してもらえることもありますが、支払いの保留はあくまで病院の厚意です。保険証が届き次第、速やかに提出・支払いを済ませるようにしましょう。
費用に関する不安は、ソーシャルワーカーや診療費窓口に相談することで解消できる場合があります。健診については自治体の補助が出ることもあるため、地域の保健センターにも確認してみると安心です。
この記事を読んだママやパパが少しでも不安を和らげて、安心して赤ちゃんとの時間を過ごせますように。


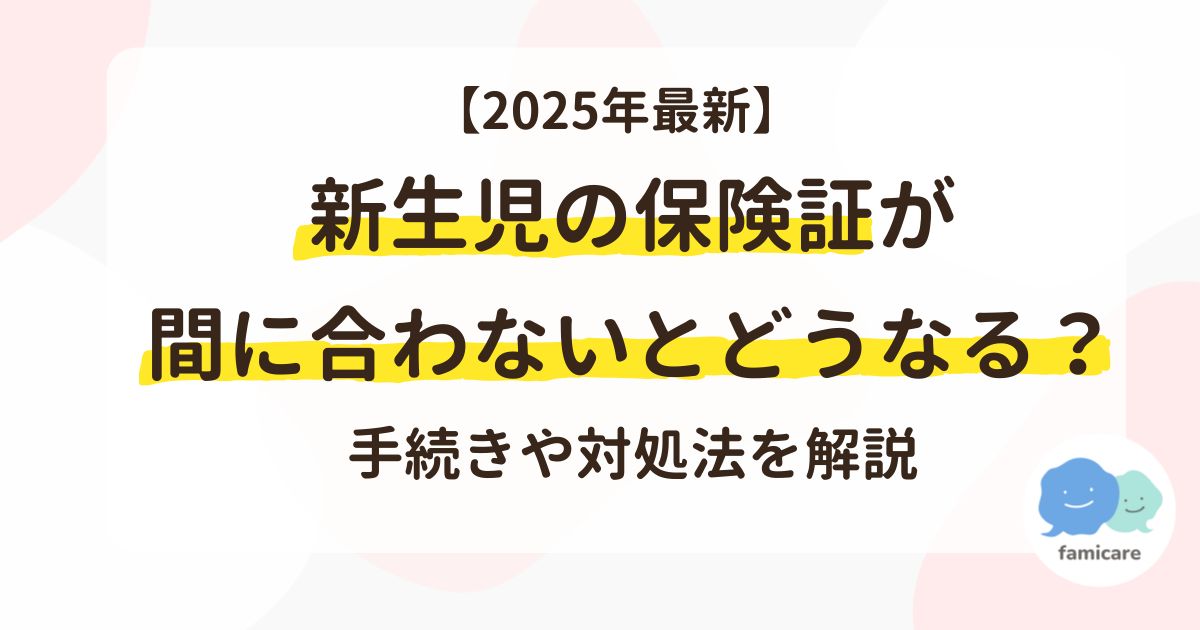

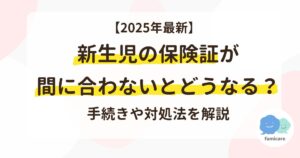


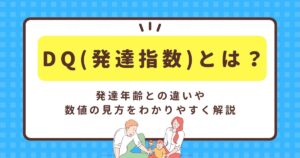



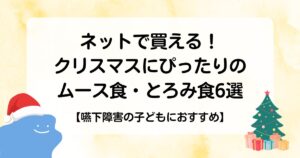
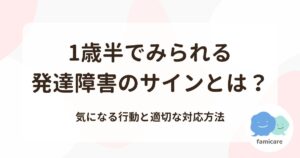

コメント