まもなく年長になる障がい児がいる親御さんの中には、もうすぐ就学準備が本格的になる、と不安や緊張を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
小学校は6年間と長いですし、「我が子に合った学校を決めないといけない」と思うと、プレッシャーにもなりますよね。
そのプレッシャーや不安を解消するのはなかなか難しいですが、「これからの1年、学校を決めるためにどう動いていくのか」がわかると、先が見えて準備しやすく少しは気持ちが楽になるかもしれません。
そこで今回の記事では、「就学準備が本格化する年長の時期に親がすること」に焦点をあて、就学先がどう決まっていくのか、いつ何をしたらいいのか、についてお伝えします。
※筆者が経験した仙台市のケースでご紹介します。自治体によって違う可能性が高いので、お住まいの自治体のケースについては必ずご確認ください。
▼年中までにしておくといいことはこちらの記事で読めます
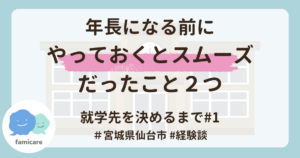
障がい児の就学先候補
子どもに障がいがある場合、就学先は次のような選択肢があります。
特別支援学校
特別支援学校とは、障がいのある子どもが教育を受けるほか、生活を送るにあたって子どもが苦手なことを克服し、自立を図るための技能を身につけることを目的に通学する学校です。その障がいごとにそれぞれの支援学校で受け入れる児童が決まっていて、「視覚障害者」「聴覚障害者」「知的障害者」「肢体不自由者または(身体虚弱者を含む)病弱者」のための学校があります。
教師の配置基準は普通級よりも手厚くなっています。普通級では一人の先生が児童40人を見ることが基準になっているのに対し、特別支援学校では単一障害のクラスの場合、児童6人に対し先生が一人、重複障害のクラスの場合は児童3人に対し先生が一人、という配置基準です。
地域の学校の特別支援学級
特別支援学級は、障がいによる学習上又は生活上の困難を克服するために地域の学校に設置されるクラスです。
障がいによってクラスが分かれ、子どもが通う学区の学校に該当クラスがなければ新設されることになります。障がいの種類は、「知的障害」「肢体不自由」「病弱及び身体虚弱」「弱視」「難聴」「言語障害」「自閉症者・情緒障害」です。
こちらも教師の配置基準は普通級よりも手厚く、児童8人を一人の先生が見ることになっています。
通級
学校生活のほとんどを普通級で過ごし、一部特別な指導を受ける時にだけ別室で特別支援教育を受けられる指導形態が通級です。対象は「言語障害者」「自閉スペクトラム症者」「情緒障害者」「弱視者」「難聴者」「学習障害者」「注意欠陥多動性障害者」「肢体不自由者」「病弱者及び身体虚弱者」です。
たとえば、発達障害などで、対人関係や読み書きなど、一部の技能が苦手な子どもがこの指導形態を利用できます。クラスは先生一人に対し、児童4〜5人ほどの少人数で編成されることが多いようです。
地域の学校の普通級
もちろん、普通級も選ぶことができます。先生の配置基準は児童40人に対し一人ではありますが、障がい児の学校生活をサポートしてくれる「特別教育支援員」が配置されることもあります。特別教育支援員は、食事や排泄など日常生活の介助をはじめ、教室の移動補助を行ったり、発達障害の児童生徒に対しては学習活動上のサポートを行ったりもします。
このように、障がいのある子の就学先は様々ですが、子どもの状況や特性に合った就学先を選び、無理なく通学できるようにしていきたいですね。
就学先はいつまでに決めるべき?
障がいのある子どもの場合、居住地の学区で自動的に学校が決まるわけではなく、子どもの状態に合わせて子どもに合った学校選びが必要です。
しかし学校選びといっても、子どもの障がいによっては、「支援級や特別支援学校どちらが子どもにとって適切なのか」など悩む方もいますよね。
この学校選びの決定時期の目安としては、年長の春から秋頃までです。10月頃までに家族内で決めておき、市区町村が定めている入学申込書の提出日までに最終決定となります。入学申込書を提出した後は、入学通知書が届いた学校へ通うことになります。
入学先を決定するまでには教育相談会などで進学先を相談する機会が設けられていることも多くあります。
筆者が経験した仙台市の場合では、11月に入学申込書の提出がありました。
【就学先決定までの具体的な流れ】(2024年度小学校入学児童の場合)
- 【5月】教育相談会の案内が5月の市政だよりに掲載される
- 【5月〜6月】教育相談会の申し込み
- 【8月】教育相談会に参加
- 【9月〜10月】審議結果通知の受け取り
- 【10月〜12月】学びの場の検討
- 【10月〜12月】学びの場の決定
- 【12月〜1月】入学申込書の提出
- 【2月】入学通知書の受け取り
- 【2月〜3月】入学する学校と相談
【参照】新年度入学予定のお子さんにふさわしい学びの場を考えるために(就学相談ガイド)|仙台市教育委員会
URL:https://www.city.sendai.jp/kyoiku-tokubetsu/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/shogai/madoguchi/documents/shuugakugaido.pdf
就学先を決めるにあたり悩んだポイントとどう解消したか
ここからは筆者の経験談として、就学先を決定するまでに悩んだポイントとどう解消したかについてお伝えします。
学ぶ環境か、授業の内容か、どちらを優先させるか
一番悩んだのは、学習環境か、学習内容か、どちらを優先して学校選びをするかでした。
筆者の息子は今保育園に通っており、そこで初めて、健常児と一緒に生活をすることになりました。最初は不安でしたが、健常児と一緒に遊んだり生活したりする中で、息子にも刺激になっているのか、特にコミュニケーションや食事面で、できることが増えてきたのを実感しています。
また、健常の子どもたちが、息子を見て「自分と違う」というのを感じ取りながらも、変に区別することなく「友達の一人」として息子と関わったり生活の手伝いをしてくれている姿を見て、とても微笑ましく、嬉しくも思いました。こうして子ども同士の触れ合いをすることで得られるものって大きいなと思ったので、健常児と一緒に学べる地域の小学校に通うという選択肢を最後まで捨てきれなかったのです。
学校に行っている時間は長いので、授業だけでなく、生活の中で得られる刺激も大きいかな、と思ったのですが、それでもやはり、数十分にわたって授業を受ける、自分の好きなことができない、ということが息子にとって苦痛の時間になりそうだなと判断し、特別支援学校を選びました。
 ライター小澤
ライター小澤特別支援教育を受けながらも、健常児と過ごす機会を多く持てるような方法があればいいのにな…
親の生活への影響
地域の小学校を選んだ場合、親の就労にも影響することも悩んだポイントです。
地域の小学校には送迎はなく、特別支援学校にはバスによる送迎がありました。もし地域の小学校を選んだ場合、朝と、学校が終わってから、親が送り迎えをする必要があります。朝はまだいいですが、問題は下校時です。14時、15時に迎えに行かないといけないとなると、フルタイムで仕事をすることはできません。
特別支援学校であれば、学校が終わる時間に放課後等デイサービスがバスで支援学校に迎えに行き、そのまま放課後等デイサービスに連れて行ってくれます。朝登校してから放課後等デイサービスから帰宅する17時〜18時まで、中断することなく仕事ができるというのも、特別支援学校を選んだ理由の一つです。



もちろん、子どもの学ぶ環境としてどこが適切か、と考えるのが最優先です。でも、親が仕事を持てるかどうかも私にとっては大切なポイントでした。
同じような障がいのある先輩ママの話が一番参考になった
最終的に特別支援学校に決めた大きな理由は、先輩ママの話でした。
通所していた児童発達支援センターでは、年に一回、先輩ママ数人を招き、「就学について」というテーマで経験談を聞ける機会を設けてくれていました。その時に聞いた、息子と同じような障がいのある子どもの就学エピソードや、地域の小学校、特別支援学校、それぞれに通うママの話を聞いて、「うちの子は特別支援学校の方が楽しく生活できそうだな」と思ったことが一番です。
また、それ以外でも特別支援学校に通うママ数人に話を聞いて、その全員が「特別支援学校楽しいよ!先生がすごく良くしてくれるし、子どもも楽しそうに通ってる。」と口を揃えて言ったことは大きな決め手になりました。



やっぱり先輩ママの声は頼りになります。
就学先希望の最終決定は10月までに。
障がいのある子どもの就学先は、特別支援学校や地域の小学校の特別支援学級、通級、普通級と複数の選択肢があります。小学校ごとに特色がありますので、それぞれの子どもの特性に合った学校を選ぶことになります。
どの学校が子どもにとって適切なのか迷うところですが、家族の意向として10月までに最終決定できていると安心です。その間に学校見学をしたり、教育相談会で疑問をクリアにしたりなど、決定材料を揃え家族で話し合いをしておきましょう。
就学までの過程は多いように見えますが、具体的に何をするかという行動だけを見るとそこまで大変でも難しいことでもありません。子どもの就学先決定、というただでさえプレッシャーを感じる場面、この記事を読むことでせめてスケジュールだけでもクリアになり、見通しがついて心の準備ができるようになったら嬉しく思います。
▼就学に関する情報をまとめた特集はこちら
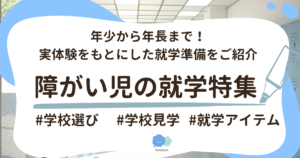
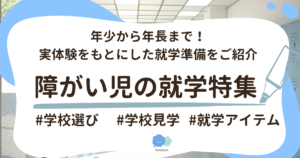


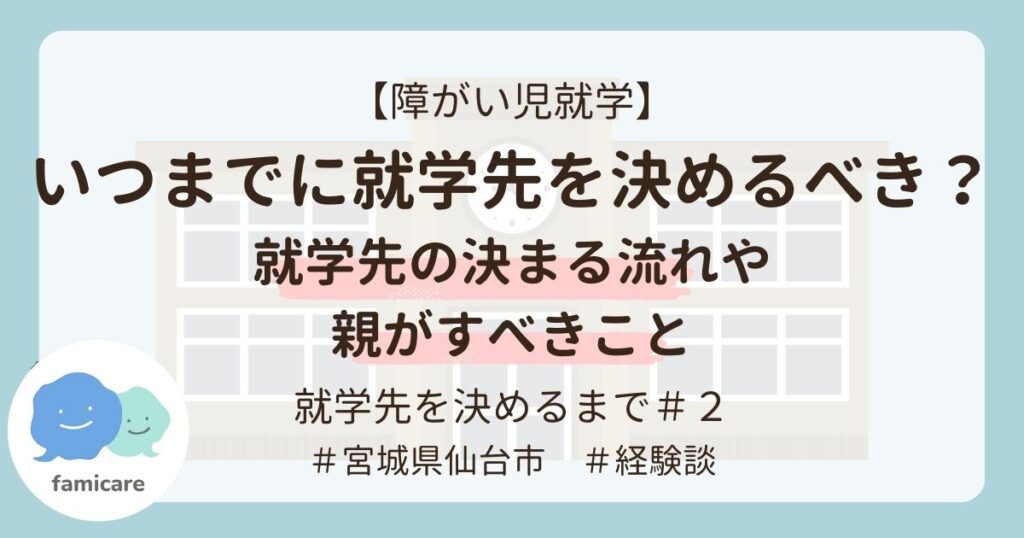

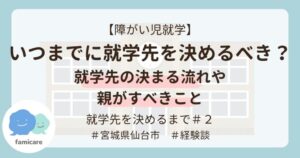

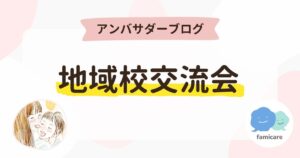
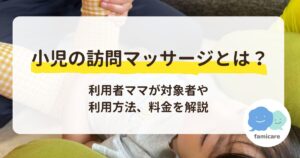
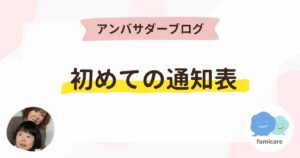

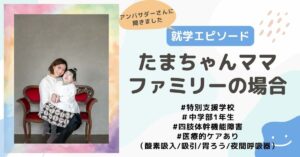


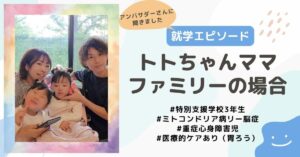
コメント