大声で泣きわめく、汚い言葉を使う、物を投げつけたり暴れたりするなど、激しい感情の爆発によって見られる行動の一つ、「癇癪(かんしゃく)」。
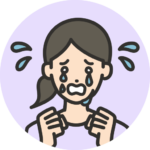
子どもの癇癪がひどく、どう対応していいか分からない



癇癪と向き合っているうちに疲弊してしまった
そんな方も多いのではないでしょうか。
この記事では、発達障害の一つ「自閉スペクトラム症」と診断されている娘と暮らす筆者が、癇癪を軽減するために実践している方法などをご紹介。発達障害と癇癪の関連性や要因なども、ゆったりと紐解いていきます。
癇癪とは?
癇癪は、主に欲求不満や疲労、空腹などのストレスを人や物にぶつけてしまう状態です。主に子どもが0歳の終わり頃から発現し、2〜4歳で最も多くなるといわれています。
この時期は「自分でやってみたい!」の気持ちが芽生え始めますが、その一方で失敗の経験も自然と多くなり、癇癪を起こしやすくなるのが特徴です。
通称「イヤイヤ期」「一次反抗期」とも呼ばれます。
子どもの成長に合わせて徐々に少なくなっていきますが、5歳を過ぎても癇癪が頻発する場合や15歳頃までの小児期全体を通して継続するケースもあります。
▼癇癪行動の一例
- 大きな声で叫ぶ
- 泣き叫ぶ
- 「キー」「キャー」など金切り声を上げる
- 手足をばたつかせて暴れる
- 足を踏み鳴らす
- 物を投げたり壁を叩いたりする
癇癪の判断基準で挙げられるのは「癇癪が起きている間、ご家族や周囲が身の危険を感じるか」「外出が困難か」などです。
発達障害が要因の癇癪は、特性から起こる不安や戸惑いによるもの。「子どものわがまま」ではなく「癇癪で表現するしかないほど子ども自身も辛い状況」と考えられます。
発達障害と癇癪との関係
癇癪が頻繁に起きたり、比較的長く続いていたりすると「我が子は発達障害なのでは」と考えるご家族もいらっしゃるのではないでしょうか。
前提として「癇癪がある=発達障害」とは言い切れません。そして、親の育て方のせいでもありません。癇癪は、子どもの性格や周辺環境など、さまざまな要因が関わっています。



成長のスピードや過程は人それぞれ。筆者はすでに大人ですが、感情のコントロールにしばしば悩みます。
しかし、発達障害の特性が癇癪に繋がっている可能性はあります。例えば、発達障害の一つ「自閉スペクトラム症」で癇癪を引き起こす要因として考えられるのは、次のような特性です。
- こだわりの強さ
例:「自分なりのルールで物事を進めたい」「特定のアニメの一部を繰り返し見続けたい」など
- 強い不安や恐怖、葛藤を感じやすい
例:「急なスケジュール変更は強烈に不安」「いつもと違う道を通ると怖い」など
- 対人関係や社会性でストレスを受けやすい
例:「『ちょっと待って』『そこに置いて』などの曖昧な表現を理解しにくい」 「相手の気持ちを読み取りにくい」など
- 感情のコントロールや表現が得意でない
例:「どうしても怒りを抑えられない」「気持ちを言葉ではなく暴力行為で表現してしまう」など
上記は、あくまでも一例に過ぎません。「我が子は発達障害かな?」と気になる場合は、子育て支援センターや児童発達支援事業所などの専門機関へ相談してみてください。
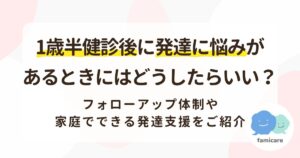
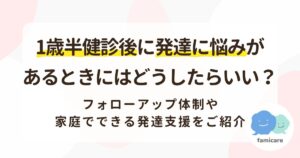
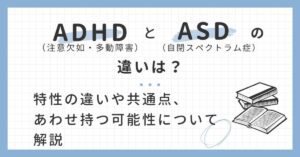
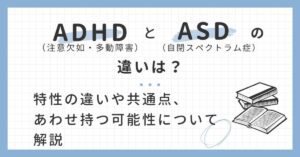
癇癪が起きる原因は?
子どもの癇癪が起きると、つい「どう対応すれば早く収まってくれるか」を中心に考えがちです。しかし、実は「そもそもなぜ起こるのか」と原因を探ることが、癇癪を軽減できるポイントでもあります。
癇癪の主な原因に挙げられているのが「欲求不満」「疲労感」「空腹」です。また、周囲の注意を引くためや何かを手に入れるため、あるいは特定の行為を回避する手段として用いられる場合もあります。
自分の要求や思いを言葉で表現するのが苦手な子どもにとって、癇癪は貴重なコミュニケーションともいえます。
娘の癇癪を軽減するために筆者が実践していること
「癇癪は貴重なコミュニケーション」…とはいえ、真っ赤な顔で手足をばたつかせて泣き叫ぶ我が子を見るのは、親としても辛いですよね。



そして対応に疲弊してしまうのも本音…!
自閉スペクトラム症と診断されている9歳の娘と暮らす筆者は、できる範囲で次のことを実践しています。
見通しを立てて不安を取り除く
癇癪に繋がりそうな要因の一つ「見通しが立っていない状態」をできるだけ取り除きます。
ポイントは、とにもかくにも「可視化」。お出かけの予定が決まった時点でカレンダーに書き込む、覚えていて欲しいことはメモをして見える場所に貼っておくなど、次の行動の予測がつきやすいように文字や写真で提示しています。
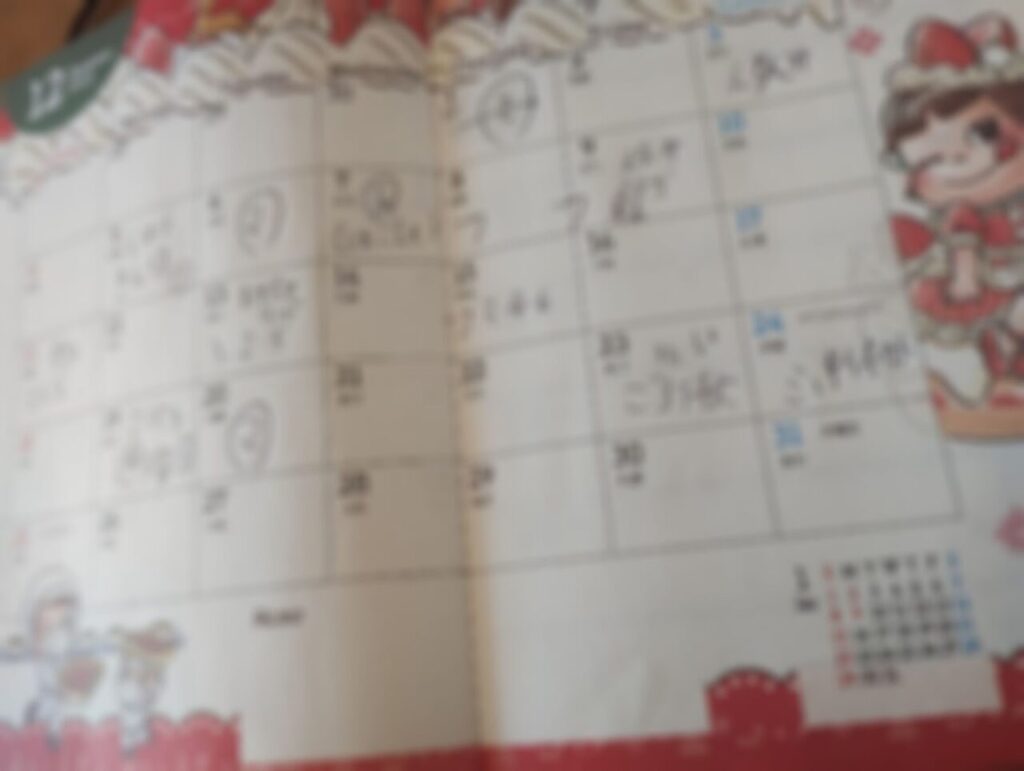
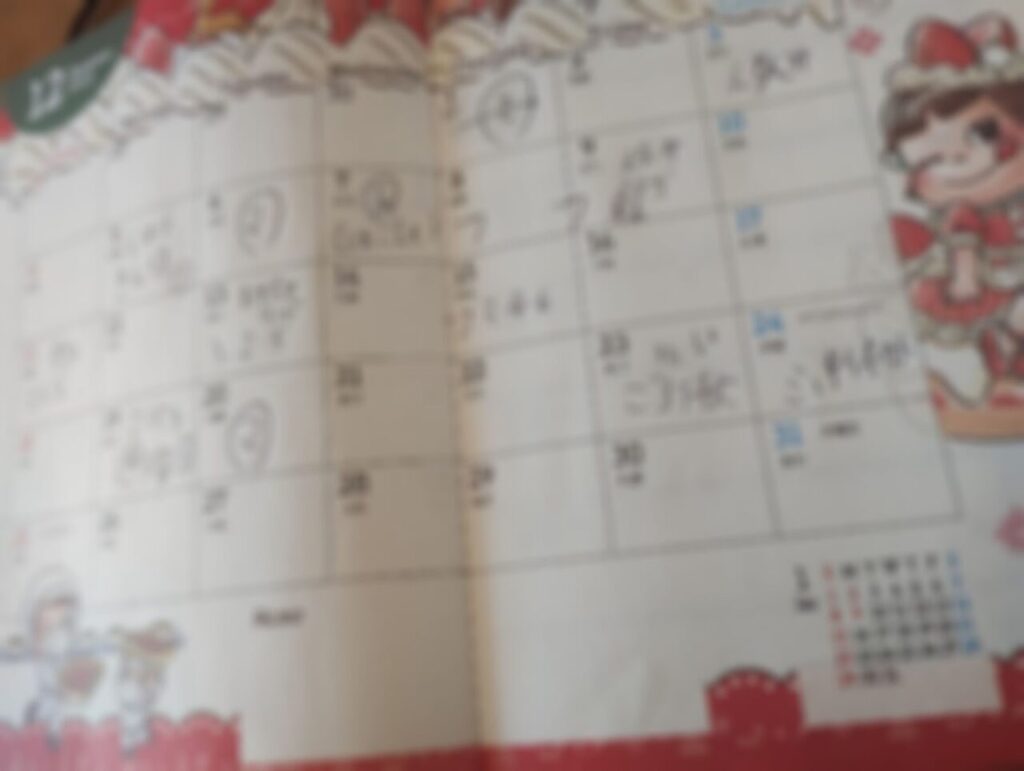



子ども専用のカレンダーを用意し、一緒に予定を書き込む習慣をつけるのもおすすめです。
自分の気持ちを「言葉」にする練習をする
自分の思いを分かってもらえないもどかしさやストレスも癇癪の要因になりやすいため、「気持ちを言葉で表現する練習」を取り入れています。
とはいえ、癇癪の最中に「いまの気持ちを言葉にしてみて!」と伝えても、子どもは当然「そんなのできないーー!」となりがち。
あくまで癇癪が起きていない穏やかな状態のときに「イライラしたら暴れるんじゃなくて『イライラしてるの』と言ってみない?」「『困っている』『落ち着いてきた』の絵カードを見せるのもいいね」と対処法を話し合っておきます。



いざ癇癪が起きた際、あらかじめ話し合った内容を完璧に実践できるわけではありません。大切なのは、子ども自身が「私ってこのときに暴れたくなっちゃうんだ」と少しずつ理解した先に、自分なりの対策を見つけられることです。
癇癪の代わりにできる行動を見つける
見通しを立てる、気持ちを言葉で表現するだけでは我慢できない場合のために「大きい声を出したくなったらコレ」という行動を明確に決めておきました。
娘の場合、ひたすら文字を書くことが好きなため「叫ぶくらい泣きたくなったら紙に文字を書く」と約束。癇癪を自分の落ち着く行動に置き換えて、少しずつ頻度を減らせるようにしています。
▼こちらの記事では環境面の対策も紹介しています
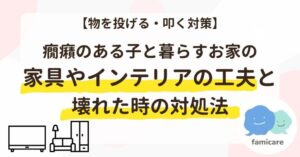
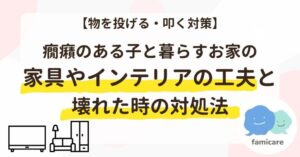
癇癪が起きたときの対処法
それでも、どう頑張っていても癇癪が起きてしまう…!そんなときに筆者がしている対処法をいくつかご紹介します。
安全が確保できて落ち着ける場所(カームダウンスペース)を用意
癇癪が起きてしまった状態で「やめなさい」「落ち着きなさい」と収めようとするのは、とても困難。そのために作っているのが癇癪が起きた場合に一人で落ち着けるスペース(カームダウンスペース)です。
かならずしも個室である必要はなく、子どもが落ち着けるなら、小さなテントやクローゼット内でもOK。場所の確保が難しいときは、いつもの居住スペースにマットやレジャーシートを敷いて区切るだけでも十分です。


また、娘は物を投げてしまう傾向があるため、硬いものや尖ったもの、鋭利なものなど危険な道具は遠ざけています。



床や壁に頭を打ちつけるなどの行為がみられる場合は、クッションやバスタオルを挟んで怪我を防ぎましょう。
▼カームダウンスペースについて詳しくはこちらの記事を参考にしてください


クールダウンするまで見守る
癇癪を起こしている最中に繰り返し声かけをしたり注意したりしても、余計に興奮させてしまう場合があります。そのため、極力話しかけるのをやめ、見守れる範囲で筆者自身もその場を離れます。
ただし「頭を壁に打ちつける」「自分の手を噛む」などの自傷行為がみられる場合は、大怪我に繋がってしまう可能性もあるため、注意して見守りをしましょう。



学校や保育園など家以外の場所で癇癪が起きてしまった場合も、クールダウンできる場所を確保しておくと安心です。担任の先生やスクールカウンセラーに相談してみるとよいかもしれません。
癇癪を起こさなかったときには褒める
気持ちを言葉にするのが大切なのは、大人も同様。いつも癇癪を起こしてしまうシーンで起こさなかった場合、または癇癪を終えて気持ちが落ち着いたタイミングで、その事実をしっかりと褒めます。
「気持ちを切り替えられたね」「泣き止めたね」と言葉をかけることは、子どもにとって「癇癪を起こさないっていいことなんだ!」という学びに。小さな積み重ねで、癇癪の軽減を目指しています。



なお、子どもの癇癪を軽減させてあげるのと同じくらい大切なのは、親自身が疲弊しきってしまわないように「全てをいつも完璧にこなすことはできなくて当然」と自分も労わることです。
▼疲れてしまったと感じたときはこちらの記事がおすすめです
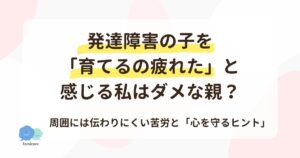
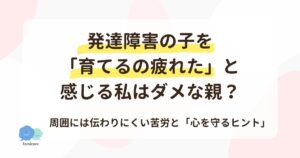
子どもの癇癪は家族だけで抱え込まずに相談を
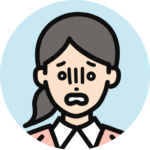
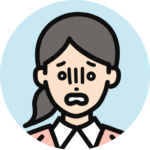
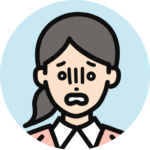
我が子の危険行為は親の自分がしっかりと止めてあげなくては



周囲の人に迷惑がかかるので癇癪が起きないように徹底しなくては
頑張りすぎてしまうあまり、子どもよりも先にご家族が疲弊してしまうパターンは少なくありません。
前述したように、癇癪は親の育て方が原因ではありません。癇癪の大きさによっては、ご家族だけでは対応が難しい場合もあります。
一人で抱え込まず、子育て支援センターや児童発達センター、発達障害者支援センターなどの支援機関に相談してみてください。
▼こちらの記事もおすすめ
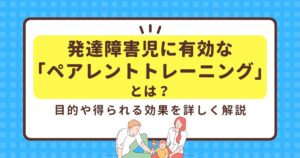
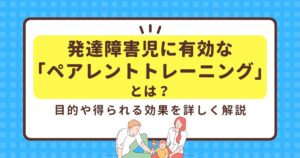
【参照】かんしゃく|MSDマニュアル 家庭版
【参照】かんしゃく|MSDマニュアル プロフェッショナル版







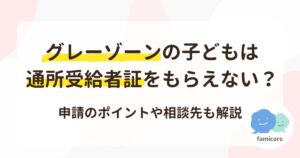
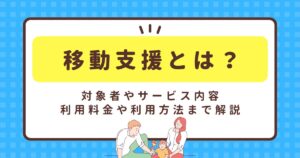
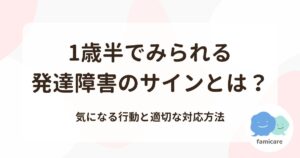
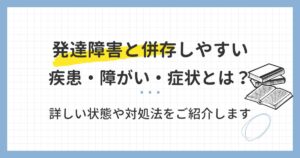
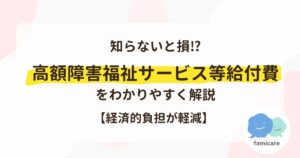
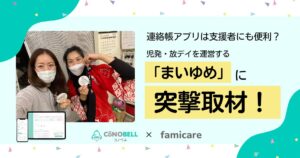

コメント