医療的ケア児を育てている筆者は、子どもが1歳くらいの頃、保健師さんに「この子は小学校に入れますか?」と聞いたことがあります。
子どもが健常児だったら小学校に入れるのかどうかなんて心配しなかったと思いますが、子どもに障がいがあると自分が歩んできた道とは違うことが多いため、今までの「当たり前」を疑うようになってしまっていました。
そして、子どもが小学校に入るためにはどう動いたらいいのか、きっと特別なことが必要なんだろうけど、いつ何をしたらいいのかわからない、と不安に思うようになりました。
読者の中にもそんな方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事から数回にわたって、就学準備をテーマにして記事をお届けしたいと思います。

障がいのある子が小学校に入るまでってどんな流れになるの?
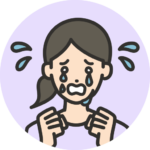
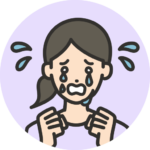
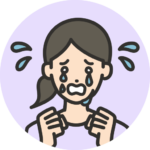
いつから何を準備したらいいの?
と、先が見えず不安に思っていらっしゃる方に、今年年長の子どもを抱え、就学準備を経験した筆者が、就学先決定までの流れと実際にどんなことをしたのかをお伝えしていきます。
筆者の子どもの情報
- 宮城県仙台市在住
- 年長(5歳)(2023年11月現在)
- 障がい:肢体不自由、知的障害(身体障害者手帳1級、療育手帳Aのいわゆる重症心身障害児)
- 医療的ケア:あり(胃ろう)
- 現在保育園と児童発達支援に通園・通所中
- 検討した小学校:特別支援学校のみ(特別支援級も含め地域の小学校は検討しなかった)
※就学に関しては各自治体で異なることも多いと思いますので、実際の流れについては必ずお住まいの自治体でご確認ください。
まずは「就学先決定までの流れ」をつかみ、「教育相談会」の案内を見逃さない。
筆者はまず、就学先決定までの流れをつかむことからはじめました。仙台市の場合は、仙台市教育委員会から就学先決定までの流れが発表されています。
【就学先決定までの流れ】(2024年度小学校入学児童の場合)
- 【5月】教育相談会の案内が5月の市政だよりに掲載される
- 【5月〜6月】教育相談会の申し込み
- 【8月】教育相談会に参加
- 【9月〜10月】審議結果通知の受け取り
- 【10月〜12月】学びの場の検討
- 【10月〜12月】学びの場の決定
- 【12月〜1月】入学申込書の提出
- 【2月】入学通知書の受け取り
- 【2月〜3月】入学する学校と相談
【参照】新年度入学予定のお子さんにふさわしい学びの場を考えるために(就学相談ガイド)|仙台市教育委員会
URL:https://www.city.sendai.jp/kyoiku-tokubetsu/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/shogai/madoguchi/documents/shuugakugaido.pdf



たくさん工程がある!ちゃんとできるかな…
と不安に思うかもしれませんが、一つのポイントさえ抑えればあとは流れに乗るだけでしたので、大丈夫です。そのポイントとは、5月の「教育相談会の案内」を見逃さないことです。
仙台市在住で、障がいのある子の特別支援教育を検討している場合には、8月に教育委員会によって行われる「教育相談会」に出席する必要があります。その教育相談会に申し込みをすれば、あとは案内される通りに動けばいいだけ、という状態になります。
ですので、まずは上記「1」の教育相談会の案内を見逃さないようにすることが大切です。



障がい児の就学に慣れている児童発達支援センターなどに通っていれば、先生から案内があると思いますが、できるだけ自分でも市政だよりの確認や仙台市HPでの確認をしておくようにすると漏れがないと思います。
ポイント
- 就学先決定までの流れをつかむこと
- 「教育相談会」の案内を見逃さないようにすること
いつまでに何しておく?
就学までは基本的には先に紹介した流れになるのですが、実はここに書いていないこともあります。
市からは案内されないことで、経験者として「この時期にこれやっておいてよかった!」と思うことを次にお伝えしていきます。
年長になる前にしておくといいこと
まずは年長になる前にしておくといいことが二つあります。
それが、「検討している学校の見学」「仙台市発達相談支援センター(通称:アーチル)への相談予約」です。
【年少・年中のうちに】検討している小学校は教育相談会の前に見学や問い合わせを
子どもの学校を検討する時には、それぞれの障がいや特性を鑑みて「どこに通うのがいいの?」と悩むことも多いと思います。
特別支援学校か、地域の小学校がいいか悩んでいる



どの学びの場がいいかまだ見当がつかない



特別支援学校以外考えていない
いずれの場合でも、8月に行われる教育相談会の前に、検討しているところを全て見学しておくと気持ちに余裕が持てるんじゃないかと思います。
教育相談会で就学先が決定するわけではなく、上記の流れの通り、実際の審議・決定は教育相談会後に行われるようです。ですので、学校の見学は必ずしも教育相談会前に行う必要はありません。
でも、教育相談会前に見学しておくことで「疑問点を教育相談会のときに質問して解消できる」というメリットがあります。
さらに言うと、年少・年中の時に学校見学に行っておくとより早く情報収集ができ、気持ちに余裕が生まれるため、経験者としてはおすすめです。見学自体は年長の年でなくても受け入れてくれる学校(特別支援学校・地域の小学校問わず)がほとんどなので、ある程度エリアが決まっている時には見学に行っておくと後から楽になると思います。



我が家では引っ越しを考えていたこともあり、どこの学校に通うのかイメージをしておきたかったため、子どもが年少の時に学校見学をしました。そのことでより就学後のイメージがわき、年長になってからの検討がスムーズだったと思います。(このあたりの話はまた別の記事で詳しくお伝えします!)
【年中の年の3月に】仙台市発達相談支援センター(アーチル)への相談を予約
特別支援学校や地域の小学校の特別支援学級への就学を検討しているご家庭の場合、教育委員会が子どもにとってどの学びの場がふさわしいかの判断を行います。その判断のためには、子どもの状態を仙台市発達相談支援センター(通称「アーチル」)が評価し、作成した資料が必要です。
仙台市発達相談支援センター(以下「アーチル」)とは?
乳幼児期から成人に至るまで、発達障害を初めとするさまざまな障がい児者の相談を受け、支援を行う機関。就学を控えた子どもに対しては、年長時に「就学相談」を実施しています。
つまり、アーチルにその資料を作成してもらうためには、8月に行われる教育委員会による「教育相談会」とは別にアーチルの「就学相談」を受けなくてはいけません。
ここで注意することは、年中の年の3月になったらアーチルの予約を取る必要があるということです。毎年教育相談会前の5月〜8月あたりに就学相談が集中するため、アーチルの相談予約が早期に埋まってしまうためです。年中の時点で特別支援教育を希望しているのであれば、まずアーチルへの相談予約をしておくことを忘れないようにしましょう。
▼年中までに行うことについて詳しくはこちらの記事に書いてあります。
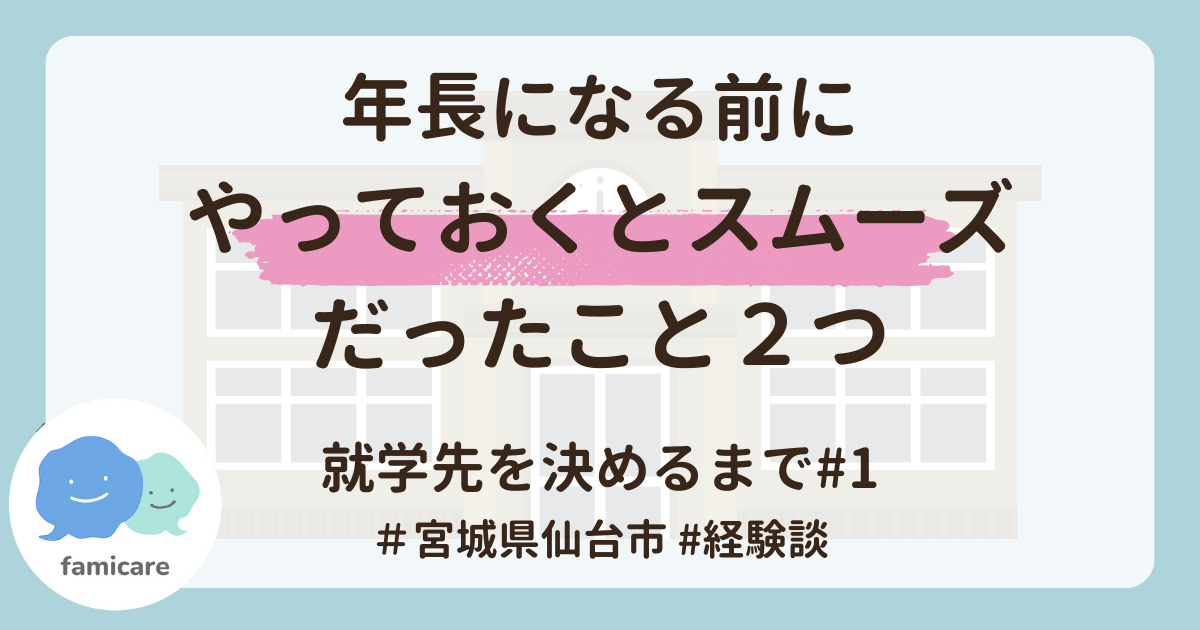
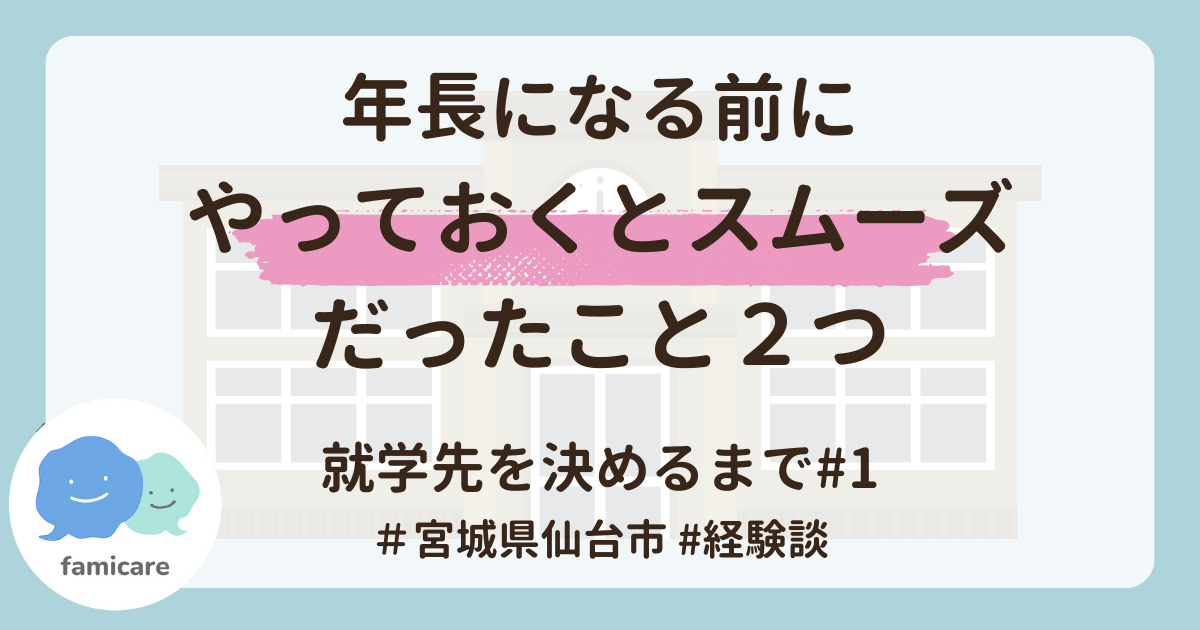
年長になってから行うこと
【8月の教育相談会までに】情報収集・教育委員会に聞きたいことを整理しておくとスムーズ
前述の通り、8月の教育相談会で全てが決まるわけではありません。そこまでに気持ちを完全に決めておかなくても大丈夫です。
ただ、教育相談会で「どこの学校を希望しているか」というのは聞かれます。そこでヒアリングした結果をもとに審議されますので、ある程度家族としての希望を伝えられるようになっておくとスムーズです。
また、その時までに収集した情報で足りないところ、学びの場決定にあたり疑問や不安に思っているところがあれば、教育委員会の方に直接聞くこともできますので、教育相談会までに情報収集をしておけるといいと思います。
【10月までに】結果の通知が来るまでに自分の気持ち(行きたい学校)を決めておけるようにする
教育相談会を受けたら、10月〜11月くらいに審議結果の通知が郵送されます。
その後、教育委員会から電話がきて、改めて結果を伝えられ、就学先を最終的にどうするか聞かれます。
もし自分の希望と通知の内容が異なっている場合(例えば、特別支援学校を希望したのに結果が地域の小学校となっている、など)、ここで「希望と違う」と伝える必要があります。ですので、遅くとも10月には家族の希望を固めておかないといけません。



我が家の場合、「特別支援学校が適切」というような通知で、家族の希望と相違なかったので、「特別支援学校にします」と伝えただけで終わりました。この電話を持って、就学先が決定となったと伝えられ、なんとなくホッとしたのと同時に「これでよかったのかな」とも思いました。正解がないだけに、完全に納得するのは難しいですね。
その他、就学に向けて準備しておくといいこと
ここまで、学校が決まるまでのことをお話ししてきましたが、我が家の場合、就学前に他にも準備しておくことがありましたので、簡単にご紹介します。
【年長の夏くらいまでに】放課後等デイサービスを使う場合には夏くらいまでに検討を!
放課後等デイサービス(以下「放デイ」)の利用を検討している場合、年長の夏くらいまでに候補を決めておけると安心です。
特に重心児・医ケア児向けの放デイは数が限られているので、学校が決まってからの見学や申し込みではもう遅い可能性があります。



ママ友の中には年長になりたての4月に決めている人もいました!筆者の場合、利用している児童発達支援施設が放デイもやっていたので、持ち上がりで利用できることになりましたが、それでも確実に枠を確保するには8月までに利用意向を教えてほしいと言われました。
▼放課後等デイサービスについてはこちらで詳しく解説しています
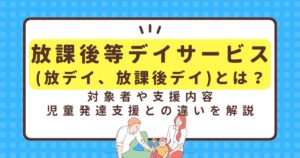
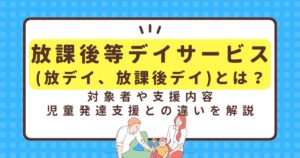
【年長の冬までに】装具や車椅子など、学校で使う福祉機器を主治医に相談
年長の冬までに、学校で使う福祉機器にも目星をつけておけると余裕を持ったスケジュールにできます。
福祉機器を決める前に主治医に相談、必要なものを選定、さらにメーカーや種類を決める、という流れになりますので、年長の時点で車椅子や装具など、何かしらの福祉機器が必要かな、と思ったらまずは主治医に相談しておきましょう。それに間に合うスケジュールを提案してくれるはずです。また、リハビリを受けている場合、理学療法士も相談に乗ってくれます。



我が家の場合、年長の夏くらいに主治医に相談し、「12月くらいまで成長を見てみて、その時点で必要なものを決めて、作りましょう」と主治医に言われていましたので、そのスケジュールで進めています。
就学準備は年長からでも間に合うが、できることは早めにしておくと考える余裕が持てる
最後に、今まで書いてきたことを時系列でまとめてみます。
【年少〜年中】
学校の見学
※以下のうち選択肢になるところは全て見学しておく
- 地域の小学校(普通級・特別支援学級)
- 特別支援学校(県立)
- 特別支援学校(市立)
【年中】
3月:アーチル(発達相談支援センター)に相談予約
【年長】
- 5月:市政だよりや市のHPを確認して教育相談会の申し込みをする
- 〜夏くらいまで:放デイの検討
- 8月(教育相談会)まで:学校の情報収集
- 10月(決定通知)まで:希望の学校を決める
- 〜冬までには:主治医に福祉機器の相談
実際の就学準備は年長からでも間に合うかなというのが、体験してみて筆者が思ったことです(ただし、特別支援学校以外を検討しなかった筆者の場合ですので、他のケースはもう少し早めがいいかもしれません)。
ですが、年長になる前にも準備できることがあります。年少・年中のうちにできることはやっておけると検討材料が揃ってから考えられる時間も増えますし、気持ち的にも余裕が生まれます。
「今からできることはない?」「いつから何したらいいの?」と気持ちが焦ってしまう時には、無理のない範囲で少しずつ動いておくと、不安や焦りの解消につながるかもしれません。
各所に電話したり会って話を聞いたり、ということがちょっと億劫になることもあると思いますが、「今これやっておくことで未来の自分を楽にする!」と思うと少し勇気が出ませんか?私も心からエールを送っています!
\就学に関する情報をまとめた特集はこちら/
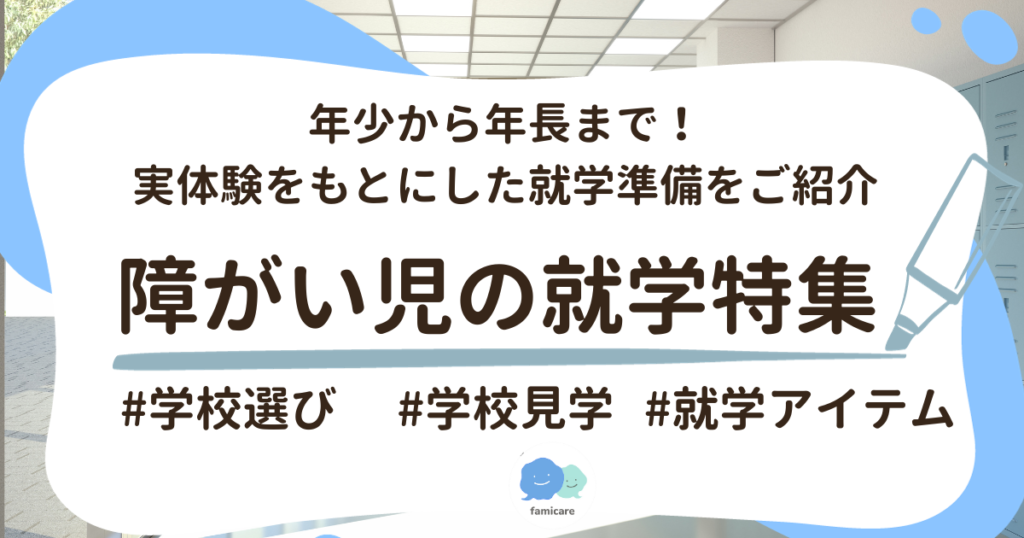
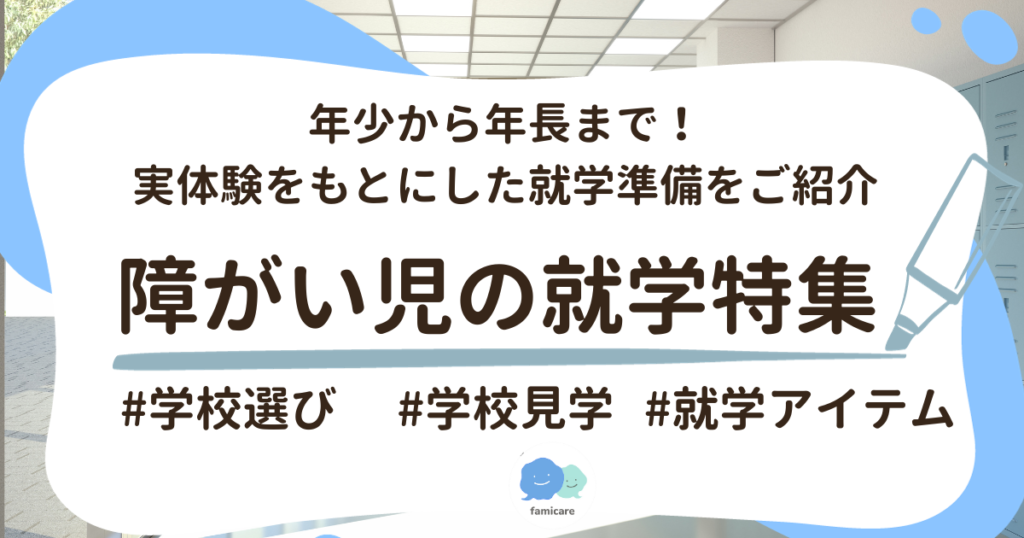


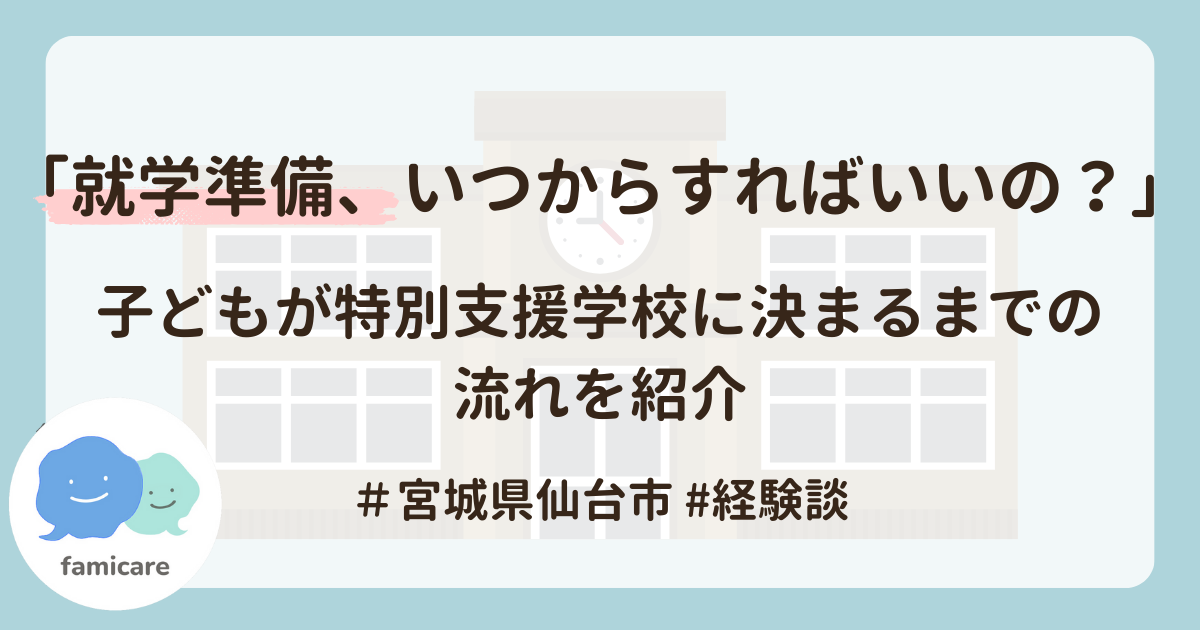

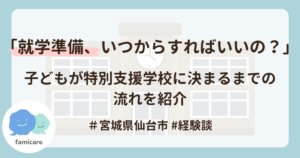

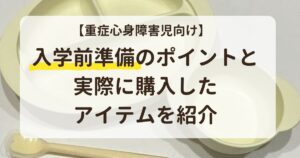
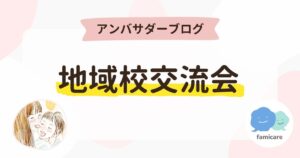
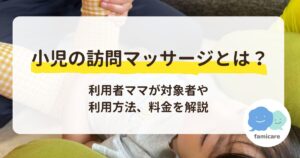
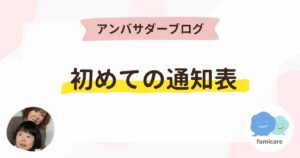

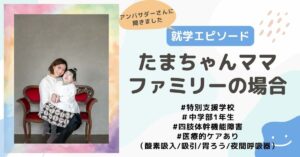


コメント